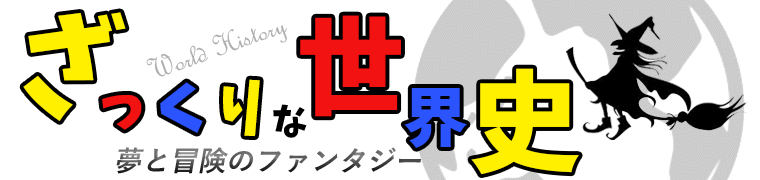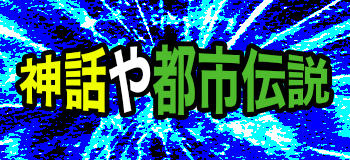パックについて -民話・神話や伝説の英雄と妖精-
パックPuckはイギリスの古語ポークPoukeにあたり、元来の意味は「悪魔・魔神・悪霊」だった。それで、シェークスピア以前の作品中では、ホブゴブリンなどの家の精とははっきりと区別されていた(14世紀の詩人W・ラングランドは、地獄を<プーク(パック)の檻>と呼んだ)のだが、「真夏の夜の夢」によってパック=陽気でいたずら好きな妖精というイメージが定着してしまった。
アイルランドの南西部にあるキローグラン(Killorglin)という小さな町には、昔(クロムウェルの時代=17世紀半ば)「パック」という名の王様がいたらしい。(司馬遼太郎著「愛蘭土紀行II」より)
伝承
夜道を行く旅人を迷わせては困っているのを見て笑い出す。
焼き林檎に化けてコップの中に飛び込み踊りまわる。
三脚椅子に化けてお婆さんが腰を下ろそうとするとスルリと逃げる。
戯曲「夏の夜の夢(1600)」ウイリアム・シェークスピア(1564-1616)作
シェイクスピア浪漫喜劇の第一作目で、その流れは「お気に召すまま」「十二夜」「あらし」へと続く。作品中のパックは、またの名をロビン・グットフェロー(妖精王オーベロンと人間の娘の間に生まれた半妖精)ともいわれ、ホブゴブリン(親しみやすい妖精を意味する言葉)の集約された姿として描かれている。シェイクスピアの描いたパックはその後のパック像に大きな影響を与え、後にルドヤード・キプリングが発表した「プークが丘のパック」に登場するパックもその(ひょうきんで悪戯好きな)性格を受け継いでいる。
オベロン「おお、パック、ここへ来い。覚えていような、いつかの事を。それ、俺は岬の出ばなに腰をおろし、人魚が海豚(いるか)の背で歌っているのを聴いていた。そのうっとりするような美しい声音に、さすがの荒海もおだやかに凪ぎ静まり、天上の星も、その歌の調べを聴こうとして、狂おしく騒ぎたったものだ。」
パック「ええ、覚えていますとも。」
オベロン「その時のことだ、ふと見ると….お前は気がつかなかったろうが….あのキューピッドが、冷たい月とこの地球の間を飛びめぐり、弓に矢がつがえて、何かをねらっている。その的は西方に玉座を占めるヴェスタ星、つまりあの美しい処女王だった。恋の矢は勢いよく弓弦を離れ、千万の若い心を射抜くかと見えたが、さすがのキューピッドの燃える鏃も、氷の月の清い光に打ち消され、処女王は無傷ののまま立ち去ってしまったのだ。無垢の想いにつつまれ、恋の煩いも知ることなく….。が、それはさておき、俺の目はキューピッドの矢が落ちた場所をとらえたのだ。西のかた、そこには小さな花があって、それまで乳のように真白だったものが、恋の矢傷を受けて、たちまち唐紅に変じてしまった。娘たちはその花を「浮気草」と呼んでいる….。じつは、それを摘んで来てもらいたいのだ。いつか見せたことがあるな。その汁を絞って、眠っているまぶたのうえに塗っておくと、男であれ女であれ、すっかり恋心にとりつかれ、目が醒めて最初に見た相手に夢中になってしまうのだ。その草を取って来てくれ、すぐに戻って来るのだぞ、鯨が一里と泳がぬうちにな。」
パック「地球ひとめぐりが、このパックにはたった40分。」(「夏の夜の夢」福田恒存訳より)
シェイクスピア作品の多くが映画化されているが、「夏の夜の夢」にも1935年のアメリカ版、1983年のイギリス・スペイン合作版などがある。