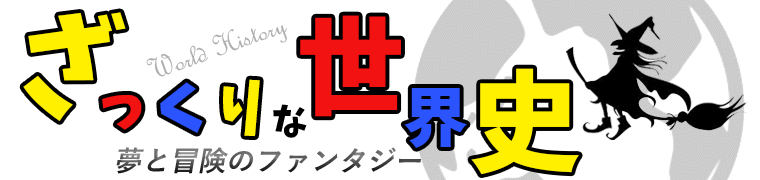ざっくり世界史 -読み物-
ミノス文明
クレタ島で前2000~前1400年ごろに最も栄えた青銅器時代の文明。キクラデス諸島で栄えたキクラデス文明とギリシア本土で栄えたミケーネ文明とともにエーゲ文明の3つの主要な文明のひとつ。クレタ文明ともいう。
イギリスの考古学者エバンズが1900年に発掘をはじめ、クノッソスの宮殿を発見し、伝説の王ミノスにちなんでミノス文明と名づけた。それまでミノス文明の存在は知られていなかった。
この文明は前3000年にはじまり、前2000年ごろに大きく発展し、クノッソス、ファイストス、マリアなどに6つの宮殿がきずかれた。前1700年ごろ地震によって破壊されるが、ただちに再建され、かえってミノス文明は最盛期をむかえる。クノッソスの新宮殿は複雑な構成の3~4階建てで、中庭をかこむたくさんの部屋や廊下があり、王や王妃の部屋は壁画などで飾られていた。この複雑な構造が、のちに迷宮伝説を生みだした。
数多くの絵画は鮮やかな色彩で宮廷生活や海洋生物などを写実的でダイナミックにえがいている。有名な「牛跳び」は、人身牛頭の怪物ミノタウロスの伝説にちなむ宗教儀礼をかねた競技の一場面である。宮殿の聖域には両手にヘビをもつ蛇女神がまつられ、壁画にえがかれているいくつもの双斧(そうふ:左右対になった斧)はこの蛇女神に関連するものと思われる。壁画のほか宮殿内から出土した彫刻や陶器、工芸品などもみごとである。また他の宮殿もその構造はクノッソス宮殿と似ている。
クレタの首都として繁栄していた前1600年ごろのクノッソスは推定8万人の人口を擁する大都市であった。エーゲ海を支配し、広くエジプトなどとも交易をおこなっていた。ミノス文明は前1450年ごろ、ギリシアのミケーネ人の侵入により滅亡した。ミュケナイ文明はミノス文明の影響をうけて発展、このころから最盛期をむかえることになる。
1900年以来の発掘で絵文字と、線文字A、Bと分類される2種の文字が書かれた数千枚の粘土板や、壺がみつかった。線文字Aは、ミノス人が絵文字にかわって考案したもので前1750年ごろ盛んにつかわれていたが、いまだに解読されていない。
線文字Bはクレタ島やギリシア本土のミケーネで見つかっており、ほとんどが前1400~前1150年ごろのものとみられている。1952年イギリスのマイケル・ベントリスらが解読に成功した。この文字はミュケナイ人が線文字Aを真似て考案、自分たちのギリシア語を書きあらわしたものといわれる。
ミケーネ文明
エーゲ文明後期の前1600年ごろから前1200年ごろに栄えた文明で、後期青銅器時代にあたる。前2000年ごろバルカン半島に南下してきたインド・ヨーロッパ系の人々は、先住のミノス人(クレタ人)のミノス文明を目の当たりにして、前1600年ごろからこの文明を吸収しつつ独自の文明を発展させた。
ミケーネ文明という呼び名は、この文明の中心の一つミケーネ(ミュケナイ)にちなんでいる。ミケーネは、ギリシア本土のペロポネソス半島北東部アルゴリス地方に位置し、シュリーマンの発掘によってその存在が知られることになった。ミケーネ文明の重要な遺跡としては、ほかにティリュンスやピュロスなどが知られる。
ミケーネ人は線文字Bと称される文字を使用していた。1952年にベントリスとチャドウィックによって線文字Bが解読されると、これが初期のギリシア語であることから、ミケーネ文明の担い手はギリシア人であったことが明らかになった。
形成期(前1600頃~前1450頃)
前1600年ごろまでに、ミケーネ社会には階級分化が生じた。墓から出土した多数の黄金製品から富裕階級がいたことが知られる。ミケーネ人は、海上交易をとおしてミノス文明の影響を強くうけたが、彼らよりもはるかに好戦的だった。埋葬品の中には青銅刀剣類などの武器がふくまれ、壁画には狩りや戦闘のようすがえがかれている。このことは、彼らの社会が動乱続きであったことをしめしている。この時期のエーゲ文明の中心はクレタ島のミノス文明であり、エーゲ海の海上権もミノス人が掌握していた。
宮殿時代(前1450頃~前1200頃)
前1450年ごろ、ミノス人の宮殿が次々と破壊され、ミノス文明が滅亡した。これはミケーネ人のクレタ島侵入によるとされる。そして、ミケーネ文明はギリシア本土からクレタ島にも広がり、エーゲ文明の中心として繁栄した。ただ一つ破壊をまぬがれたクノッソス宮殿の主も、ミケーネ人がとってかわった。ミケーネ人がミノス人の宮殿の破壊にかかわっていたという確実な史料はないが、宮殿の破壊によって繁栄のきっかけをえたことは確かである。
このころから、ミケーネ人の諸王国はギリシア本土にも宮殿の建設をはじめた。ミケーネ、ピュロス、ティリュンス、テーベに代表される諸宮殿である。前14世紀にクノッソス宮殿が破壊されると、これらの宮殿を中心にしてミケーネ文明は最盛期をむかえ、ミケーネ人の交易圏ははるかに大きくなり、その影響は小アジアにまでおよんだ。
宮殿の規模や様式に違いがみられるものの、その機能はミノス人の宮殿とかわらなかった。宮殿は行政や宗教儀礼の中心であり、また食糧貯蔵庫や工房であった。そして、宮殿には王国の財政を記録した大量の粘土板文書が保管されていた。
線文字Bで記述されたこれらの粘土板文書から、この時代の王国のようすをうかがうことができる。それによれば、ミケーネ人の王はワナカとよばれており、王国の構造はオリエントの専制国家に類似していた。王は官僚を組織し、地方村落は王に対して貢納の義務をおっていた。
ホメロスの「イーリアス」および「オデュッセイア」に登場する英雄の活躍した時代は、ほぼこの時期にあたる。アガメムノンはミケーネの王であった。
前13世紀後半ごろからミケーネ社会は衰退をはじめ、前1200年ごろ宮殿が次々に炎上して文明は終焉をむかえる。ミケーネ文明の崩壊の原因としては「海の民」の襲来説が有力だったが、近年はミケーネ社会内部に原因をもとめる説、気候変動説などもとなえられ、その真相は明らかでない。
終末期(前1200頃~前1000頃)
ミケーネ諸王国の崩壊後、生き残った人々は新しい定住地をもとめて移住した。一時的に社会の再建が試みられたものの、宮殿の再建は行われず、まもなくかつての中心地は放棄され、人々は小さな集落に定住した。人口は減少し、文化水準も低下した。墓も粗末になり、副葬品も貧弱になった。ギリシア史で「暗黒時代」ともよばれるこの時期は、しかしながら、新しいポリス社会の時代への胎動期でもあった。
アテネ Athinai
元々はアッティカ地方に存在する小王国の一つでしかなかったが、前9世紀中ごろ、アテネはピレウス港をふくむ周辺地域を領土に加えた。政治形態は王政から貴族政に移行したが、民衆にはほとんど参政権がなかった。実権をにぎっていたのは、長老貴族からなる評議会のアレオパゴス会議で、彼らは戦争、宗教、司法の遂行の任にあたる3人(のちに9人)のアルコン(公職者)を指名した。この貴族支配への不満が高まった前632年、キュロンは貴族と市民との対立を利用して、公式には政権をみとめられない者が独裁者として実権をにぎる僭主政樹立を試みたが、失敗におわった。その後も治安が安定しなかったため、前621年、ドラコンは成文法を制定し、治安回復をはかった。前594年、あらゆる階層の人々の一致した意見でソロンをアルコンに任命した。彼は評議会(ブーレー)、民会(エクレシア)、法廷を設立するいっぽう、交易の促進、貨幣の改鋳、外国人技術者の招聘などの改革を実施した。しかしながらその改革は部分的にしか成功しなかった。
前560年、ペイシストラトスが僭主政を樹立してアテネの支配者となった。彼はソロンの時代に設立されたアゴラ(集会場・市場)を拡充し、またポリスの守護神、アテナ女神をまつる神殿をアクロポリスに建立した。また4年おきにおこなわれるパンアテナイア祭のような公的な行事を後援した。前560~前510年にこの僭主とその息子たちによりさまざまな公共事業が実施された。
前509年、クレイステネスが海岸党をひきいて僭主政を打倒、民主政を樹立した。彼は支持基盤が市街部におかれるように、従来の四部族にかわる十部族制を導入して、都市国家の体制をととのえた。民会が実権をもち、アクロポリスの西方のプニクスの丘で開催されるようになった。
前480年、アテネはペルシア軍の略奪をうけ、町の大部分が破壊された。指導者のテミストクレスはサラミスでペルシア軍を撃破したのち、アテネとピレウスの周囲に城壁をきずき復興に着手した。彼は同時にアテネとピレウスをつなぐ城壁の建設もはじめ、この事業は前450年代にペリクレスにうけつがれた。ペリクレスは他のいかなる民主政の指導者にもましてアテネを強大なポリスにした。彼はパルテノン神殿、アテナ・ニケ神殿、エレクテイオン神殿その他の大建築物の建設に公共資金をもちい、他方、世界じゅうからめずらしい品物を輸入してアゴラを盛んにした。
前477年、対ペルシアの軍事同盟であるデロス同盟の盟主となったアテネは、スパルタとならんでギリシア世界で大きな影響力をおよぼした。アテネの法廷ではエーゲ海全域の訴訟が審議された。また文化も花ひらき、アクロポリスのふもとのディオニュソス劇場では悲劇や喜劇が上演され、ペリクレスは多くの知識人と交友関係をもった。アテネはその民主政とかがやかしい生活習慣で「ギリシアの学舎(まなびや)」となった。絶頂期には人口は約20万をかぞえ、うち5万人が民会に参加できる市民資格をもつ成人男子だった。
栄光のアテネは、ペロポネソス戦争(前431~前404)でスパルタに敗北したのち、急速に衰退へとむかった。しかし、哲学はすばらしい展開をみせ、前4世紀には、ソクラテスにつづいてプラトンが哲学の学校としてアカデメイアを、アリストテレスがリュケイオンをひらいた。またデモステネス、イソクラテスなどにより弁論がまなぶべき1つの技術となった。
スパルタ Sparta
スパルタは、もっとも繁栄した時代でも、簡素な家屋といくつかの公共の建物がたちならぶ5つの村落の集合だった。道がエウロタスの谷へ通じていて外敵から防衛しやすく、前4世紀末まで防壁はなかった。住民は、隷農身分のヘロット(ヘイロータイ)、兵士の義務をおうが市民権をもたず主として商業に従事する自由人の従属身分ペリオイコイ、前1100年ごろこの地域に侵入してきたドリス人の子孫で統治者や戦士など支配階級を占めるスパルタ市民の3つの階層にわかれていた。
スパルタの強さは、前9世紀の人とつたえられるリュクルゴスが定めた法によるものともされるが、むしろ長い間の変革の結果であろう。前7世紀ごろのスパルタの生活は他のギリシア諸都市とかわらず、芸術や詩、とくに抒情詩が全盛を極めていた。しかし前6世紀以降、スパルタ人はすべて軍人をめざし、全力を戦争にかたむけた。スパルタ市民よりも圧倒的に数の多いヘロットやペリオイコイをおさえるためでもあったと考えられる。
虚弱な子供は生存をゆるされず、少年は7歳になると軍事教練をうけ、20歳で入隊した。結婚がゆるされた場合も30歳までは兵舎に住まなければならず、20歳から60歳までのスパルタ人の男子はすべてホプリテス(重装歩兵)として兵役につき、食事も全員が同じ夕食をとる共同食事(フィディティア)を義務づけられた。スパルタ市民のあいだでは平等の維持が配慮され、貧富の差を解消する政策がとられた。軍の司令官としての2人の王が存在した。
スパルタの初期の戦闘相手は、ペロポネソス半島南西部のメッセニア地方と、北東部の都市アルゴスだった。メッセニア戦争は前650年ごろ終結し、メッセニア人は敗北してヘロットの地位におとしめられた。以後、きびしい訓練によって、スパルタ人は質実剛健な戦士となり、祖国のために自己犠牲をいとわない民族となった。ペルシア戦争のさなかの前480年、王とともに300人の英雄が戦死したテルモピュライの戦はその一例である。
前431年のペロポネソス戦争勃発により、スパルタとアテネの抗争は頂点に達し、前404年にアテネが降伏すると、スパルタはギリシア諸都市の支配者となった。しかし、そのために貧富の差が深まり、平等を基礎とするリュクルゴス制がしだいに崩壊して、以後スパルタは衰退していった。前371年エパメイノンダスひきいるテーベに獲得領地をうばわれ、領土は当初の境域にもどった。のちにはローマの属州アカイアに編入され、後396年に西ゴート族の王アラリック1世の襲撃をうけて壊滅した。
共和政ローマ Roma
伝説によるとローマは、近隣のラテン人の都市アルバ・ロンガのヌミトル王の娘レア・シルウィアの双子の息子、ロムルスとレムスにより、前753年に建国されたといわれている。後代の伝説は、ローマ人の起源をトロイアのアエネアスにまでさかのぼらせ、アエネアスの息子アスカニウス(あるいはユルス)をアルバ・ロンガの設立者かつ最初の王としている。
ロムルス治下のサビニ人の女たちの強奪とそれにつづくティトゥス・タティウス指揮下のサビニ人との戦いは、ローマ人とサビニ人の混交がはやくからすすんでいたことを示唆し、ラムネス、ティティエス、ルケレスの3部族構成は、ローマがラテン人、サビニ人、エトルリア人の混合からなっていたことをしめしている。
七王伝説による諸王は、初代王ロムルス(前753~前715)、宗教制度を整備したヌマ・ポンピリウス(前715~前676または前672)、アルバ・ロンガを破壊し、サビニ人と交戦したトゥルス・ホスティリウス(前673~前641)、オスティア港を建設し、多くのラテン人の町を征服したアンクス・マルキウス(前641~前616)、エトルリア人で近隣の征服とローマの公共建設活動を推進したタルクイニウス・プリスクス(前616~前578)、ローマ市域を拡大したセルウィウス・トゥリウス(前578~前534)、エトルリア人の王タルクイニウス・スペルブス(前534~前510)と続く。最後の王タルクイニウス・スペルブスは暴君と化したため貴族たちによって追放され、王政時代はおわる。
これらの伝説からたしかめられることは、ローマが最初王により支配され、都市の発展にともない近隣の諸族と交戦したこと、エトルリア人王のローマ支配とその打倒の結果王政が廃止されたことである。当時の社会は、奴隷をのぞくと貴族(パトリキ)と平民(プレブス)の2身分にわけられていた。貴族は参政権を独占し、もとは彼らのみが軍務に服していた。平民には参政権はなかった。
王は有力貴族の長老(パトレス)の集まりである元老院(セナトゥス)から選出され、軍を指揮した。王は権力と懲罰権を象徴するファスケスをたずさえたリクトル(先導警吏)をしたがえ、裁判では最高権を行使した。元老院は王の諮問機関にすぎなかったが、元老院議員の任期は終身だったから、長老たちの権威は大きかった。
平民の富裕化にともない、伝説ではセルウィウス・トゥリウスによる軍事改革で、貴族、平民にかかわらず、すべての有産者は財産所有高に応じて等級づけられ、それぞれにわりあてられた軍務に服するようになった。この新制度は、共和政時代の参政権拡大をめぐる貴族と平民の争いに道を開くことになる。
そしてタルクイニウス・スペルブスの追放により、共和政が成立する。共和政期には、王に代わって毎年2名の最高位の公職者(政務官)が選出された。彼らは最初プラエトル(先頭にたつ者)とよばれたが、のちにコンスルという称号にかわった。同僚制と任期制は、独裁化を防ぐ手段であった。共和政にはいって間もなく「身分闘争」とよばれる貴族、平民間の抗争がおき、平民の参政権が拡大した。たとえば平民が元老院にはいれるようになり、彼らはコンスクリプティ(追加登録された者)とよばれた。以後元老院議員は、公式にはパトレス・コンスクリプティと呼ばれるようになった。
さらに身分闘争がつづいた前494年には、平民兵士の市外退去(セケッシオ)の結果、平民の権利をまもり、政務官の行為に対して拒否権をもつ護民官(トリブヌス・プレビス)が創設された。前451年には10人の委員により、ローマ最古の包括的な法典、十二表法が成文化され、前445年のカヌレイウス法により、貴族と平民の通婚がみとめられた。さらに前367年のリキニウス-セクスティウス法により、2名のコンスルのうち1名が平民にも開放され、その後も独裁官(前356)、監察官(前350)、法務官(前337)、神官および卜占官(前300)の平民への開放がつづいた。
しかしこれらの権利の拡大を享受できた平民は、極一部の富裕者の家柄に限られていた。彼らは従来の貴族と同様、ノビリス(名門)とよばれるようになり、彼らを加えた元老院は、本来その権力は小さかったが、今や事実上の国政の最高権力機関となり、戦争、外国との同盟、植民市の建設、国家財政の管理などの重要問題を担当した。しかし、貧しい平民の境遇は改善されず、新しい貴族層と貧しい平民の対立は共和政末期の内乱における閥族派と民衆派の対立につながっていった。
この時期、ローマによるイタリア半島の軍事征服がすすんだ。すでに王政末期、ラテン人諸都市の主導権をにぎっていたローマは、エトルリア人、ウォルスキ族、アエクイ族と交戦したが、ローマをめぐる状況はしだいにきびしくなっていった。前390年にブレンヌスを首領とするガリア人が侵入し、ローマはアリア河畔で敗戦し、ローマ市の占領と放火略奪という大災厄をこうむった。しかし一方、前396年のカミルス指揮下のローマ軍によるエトルリア都市ウェイイの攻略以後、前4世紀半ばまでにローマ人の植民活動などにより、エトルリア南部のローマ化がすすんだ。
他方、ウォルスキ族、他のラテン人、ヘルニキ人に対する勝利によりローマはイタリア中部を支配下におさめ、さらにサムニウム人との3度にわたる戦争(前343~前290)の結果、南部にも進出した。ローマに対抗したラテン諸都市の同盟とウォルスキ族は鎮圧され、前338年、ラテン同盟は解体された。当時北部ではエトルリア人、ウンブリア人、ガリア人により、南部ではルカニア人、ブルッティイ人、サムニウム人により反ローマ連合が形成されたが、北部の反ローマ連合は前283年に打倒され、南部の連合も間もなく敗北した。
イタリア半島南部のギリシア人の植民市タレントゥム(現ターラント)は、ギリシア北方のエペイロス王ピュロスに救援をもとめ、ピュロスは前280年から前275年にかけてローマとたたかったが勝利をえられずに帰国し、前3世紀前半までにローマはアルノ川とルビコン川以南の全イタリア半島の征服を完了した。
前264年、ピュロスに対する勝利の11年後、ローマはカルタゴと地中海支配権をめぐる戦争に突入した。当時カルタゴは最強の海上大国として、ローマのイタリア半島支配におとらない絶対的支配権を、地中海の中部・西部海域とその沿岸地方におよぼしていた。
そんな情勢の中起きた第1次ポエニ戦争は、主としてシチリアの領有権をめぐって争われ、ローマの海軍創設の切っ掛けとなった。ローマはシラクザの支配者ヒエロン2世の支持をえ、アグリゲントゥム(現アグリジェント)を占領し、前260年の最初の海戦で、ドゥイリウス指揮下のローマ海軍はカルタゴ軍を打ち破った。その後、アフリカ遠征の失敗(前255年、将軍レグルスが捕虜となった)や遭難事故にもかかわらず、前241年にシチリア西端沖の海戦で勝利をおさめたローマは、初の海外領土としてシチリアを獲得、その後サルデーニャ島とコルシカ島をも加え、これらをローマの属州とした。
戦後カルタゴは、ハミルカルによりイベリア半島(ヒスパニア)に進出、その後もハミルカルの娘婿ハスドルバルやハミルカルの息子ハンニバルにより、カルタゴの征服地はイベルス川(現エブロ川)まで拡大した。前218年に第2次ポエニ戦争がはじまり、ハンニバルはアルプス越えを決行して北からイタリアに侵入、各地でローマ軍を撃破し、南イタリアを中心に略奪活動をつづけたが、ローマの将軍スキピオ(大)がカルタゴ本土を攻撃したため、本土に召還された。前202年のザマの戦はローマ側の完勝におわり、カルタゴは莫大な賠償金支払いとともに海軍を放棄させられ、イベリア半島と地中海の島々をローマに割譲した。その結果、ローマは西地中海の制海権を手にした。
このころから、ローマのイタリア諸都市に対するよりきびしい姿勢がめだつようになった。戦争中ハンニバル側についた南イタリアのギリシア人都市は、ローマ植民市とされた。いっぽう北方では、前201~前196年の戦いでポー川峡谷のケルト人が征服され、その領土はラテン化がすすんだ。コルシカ、サルデーニャの征服もすすみ、ヒスパニアも困難な戦いののち占領し、ローマ軍が駐留した。
ハンニバルと同盟したマケドニア王フィリッポス5世のエーゲ海進出の野心は、ローマとの第2次マケドニア戦争(前200~前197)の引き金となった。フィリッポスは敗北し、ギリシアの自由が宣言された。その後ギリシア進出をはかったシリア王アンティオコス3世との戦い(前190年のマグネシアの戦)もローマの勝利におわり、シリアはヨーロッパと小アジアの領土を放棄した。
いっぽうマケドニアでは、フィリッポスのあとを継いだ息子のペルセウスが第3次マケドニア戦争でローマと戦い、ピュドナの戦(前168)でローマの将軍パウルスに完敗した。前147年、マケドニアはローマの属州とされ、翌年アカイア同盟の反乱も鎮圧され、コリントス市が破壊された。こうしてローマは、東方にも勢力を拡大した。
同じく前146年、その3年前からはじまった第3次ポエニ戦争も、スキピオ(小)によるカルタゴ征服と破壊という結末におわった。カルタゴは滅亡し、領土はローマの属州とされ、ヒスパニアでの反抗も、前133年のヌマンティアの戦で決着した。小アジアにおいては同年亡くなったペルガモン王国の王アッタロス3世は、遺言で国土をローマにおくり、属州アシアとされた。
こうして131年の間にローマは、シリアからイベリア半島におよぶ地中海を支配する世界帝国に発展した。いっぽう東方世界との交流により、美術、文学、哲学、宗教などの先進文化が流入し、その影響でローマの文化も発達した。ローマ文学は前240年、ギリシア文学作品の翻訳からはじまり、前155年にはさまざまなギリシア哲学の流派がローマに紹介された。
対外支配権の確立にともない、ローマの国内問題も深刻化した。極少数の富裕な平民は、旧貴族の名門と結んで、政治権力と経済的利益を独占した。彼らは閥族派(オプティマテス)とよばれた。一方一般の平民は、貴族による大土地保有の進行や軍役と戦争による農地の荒廃などにより土地を失い、無産化して都市に流入した。こうして貴族、平民の対立が強まった。護民官ティベリウス・グラックスとその弟ガイウス・グラックスは、平民の経済的困窮をすくうための土地法や穀物法などの改革を試みた(グラックス兄弟の改革)が、結局改革は失敗し、兄は前133年、弟は前121年に殺された。
コンスルのマリウスは、前106年にヌミディア王ユグルタとの戦争に勝利し、ついで北方から侵入してきたゲルマン人のキンブリ族とテウトニ族も打倒した。これらの勝利はマリウスの名声を高め、マリウスのまわりには民会を基礎にして閥族派支配を打倒しようとする民衆派(ポプラレス)が形成された。ユグルタ戦争では、副官のスラの働きも大きかった。
イタリアのローマの同盟諸市は、征服戦争での役割が高まる一方で、ローマから差別的な扱いをうけることへの不満を高めていた。同盟市にもローマ市民権を付与しようとした護民官ドルススが前91年に暗殺されると、翌年イタリアの同盟諸市は、新しいイタリア国家の建設をめざしてローマに反抗した。この同盟市戦争は前88年までつづき、同盟諸市はローマに降伏したが、代償として完全なローマ市民権を獲得した。
ローマでは、ポントス王ミトリダテス6世との戦争の指揮権をめぐってマリウス(民衆派)とスラ(閥族派)の対立が強まり、同盟市戦争でローマ軍を指揮したスラは、はじめて軍隊をローマ市に進軍させ、マリウスの逃亡によって指揮権を獲得し、前87年、対ミトリダテス戦に出発した。その間にローマを追われた反スラ派のキンナは、アフリカから戻ったマリウスおよび彼の軍隊とともにローマに進軍し、マリウスはスラ派を残酷に粛清したが間もなく死亡した。
ミトリダテス戦争を収拾したスラは、前83年に4万人の軍隊とともにイタリアに上陸して民衆派を打倒、強力な軍隊を背景に、前79年に引退するまで、独裁官としてローマを支配した。その間政敵を処刑し、財産を没収して自分の退役兵に与えた。このころローマの農業は荒廃し、外国からの穀物輸入が増加したが、特にアフリカはローマへの主要な穀物供給地となった。
前67年、スラの副官だったポンペイウスは、アフリカ、シチリア、ヒスパニアのマリウス派の残党の一掃、地中海の海賊の討伐、ミトリダテス戦争の最終決着などの成果をおさめた。一方彼のライバルで民衆派のカエサルは、民衆に人気の高かったマリウスやキンナの名誉回復、スラが行った追放、財産没収の処分を取り消して、ローマでの人気を高めた。
前63年に、コンスル職を目指したカティリナが内乱を起そうとした陰謀は、当時のコンスル、キケロに鎮圧されたが、この陰謀には旧スラ派の不満分子が多く結集し、スラ派支配の破綻を示すものでもあった。翌年帰国したポンペイウスは、東方遠征中の彼の施策と軍団兵への土地分配の批准を元老院に求めたが、拒否された。事態打開のためカエサル、ポンペイウス、富豪のクラッススは第1次三頭政治とよばれる協力関係をむすび、元老院に対抗して権力を3人で独占した。
前59年、カエサルはコンスルとなり、ポンペイウスの要求した土地分配法を成立させた。さらにカエサルは、5年にわたるイリュリクムとガリアの軍指揮権を獲得し、その征服活動で名声を高め、同時に莫大な利益をえた。
前56年に三頭政治体制は更新され、ガリアにおけるカエサルの命令権の5年間延長、ポンペイウスとクラッススの前55年のコンスル就任、ポンペイウスのヒスパニアとアフリカの獲得とクラッススのシリア獲得などが決められた。しかし、前53年にクラッススが対パルティア戦中に戦死すると、ポンペイウスとカエサルの対立が表面化した。無力化していた元老院はポンペイウスとむすび、彼を前52年の単独のコンスルに選んで、カエサルと対抗した。
元老院はカエサルの軍指揮権をとりあげ、前49年のコンスル職への立候補を妨害するために、軍隊の解散と選挙時におけるローマ滞在か、さもなければ立候補の放棄を要求した。これに対しカエサルは、前49年、ガリアからの軍を率い国境のルビコン川を超えてローマに進軍し、5年にわたる内乱がはじまった。ポンペイウスらはギリシアに退却し、カエサルは勝利者としてローマに入城した。
カエサルは様々な行政、経済の改革に着手したあと、ヒスパニアのポンペイウス派の軍と戦って勝利を収め、前48年には、ギリシアのファルサロスでポンペイウス軍を破り、ポンペイウスはエジプトに逃亡したが殺された。このとき、カエサルは、エジプトのプトレマイオス王国女王クレオパトラも勢力下におさめている。そして、前45年にはヒスパニアのムンダの戦でポンペイウス派の残党を撃破、終身独裁官となった。
前44年3月15日、共和派によるカエサル暗殺後、キケロらにより共和政復活が試みられたが、カエサルの部下アントニウスとレピドゥス、それにカエサルの姪の子で遺言により彼の相続者となっていたオクタウィアヌス(のちの皇帝アウグストゥス)は、第2次三頭政治体制を形成し、キケロら反対派の暗殺や追放をおこなった。そして、前42年フィリッピの戦で、カエサル暗殺者のブルトゥスとカッシウスを打倒すると、国土を3分割し、オクタウィアヌスはイタリア半島と帝国西部、アントニウスは帝国東部、レピドゥスはアフリカを獲得した。
東方にむかったアントニウスは、エジプト女王クレオパトラの魅力に魅かれ、彼女との関係を強めて東方での勢力を拡張した。レピドゥスは、当時シチリアを根拠地としていたポンペイウスの息子セクストゥスとオクタウィアヌスとの戦いに際して、オクタウィアヌスへの反乱をおこして逆に失脚した。セクストゥスを破って西方での地位を安定させたオクタウィアヌスは、前31年のアクティウムの海戦でアントニウスとクレオパトラの連合軍をやぶり、翌年の両人の自殺により、前29年には東方をもふくむ全ローマ帝国の支配権を手中にした。
また、共和政末期の内乱期は、ローマ文学の黄金期でもあった。カエサルやキケロは優れたラテン語の散文作品を残し、護民官などをつとめた政治家ウァロは当時の最大の学者でもあった。また、カトゥルスやルクレティウスが詩人として活躍した。
ムー Mu
太古にインド洋か太平洋上に存在したとされる伝説上の大陸。この伝説は、イギリスの動物学者スクレーター(1829~1913)が、アフリカからマレー半島にいたるレムール(キツネザル)の分布調査から、かつてインド洋上にあった大陸の存在を指摘、これをレムリアと名づけたことにはじまる。その後、この説は大陸移動説などの登場によって否定されたが、神智学者のブラバツキーや人智学者のシュタイナーなど神秘思想家たちの支持をうけて生きのこり、その場所もインド洋ではなく太平洋であると信じられるようになった。
チャーチワードの著書
伝説の大陸レムリアをムーとよび、世界的にその名を知らしめたのは、イギリスの元陸軍大佐チャーチワード(1852~1936)である。彼は、19世紀後半にインドに駐留したおり、現地のヒンドゥー教の僧院長からナーカルというマヤの古代言語でしるされた碑板があることをおしえられ、その内容を解読して1926年に「失われた大陸ムー、人間の母国」という著書にまとめた。同書は世界的なベストセラーとなり、その後も彼によるムー大陸関係の本が続々と刊行された。
ムー大陸の概要
チャーチワードによれば、この大陸の大きさは東西約8000~9000km、南北約5000kmにおよび、人類は今から約20万年前にここで誕生した。そしてやがて高度に発達した文明を誇るようになり、世界各地に植民地をきずいたが、1万2000年ほど前に火山の大噴火による地殻変動で水没し、総人口6400万人のうちほとんどがほろんだ。ただしごく一部の者は生き残り、現在のポリネシア人、ミクロネシア人、メラネシア人の先祖になったほか、ひと握りの植民者はメキシコに移り住み、その末裔がインカ、アステカなどの古代文明を築いたという。
失われた大陸伝説
しかしチャーチワードは、碑板やナーカル語が確かに存在するという証拠を本の中で何も示しておらず、やがてそれらの話がでっちあげだとわかると、ムー大陸に対する世間の興味も下火となった。
とはいえ、大昔の太平洋上に大陸があったという考えは、今も一部で根強く支持されており、謎の巨石像モアイで有名なイースター島はそうした古代大陸の外れに位置していたのではないか、という説も唱えられている。
古代エジプトの歴史
西洋文化の発祥地ともいわれる古代エジプト文明の起源は、現在も明らかにはなっていない。エジプトの第1王朝からプトレマイオス王国の時代までの概要は、前3世紀にプトレマイオスの神官マネトンがエジプトの30の王朝についてしるした「エジプト史」による。古代エジプト史は、アレクサンドロス大王の侵入までを、中間期もまじえて古王国、中王国、新王国の3つに大別し、その後に末期王朝時代とプトレマイオス王国の時代がつづいている。
先王朝・初期王朝時代
ナイル川の氾濫で肥沃な土がもたらされたことで、ナイル川付近には6万年前から人がすんでいたと考えられている。前4000年ごろから、バダーリ、アムラ、ゲルゼなどの文化があり、ゲルゼ期後半の前3200年ごろになると、エジプトの最初の王国が登場した。最古の象形文字もこの時代のもので、記念碑には初期のころの支配者の名がきざまれるようになった。第1王朝から第2王朝までが初期王朝時代として知られ、ピラミッド以前の形である埋葬形態が、サッカラやアビドスなどにみられるようになった。
古王国時代と黄金期
第3王朝から第6王朝までの約5世紀が、古王国時代(前2755~前2255)とよばれている。首都は北部のメンフィスで、国王であるファラオを絶対専制君主とするはじめての中央集権国家ができた。
第3王朝にはじまった文化的黄金期は、第4王朝でそのピークをむかえ、第5、第6王朝へとうけつがれていった。第4王朝初代の王スネフルは、最初のピラミッドをたてた王として知られている。スネフルは商業と採鉱を奨励し、王国に繁栄をもたらした。その子のクフはギーザに巨大なピラミッドをたてた。クフの子レジェデフが太陽を信仰にむすびつけ、神殿が造営された。
技術のすばらしさはピラミッドだけでなく、建築、彫刻、絵画、航海、工芸、科学、天文学など多くの分野で発揮される。メンフィスの天文学者たちがはじめて1年を365日とする太陽暦をつくりだし、この時代の医師たちは、生理学、手術、身体の循環系、消毒についておどろくほどの知識をもっていた。
衰退の始まりと第1中間期
第5王朝は外国との交易やアジアへの侵攻で繁栄していたにもかかわらず、地方長官の力が強くなったため、王権の弱体化がはじまった。第7王朝からは第1中間期とよばれる時代となる。第7、第8王朝はあわせて25年という短期間だが、その間の領土は正確にはつかめていない。このころには、強い権力をもつようになった地方長官が割拠して、各自の地域を統治する分立時代になっていた。
ヘラクレオポリスの第9、第10王朝では、ヘラクレオポリス近くの長官がその地域を統治し、北はメンフィスから南はアシュートまで勢力をのばした。それに敵対するかたちで、テーベ付近の県からでた長官が第11王朝を設立した。第10王朝の末期と、中王国時代の最初とは重なっている。
中王国時代
中央政府のない状態では、それまで力を発揮した宮廷の官僚も意味をなさず、小国に分立して地域間の争いがたえなかった。エジプト美術も地域色がこくなり、宗教は王家のものからしだいに民衆に拡大した。
中王国(前2134~前1784)は第11王朝を最初からふくんでいるものの、正確には前2047年ころにメンチュヘテプ2世(在位、前2061~前2010)が、地方分立と南北に分裂したエジプトを再統一させたときからはじまったともいわれている。メンチュヘテプ2世は50年以上も在位し、たびたび反乱がおこったにもかかわらず、テーベを首都として再統一した王国の安定と支配を維持した。テーベの王のもとで、エジプト文化のルネサンスがおこなわれた。建築・美術・宝石にみられるデザインは繊細で、この時期はエジプト文化の第2の黄金期といわれる。
第2中間期
第13王朝の王たちは、それ以前の王にくらべると力は弱く、次々と王がかわった。第13王朝末期になると、ライバルの第14王朝のほかに、西アジアのヒクソスの侵入にもおびやかされるようになる。王朝の衰退がはじまり、フェニキアやパレスチナから圧迫される中で、異民族のヒクソスが王朝を開いた。これがその後214年間つづいた第2中間期の始まりである。このころ西アジア地域は民族大移動がおきた時期で、この影響がエジプトにまでおよんだ。ヒクソス第15王朝のほかに、中央エジプトには第16王朝が、テーベには第17王朝がたつなど、国内は混乱をきわめた。
しかし、前1576~前1570年に在位したテーベのカモセ国王はヒクソスをやぶり、弟アアフメス1世のときにエジプトは再統一をはたした。 新王国時代と第18王朝 アアフメス1世によってエジプトが再統一されると第18王朝が開かれ、新王国時代(前1570~前1070)がはじまった。アアフメスは軍の支持をえて、地方長官との力関係のバランスをとりながら中王国時代の国境や官僚制をたてなおし、土地開拓計画を再開、建築・芸術の復興をはかった。
前1551~前1524年に在位したアメンヘテプ1世は、ヌビアやパレスチナまで領土を拡大した。アメン神への信仰が強かったトトメス1世は、王家の谷にみずからの墓をつくった最初の王である。彼の子のトトメス2世は、王女ハトシェプストと結婚して王位をつぎ、前1504年に2世が死ぬと、後継者であるトトメス3世はまだ子供だったので、ハトシェプストが摂政として政治をおこなった。1年もたたないうちに、彼女は自分をファラオとし、息子と2人で国を統治するようになる。前1483年にハトシェプストが死に、トトメス3世の単独政権になると、彼はシリアとパレスチナに侵入し、領土を広げて帝国をきずいた。 アメンヘテプ3世は、外交政策で近隣諸国とのバランスをたもち、前1386~前1349年の約40年間を統治した。その子のイクナートン(アメンヘテプ4世)は、アメン神官とあらそってテーベを首都とすることをこばみ、彼が信仰した一神教のアテン神の都としてアケトアテン(現テル・エルアマルナ)を新首都とした。しかし宗教改革は挫折し、養子のツタンカーメンがふたたび首都をテーベにもどす。ツタンカーメンは今日、1922年にイギリスの考古学者カーターとカーナーヴォン卿が王家の谷でみつけた豪華な墓で知られる。
ラメセス朝時代と第3中間期
第19王朝を創立したラメセス1世は、前1293~前1291年のわずか2年間しか在位しなかったが、その後は彼の子孫たちが後をつぎ、エジプトは周辺諸国に侵攻して領土を拡大した。しかし、第20王朝の2代目国王ラメセス3世が没すると、アメン神官や傭兵の力が強くなり、新王国は衰退していく。
第21~第24王朝は第3中間期で、第21王朝はタニスでおこったが、国王たちはリビア人の血をひいていると考えられる。ついでリビア人の将軍が即位して第22王朝がはじまったが、エジプトの情勢は官僚の汚職、神官への富の集中、傭兵の増大などで国内に多くの反発が生まれた。その結果、国力は衰退し、第23王朝と第24王朝は第22王朝と同時期に発生し、第22王朝と第24王朝の末期に第25王朝があらわれた。
第25~第31王朝は末期王朝時代といわれる。前767年からエチオピアのクシュト人がエジプトを支配したが、前671年にアッシリアにおわれた。エジプト人の支配は第26王朝に復活したが、前525年にエジプトの王がカンビュセス2世にやぶれると、その後の第27王朝はペルシアの支配となる。エジプトは第28、第29王朝が独立を維持したが、第30王朝がエジプト人による最後の支配となった。マネトンの年代記にはのっていないものの、次の第31王朝は2度目のペルシア支配の時代である。 ヘレニズムとローマ時代 前332年のアレクサンドロス大王によるエジプト征服で、エジプトに対するペルシア支配がおわった。アレクサンドロスはエジプト在住のギリシア人クレオメネスと、のちにプトレマイオス1世として知られるようになるマケドニアの将軍に太守として統治するよう命じる。2人のエジプト人も任命されたものの、権力はプトレマイオスがにぎり、2~3年で彼の独裁体制になった。
プトレマイオス王国
前323年のアレクサンドロス大王の死後、プトレマイオスはほかの将軍との勢力争いにうちかって、前305年にはみずからの名をつけた王国を建国した(→ プトレマイオス王国)。この王国は、経済改革や東西交易の振興などで力をつけ、ヘレニズム世界の大国のひとつとなり、シリア、小アジア、キプロスなど多くの国に勢力を拡大した。
プトレマイオス王国のもとで首都のアレクサンドリアは国際都市として繁栄し、朝廷は豪奢(ごうしゃ)をきわめた。しかし王国の領土は少しずつローマにうばわれ、クレオパトラが最後の統治者となる。王朝の権威を維持するために、彼女は最初はカエサルと、のちにアントニウスと手をむすんだが、それは終焉(しゅうえん)をおくらせたにすぎなかった。彼女の軍がオクタウィアヌス(のちの皇帝アウグストゥス)ひきいるローマ軍にやぶれると、前30年にクレオパトラは自殺し、古代エジプトの王朝はおわった。
メソポタミア Mesopotamia
メソポタミアとはギリシア語で「河の間」を意味し、ティグリス、ユーフラテス両河にはさまれた、現在のイラクとシリア東部の地域をさす。前4千年世紀末この地で世界最古の都市文明が誕生し、その後多くの文明が興亡をくりかえした。
トルコからながれでる全長1850kmのティグリス、全長2800kmのユーフラテス両河は、水源近くでは約400kmの間隔をおいて南東方向にながれ、ペルシア湾の手前200kmほどで合流し、以後はシャット・アルアラブ川となる。川筋や平原は毎年一定の時期に洪水になりやすく、北部や東部は丘陵地帯、西側は砂漠や乾燥した草原地帯、ステップとなっている。肥沃(ひよく)なメソポタミアの地は近隣諸民族の標的となり、流入や侵略がくりかえされた。この地域の大部分は一時期をのぞき年間を通じては雨にとぼしいが、用水路によって灌漑(かんがい)されると、肥えた土地は豊かな作物をもたらした。南部ではナツメヤシがそだち、食物、繊維、木材、飼料を供給した。両河では魚が、南部の沼地では水鳥がとれた。このようなめぐまれた自然を背景としてメソポタミア文明は誕生、発展した。
メソポタミアの初期国家
古代のメソポタミア南部では、土地を灌漑するために用水路網を整備することと、他民族の侵入をふせぐために城壁をもった居住区が必要だった。人々の居住は前6000年ごろからはじまり、前4千年紀には都市に成長した。この地域での最古の居住地はエリドゥとされ、都市としてのもっともよい例はウルクにみられる。そこでは日干しレンガで神殿がたてられ、金属や石材の加工がおこなわれ、また行政的な必要から楔形文字が発明された。この初期の都市文明はシュメール人)によってきずかれ、しだいにユーフラテス川北部へとひろがっていった。主要なシュメールの都市には、上記2都市のほかにアダブ、キシュ、ニップール、ウルなどがある。 前2350年ごろ、この地域はメソポタミア中央部からきたセム系のアッカド人に征服され、サルゴン(在位、前2350頃~前2295頃)がアッカド王朝をひらいた。この時代にはアッカド語がシュメール語にかわって主流になった。しかし、前2218年に東部の山岳民族グティ人がアッカド人の支配をおわらせ、その後しばらくしてシュメール人のウル第3王朝がメソポタミアの大半を支配した。この王朝において、シュメール人の伝統的な文化は最後の花をひらく。
前2000年ごろ、ウルの町はイラン南西部から侵入してきたエラム人によって破壊された。ほかのシュメール都市はことなるいくつかの民族に支配され、どの都市国家もメソポタミア全体を支配するにはいたらなかった。その後バビロンのハンムラピ(在位、前1792~前1750)が治世の晩年に国土を統一したが、まもなく小アジアにおこった新興勢力のヒッタイトに略奪され、前1595年ごろ、バビロンは陥落した。その後の4世紀間、バビロンは非セム系のカッシートの支配をうけた。いっぽう北部のアッシュールでは、カフカス方面からきたフルリ人がミタンニ王国をおこした。フルリ人はアルメニア人に近いとされ、メソポタミアに何世紀も前からすんでいたが、前1700年以降は北部メソポタミアからアナトリアにまでひろがった。
アッシリア、カルデア帝国
北部メソポタミアのアッシリア王国は前1350年ごろから勢力を拡大しはじめた。ミタンニをやぶり、バビロンを征服し(前1225頃)、地中海にまで領土はひろがった(前1100頃)。ところが、シリアのステップからあらわれたアラム人がアッシリアの拡大をとめ、その後2世紀にわたって、民族的に近いカルデア人とともにバビロニアを支配した。アッシリアは防衛のためにこれらの勢力とたたかって侵入をゆるさず、前910年以後ふたたび勢力は拡大した。最盛期のティグラトピレセル3世のときには、エジプトからペルシア湾までの中東を支配する世界帝国となった(前730頃~前650頃)。
アッシリアは、征服した土地の住民をアッシリア本土に移住させ、あとにはほかの地域の住民をいれるなどして支配を強化した。それは結果的には帝国全土にわたって人種の融合をすすめることになった。また、たび重なる反乱に対処するため、強力な軍隊機構がつくられた。しかし、広大な国土を長い間維持しつづけることはできなかった。国内でイラン系のメディア人やバビロニアのカルデア人が勢力を拡大し、前612年にアッシリアはこれらの勢力によって内部から崩壊した。帝国の領土は2つにわけられ、山岳地方はメディア人が領有し、メソポタミアはネブカドネザル2世ひきいるカルデア人が領有した(新バビロニア)。ユダ王国を征服した前586年には、住民を強制的にバビロニアに移住させている(バビロンの捕囚)。いっぽうカルデア人は前539年までメソポタミアを支配したが、キュロス2世ひきいるペルシアがバビロンを攻略し、メディア王国もほろぼした。
ペルシアの支配
ペルシア帝国(アケメネス朝)のもとで、メソポタミアのバビロンやアッシュールにサトラップ(地方総督)がおかれた。バビロンは首都ではなかったが、帝国内で重要な役割をもっていた。ひろく話されていたアラム語が共通語となり、帝国は行政的にも安定、東方とも商取り引きをおこない、繁栄をほこった。しかしペルシアの支配の仕方は基本的には圧政だったので、治世は長くはつづかなかった。
シュメール Sumer
古代バビロニアの中・南部をさす地名で、現代のイラク南部にほぼ相当する。前3千年紀初期には、シュメール語でキエンギ(ル)、アッカド語でシュメールとよばれた。シュメールという語は同時に、世界最古といわれるこの地でさかえた文明や、その文明をつくりあげた民族や言語もさす。初期のシュメールの歴史は、後世の粘土板の神話的な記述にみることができるが、碑文などの考古学的な証拠をともなって具体的に王の実在などを証明できるのは、ほぼ前2500年以後である。 この地には、ウバイド人が前5千年紀に定住しはじめた。彼らの文明はしだいに発展し、ウル、ウルク、ラガシュ、アダブ、エルドゥ、キシュ、ニップールといったシュメールの主要な都市の原型をつくりあげた。ついで数世紀後に、シリアやアラビアの砂漠からセム系の人々が流入しはじめた。
さらに前3250年ごろ、別の民族が移りすみ、先住民とまざりあった。シュメール人として知られるようになるこの人々は、系統が不明な膠着語をはなし、また民族的にも不明な点が多く、彼らがどこからやってきたかについても定説はない。しかし、メソポタミア北部からきたとする説が有力である。シュメール人が移りすんだあと、国土はいっそう豊かになって都市が発達し、芸術や建築、工芸品のほか、宗教的、倫理的な思想も発達した。シュメール語がひろくはなされるようになり、人々は楔形文字をつかって粘土板に文字を書いた。楔形文字はその後2000年にわたって中東地域で使用されることになる。
初期王朝期
粘土板の記録によると、シュメールの最初の支配者は都市国家キシュの王エタナ(前2800頃活躍)で、記録には、「すべての土地を安定させた男」と記されている。彼の治世がおわるとすぐに、メスキアガシェが、キシュよりもずっと南のウルク(聖書ではエレク)に、対抗する王朝を創立した。メスキアガシェは領土を拡大させ、地中海から現イラン西部のザーグロス山脈までの地域を支配したとつたえられている。その息子エンメルカル(前2750頃活躍)は、メソポタミア北東部にあった都市国家アラッタまではるばる遠征した。エンメルカルのあとは将軍のルガルバンダがついだ。エンメルカルおよびルガルバンダの業績や征服物語は、一連の叙事詩の主題となり、初期シュメールの歴史を知るうえで重要な資料となっている。
ルガルバンダの支配がおわると、キシュのエタナ王朝エンメバラゲシ(前2700頃活躍)がシュメールの支配者となった。彼の重要な功績は東のエラム国に勝利したこと、ニップールにシュメールの主神エンリルの神殿をたてたことである。これによってニップールはしだいにシュメールの宗教的、文化的な中心となっていった。エンメバラゲシの子アガ(前2650頃没)は、ウルの王メスアネパダ(前2670頃活躍)にやぶれ、エタナ王朝最後の王となった。
ウルの王メスアネパダは、いわゆるウル第1王朝の創始者で、ウルをシュメールの首都の地位におしあげた。メスアネパダの死後まもなく、ギルガメシュ(前2700頃~前2650頃活躍)のもとでウルの近くにあった都市国家ウルクが政治的な主導権をにぎった。ギルガメシュの活躍は、人類最古の叙事詩とされる「ギルガメシュ叙事詩」など、多くの物語や伝説になっている。 前2500年直前のシュメール国家は、アダブの王ルガルアンネムンド(前2525頃~前2500頃活躍)のもとで領土をひろげ、ザーグロス山脈からタウロス(トロス)山脈まで、そしてペルシア湾から地中海までを支配下においた。その後、帝国はキシュの王メシリム(前2500頃活躍)によって支配されたが、彼の死後シュメールは衰退しはじめ、都市国家どうしで互いにはげしい戦争にあけくれた。ラガシュの支配者エアンナトゥム(前2425頃活躍)はシュメール全土をまとめ、さらに近隣諸国も領土にくみいれたが、統治期間は長くなかった。彼の何人かの後継者のあと、王位についたウルカギナ(前2365頃活躍)は、多くの社会改革を実施したことで知られている。しかし、隣の都市国家ウンマの支配者ルガルザゲシ(在位、前2370頃~前2347頃)にやぶれ、その後20年間は、ルガルザゲシがもっとも強力な支配者となった。
これらの都市国家には、大工・陶工・金細工人・鍛冶工・毛織職人などの専門技術者がいて、肥沃(ひよく)な土地では農業・牧畜業が発達、住民の暮らしは豊かだった。すでにビールがつくられていたことも知られている。 全体としてシュメールの力が弱まり、多民族の侵略を食いとめることができなくなっていたところへ、セム人の指導者サルゴン(在位、前2335頃~前2279頃)が、メソポタミア南部をすべて征服し、北部のアガデを首都にえらんだ。シュメール北部にすんでいた人々と、征服者であるセム人はしだいにまざりあってアッカドとよばれるようになり、この地方の呼名も、シュメールからシュメール・アッカドになった。
ウル第3王朝
アッカド王朝は約1世紀つづいた。国王は「四方世界の王」とよばれ、ひろく世界貿易にのりだした。サルゴンの孫ナラムシン(在位、前2255頃~前2218頃)の時代に、ザーグロス山脈の好戦的な民族グティ人がアガデの町を破壊し、シュメール全土を征服した。数世代のちにシュメール人はグティ人の束縛をのがれ、都市国家ラガシュが、グデア王の治世によってふたたび勢力を回復した(在位、前2144頃~前2124頃)。グデアは敬虔(けいけん)で、有能な王として知られ、数多く発掘されている彫像によって、シュメール人の中で今日もっともよく知られた存在となっている。シュメール人がグティ人の支配を完全に脱したのは、ウルクの王ウトゥヘガル(在位、前2120頃~前2112頃)がグティ人をうちやぶったときで、その功績はのちのシュメール文学の中でたたえられている。
ウトゥヘガルの将軍だったウルナンム(在位、前2113~前2095)がウル第3王朝の創始者となった。有能な軍人であると同時に社会改革者でもあったウルナンムは、法典をつくったことでも知られる。ウルナンム法典は、有名なバビロニアのハンムラピ王の法典より3世紀前のもので、知られているかぎり世界最古の法典である。ウルナンムの子シュルギは、やはりすぐれた軍人であると同時に外交にもたけ、文学の擁護者でもあった。彼の治世下、王立の学校は重要な役割をはたした。 前2千年紀の初めごろ、西部の砂漠からきたセム系遊牧民のアモリ人が、王国に侵入し、しだいにイシンやラルサといった重要な都市の支配者層になっていった。その結果、政治的な崩壊や混乱が国内にひろがり、東方のエラム人がウルの町を攻撃し(前2004頃)、ウル第3王朝の最後の王イビシン(在位、前2029~前2004)を捕虜としてつれさる事態まで発生した。
ウル第3王朝崩壊後は、シュメール・アッカド地方の支配をめぐり都市国家どうしの戦いがはじまった。初期にはイシンとラルサの間で、のちにはラルサとバビロンの間で戦いはくりひろげられたが、バビロンのハンムラピ王が前1763年にラルサのリムシンをやぶり、シュメール・アッカドの単独の支配者となった。これをもってシュメール人国家はなくなるが、彼らの文明はほぼ完全にバビロニア人にうけつがれた。
考古学
シュメールの最初の発見となるおもな発掘は、1842年から54年にかけてアッシリア地域のニネベ、ドゥル・シャルキンなどで、フランスの考古学者ボッタやイギリスの考古学者レヤードらによっておこなわれた。前1千年紀の何千枚もの粘土板が発見されたが、その大部分はアッカド語で書かれていた。このため学者たちは最初、メソポタミアのすべての楔形文字はアッカド語で書かれていると考えた。
しかしイギリスの言語解読学者ローリンソンやアイルランドの牧師ヒンクスは、粘土板の文字を研究した結果、その中のあるものはセム系でない言語であることを発見した。1869年フランス人考古学者オッペールは、たくさんの記述の中にみられる「シュメールとアッカドの王」という王の称号から、「シュメール」という名前を提案し、これを言語にも適用した。
19世紀末から、ラガシュではフランス、ニップールではアメリカによる継続的な発掘がはじまり、そのほかキシュ、アダブ、ウルク、エリドゥ、ウルなどのシュメール都市の発掘もおこなわれた。考古学者たちは各地で貴重な土器や、多数の粘土板を発見し、さらにアッカドのサルゴン王の王宮や、前3千年紀から前550年にいたる多くの遺跡を発掘している。
アッシリア Assyria
西アジアの古代国家で、前8世紀ごろ最盛期をむかえ、広大な帝国をつくりあげた。現イラクの北部国境と、ティグリス川、小ザブ川の合流点あたりから、三日月形にのびる広大な領土を保有した。東部にはティグリス川の肥沃な河谷があり農業に適しているが、西部は乾燥した原野がつづく。東端にはザーグロス山脈が位置し、北部はメソポタミア平原がアルメニア山塊へとせりあがっていく。南部はティグリス、ユーフラテス両川地帯で、最初はシュメール、次にシュメール・アッカド、のちにはバビロニアとよばれた。
アッシリアのよく知られた都市には、アッシュール(現カルア・シルカ)、ニネベ(現在発掘されているクユンジュクの丘)、カルフ(現ニムルド)、ドゥル・シャッルキン(現コルサバード)などで、いずれも今日のイラクに属している。
勢力の拡大と一時的な衰退
前1810年ごろ、アッシリア王のシャムシアダド1世(在位、前1813~前1781)は、アッシリアの領土をザーグロス山脈から地中海にいたるまでに拡大した。シャムシアダドは、おそらく古代中東世界における最初の中央集権的な帝国の支配者だった。彼は王国をいくつかの地域にわけ、特別に任命された行政官や顧問団にまかせたほか、連絡のために駅伝の制度をもうけ、さらに定期的な人口調査もおこなった。しかし最初のアッシリア帝国は長続きせず、シャムシアダドの息子イシュメダガンはバビロニアのハンムラピ王にやぶれ(前1760頃)、アッシリアはバビロニア帝国の一部となった。
バビロニア帝国は2世紀ほどで衰退し、前16世紀、非セム系のカッシート人がバビロニアに侵入し、政治的な力をもった。いっぽう、別の非セム系山岳民族フルリ人は、メソポタミア北部全域に侵入し、彼らはさらにパレスチナにまで達した。また、別のインド・ヨーロッパ系の民族がフルリ人に混じってあらわれたとされるが、彼らの名は知られていない。このような民族の複雑な動きのため、前16世紀のメソポタミアの歴史は混沌としている。
前1500年ごろのアッシリアは、ミタンニ王国の属国になった。当時のミタンニは、北部メソポタミア全域を支配する帝国規模の国家だった。アッシリアは前14世紀初めまでミタンニの支配下にあったが、北部で勃興(ぼっこう)してきたヒッタイトによってミタンニが敗北すると、その混乱を利用してアッシリア王アッシュールウバリト1世(在位、前1365~前1330)が、ミタンニの支配をのがれ、逆にその領土を併合した。
アッシュールウバリト1世のあと、アダドニラリ1世(在位、前1307~前1275)、シャルマネセル1世(在位、前1275~前1244)、トゥクルティニヌルタ1世(在位、前1244~前1208)といった強力な支配者がつづき、アッシリアの領土はひろがり、エジプト、バビロニア、ヒッタイトとならぶ強国となった。
戦う帝国
前1200年ごろ、新たな民族移動の動きが西アジアの様相を一変させた。「海の民」とよばれる雑多な民族集団がバルカン半島付近からあらわれ、アナトリアのヒッタイト帝国を崩壊させ、シリアやパレスチナに流入した。アッシリアの北西部は、ムシュキとよばれるインド・ヨーロッパ系の民族があらわれ、アッシリアの脅威となっていた。また西部ではセム系の遊牧集団アラム人の動きも活発化していた。アッシリアはこのような新たな外敵の攻撃や圧力に対して盛んに抵抗し、この生存をかけたはげしい戦闘の中から、残酷さで悪名高い軍隊「戦争機械」をうみだし、中東地域全体の恐怖の的となった。これが「前12世紀の危機」と呼ばれるものである。
ティグラトピレセル1世(在位、前1115~前1077)は、アラム人やムシュキから国境を防衛するために、はるか北のウラルトゥ国の支配下にあったワン湖付近や、西のパルミュラまで侵入した。たいていの場合、侵入された地域の人々はアッシリア軍が近づくとすぐ逃走したが、のこった人々は皆殺しにされるか、捕虜としてアッシリアへつれていかれた。アッシリア軍の目的は侵入した地域を併合することではなく、町や村を略奪し、破壊することにあった。しかしやがて、彼らの征服の仕方は変化し、征服した土地を領土にくみいれ、それによってできる新しい領土国家の中心にアッシリアをおくようになった。
アッシリア支配の拡大
アッシュールナシルパル2世(在位、前883~前859)は、アッシリアの領土を北方および東方にひろげ、戦いにつぐ戦いの中で、帝国に隣接する地方を荒廃させた。しかし、北のウラルトゥ、南のバビロニア、西のアラム王国といった力のうわまわる近隣諸国には攻撃をしかけなかった。彼はアッシュールにかわる新首都にカルフをえらび、アマヌス山脈からうばいとってきたレバノン杉でカルフの町を再建した。カルフの遺跡からはアッシュールナシルパルの数多くの文書が出土している。
アッシュールナシルパルの子シャルマネセル3世(在位、前858~前824)は、35年の治世中に32回の戦いをおこなった。そのほとんどはユーフラテス川の西の地方、とくに強力なアラム王国に対するもので、いくつかの戦いには勝利し、イスラエルなど、アラム王国の同盟国からかなりの貢税をえた。現在、大英博物館にあるシャルマネセルの2つの記念碑はとくに注目に値する。ひとつは、イスラエルの王が彼の足に口づけする姿をえがいた「黒いオベリスク」、もうひとつは「バラワトの門」として有名な青銅製の額である。
世界帝国の誕生
シャルマネセルの治世の末期、宮廷で争いがおき、数年間にわたって内戦がつづいた結果、アッシリアの力は数十年にわたって衰退し、多くの領土をうしなった。しかし前744年にティグラトピレセル3世が王位につき、アッシリアを世界帝国へと発展させる動きがはじまった。彼はおもに被征服国や属州から集めた人々からなる常備軍をつくり、征服した民族をアッシリア領内に移住させ、民族として結束することや、民族意識をとりもどすことを封じた。
ティグラトピレセルの後継者シャルマネセル5世の次に王位についたサルゴン2世(在位、前721~前705)は、帝国の領土をさらに拡大し、その支配地域はアナトリア南部からペルシア湾にまでいたった。彼は治世の始めにイスラエル王国を属州とし、ついでウラルトゥとメディア王国を攻撃、シリアやアナトリア南部のひろい地域を併合しただけでなく、ティグリス河谷中央部のアラム人やユーフラテス河谷下流部のカルデア人をうちやぶった。
エジプトとの国境からザーグロス山脈まで、そしてタウロス山脈からペルシア湾にいたる広大な帝国を効果的に支配するために、国内を70の地域にわけて王に直属する知事をおき、首都カルフでは中央集権体制をつくりあげた。治世の晩年には新首都ドゥル・シャッルキン(サルゴン城の意)を建造し、王宮を印象的な浅浮彫でかざった。またニネベに図書館をたてたほか、彼の治世で交易や農業は大いに発展した。
センナヘリブ(在位、前704~前681)は、父サルゴン2世が征服した領土を維持しただけでなく、エジプト国境にせめこむこともあった。父と同様、センナヘリブも首都をかえ、ドゥル・シャッルキンからニネベにうつし、そこに王宮をたてた。バビロニアがふたたび勢力を回復してくると、聖なる古都バビロンを完全に破壊し、水路をほって町を水浸しにした。
しかし彼の息子エサルハドン(在位、前680~前669)は、バビロンに対して好意的で、その再建をたすけた。エサルハドンのおもな軍事的な功績は、エジプトの国境をこえ、首都メンフィスを攻略したことである。その子アッシュールバニパル(在位、前668~前627)はエジプトとの戦いをつづけ、さらに南下してテーベまで侵入した。また、東のエラム王国に対しては首都スーサの略奪もおこなった。アッシュールバニパルは、征服者としての名声とは別に、ニネベに大図書館を築き、数多くの粘土板文書をあつめたことでよく知られている。
アッシリアの文化と習慣
アッシリアの文化は多くの点でバビロニアのものと似ている。たとえば、アッシリアの文学は、王の年譜をのぞけば、実質的にバビロニアのものと同一であり、文字もバビロニアの楔形文字をわずかにかえたにすぎない。アッシュールバニパル王をはじめ、アッシリアの教養ある王たちは、バビロニア文学の写本を数多く図書館に所蔵することを誇りにしていた。アッシリア人は、美術や建築の分野においてすぐれた能力を発揮した。社会や家庭、結婚の習慣、財産に関する法律などもバビロニアのものと似ており、これまでにみつかっている3つのアッシリアの法律集も、すべてシュメールとバビロニアの法律に似ている。ただしアッシリアの法律では、罪人に対する罰はもっと残忍で、野蛮であった。
帝国の終焉
前627年にアッシュールバニパルが死去すると、広大な帝国を維持していくことが困難となり、また宮廷内で内紛もおき、力は急速に弱まった。そして、メディア人とバビロニア人によって、前614年にアッシュールを、前612年にはニネベも攻略された。アッシリア帝国最後の王アッシュールウバリト2世は、首都ニネベから北西方向にはなれたハランの地まで後退したが、この敗北がアッシリア帝国の実質的な最後となり、帝国は新バビロニア、メディア、リュディア、エジプト第26王朝の4国に分裂した。
アケメネス朝ペルシア
アッシリア帝国の崩壊後は、新バビロニア、メディア、リュディア、エジプト第26王朝の四国分立していた。メディアに服属していたペルシアは、前553年から前550年の対メディア戦争で、メディア国内で王と貴族が対立している隙をつき、メディア貴族の王に対する裏切り行為によって勝利する。当時最強といわれたメディアの軍隊を手に入れたペルシアは、キュロス2世の元、前547年にリュディア、前539年に新バビロニア、前525年にエジプトと次々に征服していった。その支配領域はアッシリアのおよそ六倍に当たる。
ペルシア帝国では、それぞれの国を支配するにあたってそれぞれの国での手続き、儀式により王となった。「王の道」と呼ばれる交通路を整備し、地方行政もそれぞれの州にサトラプと呼ばれる総督を置き、行政、治安、裁判を行なわせ、州召集軍の指揮権、徴税権、貨幣鋳造権(金貨を除く)などの特権も与えた。さらに「王の目」と呼ばれる中央の高級官僚を地方へ巡察に行かせたり、「王の耳」と呼ばれるスパイを地方に配置したりした。また、地方官庁には王室の書記を配置し、地方守備隊やその隊長は王に直属した。
ペルシア帝国支配の特徴は、二重構造にあり、軍事的には、王の親衛隊、一万人部隊、歩兵隊、騎兵隊などのペルシア軍と、歩兵、騎兵、戦車兵などの陸軍とエジプト、フェニキアなどの海軍からなる民族召集軍に分かれ、政治的には、ペルシア帝国の王として帝国を支配しながらも、各国の旧支配体制を利用し、従属民族内部の問題や伝統に干渉したりせず、征服した民族の慣例にしたがって各国を支配した。
しかし、ペルシア戦争をはじめとするギリシアとの長い戦争、ついで新しく台頭してきたマケドニアとの戦いなどで国力はおとろえ、アレクサンドロス大王の遠征軍にやぶれて、アケメネス朝は第5代ダレイオス3世の死(前330)をもっておわった。
アトランティス Atlantis
古代の伝説の島。かつてギリシア人が「ヘラクレスの柱」とよんでいたジブラルタル海峡のはるか西方のアトランティス海(大西洋)にあったという。記録にのこる最初の記述は、地震の結果、大西洋にのみこまれたというもので、プラトンの2つの対話編「ティマイオス」と「クリティアス」にあらわれる。
「ティマイオス」では、アテネの政治家で詩人でもあったソロンがエジプトを旅行したときに、土地の神官が彼に古い記録をかたる。神官によれば、アトランティスは小アジアとリビアをあわせたよりも大きく、当時のおよそ9000年前、そこを中心に文明が繁栄しており、アテネ人をのぞくすべての地中海の人々を征服していたという。「クリティアス」では、アトランティスの歴史がかたられ、この国を理想の国家として賞賛している。アトランティスはプラトンの創作といわれているが、当時の伝説をもとにえがいた可能性ものこっている。
アトランティスのようにうしなわれた島がかつては繁栄していたという伝説は、人々をつねに魅了し想像力をかきたて、存続しつづけた。20世紀には研究がすすみ、かつてエーゲ海にあり、前1500年ごろの火山噴火によってうずまってしまったサントリニ島をアトランティスとする海洋学者もでた。また、考古学的発見にもとづく理論などによって、クレタ島、カナリア諸島、スカンジナビア半島、あるいはアメリカ大陸などとする説もある。
インダス文明 Indus Valley Civilization
前2300~前1700年ごろインダス川流域を中心にさかえたインドの古代文明。エジプト文明、メソポタミア文明、中国文明とともに古代の4大文明にかぞえられる。1920年代初頭、ハラッパーがサハニにより、ついでモヘンジョ・ダロがバネルジーによって発見され、この文明の存在が明らかになった。その後、各地で発掘調査され、現在までこの文明の遺跡が大小300ほどみつかっている。遺跡は、パキスタンのインダス川流域を中心に、西は海岸沿いにイラン国境まで、東はニューデリーにいたるまでのインド北西地域、そして北アフガニスタンのオクサス川流域までひろがっている。
発掘された遺跡をみると、日干し煉瓦の建物の小規模な村落遺跡が多い。モヘンジョ・ダロやハラッパーのような大都市では、焼成煉瓦造りの建物が道路によって区画されており、大きな公共の建物も多く計画性がみとめられる。大都市の広さは1km2にみたないが、市街地区と城塞(じょうさい)地区に2分され、城塞の周囲を壁がめぐっている。
インダス文明は、高度な工芸技術をもっていた。赤地で黒色彩文の土器、車など土製の玩具、人間あるいは神をかたどった彫像、紅玉髄製の数珠(じゅず)玉、青銅・金・銀など貴金属の装飾品、道具類といったものである。表にドラビダ語の特徴をもつインダス文字や一角獣・牛・サイなどを陰刻した印章も多数出土している。しかしインダス文字が未解読なこともあって、この高度な文化をもっていた人々の社会がどのようなものだったかほとんどわかっていない。
前2000年をすぎて間もなく、生態系の変化や異常隆起がインダス川流域でおこり、洪水や流路変更で人々は多くの村落をすてなければならなかった。そのため大都市を中心にきずかれてきた文明の基盤がくずれてしまい、前1700年ごろには活力をうしなった。衰退要因には、このほかにもメソポタミアとの交易の途絶などがあったと考えられる。
十六大国 じゅうろくたいこく
初期の仏典にしるされた、仏陀とほぼ同時期、前6~前5世紀初めのインドの地域国家(マハージャナパダ)の総称。列記されている仏典によって国名や存在した時期にわずかながら違いがあるが、アンガ、マガダ、カーシ、コーサラ、ブリジ、マッラ、チェーティ、バツァ、クル、パンチャーラ、マツヤ、シューラセーナ、アシュマカ、アバンティ、ガンダーラ、カンボージャの16カ国をかぞえる。
ガンダーラ、カンボージャの2国はインド北西からパキスタンにかけての地域、アシュマカがデカン高原西部にあたるほかは、ほとんどがガンガー流域およびその近隣の国家である。
なかでもマガダ、コーサラ、バツァ、アバンティが四大国と称されて強い王権のもとに国力を高め、ブリジ、クル、パンチャーラなどの「ガナ」「サンガ」とよばれる部族共和制国家をしだいに併合していった。
最終的にはマガダ国が北インドを統一し、前3世紀のマウリヤ朝のもとでその勢力を最南部をのぞいたインド亜大陸のほぼ全域におよぼした。首都パータリプトラはその後約1000年にわたって北インド政治の中枢の位置を占めつづけた。
マガダ Magadha
前6~後6世紀に古代インド政治の中心となった地名及び国名。今日のビハール州南部一帯で、水陸交通の要衝の地であり、鉄をはじめとする鉱物資源にもめぐまれていた。前6世紀に十六大国のひとつとして頭角をあらわし、最初の偉大な王ビンビサーラ(在位、前543~前491)と、その子アジャータシャトル(在位、前491~前459)のもとでしだいに勢力を拡大して、前4世紀までには北インドのほぼ全域を支配下におさめた。アレクサンドロス大王とその後継者によって領土の一部だった西北インドの支配は中断したが、前321年にチャンドラグプタがふたたびマガダを征服して、古代インドで最初の統一国家となるマウリヤ朝をおこし、マガダ地方はその中枢を占めた。
マウリヤ朝は前180年ごろに滅亡したが、マガダ地方の政治的重要性はかわることなく、ヒンドゥー教とサンスクリットの古典文化を完成したグプタ朝時代(320頃~550頃)までつづいた。グプタ朝の滅亡後は、政治の中心はマガダ地方からガンガー上流域のカナウジにうつった。その後、パーラ朝の王ダルマパーラ(在位770~810)のもとで一時期政治の表舞台にうかびあがったが、12世紀のイスラム教徒による北インドの征服以降は、デリーを首都とするデリー・サルタナット統治下の単なる一地方となった。
春秋戦国(東周) しゅんじゅうせんごく(とうしゅう)
前770~前221年の、古代中国における周の東遷から秦による中国統一までの時代をいう。
春秋戦国時代とは、「春秋時代」と「戦国時代」の2つの時代をあわせた呼び方である。春秋時代という呼称は、当時の有力諸侯であった魯の役人が当時の国際関係についてしるし孔子が添削したとされる「春秋」という書物からとられた。そのあと、戦国の七雄とよばれる韓・魏・趙・斉・秦・楚・燕の7大国が争覇戦をくりひろげた時代を戦国時代とよび、この時代の記録でもある弁士の遊説をあつめた「戦国策」から命名された。
春秋と戦国をどこでわけるかについて、現在では、大国だった晋が3つの国(韓・魏・趙)に分裂した前403年までを春秋時代、以後、秦によって統一される前221年までを戦国時代とよぶことが多い。
また、春秋・戦国をあわせて東周時代とよぶことがある。これは以下で述べるように、当時の周が西の都であった宗周をうしない、東の都、成周に移った事に由来する。
前771年、周王朝の西の都、宗周は、北方から侵入してきた犬戎によって陥落した。周の幽王は犬戎に殺され、王朝の生き残りの人々は東の都、成周へとおちのびた。
翌年の前770年、幽王の子が平王として成周で即位するが、これ以降、権威の失墜した周王は形だけの存在となり、各地の諸侯は自国の利益によって行動し、互いに侵略戦争をくりひろげた。
西周時代、黄河流域には無数の小国家が乱立し、その数千余国とつたえられる。春秋時代にかなり減ったが、それでも百余りはあったという。その中で比較的大きな国は晋(のちに韓・魏・趙に分裂)・斉・秦・楚・燕・魯・衛・曹・宋・陳・蔡・鄭・呉・越だった。
春秋時代には、堕ちたとはいえ周王室の権威はまだ残っており、諸侯は周王に対して臣下の形式をとった。諸侯があつまって誓いをたてる会盟に際しては、周王室を異民族からまもることが重要な名目の一つとなっていた。しかし、戦国時代になると周王室の権威は失われ、小国は次々と大国に併合され、勝ち残った戦国の七雄は、それぞれの存亡をかけてたがいに侵略をくりかえした。
家柄と儀礼によって機能していた西周時代以来の社会システムは完全に崩壊した。実力主義にもとづく下剋上は当たり前となり、君主は、富国強兵や外交交渉に必要な人材を家柄に関係なく才人にもとめた。戦国時代とは、このような実力第一主義の世界だった。
また、諸侯が富国強兵策につとめた結果、産業が発展し、とくに農業では鉄製農具がつかわれはじめ、牛耕農法とあいまって、生産力が急速に高まった。交換経済が発達して、各国はさまざまな貨幣を発行するようになった。商品の集散地は都市として発展し、巨富を蓄える大商人もあらわれるようになった。
さらに、君主たちは、より強い国家をもとめつづけた。そのため政治哲学が重視され、さまざまな思想家が輩出、「諸子百家」と称される思想界の黄金時代となった。儒家の孔子・孟子・荀子、道家の老子・荘子、墨家の墨子、法家の商鞅・韓非、兵家の孫武・孫ピン・呉起、縦横家の蘇秦・張儀など、今に伝わる多くの思想家が活躍した。
これまでの定説では最初のアメリカ人は、大型の動物を追う狩猟民で、1万4000年ほど前にアジアからベーリング陸橋を渡って北米に到達し、動物を追っていく形で南北アメリカ大陸各地に拡散したと考えられていた。
しかし、上の図にあるように従来の内陸ルート説のほかに現在では沿岸ルート説という仮設が出されている。沿岸ルート説とは、今から約1万7000年前、氷河が溶けると、北太平洋の沿岸部の所々に氷に覆われていない土地が現れた。その土地を拠点としながら海岸線沿いに移動を続け、やがて北米大陸に到達したのでは、と言う説である。
この他に、太平洋横断ルートや初期ヨーロッパ人が渡っていた(大西洋横断ルートと北の氷床ルート)という仮設も出されている。また、それぞれのルートは一方通行ではなく、行き来していた可能性もあり、何万年もの間に様々な場所から何度も移住者の群れが押し寄せていたとも考えられている。
オルメカ Olmec
メソアメリカ最古といわれる都市文化をきずいた先住民族集団。メキシコ湾岸、現在のメキシコのベラクルス州からタバスコ州にかけての熱帯湿地に居住していた。その文化的影響はしだいにひろがり、アナワクの名で知られるメキシコ中央高原、メキシコ盆地、オアハカ地方、さらに西方のゲレロ地方にまでおよんだ。
オルメカ文化は前1200~前300年にかけて繁栄し、最古の中心地サン・ロレンソは神事・祭事の場である中心部を取り囲んで、大量の盛り土をして築かれた。大宗教センターとして繁栄したが、前900年ごろに破壊されている。サン・ロレンソにとってかわったラ・ベンタは、一定方向の軸にそって建設された宗教都市だったが、この都市建設パターンはテオティワカンなど、のちのメソアメリカの都市建設に大きな影響をあたえた。ラ・ベンタのピラミッドは盛り土によるもので高さ30m、メソアメリカ最古のもののひとつで、神殿や広場などの中心だったと推定されている。 オルメカはメソアメリカで最初に石材を建築・彫刻に利用した民族集団だが、これらの石材はラ・ベンタの場合、西方へ100kmほどはなれたトゥストラ山系から切りだされたことがわかっている。彼らの石材加工技術の水準をものがたる、サン・ロレンソ出土の高さ2.7mにも達する巨石人頭像などは、現在ほかの遺物とともにメキシコのビヤエルモサ市のタバスコ博物館に展示されている。
オルメカの記述法は、絵文字や数をしめす文字など、メソアメリカ固有の文字体系の先駆的なものである。オルメカ文化は、あらゆる面で、メソアメリカにおけるその後の文化のありかたを規定するパターンを生みだしたといえる。
マヤ Maya
マヤ語系の言語を話す中央アメリカの先住民集団の総称。現在は、メキシコのベラクルス、ユカタン、カンペチェ、タバスコ、チアパスの各州のほか、グアテマラのほぼ全域とベリーズやホンジュラスの一部地域に分布している。もっともよく知られているのがマヤ人であり、おもにユカタン半島にすんでいる。そのほかにはベラクルス州北部のワステカ人、タバスコおよびチアパス州のツェルタル人、チアパス州のチョル人、グアテマラの高地地方のキチェー人、カクチケル人、ポコムチェ人、ポコマン人、グアテマラ東部およびホンジュラス西部のチョルティ人などがいる。ワステカ人だけはやや離れているが、それ以外の人々は隣接した地域にすむ。かつてそこにさかえた古代マヤ文明は、アメリカ大陸でもっとも発達した文明だった。ただし統一王朝は最後まで成立しなかった。
スペイン人が渡来するまでは、トウモロコシを主作物とする農業がマヤ経済の基盤をなしていた。そのほかにはワタ、豆、カボチャ、マニオク(キャッサバ)、カカオなどを栽培していた。犬と七面鳥をかっていたが、荷物をはこぶ家畜はもたず、車輪をもちいた運搬手段はなかった。染色と織物に高度の技術をもち、土器芸術は、ペルーの古代アンデス文明とともに、新大陸で最高の水準にあった。物の交換には、カカオ豆と銅の鈴が貨幣がわりにつかわれていた。銅は装身具にも利用された。金、銀、ヒスイのほか、貝や鳥の羽根も装身具としてもちいられていた。しかし、鉄は利用されなかった。
建築
古代マヤ文明は、すばらしい建築をのこした。パレンケ、ウシュマル、マヤパン、コパン、ティカル、ワシャクトゥン、チチェン・イッツァなどの大遺跡が知られている。その多くは宗教儀式のための巨大なセンターで、広場をかこむようにしてピラミッド建築などが配置されていた。 マヤのピラミッドは何段もの基壇構造をつみかさねたもので、急傾斜の階段がもうけられていた。ピラミッドの内部は土と砂利でできており、漆喰もつかわれた。表面には切り石をはり、化粧漆喰で仕上げがなされることもある。入口の梁の部分には木材がつかわれ、木彫りの彫刻もある。本格的なアーチ構造ではないが、両側の石積み壁の上部を少しずつ張りださせ、天井部分であわせる持ち送り式アーチを採用していた。この方法では壁があつくなり、内部空間もせまくなる。ほとんどの場合、窓もない。建物の外壁は、彩色された彫像、化粧漆喰の像、石彫、石のモザイクなどでかざられた。
一般の人々の家は、アドベ(日干し煉瓦)や木の枝を利用したもので、現在のマヤ社会にみられるような簡単な構造だった。
文字
古代マヤ文明は文字を考案し、人々は石碑や石の階段などに神話や歴史をきざんだ。マヤ文字は石碑だけではなく、樹皮などを利用した折りたたみ形式の本にものこっている。これらは絵文書とよばれ、4冊だけがこんにちまでつたえられている。ドレスデン絵文書、ペレス(パリ)絵文書、トロ・コルテシアノ(マドリード)絵文書、グロリア絵文書である。これらの書物には、農業、狩猟、天候、病、天文などについてかかれており、暦をもとにした占いのためにつかわれていたようだ。
宗教
マヤの人々は多くの神々を信仰していた。一般の人々の儀礼では、とくに雨の神チャクが重要だった。最上位の神は天の神イツァムナーと創造の神ククルカンである。ククルカンはトルテカやアステカの神ケツァルコアトルと関係がある。マヤの宗教でもっとも重要な特徴は、神が時間を支配しているという観念である。さだめられた期間を特定の神が交代で支配し、その神が同じ期間、人々の行動も支配すると考えていた。また、マヤではひじょうに複雑な暦のシステムが発達していた。
歴史
マヤ文明の形成期は前1500年ごろにさかのぼる。最盛期は後300~900年で、古典期とよばれている。この時期、パレンケ、ティカル、コパンなどの大祭祀センターがきずかれた。 後古典期になると、マヤ文明の中心はユカタン地方にうつった。この時期のマヤ芸術は、メキシコ中央部のトルテカ文明の影響が顕著にみられる。メキシコ系の人々がマヤの地を侵略したか、移住してきたと考えられている。後古典期の前半はチチェン・イッツァが中心であり、その後、中心はマヤパンにうつったが、やがて分裂をくりかえし、マヤパンも放棄されてしまった。16世紀にスペイン人が到来したときには、もはや強大な国家はなく、征服はたやすくおこなわれた。しかし実際には、そのあともマヤの抵抗運動はしばしばおこり、独立を主張する村々をメキシコ政府が掌握したのは1901年のことだった。
ティアワナコ Tiahuanacu
ボリビアのチチカカ湖南東にあるインカ文明以前の都市遺跡。標高3800mのアンデス山中にある100~1200年ごろの古代都市で、大宗教建造物群からなる。高地での穀物栽培を中心とする農業民族がつくり、全盛期は200~600年ごろでペルー海岸のモチェ(モチカ)文化、ナスカ文化と同時期と考えられている。しかしなんらかの理由で放棄されたため、いくつかの建物は未完成のままのこされた。
ティアワナコの石造物は、建物に100tをこす切り石をつかうなど高度な石工技術によってつくられている。またアメリカ大陸ではじめて銅や青銅のかすがいをつかった石造建築である。もっとも大きい建物のアカパナは、高さ約15m、四方が152mの階段状の基壇ピラミッド。カラササヤは大きな方形の基壇で、もとはつながった壁の一部であったと思われる直立した一枚岩が境界になっている。有名な「太陽の門」は、高さ3mほどの巨大な一枚岩の門。上部中央の神をはじめ、みごとな浮き彫り文様がほどこされている。付設の半地下式神殿は修復されている。
ナスカ
ペルーの南海岸のナスカ文化は、モチェとほぼ同時代にさかえた。先行したパラカス文化と同様、ナスカでは建築物はあまりつくられなかったが、織物と土器にすぐれていた。土器には豊かでうつくしい彩色がほどこされている。モチェでは彫塑的にすぐれた土器が発達したが、ナスカの土器では彩文が特色となっている。
ナスカは、謎めいた地上絵でも有名である。地表の暗い色の石をとりのぞくことで、その下の明るい色を露出させ、大地に幾何学文様、動物、鳥、魚などがえがかれた。アメリカの天文学者ポール・コソックによって再発見された(存在自体はすでに知られていた)この地上絵は、上空からみてはじめて完全に識別できるほど巨大なものである。この地上絵は30個以上ある動物絵を含めて、全部で200以上残されている。しかしなんのために作られたのかは不明。目的は大きく分けて二通りに分けられると思う(ここから先は個人の意見)。
一つは誰かに見せるため。もう一つは全体像を見るのを目的としないもの、または人以外が描いたもの。誰かに見せる場合、誰にが問題となってくる。人が見るのか、人以外(例えば神様や宇宙人)が見るのか。人であればあの地上絵を見ることが出来る技術(空を飛ぶとか、高層建築物を作るとか)があったことになる。人以外であるなら特に問題は無い(宇宙人だったら問題あるが・・・)。ただ見ることが出来ずにどうやって描いたかという問題は残る(前者は見ることが出来るので確認しながらの作業が出来ると言うことになる)。
全体を見ることを目的としない場合は、何のためにわざわざ描いたかが問題となる。天体の模式図と言う説や儀式のためと言う説、宇宙人が書いたとかUFOの発着陸場と言う説もある。しかし、天体の運行を記した物であれば見にくいし、少々ずれていると言う研究結果も出ている。宇宙人説は論外だと思う。宇宙人がいるというのは特に否定しないが、昔地球にきたと言うなら何故今いない?納得のいく説明を聞いたことも見たことも無いので却下である。個人的に一番あってるんじゃないかと思う説は逃げ水(蜃気楼の一種)をとりこむための祈願用と言う説である。この地に水が足りなかったことや、蜃気楼の見えやすい地形・気候であることからそうじゃないかと思う(あくまで個人の意見)。
トルテカ Toltec
10~11世紀にメキシコ中央高原を中心にさかえたメソアメリカの先住民族集団。現在のメキシコ北部に居住していたが、当時のメソアメリカ文明の中心テオティワカンが7世紀末に衰退すると、南にむかって移住を開始し、10世紀にはメキシコ中央高原に王国を樹立した。近隣の諸民族を支配するため、卓越した軍事力をそなえた軍事国家をつくりあげていたと考えられている。
トルテカはトゥーラに都を建設した。それは、現在のメキシコ市の北方60kmほどに位置し、3つのピラミッド状の神殿を中心にひろがっている。最大の神殿は5段の階段式ピラミッドで、最上部には人間や神をかたどった巨大な石柱がたちならび、メソアメリカで農耕神としてひろく信仰の対象となっていたケツァルコアトル(金星の神)にささげられたと推定されている。
伝説によると、ケツァルコアトルとその信奉者たちは10世紀末ごろ、ライバル神のテスカトリポカによりトゥーラをおわれ、さらに東南へ移動した。マヤの地であるユカタン半島にまで到達したトルテカの集団はチチェン・イッツァを都にさだめ、一大宗教センターに発展させた。
12世紀にはいり、メキシコ北部からチチメカをはじめとする民族集団が次々と中央部に侵入し、トゥーラはたびたび侵略されてトルテカ文化は衰退の一途をたどる。ユカタン半島方面に移住していたトルテカも、かつて支配していたマヤに吸収されていった。
チムー Chimu
14~15世紀にペルーで繁栄した、インカ文明に先だつ文化。1000年ごろにチムー文化は生まれたといわれ、チムー王国の最盛期にはペルー北部の海岸地域の大部分を支配し、その経済はすぐれた灌漑(かんがい)システムをそなえた農業にささえられていた。現在のトルヒーヨの近くにあった首都チャンチャンは、広さ15km2以上もあり、中心域は高さ9mの城壁にかこまれていた。遺跡の保存状態はたいへんよく、ペルーでもっとも重要な遺跡である。
16世紀のスペインの学者によると、チムー王国には9人の王が君臨したという。1470年ごろ、最後の王ミンチャン・サマンのときにチムー王国はインカに征服された。チムー文化はモチェ(モチカ)文化とワリ文化の美術・工芸の伝統をうけつぎ、黄金製品、青銅製品に注目すべきものがあり、インカ文明にもそれはつたえられた。
インカ Inca
15~16世紀初期に南アメリカのペルー南部高原のクスコを中心にアンデス一帯に大帝国をきずいたケチュア語を話す先住民族(ケチュア)。インカはケチュア語では太陽の子すなわち王の意味だが、南アメリカを征服したスペイン人は王だけでなく帝国や帝国をささえた民族集団もインカとよんだ。
歴史
インカはもともとペルー南部高地にすむ、勇武な小部族だった。1100年ごろクスコの谷に移動し、それから約300年間、その地域の人々を支配して貢物をおさめさせていた。15世紀までは、とくに勢力をひろげようとはせず、せいぜい14世紀後半の第6代ロカ王の時代にクスコから約30km南までを領土とした程度だった。
最初に帝国主義的な拡張をはじめたのは、15世紀初めの第8代ビラコチャ王の時代で、勢力をクスコを中心とした40km四方の範囲にひろげた。その後数十年間、2人の王のもとでインカ帝国は拡大していく。1人は一部の歴史家の間で最大の征服者と目されている第9代パチャクティ王で、次がその息子のトパ王である。帝国の勢力がもっとも拡大したのはトパ王の息子ワイナ・カパク王の治世である。領土は南北4000km、東西が805kmに達した。学者の推定では350万~1600万人のさまざまな部族出身者がこの帝国に属していたとされる。
1525年、ワイナ・カパク王は後継者をきめずに死去したため、帝国は分裂する。彼の2人の息子ワスカルとアタワルパは王位継承をめぐって対立、32年アタワルパにワスカルはとらえられてしまった。このような微妙な局面で、スペイン人の征服者ピサロが火器と約180名の部下をともなってやってきたのである。
人々は白い肌をしたスペイン人を、インカの神の生まれ変わりと信じて抵抗せず、ピサロらは、アタワルパ王をとらえるだけで、高度に中央集権化された広大な帝国を支配することができた。アタワルパは、ピサロが自分を王位からしりぞけて代わりにワスカルをたてることを恐れ、ひそかにワスカルを処刑するよう命じる。そして、自身の身代金として帝国の隅々から莫大な金の装飾品をあつめてさしだしたが、1533年ワスカルの殺害などを理由に絞首刑になった。ピサロはワスカルの弟マンコに王位をつがせたが、マンコは数年後、反乱をおこして失敗、山岳地帯においこまれたところで供の3人に暗殺された。すでに帝国は分裂し、最後の王となったマンコの息子トゥパク・アマルはスペイン人に斬首され、王統はたえた。
文化
インカ帝国の絶頂期には、ほかのどのアメリカ大陸の先住民国家にもまさる政治・行政システムをつくりあげていた。帝国は農業を根本とし、高度に組織化された神権国家であり、全能の神とみなされる王が統治していた。王の次に権力をもっていたのは王族と上流貴族で、その下に行政官と下級貴族が属し、さらに職人と大多数を占める農民がいた。
国は4つの行政区域に大別され、それぞれがいくつかの県、そしてさらにより小さな社会経済単位にわかれており、もっとも小さい単位は地縁・血縁にもとづく大家族的な集団アイユとよばれる。ほぼ自給自足を実現しているアイユの農業は帝国の監督下にあり、役人が作物の選定や植えつけを細かく指導し、排水、肥料のやり方、灌漑(かんがい)、段々畑の作り方などの技術をおしえた。帝国は収穫の一定割合を徴収して貯蔵し、必要なときに配給した。
もっとも主要な作物はジャガイモとトウモロコシである。リャマは運搬にもちい、アルパカは家畜として毛を衣服に利用した。ほかには犬、モルモット、アヒルなどが飼われていた。手工業として重要だったのは土器類、織物、金属装飾、道具・武器の製造などである。
馬や車はなく、伝達手段としての文字もなかったが、首都クスコでは帝国中の出来事をくわしく知っていた。道路網を国土にはりめぐらせ、訓練された飛脚がリレーして1日で約400kmをつなぐ、迅速なコミュニケーションを可能にした。また軍隊の人数、人口データ、穀物の在庫などの統計を、縄の結び目と色で記録するキープ(結縄)があり、容易にコミュニケーションをはかることができた。バルサ材のボートによって迅速な河川交通もおこなった。帝国の隅々まで管理することができたのも、このような効率的な情報交換システムのおかげといってよい。
インカ文化のすばらしさにはさらに大規模な神殿・宮殿・要塞(ようさい)、および公共建築物にみられる石造建築の見事さがあげられる。とくにクスコにある太陽神殿は、土木器材を最低限しかつかわないで巧みにたてられている。ほかにも、全長約100mの吊り橋、灌漑のための水路、水道橋など技術水準の高度な土木建築が数多い。鋳物や道具、装飾品の製造に適している銅とスズの合金、青銅の技術もすでにひろまっていた。
宗教は高度に制度化されていた。最上の神格は、創造神で万物の支配者たるビラコチャである。ほかの主要な神には、太陽の神・星の神・気象をつかさどる神などがある。数多い祭礼儀式には、農作物の生長と収穫および病気の治癒をいのるものが多い。とくに重要な儀式では生きた動物が生けにえにされ、ときには人間が神にさしだされることもあった。インカは民俗音楽などの豊かな民衆文化も生みだしたが、現在ものこっているのはごく一部である。マチュ・ピチュは、インカ文明の一端をつたえてくれる貴重な遺跡である。
アステカ Aztec
14~16世紀にメキシコの中央部および南部を支配していた王国で、のちにスペイン人によって征服された。その名は神話上の起源の地である北方のアストランに由来するが、アステカの人々はみずからをメシカとよんでいた。彼らの言語はウト・アステカ語族の中のナワトル語である。
起源
メキシコ中央高原では、10~11世紀にさかえたトルテカ文明がほろんだのち、異民族がテスココ湖地方に次々と侵入してきた。いちばんおくれてやってきたのがアステカの人々であり、彼らには湖の西側の沼地しかのこされていなかった。かろうじて小さな島にすみついたが、まわりの強力な部族集団に対して貢ぎ物をしなければならなかった。
この当初のみじめな状態から200年ほどの間に、アステカは強大な国家を建設していった。彼らは、ある伝説を信じていた。沼地の岩にはえているサボテンに蛇をくわえた鷲がとまると、そこに偉大な文明が生まれるという伝説である。アステカの神官は、その沼地で、まさに伝説のとおりの鷲の姿をみたと人々につげた。この話はいまでも語りつがれており、メキシコの紙幣にはサボテンと鷲と蛇がえがかれている。
やがてアステカの人々はすぐれた軍事組織と行政機構を確立し、1325年には都テノチティトランを建設した。それが現在のメキシコ市になっている。
アステカの都
アステカの人々は湖の浅瀬をうめてチナンパという人工の島をつくり、都を建設した。湖底の泥をすくいあげた畑の土壌は肥沃(ひよく)で、高い生産性が得られた。島とまわりの陸地をむすぶために橋や土手がきずかれ、都の内部には人工水路がはりめぐらされた。人の移動や荷物の運搬は水上交通によっておこなわれていた。のちにこの都をみたスペイン人は、「新大陸のベニス」とよんだ。都の中心にそびえたっていたのは多くの巨大な宗教建築である。石灰岩の切り石で表面をかざった階段構造のピラミッドがたちならび、その上には神殿がつくられていた。
アステカの都は立地条件にもめぐまれ、政治や経済の組織も発達して、大いにさかえた。1519年、征服者コルテスにひきいられたスペイン人がやってきたとき、テノチティトランの市場は、毎日6万人の人でにぎわっていたという。アステカが征服した各地の領土からは数多くの品物が租税としてはこびこまれてきたし、広く中央アメリカ一帯にさまざまな交易物資がおくられていった。
アステカ同盟
アステカはさまざまな部族集団と軍事同盟をむすび、メキシコ中央部からグアテマラ国境にいたる広大な王国をつくりあげた。もともと15世紀初めごろには、3つの都市国家テノチティトラン、テスココおよびトラコパンが同盟をむすんで共同統治をおこなっていた。しかし100年の間にアステカが実権をにぎり、ほかの都市国家の王は名目だけのものになってしまう。
アステカ最後の王モクテスマ2世の時代には38の属州をしたがえていたが、辺境地帯では王国からの独立をこころみる人々もあらわれてきた。コルテスが1521年にアステカ王国をたやすく征服できたのは、この王国が同盟国家の連合体であり、たえず内紛をかかえていたからである。しかし、アステカが崩壊した理由は国内の政治問題だけではなかった。モクテスマ2世は、征服者であるコルテスを伝説の神ケツァルコアトル(羽毛ある蛇)の再来と信じ、王位をゆずるのも、さだめられた運命であると考えてしまったのである。
アステカの社会と宗教
アステカの社会は奴隷・平民・貴族の3階層にわかれていた。奴隷は年季奉公のようなものだった。まずしい人々は自分の子供を奴隷として売ることもあったが、その場合には、奉公の期限がきめられていた。また奴隷はみずからの自由を買うこともできた。さらに、主人からにげて無事に王宮までたどりついた奴隷は解放されたという。マセワルとよばれる平民は、土地をあたえられ、そこに自分の家を建てて住んだ。しかし、平民の中でも最下層のトラルマイトルは土地を所有することができず、小作人となった。貴族階層には、生まれながらの貴族のほか、神官や、功績をみとめられた戦士などもいた。
アステカの人々は多くの神々を信仰していた。日々の生活はこれらの神が支配していると考えられていた。ウィツィロポチトリは太陽の神である。コヨルシャウキは月の女神で、アステカ神話によれば兄である太陽神に殺されてしまう。トラロックは雨をつかさどる神だった。ケツァルコアトルは文字と暦を発明した神で、金星と関係があり、再生や復活とむすびつけられていた。
アステカでは、動物や人間を犠牲としてささげることが重要な宗教儀式とされていた。戦士にとってもっとも名誉なことは、戦場で死ぬことか、儀式の場でみずから犠牲になることだった。それほど重要ではない儀式のときには、戦争でとらえた捕虜が犠牲にされた。犠牲にえらばれた者はピラミッドの階段をのぼり、石の台に横たえられる。そして神官がするどいナイフで胸を切りさき、心臓をとりだしたという。
アステカには絵文字があり、紙や動物の皮に記録された。これはコデックス(絵文書)とよばれるもので、いくつかは現存している。暦はマヤ文明で発達したものをうけついだようだ。各20日からなる18カ月と5日間の不吉な日をくわえた365日が1年として計算されていた。また、それぞれ名前のきまっている20の日と13の数字をくみあわせた260日暦もあり、これは占いなどにつかわれた。