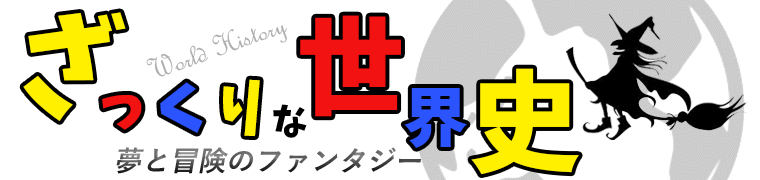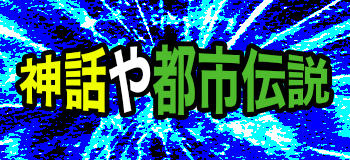エジプト神話
エジプト神話
古代エジプトでは多くの神々が信仰された。人々の信仰心は文化の発展に大きく影響したが、統一された論理体系としての真の宗教は存在しなかった。彼らの信仰は、古くからの神話や自然崇拝、無数の神々をよせあつめたものだった。なかでもよく知られた神話には、万物の創世が説明され、神々の序列がかたられていた。
万物の創世 ラー
エジプト神話によれば、世界の始まりは「原初の水」である。その水面へうかびでた卵(他説ではハスの花ともされる)から、天地の創造者ラーが誕生したとつたえられる。ラーはシュー、ゲブ、テフヌート、ヌートの4人の神を生みだした。シューとテフヌートは大気、ゲブは大地、ヌートは天空となり、ラーがそのすべてを支配した。その後ゲブとヌートは、セトとオシリスの2人の息子、イシスとネフテュスの2人の娘をもうけた。
オシリス
オシリスは妹イシスを妻とし、ラーの後継者となったが、セトに殺害される。イシスはアヌビスの助力をえて、夫オシリスの遺体に防腐処置をほどこした。このためアヌビスは防腐処理をつかさどる神とされた。イシスの魔力によって復活したオシリスは、死者の国の王となる。のちに、オシリスとイシスの息子ホルスはセトとたたかって勝利し、世界を支配した。 各地の神々 この万物創世の神話から、九柱神や、聖なる父・母・子の3柱からなる三柱神の信仰が生まれた。エジプト各地の神殿は、それぞれの九柱神や三柱神をまつっている。もっとも有力な九柱神はラーとその子孫からなるもので、太陽信仰の中心地ヘリオポリスで信仰された。
神々の起源
土着の神々の起源は明らかではなく、異国の神々や先史時代のアフリカの動物神からきているものもあった。それらがしだいに融合し、複雑にいりくんだ信仰を形成したが、その中の一部の神々は、エジプト全土でひろく崇拝されるようになった。前述した以外に重要とされる神は、アメン、トート、プタハ、クヌム、ハピ、女神はハトホル、ムート、ネイト、セクメトなどである。
メンフィスとテーベの神々
各神々の地位は、その信仰の中心地の盛衰に大きく左右された。たとえば、メンフィスの九柱神は、聖なる父プタハ・母セクメト・息子ネフェルテムの三柱神を主神とした。そのため、王朝がメンフィスを首都としていた間、プタハはエジプト全土でもっとも重要な神とされた。また、テーベが首都とされた時代には、アメンとムートとコンスの三柱神が主神としてひろくあがめられた。
人間の神格化
信仰が民衆にまでひろがるにつれ、死後に神格化された人間が神と混同されるようになった。プトレマイオス王朝時代に医術の神として崇拝されたイムヘテプは、もともとは第3王朝のジェセル王の宰相で、死後に半神とされた。第5王朝時代に、ファラオたちは自らを神の子孫と主張するようになり、こののち、彼らはラーの息子としてあがめられるようになった。このほかにも、各地方ごとにさまざまな下位神が信仰された。
神々の姿
エジプトの神々は、人間の体と動物の頭部をもつ姿で表現された。動物や鳥は神々の特質を象徴する場合が多い。たとえば、ラーの頭部はハヤブサであり、ハヤブサは天空をすばやくかけめぐるところから、ラーの聖鳥とされた。愛と美の女神ハトホルは、雌牛の頭部で象徴される。死者の神アヌビスはジャッカルの頭部をもつが、これはジャッカルが、死者の国とされる砂漠を徘徊する動物だからである。ムートはハゲワシ、トートはトキの頭部をもつ。プタハは人間の姿をしているが、アピスとよばれる雄牛の姿でえがかれることもある。 このような聖獣たちは神々とのつながりからあがめられたが、神として信仰されたのはエジプト王朝衰退期の第26王朝になってからである。 神々は太陽の円盤やハヤブサなどの象徴によってもえがかれ、ファラオたちは王冠をこれらの象徴でかざった。
太陽信仰
「神々の王」とされるラーは、古代エジプトで一貫して信仰された唯一の神であり、ファラオたちは権威を高めるためにラーの息子と自称した。中王国時代(前2134~前1784)にラー信仰は国教とされ、テーベに首都がおかれていた時代に、しだいにラーはテーベの地方神アメンと融合し、アメン・ラーとなった。
しかし、第18王朝のアメンヘテプ3世はアメン・ラーを廃し、太陽神アテンを信仰した。アテンとは古代エジプト語で太陽光の力を意味する。つづいて後継者となった息子のアメンヘテプ4世は、父の宗教改革をさらに推進し、アテンを唯一の神と宣言し、自分の名前を「アテンは満足する」という意味の「イクナートン」と改名した。エジプトではじめての一神教信者となったこの王は、アメン・ラーの名前を神殿からけずりとり、神官たちを迫害した。
イクナートンの太陽信仰は当時の美術や思想に多大な影響をあたえたが、王の死後は力をうしない、エジプトは複雑な多神教の世界に逆戻りした。
埋葬儀礼 ミイラ
エジプトでは死者の埋葬は宗教的に重大な意味をもち、世界でも類のないほど手のこんだ方法によっておこなわれた。エジプト人は、人間の生命力はいくつかの要素によってできており、なかでももっとも大切なのは「カー」であると信じていた。カーは人間の魂・分身であり、生きている間は肉体とともにあるが、死後は肉体をはなれて死者の国へとびさるとされていた。
しかし、カーは肉体なしには存在できないため、人々は死体の保存に努力をそそいだ。このため死体には、イシス女神が夫のオシリス神をミイラにしたときに使用したとつたえられる、複雑な防腐処理がほどこされた。そのうえ万一ミイラが破壊されたときのために、死者に似せた木製や石造りの像が何体も墓へおさめられた。像の数が多ければ多いほど、死者が復活できる可能性が高いとされていたからである。そして、遺骸は死者の世界での生活に必要とされる数々の備品とともに、入念にきずかれた墓へおさめられた。
死者の国
死者の国へむかう魂は無数の困難にであうとされ、墓には「死者の書」がいれられた。死者の書には、死者の国への道しるべや、悪霊を退散させる呪文などが書かれていた。
死者の国へ到着した魂は、冥界(めいかい)の王オシリスと42人の審判官によって審理にかけられる。死者の書は、この審理でのただしい受け答えについても指示している。審判によって罪人とされた魂は、飢えと渇きの責め苦にあう。あるいはおそろしい怪物に八つ裂きにされる。しかし、判定がのぞましいものであれば、魂は楽園にはいれる。そこでは穀物が4m近くまでのびそだち、死者たちは現世よりもすばらしい生活をおくることができる。
この楽園での生活に必要な品々は、家具から書物にいたるまで、すべて副葬品として死骸とともに埋葬された。楽園での死後の生活を保証するかわりに、オシリスは死者たちに農園での労働などを義務づけたが、ウシャブティとよばれる小像を墓におさめれば、ウシャブティが肩がわりしてくれるので死者は労働する必要がないとされた。