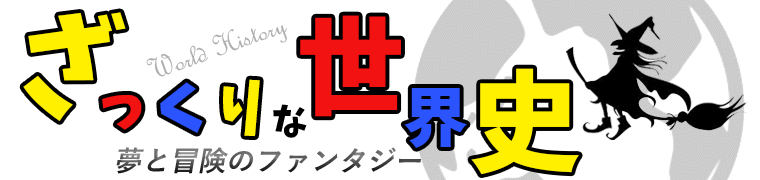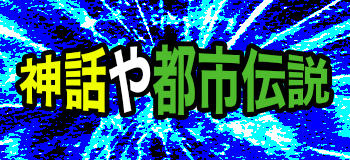ケルトの信仰・宗教
古代ケルト人は自然の中に神々を見出し、彼らの力を恐れてドルイド(=druid/神官)と呼ばれる予言者を通じて、数々の供物や生け贄を捧げた。と同時に牛や豚などの家畜、知恵の源泉とされた鮭、唾液に治癒力がそなわっていると考えられた犬なども特別な魔力を持つとされて、信仰の対象となった。
万物の父神と崇められるダグサ(豊穣を司る)、太陽の化身ルフ(技芸と商業の守護神)、ディアン・ケヒト(医神)、オグマ(肉体的な力の象徴)、ゴブニュもしくはゴブンノン(鍛冶の神)、ベレノス(穀物と牛の守護神)、マトレスあるいはマトロナ(地母神)、ケルヌンノス(森の神)、マナ・ナーン(海神)、サイブ(鹿の女神)、ブリギッド(三位一体の女神)、セーヌ川の名の由来とされるセクアンナ(女神)、ダーナ(女神)、残忍さを恐れられたテウターテスやタラニス、善神だが、人間の血を好んだというエスス、そして古代ケルト人が自らを彼の子孫と称していたディス・パテール(大地の支配者)等、今も神々の名前は伝説や文芸作品に残されている。
そうした神々と人間との仲介をしたのが「樫の木の賢者(彼らが樫の木の宿り木を、神の化身した聖なるものと考えて特別な儀式を行い、それらを集めて所持していたことに由来する)」と呼ばれるドルイドたちであった。Druidという名称自体も、Dru(オーク)とwid(知る)からなる古ケルト語で「オークを知る者」の意である。彼らは文学や詩に秀で、神学や倫理、法律、天文学、占術などを学んだ特権階級として、税や兵役を免除されていた。そのかわりに、彼らは多くの歳月(20年を要することもある)を修行つまり聖なる言葉の暗記に捧げなければならなかった。聖なる言葉を文字に書き写すことは禁じられていたのである。
これはドルイドの教義が一般大衆に知れ渡り、自らの尊厳を失うのを防ぐためと、弟子たちが文字に頼って記憶力をおろそかにするのを防ぐためであった。そうしてドルイドは宗教儀式を取り仕切り、供犠をとり行い、神託の解釈を行った。彼らによれば、物質や霊魂は不滅で、人間の魂は転生にゆだねられていると教えた。そうした信仰によって、人々は死への恐怖を乗り越えることができたのである。
このように古代ケルト社会において高い地位と権利を認められ人々の信頼を得ていたドルイドであったが、宣教師パトリック(カトリック)の到来により徐々に力を失い姿を消していった。
「剃髪の男がやってくる 把手を折り曲げた杖を手に
首だけ出したマントをまとい 未だ知らぬ信仰の賛歌が彼の家からこだまする
彼に従う人々は 家の前の祭壇で声を合わせて答えてくる
そうなりますように(アーメン)、そうなりますように(アーメン)、と。
この預言が成就される時、異教の我が王国は滅びるだろう。」(ムルクー「聖パトリック伝」)
「ターラの堅き要塞は 諸王の死と共に朽ち果てて
今や偉大なるアーマーが 聖者の歌と共に生きながらえる。
勇者リーレの誇りは消え失せ 立ちふさがるものはもはやなく
今や栄光のパトリックの名が 日々名声を轟かす。
罪にまみれた異教徒達は裁きに屈し 彼らの館には住む人もいない
だが、この地に育まれた信仰は 最後の審判まで生きながらえる」(「ケリ・デ・オエンブスの聖人暦」)
キリスト教が入ってきたとき、ケルト人はそこに自分たちの宗教と同じような仕組みを見て取った。全知全能の父神であるゼウス(=ダグサ)、その息子で英雄神アポロ=キリストは(ケルトの英雄たちがそうであったように)人間界に降誕し、あらゆる技芸に秀で奇跡を行うが、結局、栄誉のうちに早死にするのである。
ケルト人は新たな宗教と自らの教えを融合させ、教会暦に合わせて儀式を行うようになっていった。それらは4大祭祀として今も残されている。8月1日のルー(ルフ)神を崇める”ルーナサ(ルグナサド)の祭”(収穫祭)、10月31日の晩に1年の始まりを祝う”サウィン(サワーン)の祭”(火の祭典かつ死者の祭。聖地ターラの丘で祝宴が催された。現在のハロウィーン)、2月1日の三位一体の神ブリギッドに捧げる”インゲボルグ(インヴォルグ)祭”(豊穣と牧畜に関する祭礼で、現在の聖ブリギッドの祝日)、そして5月1日のベレノス神に捧げる”ベルティネ(ベルテーン)祭”(家畜を清める儀式)である。加えて宣教師パトリックの命日にあたる3月17日には世界中のアイルランド系の街で「パトリックの祝日(セント・パトリック・デー)」が讃えられている。
パトリックのアイルランドにおける布教成功の鍵は、何より土着の宗教ドルイド教の神々を認め、吸収していったところにあったのだが、それは彼の境遇に拠るところが大きい。
パトリックは、ブリテン島(英本国)に住むケルト人の家(祖父はキリスト教のの司祭・父は教会の執事)に生まれ、16歳の時に、海賊にさらわれてアイルランドに奴隷として売られた。6年の間、彼は森や草原で働かされ、その間にケルトの伝統的な土着宗教ドルイド教に触れた。その後、島を脱出して故郷に戻り、聖職に就くのだが、ここでアイルランドへの宣教の命を受けることになったのである。そうして、紀元435年に彼は再びアイルランドへと渡った。
聖パトリックに続く聖コロンバ(紀元5世紀に活動)もドルイド教に寛容であったため、アイルランド特有のカトリック信仰が形成されていった。そして、新教に吸収された土着の神々は、神話や伝説の中で、目に見えない身近な存在(妖精)として生まれ変わった。
神々への信仰と共に古代ケルトで守られていた大切な約束事に「ゲッシュ(複数形はゲッサ)」と呼ばれるものが成立していた。一種の禁忌(タブー)で、それを宣言されると、その中に挙げられた行動をとることが禁じられ、戒めを冒したものは部族追放あるいは死刑になることもあった。また、ゲッシュの中には何百年にも渡って信じられ、「禁句」となって残されたものもある。たとえば月のことをそのものの言い方ではなく別の言葉で言い換えなければならないという迷信があって、19世紀になってもアイルランドでは「ガラッハ」、マン島では「夜の女王」と呼ぶ習慣が残っていた。
「星のまたたく空が頭上に落ちてこないかぎり、足下の大地が裂けないかぎり、海原が地を呑みこまないかぎり、ここに私は誓おう。ありとあらゆる牛を小屋に連れ戻し、ありとあらゆる女を自分の家に返してやるぞ」(アイルランド神話「トェン・ボー・クールニャ(クーリーの牛争い)」山本史郎・山本泰子共訳より)
「蒼天我らが上に落ちたらぬ限り、緑なす大地引き裂けて我らを飲み込まぬ限り、泡立つ海押し寄せて我らを溺らしめぬ限り、この誓い破らるることなし!我らがここに誓う、一族(クラーナ)の解放を!」(あしべゆうほ作「クリスタル・ドラゴン」より)
「蒼天我らが上に落ちたらぬ限り、緑なす大地引き裂けて我らを飲み込まぬ限り、泡立つ海押し寄せて我らを溺らしめぬ限り、この誓い破らるることなし!」「これでよいな!?」「いいわよ、誓い(ゲッシュ)は神聖だもんね」(あしべゆうほ作「クリスタル・ドラゴン」より)