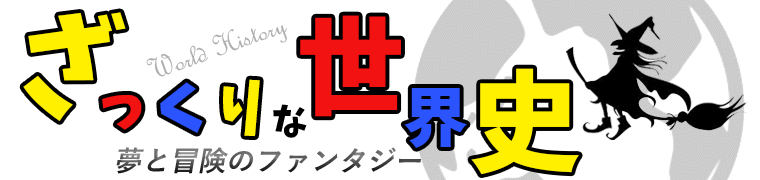中国の古代史をひとまとめ
春秋左氏伝
『春秋左氏伝』(しゅんじゅうさしでん、旧字:春秋左氏傳、拼音: Chūnqiū Zuǒshìzhuàn)は、孔子の編纂と伝えられている歴史書『春秋』の代表的な注釈書の1つで、紀元前700年頃から約250年間の歴史が書かれている。通称『左伝』。『春秋左氏』『左氏伝』ということもある。現存する他の注釈書『春秋公羊伝』『春秋穀梁伝』とあわせて春秋三伝(略して三伝)と呼ばれている。 wikipedia
左伝の時代
二百年以上にわたって黄河流域を支配した周王朝も弱体化し, 衰退の一途をたどっていた. 周は都市国家連合王朝である. この時代, 城壁をめぐらせた都市を邑(ゆう)と呼び, 一つの邑で 一つの国家を意味した.
時代が進むにつれ, 邑周辺の農地が拡大し, それまで共存していた遊牧民族との対立が表面化し, 周の失策続きも重なり, 連合各国への命令も余り真剣に実行されなく なってきた. 各国とも自分の国の国力増強を図り始めたのである.
そんな中, 西安近くの鎬京(こうけい)に 首都を置いていた周王朝は戎に攻撃されて, 首都失陥, 国王殺害の 大打撃を受け, 東のかた洛陽(成周)に遷都する.
その遷都から50年. 各国独立の風潮は強まり, 周王朝の権威は 微弱であった. 半治世半乱世の時代, 群雄たちの活躍する時代 になったのである.
左伝という書物
元となる「春秋」のさらに元は魯の史官の記録で, いわば外交記録公文書である. それを孔子が編纂し「春秋」という書物にした. これによって「春秋」は儒教の経典となり, 注釈書(伝)が 書かれることとなった.
いわゆる「春秋三伝」は, 「左氏伝」のほかに「公羊伝(くようでん)」 「穀梁伝(こくりょうでん)」がある. そのうち左伝以外の二伝は, 魯の隠公元年(722BC)から哀公十四年(481BC)の「西狩獲麟」迄を 伝えるが, 左氏伝は哀公十六年(479BC)の孔子の死まで経文を伝え, さらに記述は説話として哀公二十七年(468BC)まで続く.
この違いだけでもわかるように, 左伝は説話を積極的に採り入れていて 面白いエピソードに溢れる書物である. ただ, 編年形式なので読むのに難はあるけれども.
古代史年代順人物名
恵公(けいこう, 姫 弗湟 き ふくこう)
13代魯公 (在位 769~723BC)隠公, 桓公の父.孟子(もうし, 子姓)
子姓の長女の意味の名. 恵公の最初の夫人. 早くに亡くなった.
声子(せいし, 子姓)
子姓の女性. 声は名か?. 隠公(息姑)の母. 720BC没.
仲子(ちゅうし, 子姓)
宋の武公の次女. 桓公(軌)の母. 魯に嫁いだのは隠公が生まれた後.
隠公(いんこう, 姫 息姑 き そくこ)
14代魯公(在位 722~ 712BC)ここでは魯公に数えるが, 実際は摂政として幼い 桓公を補佐する立場である。 先代の時, 仲違いした斉や宋や紀などと友好的な関係を回復したり, 周王都の食糧不足解決を諸侯に呼びかけるなどした. 清廉な人物で桓公が成人したら位を明け渡すつもりでいたのが, 悪臣羽父(うほ, 公子揮)の奸計により殺害された.費伯(ひはく, 字は[广今]父 きんほ)
魯の大夫. 郎(ろう)に城き(722BC), 極(きょく)を滅ぼし(721BC),
無駭(むがい, 姫姓)
魯の司空, 公族. 極(きょく)に攻めいった(721BC), 715BC没, 子孫は 展(てん)氏という. 柳下恵(りゅうかけい, 展禽 てんきん)の祖.
衆仲(しゅうちゅう)
魯の大夫. 隠公の補佐官.(719BC, 718-4, 715-9)
羽父(うほ, 姫 [羽軍] き き)
魯の公子, 名の[羽軍](き)は史記では揮の字を用いている. 我が強く野心的. 無許可で出兵(719, 713-2)したりした, 公族筆頭であり(715-9), 外交儀礼上も重要な役割を果たした(712-1). 712BC, 大宰の地位を得て実権を握るべく隠公に桓公暗殺を勧め, 断られると逆に桓公に隠公暗殺を勧め, もって隠公を弑した.
臧僖伯(ぞうきはく, 姫 [弓區] き こう)
魯の諌臣. 隠公の行動を諌め(718BC1), その年の冬, 死亡. 公はその諌言を良とし葬儀の格を一級上げたという.
[宀為](い)
魯の大夫階級の氏, 羽父に隠公暗殺の濡れ衣を着せられ, 攻撃された.
桓公(かんこう, 姫 軌 き き)
15代魯公(在位 711~ 694BC)羽父(うほ, 公子揮)にたぶらかされ, 庶兄の隠公 を殺害して位につく. 杞公が無礼だからと攻めたり(710-5,7), 鄭との講和を仲介する 申し出を宋に断られると, 鄭と共同して宋を攻めたりした(700BC). 自分はルーズなのに他人に無礼をされると許せない性質だったようである. 講和仲介は好きならしく, 斉と紀を講和させ, さらに斉との友好を深めようと 斉に赴いた際, 不貞をはたらいた夫人の策謀で 斉の公子, 彭生(ほうせい)に抱き殺された.臧 哀伯(ぞう あいはく(字)), 臧孫 達(ぞうそん たつ(諱))
父に似て桓公に諌言を行なう(710-4). 臧孫(ぞうそん)氏を名乗り始める.
申繻(しんじゅ)
博識の臣(706-5). 桓公夫人文姜の不貞を知り, 斉訪問に反対した(694-1,2).
文姜(ぶんきょう)
桓公夫人. 斉の襄公の妹. 襄公と密通し, 桓公にそれを責められると 逆に桓公殺害を兄襄公に行なわせ, 斉に出奔した.
荘公(そうこう, 姫 同 き どう)
16代魯公(在位 693~ 662BC)
閔公(びんこう, 姫 開 き かい)
17代魯公(在位 661~ 660BC) 荘公の長弟, 共仲(きょうちゅう, 慶父けいほ) が太子 般(はん, 斑(史記))を殺害して立てた君主. わずか二年後にその共仲 にそそのかされた傅役(もりやく)の卜[齒奇](ぼくき)によって殺される.
僖公(きこう, 姫 申 き しん)
18代魯公(在位 659~ 627BC) 史記には釐公(きこう)とある.
文公(ぶんこう, 姫 興 き こう)
19代魯公(在位 626~ 609BC)
宣公(せんこう, 姫 俘 き たい)
20代魯公(在位 608~ 591BC)名の[たい]の字は右下に子ではなく女が来るのが正 しいが, フォントがないので一時的に俘を当てておく.
成公(せいこう, 姫 黒肱 き こくこう)
21代魯公(在位 590~ 573BC)
襄公(じょうこう, 姫 午 き ご)
22代魯公(在位 572~ 542BC)三歳で即位.
昭公(しょうこう, 姫 稠 き ちゅう)
23代魯公(在位 541~ 510BC)国外流浪の君主.
定公(ていこう, 姫 宋 き そう)
24代魯公(在位 509~ 495BC)
哀公(あいこう, 姫 将 き しょう)
25代魯公(在位 494~ 468BC)
鄭の荘公、弟を狎れさせ内乱に至る
[ 春秋左氏伝 ]
鄭の武公は鄭国の2代目で、初代鄭公友の良き遠謀に従って黄河デ ルタの首にあたる良地を占め、鄭を大国ならしめた興国の君である。 その後を継いで, 国を堅めるか弱めるかの決め手となる三代目鄭公となったの が, 鄭の荘公, 名を寤生(ごせい)という。
寤生(ごせい)とは逆児(さかご)で生まれてきたことに由来する。 母親は武姜といい、逆児に生まれた荘公を疎み、弟の共叔(段) ばかり可愛がり, 武公に共叔こそ太子に, とせがんだ。 母の愛に恵まれず寂しがりやに育った荘公は, 君主になってからも母親に好いてもらおうと努力した。 そのため, 母の望みは何でも聞いた。弟の共叔に京という大きな邑(城廓都市) を与えてやってくれとせがまれると与えようとした。 大夫の祭仲(さいちゅう)が驚き諌めるに, 「国の首邑と同格の邑を, 野心ある弟に与えるなどもってのほ か. 災いは芽の内に摘むべきなのを, かえって育てるとは.」。 しかし, 「母上の望みは断れない」と言い切る荘公。 かくて京邑は共叔の支配下となった。
共叔にとってみれば, 自分を跡継ぎにしなかった父はもう亡く, 自分を君主にと願う母がおり, 仲の良いとは言えぬ兄から支配地を 得た今, 独立せずに何をするのか。と意気込む状況であった。 しかも, 彼は母側に育ち, 母にへつらう兄しか見たことがない。 共叔が周りの邑を攻め落として半独立し, 勢力の拡大を図ったのも 当然であろう。 共叔は鄭都の北西の京邑を根拠地にして, 鄭国北部と西部の邑々を 服属させた。
一方, こちらは鄭の都邑, 宮城の政務室。子封(しほう, 公子呂)が 「民が動揺します. 早急に討つべきでしょう. さもなくば, 臣は共叔に仕えますぞ.」と強く諌めた。荘公応えて曰く 「不義の者は自滅する. 待つが良い」。
遂に共叔は廩延(りんえん)を手に入れた。この邑は黄河に沿って 衛国の近くまで下ったところにあり, 文字通り鄭国の北東端の 最前線基地であり, 陸路, 水路ともに恵まれた大邑である。 ここを制覇したことは, 共叔が鄭国の北半分を完全に掌握した ことを意味する。
鄭都は震撼した。子封は語気も鋭く「これ以上共叔が支配領域を 広げるなら, 人望があちらに傾きます. 今攻めなければ, われらが 亡びます」。荘公「不義の者に民衆は心服せぬ. 支配領域が どれだけ広がろうとも, そのうち自壊するであろう」
共叔は, ここで兵力増強を図った。城廓補強, 武器生産, 兵士訓練を 行なった。これ以上の鄭国内の支配地拡大には国都の正規軍を無視できず, 拡大を続けるには兵力不足だと判断したのであろう。共叔にとって荘公は 脅威ではないが, 武公譲りの優秀な家臣団は十分脅威であった。 そろそろ, 都邑の制圧, 鄭公位の奪取をすべき時期だったのである。
共叔は一計を案じた。計と呼ぶのがためらわれるほど, 当然のように 鄭都内の母武姜に鄭都進撃時の内応, 荘公の暗殺を依頼したのである。 共叔の知る荘公は武人ではない。指揮は将軍に任せ, 自らは宮城内に 留まると読んだのである。
綿密に日時手順を打ち合せた共叔は, 鍛えた軍を率いて京邑を発った。 なるべく荘公の軍を遠くにおびきよせておき, 宮城内で荘公を暗殺, 主君を失った荘公の軍を無傷で吸収する算段である。が, 荘公を 侮っていた共叔は, その行動に疎漏があったと言うべきであろう。 荘公の情報網に計画が筒抜けになっていたのである。このあたり, 母親の機嫌をとるために武姜の周りに厚く敷いた情報網が, 皮肉にも役に立ったと言えよう。 これほど尽くした実の母に暗殺を企てられようとは, 荘公の心中, 悲哀が吹き荒れたことであろう。
暗殺計画の露見とともに荘公の行動は一変する。
母武姜の身柄を拘束するとともに, 軍を早急に招集し、これを子封に与えて命ずるに「共叔の本拠, 京を陥とせ」。 兵車二百乗の子封の軍は, 急速に行軍展開, 防戦の暇を与えず京邑を包囲する。 もともと鄭の第二都市であり, 鄭公の命で共叔の下にあった京邑である。 共叔に支配されてから兵役が多く, 不満を持っていた邑人はあっさり 荘公側についてしまった。
京邑陥落の報が共叔に届くのは速かった。まだ, たいして京邑から遠く ないところで, 荘公の軍を今や遅しと待っていたのだから当然である。 荘公の軍の行動は, 歴戦の共叔に自らの作戦が暴露していたと悟らせるに 十分であった。いまさら, 鄭都には近付けぬ共叔は北の自分の勢力域へ 軍を返し, 一番近い京の北にある (えん)に入城した。
共叔 に籠城との報を受けた荘公は都邑守備の軍をも率いて 自ら出陣し, 近くの原野で共叔軍と対戦。将軍子封の指揮による 激戦の末, 共叔軍を撃破した。共叔は共(きょう)国に, その子公孫滑は 衛国に亡命し、鄭の荘公は国力を疲弊した。
戦後処理で真っ先に取り上げられたのは母武姜である。 悲しみ怒る荘公は母親を潁谷(えいこく)に幽閉して言うに 「黄泉(よみ)の国に行くまで二度と会わない!」
しかし, 荘公は寂しがり屋である。 すぐに母親に会いたくなったが、さすがにみなの前で宣言した手前、 引っ込みのつこうはずがない。 「母に会いたし, 約守りたし」。 ここに荘公の煩悶が続くことになったのである。 そこに登場したのが潁考叔(えいこうしゅく)という 潁谷(えいこく)の邑の封人(ほうじん, 辺境守備隊長)。 荘公の悩みを伝え聞き, 入れ知恵しにやってきたのである。
この荘公、先の諌言の先頭、祭仲(さいちゅう)を元は祭の封人であったのを 気に入ったという理由で卿(大臣)に任命してしまうといった人事を 行なった例があった。 そこで, 潁考叔は気に入ってもらって, 昇進しようと目論んだのである。 曰く、「地下水が出るまで斜めにトンネルを掘り、 黄色く濁った泥水の泉作ってそこで会えばよろしいでしょう」
とんちの問題にすり替えたのである。
それで実行した荘公も荘公だが。 とりあえずめでたしな親子の再会とあい成り、目論みどおり 潁考叔は昇進を果たしたのである。
宋の親友, 仲良く追放さる
[ 春秋左氏伝 ]
宋に華弱(かじゃく)と楽轡(がくひ)という者がいた. この2人, 幼い時からふざけあい, 成長してからは からかい合う仲だったのが, ある時, 些細なことでからかいが非難になり, 誹謗中傷になり, ついに怒った楽轡は, 華弱を首枷をするように 弓で押えつけた.これが酒宴なら余興で済むところだが, 場所が悪かった. 華弱は司馬職にあり, 朝廷の閣議の席でのことだったのである. 閣議であるから, 無論, 宋の平公の御前でもある.
宋の平公は華弱の弓で押え付けられたさまを見て, 「一国の大臣が閣議の席でする格好ではない」 と, 華弱を追放に処した. と, そこに司空の楽喜(がくき)が, 「楽轡が罪に問われないのは不公平だ」と 「喧嘩両成敗」を唱えて認められ, かくして華弱, 楽轡の両人は仲良く追放の儀とあい成ったのである.
親しき仲にも礼儀ありとは彼らのためにあった言葉であろう.
さて, 楽轡の追放を唱えたことで, 楽轡は楽喜を怨み, 追放の間際に楽喜邸の門に向けて矢を放ち, 「いずれ, 汝も追放されるであろう」と, 呪言を吐いた. が, 当の楽喜は楽轡に対して礼を失わず, 友好を保とうと努力したため, 追放されるようなこともなかったという.
魯の襄公の六年(567 BC)の夏の話である.
楚の隆盛
[ 春秋左氏伝 ]
序
春秋は魯の桓公の二年(710BC),第六条に曰く「蔡侯,鄭伯, (とう)に会す.」 左伝,これを註するに「これ楚に対する警戒の初めなり」.楚は,漢水と長江に挟まれた陸地に興った国である. この時期の楚の首都は郢(てい)という都市に置かれており, 三国志の江陵(こうりょう)のあたりに位置していた. そばを流れる長江の水運は、 蜀に産する玉石などを中原に運ぶ主要貿易ルートであり, 蜀から峡谷を下って来て丘陵地帯に出たあたりの 長江岸の津(しん),冶父(やほ),渚宮(しょきゅう)といった 港湾都市は中原諸国への商品陸揚げ港である. 楚都 郢(てい)は,これらの港から中原諸国へと伸びる陸路が 一旦集まる地であるため, 港湾を支配する権力者が都したと思われる.
話はずれるが、この郢(てい)という楚都には 非常に面白い情報が二つある。
一つは城壁の話である。 当時、中原諸国の都市は邑(ゆう)と呼ばれ、 城郭都市でった。 つまり、宮殿を守る城壁、市街を護る郭壁を 必ず持っていたのである。 しかし、この郢という都市には城壁がなかったようなのである。 根拠として、 左伝は魯の昭公二十三年に楚の沈尹戌(しんいんじゅつ)の言が 挙げられる。 察するに、商業中継地としての役割が先にあって、 農業都市としての性格を持たなかったのであろう。
面白い点の二つ目は、本当に首都だったのかという問題である。 正式に首都としていなかっただけなのか、 他に首都があったのかは不明だが、 史記楚世家には文王(次の王)の即位時になって初めて 郢を首都と定めたとある。 おそらく、城壁を築いたのも文王の時代なのであろう。 しかし、他に首都と思われる地もないことから、 ここでは、武王の代でもすでに郢(てい)が首都であったと 仮定して話を進めていく。
話は先の春秋の条文に戻る。 条文は、鄭、蔡、 の 三カ国首脳が楚に対する対策を初めて協議したという内容であった。
時に魯の桓公の二年(710BC)は楚の武王の治世三十一年目にして, 漢長両江に挟まれたあたりのほとんどの邑(都市国家)を傘下に収め, 雄躍して中原諸国の国際外交の場に進出せんとしていた. これに危機感をいち早く抱いたのが南方交易の盛んな鄭と蔡,それに なのである.
楚から中原に至る道は 大きく二つあり,一つはすぐに漢水を東に渡って随(ずい)に至り, 大別山脈の西を越えて淮水上流,蔡,そして鄭に至る道,もう一つは 楚からまっすぐ北上してから漢水を渡り, ,申を経て鄭,蔡に至る道である. 従来,周王朝の南方の押さえは随邑であり, 楚も周の影響下にあったとはいえ,王朝内では 王朝の構成都市ではなく友好的な野蛮国という扱いであった. そのため, 楚が中原諸国を相手に通商をするためには 随を窓口にして行なわねばならなかった. しかし,周の威 衰えたる昨今において,随の占めていた貿易中継点の 利益を欲する諸侯が現れた. 公である. 公は娘らを南の楚,北の鄭に嫁がせて 姻戚関係を結び,楚北通商路の開拓を行なったのである.
しかし,楚にとっては通商路が増えただけであまり利益は増えていない. 途中で関税を設ける や随を排除してこそ さらなる利潤を追求できるのである. そこで,政治的に有利な交渉を進めるために国力軍事力の増強を図り, もって覇権の拡大,交易の安全と利潤を追求し始めたのであろう. これが,楚との交流深い 邑の知る ところとなり,鄭,蔡の公と併せて今後の対応を考慮したのが先の春秋の 条文,魯の桓公の二年の秋に記された会合なのである.
実は楚の武王,熊通(ゆうつう)は,兄である先君の嫡子を殺害して 君主となった武骨者なのであるが, 彼を最も良く補佐してその国を強盛に導いたのは から嫁いできた妻女である 曼(とうまん)なのであったという. 優秀な娘を嫁がせたばかりに自国が危うくなろうとは, の邑主は考えもしなかったであろう.
また、史記によれば、後に周王を無視して王を名乗り始めたのも、 この武王の事跡なのであるが、これは、 山田 崇仁@ 睡人亭 さまの指摘によれば、 『韓非子』和氏篇に[虫分]冒(ふんぼう、武王の父)を指して 「 王(れいおう)」と称する 記述があり、 おそらくは『史記』の武王称王の記述は司馬遷(しばせん)の作為 と推断されている。
随邑攻撃
魯の桓公の六年春.楚の武王は随(ずい)を攻撃した. 史記に依れば 周室に爵位の昇格を要求したとされるが左伝にそのような記述はない. 大夫 [艸遠]章(いしょう)を派して和議を要求し,瑕(か)に陣を張って 待機したという.おそらく本音の要求は随の服属であったろう. これに対するに随公は少師(しょうし)を和議担当に当てて, 独立維持を図る.
ここに攻める楚の名参謀,闘伯比(とうはくひ)の計謀に, 守る随の名宰相,季梁(きりょう)の采配が争う、 楚随戦の幕が斬って落とされた。
先手は攻めの闘伯比(とうはくひ)である。 楚の武王に献言していわく、
「漢水以東の諸国を服属させるのに、武力による圧迫は良くありません。 圧迫すれば諸国は恐れ、協同して楚に対抗し、分裂の隙も生じません。 それより、要となる大国随(ずい)を油断させ、 尊大になるよう仕向けるのです。 そうすれば、協同していた小国は離れ、われらに有利となります。 随の少師(しょうし)は、わがままで傲慢ですから、 わざと楚軍の弱いところを見せてつけあがらせましょう。」
同じ楚軍の熊率且比(ゆうりつしょひ)は策の成功をあやぶんだ。
「随には賢臣の季梁(きりょう)がおります。無駄になるかと。」
それに対して闘伯比(とうはくひ)は、さらりと言ってのける。
「将来に対する布石です。 少師(しょうし)は随の君主の寵愛を受けるようになるでしょう。」
楚軍との交渉を担当した少師(しょうし)は、まんまとだまされた。 楚軍に乱れを見て取って、和議に楚の惰弱を感じ取ったのである。 和議締結後に楚軍追撃を主張し随侯の許しを得かけた。 しかし、そこは、随の名宰相 季梁(きりょう)が許さない。
「これは誘いの手です。 あわてて弱みを突いたつもりが反撃を受けるでしょう。 われらは楚より小さい国。「小が大と並べるのは 小に道あり大が淫なる場合」といいます。 道ありとは、民にたいして忠、神霊にたいして信であること。 つまり、民の利益をはかり、 祝史(祭祀官)に正直な祭文を奉納させることです。 今、民は飢え、祝史は嘘を祭っております。これでは出兵はできません。 」
しかし、随の君主は出兵に傾いている。おそらく、少師(しょうし)と 似たもの同士なのであろう。 「お供え物は豪華にしている。神霊に対して信であろう。」と のたまった。
「何をおっしゃいますか。」とは季梁。
「犠牲を供える時の祭文の『博碩肥[月盾](はくせきひとつ)』とは、 民の蓄えが博(ひろく)、 家畜が碩(おおく)肥(ふとって)[月盾](怪我も無い)こと。 穀物を供える時の祭文の『潔粢豊盛(けっしほうせい)』とは、 三時(春夏秋)とも潔(無事)で、 粢(穀物)が豊盛(ゆたかに実る)こと。 酒醴(しゅれい)を供える時の祭文の『嘉栗旨酒(かりつししゅ)』とは、 嘉(よき徳)そなわり香りかぐわしく、邪悪のないこと。 民が飢え、兵を出して和議を破って なんで祭文に嘘がないなどと申せますか。 いくら豪華なお供えをしても、 嘘をつかれては神もお受けになりますまい。 政治を良くし、民が和らいでこそ神は福をくだされるもの。 ところが、民はばらばら、わが君ひとり豊かでどうして神が 福をくださいましょうか。 ここは内政を整え、周辺の同姓諸国と親しまれますよう。 そうすれば、危機は去りましょう。」
さすがに懇々と説かれて随侯も心配になった。 内政を整え、外交に心を砕くことにしたのである。 楚は随を攻められなくなってしまったのである、が。
大乱の原因, 混乱の秩序
[ 范曄 後漢書 ]
後漢書の時代
高祖劉邦より二百年あまり続いた漢朝の治世も、 外憂失わばそれ内憂の兆しなりという言葉通り、 その敵は内に現われた。外戚の王莽(おうもう)である。 彼は狂信的な儒教信奉者で、「孔子の教えは世界を救う」 という妄想の体現者であった。 仏教の未だ伝播していない中国で、一大勢力を誇った教えに 忠実に生きようとする彼は、政治人の鑑とされ、 その位は人臣を極めた。
しかし、考え方がわかりやすい人間は、また、 利用されやすい人間でもある。
彼を利用するのは簡単である。 「孔子の教えにこうあった」と納得させれば良いのである。 かくして、彼の利用を目論む政界の大物の影の手引で 彼は帝位の簒奪さえしてしまい、ここに漢王朝もその終焉を迎えた。
世の移ろいは人知では計れない。政界の大物氏はこれからという時に、 呆気なく死んだ。残されたのは狂信者王莽の治める世界である。
彼は儒教の聖なる治世、五百年以上前の制度を用いた。 現在の日本を室町幕府に支配させるようなものである。 天下大乱は火を見るより明らかであった。
乱世の群雄天下に林立し、その覇を競いその兵を誇る。
戦火の煙塵東西に立ち、凶兵の喚声天地を覆う。
後漢書の予備知識
[ 後漢書 ]
雲台二十八将
光武帝劉秀を支え,後漢(東漢)王朝樹立に貢献した二十八人の功臣. その功績を賞して南宮,雲台に図書を描かれた. 二十八という数は二十八宿という星座数に無理に合わせたもので, 実際には三十二人を主な補弼の臣として 列伝は第十二巻の末に記している. ここでは,二十八将に入り損ねた可哀想な四将も加えて 三十二人を挙げる.()内の数字は記載巻数.
太傅高密侯 禹(6)
中山太守全椒侯 馬成(12)
大司馬廣平侯 呉漢(8)
河南尹阜成侯 王梁(12)
左将軍膠東侯 賈復(7)
琅邪太守祝阿侯 陳俊(8)
建威大将軍好畤侯 耿 (9)
驃騎大将軍參遽侯 杜茂(12)
執金吾雍奴侯 寇恂(6)
積弩将軍昆陽侯 傅俊(12)
征南大将軍舞陽侯 岑彭(7)
左曹合肥侯 堅鐔(12)
征西大将軍陽夏侯 馮異(7)
上谷太守淮陽侯 王覇(10)
建義大将軍鬲侯 朱祐(12)
信都太守阿陵侯 任光(11)
征虜将軍潁陽侯 祭遵(10)
豫章太守中水侯 李忠(11)
驃騎大将軍櫟陽侯 景丹(12)
右将軍槐里侯 萬脩(11)
虎牙大将軍安平侯 蓋延(8)
太常霊壽侯 (11)
衛尉安成侯 銚期(10)
驍騎将軍昌成侯 劉植(11)
東郡太守東光侯 耿純(11)
城門校尉朗陵侯 臧宮(8)
捕虜将軍揚虚侯 馬武(12)
驃騎将軍愼侯 劉隆(12)
….. 以上二十八将, 以下は可哀想な四将.
横野大将軍山桑侯 王常(5)
大司空固始侯 李通(5)
大司空安豊侯 竇融(13)
太傅宣徳侯 卓茂(15)
雲台二十八将軍関係
三輔
註に曰く, 「三輔は京兆, 左馮[立羽], 右扶風を謂う. 共に長安の中(あたり)に在り. 諸縣を分領す. 」 つまり, 首都長安近郊の三つの郡のことです.
図讖
「讖緯説」という総合的な予言学(?)
「讖緯説」というのは「中国傑物伝」(陳舜臣)では 「陰陽、五行、暦数、天文、占星などの諸術の複合で、国家や 人間の運命を予言できるとされていた」と書いてあります。 この本では明太祖朱元璋の軍師であった劉基の所で出てきており、 民間伝承ではそのような予言を通じて劉基が朱元璋の覇業を 助けたとなっているようです。 もっとも、東洋史事典や一般的な本では「讖緯説」というと 内容には同義にせよ、後漢時代に流行ったときのもの言うようで その後はしばしば発禁となったりして学問としては続かなかったように 書かれています。
陰陽五行の説によって王朝の交替を説明するのもこの一つですし、 王莽が漢を簒奪した際に各種の風聞を予言として利用出来たのは 当時この思想が蔓延していたことが背景にあるようです。
もはや余談になりますが、後漢の光武帝の素晴らしさは(最近?) 諸処で説かれますが、実は「讖緯説」を深く信じ、これを嘘っぱちとする 学者を遠ざけたり、迫害したりしています。
[ 以上の文章は, 私的中国史調査会の高崎 真哉さまが中国史MLに投稿なさっ た文章の抜粋で, 著作権は高崎様にあります. ]
図讖の詳しい説明
日角
「日角」とは額の中央の骨が隆起し、太陽のような形を していることだそうです。天下に王たる人相だということです。[ 以上の文章は, 後漢書のホームページの渡邊さまに頂いた, 御教示です. 著作権は渡邊様にあります. ]
六隊
王奔が六郡に置いた太守職の大夫が率いる軍. 隊大夫(将軍)と屬正(副将軍)が率いた.
前隊 南陽郡, 後隊 河内郡, 左隊 潁川郡, 右隊 弘農郡, 北隊 河東郡, 祈隊 栄陽郡.
緯書の予備知識
[安居 香山 緯書と中国の神秘思想 ]
緯書とは
漢代儒教経典の一種である。本来の経典を経書と言うが、 それに対して緯書と名づけられた。 後漢書では主に図讖(としん)と呼ばれている。 経(縦糸)と緯(横糸)という関係からもわかるように、 孔子の教えを別の視点からまとめたものであった。 しかし、成立において中国固有の宗教が混じったため 予言書的な性格を持った。そのため、内容的に 儒教経典としての緯(い)の部分と 占いや未来予言に関する讖(しん)の部分が混在している。
漢王朝での緯書
信じられていた。別名「孔丘秘経」というくらいで、 孔子が経を書いた後に、 これではわかりにくいと書き直したものだと信じられていたのである。 おかげで、頑固で批判力の鋭い合理的な儒者でもなければ、 緯書に疑いを差し挟む者はいなかった。緯書の視点とは瑞祥、災異の解釈による未来予測が可能という立場で、 天が、悪政を災害や異常で懲らしめ、 善政には豊作や瑞祥をもって報いるという考え方で、 春秋以前、周王朝の頃から信じられていた考え方である。
たとえば、神話の聖天子即位の話などから、聖天子即位の時には 黄河から図版(河図)が揚がり、 洛水から書物(洛書)が見つかるはずであるとか、 善政の時期には鳳凰が飛来し、龍が野に遊んでいるとか。 逆に災害が起こるのは悪政のせいであるとか、 天文異常は悪事の警告であるなどなど。 このように天帝が人事に干渉するという思想は、 天人合一思想とか、天人相関思想と呼ばれる。 この思想の元に儒教経典を読みなおしたものが緯、 この思想を応用して未来を予測しようというのが讖である。
また、災害や変異によって為政者を諌めるという考えは、 前漢代にあっては董仲舒(とうちゅうじょ)によって すでに体系化されていた。 瑞祥を善政の証とすることでは、 王莽(おうもう)が漢王朝乗っ取りのときにおおいに利用している。 緯書ということでは、 後漢の大学者、鄭玄(じょうげん)は経緯すべてを 統一する業績を成した。 しかし、同じ後漢でも桓譚(かんたん)、 張衡(ちょうこう)、王充(おうじゅう)、 荀悦(じゅんえつ)など、少数の頑強な批判精神のある儒者たちは 讖緯説懐疑派であった。
また、緯書は陰陽や五行説も含んでおり、 これは、後に後漢後期に成立する原始道教に吸収されていく。 有名なところでは、黄巾賊の張角が五行説を用いて、 「蒼天すでに死し、黄天まさに立つべし」とうたった話がある。 木(青)、火(赤)、土(黄)、金(白)、水(黒)の順であり、 「漢王朝は火徳(赤)であるから、 蒼天(天帝)に見放された漢の次に立つのは、土徳(黄)の王朝である。」 という解釈を安居氏はなさっておられる。
付記しておくが、五行の順序は生成、相生、相勝の三通りあり、 それぞれ水火木金土、木火土金水、土木金火水である。 生成は天地生成に際して生じた順、 相生は「木は火を生み…」という関係、 相勝は「木は土に勝ち…」という関係に基づいている。 この五行説が神秘思想に結びついたのは、 戦国時代は斉の鄒衍(すうえん)の五徳終始説であったといわれる。 また、どの王朝を何の徳とするかは混乱しており、 前漢王朝は水徳の秦を受け継いで水徳とはじめ称し、 武帝の時に相勝を用いて水徳の秦を打ち破った土徳の王朝とし、 王莽の頃になると、 相生を用いて再分配して漢王朝は火徳であるとした。 実際は、この三説は順番に出てきたわけではなく、 学派にように共存し、争っていたようである。 しかし、後漢に緯書が公式学説として固定されると、 相生によって革命するということで定まった。
占いあれこれ
天文占と、雲気占が緯書での特徴的な占いのようである。 天文占は、西洋、ギリシアやローマと異なり、 為政者や政治に対する予言であって、個人に対する予言ではない。 この点、予言内容なども古代メソポタミア文明に似ており、 メゾポタミアに間接的に影響されている可能性もある。 月の運行に合わせて二十八の宿(星座)をつくり、 それぞれに意味する地域を割り当てて行った。雲気占は、主に軍事関係の占いで、兵の吉凶の予言とされた。 雲の形によってどの国の軍を意味するのか決めておこなう。 また、「どこそこに雲が立てば」など、 雲の発生や動き、色などによっても行ったようである。
後漢書の人名
[ 後漢書 ]
安得(あんとく)
明帝期、車師後国王。北匈奴に殺される。 列伝第九 耿[合廾]伝
延岑(えんしん)
東漢創立期、漢中(かんちゅう)の地に割拠。 光武帝紀第一 上(2)
爰曾(えんそう)
→城頭子路(じょうとうしろ)
王匡(おうきょう)
東漢創立期、更始帝系 定国公主。安邑で 禹に敗北。 光武帝紀第一 上(3)
王常(おうじょう)
東漢創立期、緑林軍, 廷尉大将軍. 昆陽の戦いに参戦し 王鳳と共に昆陽城を留守(りゅうしゅ)した. 光武帝紀第一 上(1)
王饒(おうじょう)
東漢創立期、王郎軍、鉅鹿(きょろく)郡太守。 河北劉秀軍を数ヶ月に渡って防いだ。 光武帝紀第一 上(2) 列伝第二 王昌伝
王尋(おうじん)
王莽の新王朝の大司徒. 昆陽の戦いに王莽軍を率いて敗戦, 戦死. 光武帝紀第一 上(1)
王覇(おうは)
雲台二十八将の一人, 昆陽の戦いから劉秀に仕え続けた 忠誠の士として知られる. また, その妻も列伝に載る. 列伝第十 王覇伝 列伝第七十四 王覇妻伝
王覇妻(おうはさい)
王覇の妻。うじうじ悩む夫に活を入れる。 列伝第七十四 王覇妻伝
王鳳(おうほう)
新市(しんし)緑林軍首脳の筆頭格. 成国上公となり、昆陽の戦いに参戦して 昆陽城を留守(りゅうしゅ)するが, 攻撃の激しさに降伏を申し出た. 光武帝紀第一 上(1)
王豊(おうほう)
東漢創立期、河北劉秀軍。突騎兵。 敗走時、馬の無い劉秀に乗馬を譲る。 光武帝紀第一 上(3)
王莽(おうもう)
前漢(西漢)の帝位を奪った人物. 儒教狂信者. 政治を混乱させ乱世を招く. 光武帝紀第一 上(1) (2) 列伝第二 王昌伝
王蒙(おうもう)
章帝初期、将軍。 列伝第九 耿[合廾]伝
王邑(おうゆう)
王莽の新王朝の大司空. 昆陽の戦いに 王莽軍を率いて参戦するが, 我欲が強く, 敗戦の原因となる. 敗戦後逃亡. 光武帝紀第一 上(1)
王郎(おうろう)
王昌(おうしょう)とも呼ばれる。東漢創立期、 邯鄲太守の不安に付け込み、邯鄲を奪取。 独立して皇帝を名乗る。 光武帝紀第一 上(2) 列伝第二 王昌伝
か
賈彊(かきょう)
更始帝系将軍 蘇茂の部将。温の戦いで戦死。 光武帝紀第一 上(3)
郭唐(かくとう)
緑林軍、信都郡の五官掾(主席事務官)、任光(じんこう)と 共に劉秀挙兵に協力する。 列伝第十一 任光伝
関寵(かんちょう)
明帝、己校尉。西域に死す。 列伝第九 耿[合廾]伝
彊華(きょうか)
劉秀の同窓生。赤伏符を持参して劉秀即位の契機をつくる。 光武帝紀第一 上(3)
巨無覇(きょむは)
王莽に仕える身長2m近い塁尉(皇帝護衛官), 昆陽の戦いに参戦. 光武帝紀第一 上(1)
倪宏(げいこう)
王郎軍将軍。邯鄲(かんたん)からの鉅鹿(きょろく)郡 救援の兵を率いるが、劉秀軍に大敗。 光武帝紀第一 上(2)
阮况(げんきょう)
緑林軍、信都郡の功曹(人事官)都尉、 任光(じんこう)と共に劉秀挙兵に協力する。 列伝第十一 任光伝
厳尤(げんゆう)
王莽軍, 納言将軍. 良将であるが, [シ育]陽(いくよう)の戦い, 昆陽の戦い, どちらも敗戦し逃れている. 光武帝紀第一 上(1)
耿 (こうえん)
河北劉秀軍、突騎の将軍。常勝不敗を誇る。 賊軍に敗れた劉秀を守護する。 雲台二十八将の一人。 光武帝紀第一 上(3)
耿況(こうきょう)
東漢創立期、上谷(じょうこく)郡太守。 王莽廃滅後、緑林軍と友好を結び、 河北に一軍をなした劉秀に援軍を送る。 光武帝紀第一 上(2)
耿恭(こうきょう)
耿[合廾]の甥。明、章二帝に仕え、 西域で北匈奴を相手に拠点を死守した。 列伝第九 耿[合廾]伝
耿廣(こうこう)
耿[合廾]の末弟。 列伝第九 耿[合廾]伝
耿宏(こうこう)
耿恭の孫。 列伝第九 耿[合廾]伝
耿國(こうこく)
耿[合廾]の弟。 列伝第九 耿[合廾]伝
更始帝(こうしてい)
→劉玄(りゅうげん)
耿純(こうじゅん)
宋子(そうし)の人、東漢創立期、その縣邑に拠って、 信都で兵を挙げた劉秀に呼応する。 雲台二十八将の一人。 光武帝紀第一 上(2) 列伝第二 王昌伝
寇恂(こうじゅん)
上谷(じょうこく)郡から劉秀への援軍を率いる。良将。 雲台二十八将の一人。 光武帝紀第一 上(2) (3)
公孫述(こうそんじゅつ)
東漢創立期、巴蜀(はしょく)の地に割拠。 光武帝紀第一 上(2)
公賓就(こうひんしゅう)
東漢創立期、校尉(副将軍)、 長安反乱軍に参加し, 王莽の首級を挙げた. 光武帝紀第一 上(2)
耿秉(こうへい)
耿國の子。明帝期の[馬付]馬都尉 列伝第九 耿[合廾]伝
耿溥(こうふ)
耿恭の子。羌族との戦いで戦死。 列伝第九 耿[合廾]伝
光武帝(こうぶてい)
→劉秀(りゅうしゅう)
皇甫援(こうほえん)
章帝初期、将軍。 列伝第九 耿[合廾]伝
耿曄(こうよう)
耿恭の孫。烏桓に兵威を振るった。 列伝第九 耿[合廾]伝
呉漢(ごかん)
東漢創立期、 漁陽(ぎょよう)郡から劉秀への援軍を率いる。猛将。 雲台二十八将の一人。 光武帝紀第一 上(2) (3) 列伝第十一 任光伝
昆彌(こんび)
明帝期、烏孫国王。親子で同名らしく、 大昆彌と小昆彌が見られる。 列伝第九 耿[合廾]伝
さ謝躬(しゃきゅう)
緑林軍更始帝の側近。 河北劉秀軍を監視するために援軍を率いて合流する。 劉秀に協力的だったが、劉秀にだまし討ちされ死亡。 光武帝紀第一 上(2) (3)
朱浮(しゅふ)
東漢創立期、河北劉秀軍の前軍将軍。 李育の奇襲に大敗する。 光武帝紀第一 上(2)
朱鮪(しゅゆう)
更始帝の大司馬。 洛陽守備にあたる。 光武帝紀第一 上(3)
城頭子路(じょうとうしろ)
通り名。本名は爰曾(えんそう)。東漢創立期、 黄河と済水の間を勢力圏にした、王莽に対する叛乱軍主将。 更始帝と友好を通じた。 列伝第十一 任光伝
任隗(じんかい)
任光の子。章帝の代、清廉公正の宰相となる。 列伝第十一 任光伝
任光(じんこう)
緑林軍系 信都(しんと)郡太守. 王郎(おうろう)に追われて逃げ惑う劉秀一行を迎え入れ, 劉秀を立てて反王郎の兵を挙げる. 雲台二十八将の一人. 光武帝紀第一 上(2) 列伝第十一 任光伝
任勝(じんしょう)
任光の曾孫。任隗の孫。任屯の子。 列伝第十一 任光伝
任世(じんせい)
任光の曾々孫。任隗の曾孫。任勝の子。 列伝第十一 任光伝
申屠建(しんとけん)
長安反乱軍のまとめ役、 王莽の首級を緑林軍に送った。 光武帝紀第一 上(2)
任屯(じんとん)
任光の孫。任隗の子。 列伝第十一 任光伝
甄阜(しんふ)
王莽軍の前隊大夫(南陽郡守備軍指令官)、 伯升ら緑林軍を一度は破るものの、 その後[シ比]水の西の戦いで大敗、戦死。 光武帝紀第一 上(1)
岑彭(しんほう)
東漢創立期、劉秀軍二大方面軍司令官の一人。 呉漢副将として謝躬(しゃきゅう)を殺害。 雲台二十八将の一人。 光武帝紀第一 上(3)
秦彭(しんほう)
章帝初期、将軍。 列伝第九 耿[合廾]伝
秦豊(しんぽう)
東漢創立期、楚の黎王(れいおう)と号し、 黎丘(れいきゅう、襄陽近く)に割拠。 光武帝紀第一 上(2)
石修(せきしゅう)
耿恭の軍司馬。 列伝第九 耿[合廾]伝
宗廣(そうこう)
東漢創立期、任光(じんこう)の後任の信都(しんと)郡太守。 列伝第十一 任光伝
宗佻(そうちょう)
緑林軍, 驃騎大将軍. 昆陽の戦いに参戦. 劉秀と行動を共にする. 光武帝紀第一 上(1)
宋弟(そうてい)
東漢創立期、長安での反王莽挙兵の先導者の一人. 光武帝紀第一 上(2)
蘇茂(そも)
更始帝の討難将軍。洛陽北の温(おん)を攻めて敗北。 光武帝紀第一 上(3)
た第五倫(だいごりん)
章帝初期の司空。 列伝第九 耿[合廾]伝
張魚(ちょうぎょ)
東漢創立期、長安での反王莽挙兵の先導者の一人. 光武帝紀第一 上(2)
張参(ちょうさん)
東漢創立期、邯鄲(かんたん)の豪族。 王郎(おうろう)を擁立して、その大将軍となった。 列伝第二 王昌伝
張封(ちょうふう)
耿恭の軍司馬。 列伝第九 耿[合廾]伝
張歩(ちょうほ)
東漢創立期、琅邪(ろうや)に割拠。 光武帝紀第一 上(2)
陳収(ちんしゅう)
新市(しんし)緑林軍首脳の一人. 光武帝紀第一 上(1)
陳俊(ちんしゅん)
河北劉秀軍将軍。漁陽郡賊伐に参戦。 雲台二十八将の一人。 光武帝紀第一 上(3)
陳睦(ちんぼく)
明帝、西域都護。西域に死す。 列伝第九 耿[合廾]伝
陳茂(ちんも)
王莽軍, 秩宗将軍. [シ育]陽(いくよう)の戦い, 昆陽の戦いに参戦. どちらも敗戦し逃れている. 光武帝紀第一 上(1)
鄭衆(ていしゅう)
章帝初期の中郎将。 列伝第九 耿[合廾]伝
義(てきぎ)
初期の反王莽反乱勢力の一人。東郡太守。 王邑(おうゆう)率いる王莽軍に破れて自殺した。 光武帝紀第一 上(1) 列伝第二 王昌伝
田戎(でんじゅう)
東漢創立期、夷陵(いりょう)に割拠。 光武帝紀第一 上(2)
杜威(とい)
王郎軍、諌議大夫。劉秀軍との講和交渉を 担当するが、失敗する。 列伝第二 王昌伝
禹 (とうう)
劉秀の学生時代からの友人。 河北に参じて劉秀の配下となる。 騒乱に乗じ、別軍を率いて関中に入る。 雲台二十八将の筆頭。 光武帝紀第一 上(2) (3) 列伝第六 禹伝
董憲(とうけん)
東漢創立期、東海(とうかい)に割拠。 光武帝紀第一 上(2)
竇憲(とうけん)
和帝の治世を牛耳った権臣。 列伝第十一 任光伝
竇固(とうこ)
明帝章帝の二帝に仕えた重臣。 列伝第十一 任光伝
董次仲(とうじちゅう)
東漢創立期、反王莽の叛乱軍のひとつ、 檀郷(だんごう)軍の将帥。 魏郡近辺を勢力圏としたが、劉秀軍に討たれて壊滅。 列伝第十一 任光伝
刀子都(とうしと)
おそらく通り名。漢書では「力子都(りきしと)」。 東漢創立期、 徐州[亠兌]州の境界付近を勢力圏にした叛乱軍主将。 更始帝と友好を通じた。 列伝第十一 任光伝
満(とうまん)
東漢創立期、河北劉秀軍、将軍。 なかなか降らない鉅鹿(きょろく)を包囲しておくために、 留将として残された。 列伝第二 王昌伝
竇融(とうゆう)
東漢創立期、隴西を固め、光武帝に帰参する。 列伝第九 耿[合廾]伝
杜呉(とご)
東漢創立期、長安反乱軍兵. 王莽を殺害する. 光武帝紀第一 上(2)
な
は伯升(はくしょう)
→劉[糸寅](りゅうえん)
馬武(ばぶ)
河北劉秀軍将軍。漁陽郡賊伐に参戦。 雲台二十八将の一人。 光武帝紀第一 上(3)
馬防(ばぼう)
章帝初期の車騎将軍。狭量。 列伝第九 耿[合廾]伝
范羌(はんきょう)
耿恭の軍吏。 列伝第九 耿[合廾]伝
萬脩(ばんしゅう)
緑林軍、信都郡の令(太守副官)。 任光(じんこう)と共に劉秀挙兵に協力する。 雲台二十八将の一人。 列伝第十一 任光伝
班超(はんちょう)
西域の英雄。 (列伝第九)
(ひとう)
元 王莽王朝 和戎(わじゅう)郡 卒正(太守)。 信都で兵を挙げた劉秀に呼応する。 雲台二十八将の一人。 光武帝紀第一 上(2)
苗曾 (びょうそう)
東漢創立期、更始帝系の幽州牧(ぼく、州管理官) 河北劉秀軍を抑えようとして、呉漢に瞬殺された。 光武帝紀第一 上(3)
馮異(ふうい)
河北劉秀軍の黄河守備将。大樹将軍。 雲台二十八将の一人。 光武帝紀第一 上(3)
武仲(ぶちゅう)
狂人。王莽の治世に首都長安で 「我こそは漢の成帝の子である」と名乗って斬られた。 列伝第二 王昌伝
鮑[日立](ほういく)
章帝初期の司徒。 列伝第九 耿[合廾]伝
彭寵(ほうちょう)
東漢創立期、漁陽(ぎょよう)郡太守。 河北に一軍をなした劉秀に援軍を送る。 光武帝紀第一 上(2)
方望(ほうぼう)
東漢創立期、平陵(へいりょう)に割拠し、 西漢最後の皇帝を再び擁立した。 更始帝丞相 李松(りしょう)に敗れて死亡。 光武帝紀第一 上(3)
ま
や
ら
李育(りいく)
東漢創立期、河北の大都市邯鄲(かんたん)の豪族。 王郎を立ててその大司馬となり、劉秀軍を柏人で防いだ。 光武帝紀第一 上(2) 列伝第二 王昌伝
李憲(りけん)
東漢創立期、自称、淮南王(わいなんおう)。 光武帝紀第一 上(2)
李松(りしょう)
更始帝政権の丞相。 平陵(へいりょう)に割拠した方望(ほうぼう)を攻撃。 光武帝紀第一 上(3)
李譚(りたん)
章帝初期、軍営謁者。小悪人。 列伝第九 耿[合廾]伝
李忠(りちゅう)
緑林軍、信都郡の都尉(軍長官)、任光(じんこう)と 共に劉秀挙兵に協力する。 雲台二十八将の一人。 列伝第十一 任光伝
李軼(りてつ)
宛(えん)の李通(りとう)の従弟。劉秀と共に挙兵する。 昆陽の戦いに参戦。のち更始帝のために洛陽に劉秀を防ぎ、 殺害された。 光武帝紀第一 上(1) (3)
李通(りとう)
東漢創立期、宛(えん)の有力者。劉秀を担いで挙兵した。 光武帝紀第一 上(1)
李曼(りまん)
おそらく架空の人物。東漢創立期、 幼い王郎(おうろう)を宮廷から救い出した郎中として、 王郎が語っている。 列伝第二 王昌伝
李立(りりつ)
王郎軍、少傅。邯鄲攻防戦で劉秀軍に寝返り、 城門を開いた。 列伝第二 王昌伝
劉嬰(りゅうえい)
西漢王朝最後の皇帝。王莽に廃さる。 平陵(へいりょう)に割拠する方望(ほうぼう)に 再び擁立されたが、更始帝の軍に殺害される。 光武帝紀第一 上(3)
劉永(りゅうえい)
緑林軍系、梁王(りょうおう)。 自立して雎陽(すいよう、商丘に同じ)に割拠する。 光武帝紀第一 上(2)
劉[糸寅](りゅうえん)
字(あざな)は伯升(はくしょう). 光武帝 劉秀の実兄. 光武帝紀第一 上(1) (2)
劉均(りゅうきん)
更始帝系 王匡の部将。 光武帝紀第一 上(3)
劉[言羽](りゅうく)
東漢創立期、城頭子路(じょうとうしろ)と共に王莽に叛乱する。 更始帝と友好を通じた。 列伝第十一 任光伝
劉建(りゅうけん)
おそらく最短の列伝文の人物。 列伝第四十 千乗哀王建伝
劉玄(りゅうげん)
字(あざな)は聖公. 更始帝と呼ばれる. 緑林系反乱軍が立てた皇帝. 光武帝紀第一 上(1) (2) 列伝第二 王昌伝
劉元(りゅうげん)
西漢滅亡期、趙の繆王。劉林(りゅうりん)の父. 光武帝紀第一 上(2)
劉賜(りゅうし)
劉秀の近い親戚。緑林軍、光禄勲となる。 人助けすることが多い。 列伝第十一 任光伝
劉秀(りゅうしゅう)
字(あざな)は文叔(ぶんしゅく). 後漢(東漢)初代皇帝.
劉子輿(りゅうしよ)
架空の人物. 成帝の隠し子が民間に存在するという噂があり, その隠し子の名前として王郎(おうろう)が自称した. 光武帝紀第一 上(2) 列伝第二 王昌伝
劉植(りゅうしょく)
昌城の人, 東漢創立期、その縣邑に拠って、 信都で兵を挙げた劉秀に呼応する. 雲台二十八将の一人. 光武帝紀第一 上(2)
劉信(りゅうしん)
初期の反王莽反乱勢力の一人。厳郷侯。 王邑(おうゆう)率いる王莽軍に破れた。 列伝第二 王昌伝
劉接(りゅうせつ)
東漢創立期、廣陽王の子。 河北に勢力を広げる王郎(おうろう)の檄に応じ, 薊(けい)城内で劉秀捕縛の兵を挙げるも失敗する. 光武帝紀第一 上(2)
劉全(りゅうぜん)
おそらく二番目に短かい列伝の人物。 列伝第四十五 平春悼王全伝
劉張(りゅうちょう)
明帝時代の騎都尉。西域に出陣。 列伝第九 耿[合廾]伝
劉奉(りゅうほう)
王郎軍将軍。邯鄲(かんたん)からの鉅鹿(きょろく)郡 救援の兵を率いるが、劉秀軍に大敗。 光武帝紀第一 上(2)
劉盆子(りゅうぼんし)
東漢創立期、赤眉軍の擁立した天子。 光武帝紀第一 上(3)
劉林(りゅうりん)
東漢創立期、邯鄲太守。 不安のあまり新興宗教に走り, 王郎(おうろう)に 邯鄲を明け渡す. 光武帝紀第一 上(2) 列伝第二 王昌伝
梁丘賜(りょうきゅうし)
王莽軍, 前隊(南陽方面軍)の屬正(副将軍). [シ比]水の西の戦いで, 伯升率いる緑林軍に敗れて戦死. 光武帝紀第一 上(1)
令狐(れいこ)
字は子伯。王覇の幼馴染。王莽期に楚の大臣となる。 列伝第七十四 王覇妻伝
西漢・東漢の中央官制
[ 那珂通世 支那通史 ]
中央高官
西漢初
秦の制度を受け、庶政を統べる丞相(じょうしょう)、 その副官・御史大夫(ぎょしたいふ)を置いた。 これを二府という。また、太尉(たいい・軍最高責任者)を 丞相と同列に扱って三公とも言った。
その後の改変
武帝:太尉を廃止。大司馬を置く。大司馬大将軍は丞相の上とされた。
成帝:御史大夫→大司空[改称]。丞相・大司馬・大司空をみな「宰相」 と言いはじめる。
哀帝:丞相→大司徒[改称]。宰相(三公)に職務範囲の区別がなくなる。
平帝:王莽の意を受け、太師(たいし)・太傅(たいふ)・太保(たいほ)を 宰相の上に置く。
王莽:太師・太傅・国師・国将を三公の上に置き、上公と称する。
東漢
光武帝:上公位に太傅を臨時職として配置。大司馬→太尉[改称]。 司空・司徒・太尉を三公または三司と称した。それぞれの職に 九卿のうち三卿ずつが属した。
太尉三卿
太常(たいじょう):祭祀礼楽を司る。
光禄勲(こうろくくん):宮殿掖門を掌る。
衛尉(えいい):門衛・警備兵を司る。
司徒三卿
太僕(たいぼく):輿(こし)馬を司る。
廷尉(ていい):刑罰牢獄を司る。
大鴻臚(だいこうろ):外交を司る。
司空三卿
宗正(そうせい):皇族を司る。
大司農(だいしのう):財務食料を司る。
少府(しょうふ):山沢管理・税務を司る。尚書はここに属す。
尚書(しょうしょ):
尚書令(中書令とも)または 尚書僕射(しょうしょぼくや)がその長官を務める。 皇帝秘書官であるため、すべての法制・勅命に関わり、 権力は三公を凌ぐようになる。 東漢後期には太傅を長官とし、これに三公を加えて 四府と称した。
大将軍(だいしょうぐん):
東漢後期の官職。 皇帝の外戚で皇帝補佐にあたる者にしばしば与えられた官位。 太尉とは別職。 地位は三公の下であるが、権力は三公を凌ぐことが多かった。
光武帝紀
劉秀
世祖光武皇帝、諱(いみな)は秀、字(あざな)は文叔。 南陽郡の蔡陽という町の出身である。 漢王朝を始めた高祖から九世の孫なり。 系図としては第六代皇帝 景帝(高祖の孫) → 長沙の定王,發 → 舂陵(しょうりょう)の節侯,買 → 鬱林の太守,外 → 鉅鹿の都尉,回 → 南頓の令,欽 → 劉秀となる。 光武は九歳で孤児になり、叔父の良(りょう)に養われた。 身長は七尺三寸、須(ひげ)や眉は美しく、口が大きく 鼻が高く、日角があった。 仕事や倹約に勤める性格であった。 兄の伯升(はくしょう、劉[糸寅]りゅう えん)は、 弟とは対称的に侠を好み士を養って 親分的な性格であった。 伯升はよく、劉秀が田業を熱心にしているのを笑って非(そし)り、 「高祖劉邦の兄、仲(ちゅう)みたいな奴だな」と言っていた。
(劉[糸寅] は書きづらいので、以降伯升と記す)挙兵
始建国元年(9 AD)に 王莽(おうもう)が 首都 長安で帝位を奪い、国号を新とし、 ここに前漢王朝は滅亡した。 王莽の劉氏懐柔策によって、劉秀はこの時期 学問を修めるべく長安に遊学している。 しかし、王莽の政治は乱れ、四年もすると 毎年のようにイナゴの大量発生に見舞われたこともあって、 経済破綻に食糧不足という最悪の状況となった。 農民は土地を捨て、指導者を得て各地で鋒起し、 官庫や大商店を襲いはじめた。 乱世のはじまりである。
地皇三年(21 AD)に劉秀のいた南陽郡が荒饑し、 諸家の賓客は多く小盗をなし、治安は最悪であった。 劉秀は 新野(しんや)に一時避難し、 近くの大都市 宛(えん、南陽郡都)に於いて 穀物を売って民の救済にあたった。 その宛の有力者に李通(りとう)という者がおり、 彼等は 図讖(としん、予言書)を 利用して劉秀に説いた。 「劉氏 復た起こらん。李氏 輔と為らん」と。 つまりは、評判の良いおとなしい劉秀を担いで挙兵し、 あわよくば新王朝の樹立、 悪くても地方の実権を握ろうという魂胆である。 劉秀は初めは相手にしなかったものの、一人で静かに考えてみると、 「兄の伯升は、もとから軽客を集めて義理を結んでいるような人物であるから、 必ず挙兵するであろうし、 誰が最後に勝ち残るかは わからないものの、少なくとも今の皇帝王莽は負けるに違いない。」 そこで遂に李 通らとともに謀議を開き、 宛の地で兵弩を調達し、 十月に李通やその従弟 李軼(りいつ)たちと宛(えん)に於いて挙兵した。 時に劉秀は二十八歳であった。
南陽郡
劉秀は、挙兵後、兄と合流するために 兵を率いて舂陵(しょうりょう)に還えった。 その時、伯升はすでに予想通り挙兵していたのだが、 日頃の行いの粗暴さから付近の住民は、みな殺されると 恐懼(きょうく)して逃亡、隠遁してしまっていた。 つまり、伯升は挙兵はしたものの、仲の良い侠客しか集まらず、 兵の募集に失敗するというお寒い状況だったわけである。 そこに劉秀が戻り、絳衣(こうい、紅い軍衣)大冠に身を包んで 武装しているのを住民が見て、 あの謹み厚い劉秀まで軍中にいるなら 自分たちが殺されることもないだろうし、 挙兵しても大丈夫なようだと安心し、 やっと戻って挙兵に協力してくれたという。
伯升は、さしあたって緑林軍という反乱軍に合流することにした。 ちょうど、江夏郡新市(しんし)の兵を主力にした緑林軍の軍団が、 随州の平林軍(へいりんぐん)を吸収して北上してきたところだったのである。 伯升は緑林軍に合流すると、すぐにその将帥、王鳳(おうほう)、 陳収(ちんしゅう)と共に、 西のかた長聚(ちょうしゅう)を撃った。 そこで、今まで馬が足りないので牛に乗っていた劉秀は、 応戦した新野の尉を討ちとって馬を得たという。 皇族とはいえ、伯升、劉秀兄弟は貧乏していたことが伺える。
伯升らの合流した緑林軍部隊は、唐子郷を制圧し、 謀略で湖陽の尉を殺すなどして、 勢力を拡大した。 しかし、この時財物の軍中の分配に不公平があり、 伯升、劉秀兄弟は配下の兵に逆に攻撃されそうになった。 それと知った劉秀が、慌てて劉氏の取り分を兵にすべて分け与えたため かえって兵の士気は揚がり、棘陽(きょくよう)をあっさり抜くという 戦果につながることとなった。
連敗の王莽勢力であるが、南陽郡に王莽の軍隊がいないわけではない。 王莽の六隊のうち、前隊(南陽方面軍)と呼ばれる、 前隊大夫(南陽方面軍指令官) 甄阜(しんふ)と 屬正(副将軍) 梁丘賜(りょうきゅうし) 率いる王莽軍が存在した。
伯升軍はこの南陽王莽軍と 南陽郡南部の小長安という集落近くで戦闘を行なった。 結果、伯升軍は大敗、棘陽に敗走する始末であった。 しかし、軍を建て直した伯升は、更始元年(23 AD)正月、 再び甄阜、梁丘賜軍と[シ比]水の西で戦い、これを大破、 両将軍を斬った。 勢いに乗った伯升軍は納言将軍 厳尤(げんゆう)、 秩宗将軍 陳茂(ちんも)の率いる王莽軍を[シ育]陽(いくよう)で 破り、南陽郡の郡都、宛(えん)を包囲した。
昆陽前夜
更始元年(23 AD)二月、緑林軍首脳は劉聖公(劉玄)を立てて天子となし、 更始帝と号した。これに伴い、伯升は大司徒、劉秀は 太常偏将軍を更始帝より拝命した。そして三月、劉秀は 伯升とは別軍で出撃を命じられ、 昆陽(こんよう)、定陵(ていりょう)、 (えん)を下し、 多数の牛馬財物を獲得し、十万斗の穀物を宛の包囲軍に輸送した。
一方、長安の王莽は、六隊 のうちの南陽方面軍が壊滅し、 甄阜、梁丘賜 両将軍が戦死したうえ、緑林軍に帝が立った と聞いておおいに恐れ、兵数百万、戦闘員数だけでも 四十二万の大軍を編成した。 これを率いて長安を発したのは大司徒 王尋(おうじん) 大司空 王邑(おうゆう) である。 この王莽軍は五月に潁川(えいせん)に至り、先に伯升軍に 敗れた厳尤(げんゆう)、陳茂(ちんも)の軍と合流し、 南陽郡の奪回を目指した。
これより少し後 王莽軍が昆陽に包囲陣を張っている時のことであるが、 王莽軍 納言将軍の厳尤に向かって昆陽城からの逃亡降伏の兵が、
「劉秀は財物を取らず、兵に分け与え、これと計謀しております。」
と警句を発したのを、
「ああ、あのヒゲや眉だけ立派な奴のことか、どれほどのことがあろう。」
と、笑い飛ばし、全く問題にしなかったというエピソードがある。
厳尤は、以前、税務の用事で劉秀と面識があり、劉秀が 評判通りおとなしく優柔不断な性格であるのを知っていたから、 というのも一因ではあるが、攻める王莽軍と守る劉秀軍では、 本当に問題にしようがない程 兵力に差があったのである。
長安から新たに到着した軍は、 王莽が天下に兵法家六十三家数百人を集め参謀諸将とし、 武衛官を選抜、訓練したものを軍吏となし、 四十万もの猛士を募り招いて兵とし、 旗さしものや輜重車が千里も絶えずに続く大軍容であり、 さらに、巨無覇(きょむは)という身長2m近い大男の 塁尉(皇帝護衛官)が将軍の傍らで威厳を正し、 虎豹犀象といった猛獣たちを駆り威武を誇る、 まさに秦漢王朝を通してかつてない盛大な軍隊といえた。
対する劉秀軍は挙兵農民軍九千人である。 長安を発した王莽軍 潁川に到着の知らせを受けて 迎撃に陽關(ようかん)まで出陣した劉秀軍は、 王莽軍の盛んな軍容を見ただけでおびえてすぐさま逃げ出し、 走りに走って昆陽城に逃げ込んだ程である。 城に籠っても、兵は皆恐れおののき、 諸将は他の城に逃げ散らんとするありさまであったという。
昆陽帰城直後に軍議を開いた劉秀は、 降伏や逃走を唱える諸将を説得にまわった、
「王莽軍は強大であるが、この王莽軍を力を併せて防ぎ切ったなら その功績は比類ないほど大きく、諸君の昇進は間違いなく、 将来の封侯は保証されたも同然である。 兵を併せず分散して他の城に行くのは、 かえって各個撃破されてしまって不利であるし、 宛城が抜けない今、本隊の救援が来るのは確かに難しい。 しかし、ここでこの昆陽が破られれば、一日と経たないうちに 南陽全郡の緑林軍は壊滅し、ついには中国全土の住民が王莽の政治に 苦しむ生活に逆戻りである。 ここは心を一つにして王莽軍を防ぎきり、 共に功を立て名を挙げようではないか。 ここで王莽に寝返って自分の妻子や財物だけを守るなどというのは 邪悪そのものと言うほかない。」
諸将はこぞって 「劉将軍、あなたの言う通りにしようではないか」と奮起し、 皆の一致を見て会心の笑みを浮かべ、すっくと立ち上がる劉秀。 と、そこに候騎(偵察騎兵)が息咳きって走り込んで叫ぶ。
「王莽軍、城北に出現!」
昆陽の城壁上から望むと、王莽軍は数百里に軍列を連ね、それでも 軍列の最後がまだ見えぬと言う光景が、城の北の緑野に陽を浴びて 広がっていた。
劉秀軍諸将は急いで作戦会議を開き、劉秀は図を書して作戦を示し、 諸将は緊迫した表情で「諾」とだけ声を発した。
劉秀は城中に八、九千の兵を残して、成国上公 王鳳(おうほう)と 廷尉大将軍 王常(おうじょう)に率いさせて留守とし、自らは 驃騎大将軍 宗佻(そうちょう)、五威将軍 李軼(りてつ)ら十三騎 と共に深夜、城の南門から出た。郊外に兵を集めに出たのである。
王莽軍は前軍十万だけが城下に至るという時点のことである。
劉秀の募兵は不振であった。定陵や (えん)の 諸営の兵はすでに昆陽城に向けて発したものの、他の緑林系諸将は 財貨を惜しんで在所を動こうとしない。そこで劉秀は、ここでも 説得にあたる。「敵を破れば珍宝は何万倍にもなろうし、大功績を なすことになる。しかし負けてみよ、首領だからといって何が 残る。命さえ残らぬではないか。いったい何のための財物か。」 ようやく、劉秀に応じる将が現れ、ついには衆を従えて、劉秀は昆陽に 向けて援兵を組織することができた。
一方、王莽軍では納言将軍 厳尤(げんゆう)が二人の総大将の 一人である王邑(おうゆう)を説得していた。
「昆陽は小さいけれど堅城であるから、まずは皇帝を号した 大逆の徒、更始帝が包囲している南陽郡都 宛(えん)に早急に進んで、宛の 守兵と共に更始帝軍を挟み討ち撃破しましょう。 更始帝本軍さえ破れば、昆陽などおのずと 降伏を申し出て来ましょう。」
しかし、王邑は納得せず、
「私は以前、虎牙将軍として 義(てきぎ)を包囲した時、 これを破ったものの、 義(てきぎ)に自殺されてしまった。 すると、陛下(王莽)は 敵将を降伏させて生捕れなかったのは、徳が足りないせいだ とおっしゃり、私は叱責を受けた。 今、百万の軍を率いて城に至り、城が下せないとなったら、 今度は何といって叱られることか。」
王莽の儒教カブレが将軍の行動を制約して いるかのような言葉である。
ついに王莽軍は昆陽を数十重に包囲した。連なる軍営は百をもって数え、 十余丈の高さの雲車(はしご車)は城中を見おろし、旗織りものは野を 覆うがごとく、埃塵は天に連なり、鉦鼓の響きは数百里に渡って鳴り響き、 あるいは、地下道を掘って攻め、または、 衝車(しょうしゃ、太い木柱で門をつき破る)で 城門を撞(つ)き、積弩は乱れうちに撃たれ、 矢の降ること雨のごとく、 城内では戸板を背負って歩かねばならないほどであったという。
留守を預る劉秀軍の王鳳(おうほう)は、攻撃の余りの激しさに 降伏を申し出たが、 王莽軍主将 王邑(おうゆう)はこの申し出を蹴った。 これに驚いたのは王莽軍 厳尤(げんゆう)将軍である。 先に宛攻め先行を進言したときの、拒否理由は何だったのか。 降伏を受け入れるのは儒教でいう君子の行動ではないのか。
以前から薄々知れてはいたものの、ここではっきりしたことは、 王邑は功績を立てて、なおかつ敵軍の物資を懐に したいという欲の塊であるということであった。 なおまずいことに、その欲を可能にできる 軍の大きさが彼の名声や財宝への情熱をより一層かきたてていた。 ここで降伏を受け入れては、名声は得ても財宝は得られないのである。 王邑の意気は逸りたっていたといえる。
夜、流星ありて営中に墜つ、昼、雲ありて壌山のごとくになる。
占いに曰く、星の墜ちるところの軍、覆りて将を殺され血千里に流れると。 王莽軍の士気は著しく落ち、厭戦気分が広がった。
昆陽の戦い
六月、劉秀は苦労してようやく集めた援軍を連れ、 自ら歩騎千余を率いて先頭に立って現れ、 大軍を前に四、五里のところに陣した。 敵を千余りと見て簡単に追い払えると思った 王邑、王尋(おうじん)両王莽軍将軍は、数千の兵で応戦させた。 王莽軍は将軍の個人的な理由で戦っていると感じたため士気がない。 それを機敏に見てとるや、 劉秀は敵陣に奔走し瞬く間に数十の首級を挙げた。
これには、劉秀軍の援軍諸兵も籠城兵も驚き喜び、次に怪しんだ。 普段は小敵を見ただけでもおびえる劉将軍が、今、大敵を見て勇ましいのであ る。しかし、怪しんでいる暇はなかった。将軍一人を敵陣に置いては、 殺されてしまうのは明らかである。援軍諸兵は、劉秀将軍の前に出て 将軍を助けなければならぬという義侠心に駆られ、一斉に奔り出た。 劉秀はさらに進んで王莽軍を叩き、その勢いに乗じて援軍千余は 迎撃に出た王莽軍数千を壊滅させる戦果を挙げた。
勢いに乗じるには時間を置いてはならない。劉秀は、宛を包囲していた 緑林軍がついに宛を陥落させ、すぐ後に続いてやってくると記した偽の矢文を 城内に撃ち込み、同時に王莽軍にも伝わるようわざと変な方向にも同じ矢文を撃っ た。陽動作戦である。しかし、劉秀は知らなかったが、本当に宛は陥落してい たのである。ほんの三日前のことであった。
王莽軍は、宛下の緑林兵が至れば籠城軍と挟み討ちにされると知って 混乱し、籠城軍はこれで勝てると意気天を衝いた。まさに劉秀軍は 一人で百人を相手にできるかのごとき勢いとなったのである。 さらに劉秀の先導も良く、王莽軍中枢を討ち、混戦の中に敵将 王尋を 討ちとったのである。
「王莽が大司徒に任じたる王尋を討ちとったり!」
喚声がひときわ高く揚がる。
これを合図に籠城軍は太鼓を破れんばかりに叩き鳴らし、 まさに王莽軍を挟み討ちに撃って出たのである。 そして、それを鼓舞するように雷雨となり、大風が吹いた。 雨の降ること注ぐがごとく、大風の興ること瓦をも飛ばしたという。 王莽軍はすでに壊滅状態にあり、敗走を始めていた。
百万を号した王莽軍正規軍と、籠城軍援軍併せて一万余りの劉秀農民軍の 戦った昆陽の戦は、なんと劉秀軍の大勝に終ったのである。 折りからの風雨に猛獣も動かず、河が増水し、溺死した王莽兵のために 水が流れなくなるほどであったという。
王邑、厳尤(げんゆう)、陳茂(ちんも)の三将軍は、 味方の死体を浮き輪がわりに 水かさの増した河を渡って逃げるという有り様であった。
戦場には王莽軍が捨て去った輜重車が数え切れぬほど残り、 その量たるや、 劉秀軍が武具珍宝を2カ月かけてあらいざらい持ち去った後、 その余りを焼き払う程であったという。
伯升殺害
昆陽の戦勝を祝う暇こそあれ, 劉秀は潁陽(えいよう)攻略に 参戦し, 持ち前の優柔不断を発揮してしていた. そこに, 宛(えん)の更始帝本軍からの報告が一つ届く.「更始帝の命により, 大司徒, 劉[糸寅](りゅうえん), 誅殺さる」
劉[糸寅]は字(あざな)を伯升といい, 劉秀の実兄である. 光武帝本紀には更始帝に害されたと記すのみで, その理由は述べていないが, 皇帝に殺害を命じられた人間の親族が連座させられる可能性は高い. ましてや乱世である. 劉秀は駐屯地の父城(ほじょう)からすぐさま 宛に馳せ参じて謝罪した.
伯升の配下たちが劉秀を迎えて弔辞を述べようとしたが, 彼らとは私語を交えず退き, 深く反省の意を表して 論行功賞中の昆陽の戦功を取り下げ, 敢えて飲食言笑を平然と行なうことで兄の喪に服さない, すなわち, 兄弟の縁を切ることを示した. この劉秀の行動には更始帝も同情を示し, 劉秀に官は破虜大将軍, 封は武信侯を与えたのである.
王莽敗死と洛陽遷都
九月, 庚戍の日, 王莽の首が更始帝のいる宛(えん)に届けられた. 主力軍壊滅でもはや武威のなくなった王莽に対して, その圧政を怨む首都長安近郊の三輔(さんほ) の人々が集結して王莽を討ったのである. 時に城中の少年, 宋弟, 張魚ら, 莽を漸台に攻め, 商人 杜呉, 莽を殺し, 校尉 公賓就, 莽が首を斬り, 将軍 申屠建ら, 莽が首を伝えて宛に向けて送る と, 本紀の注にある.
王莽死亡の報を聞いて開城した城に洛陽がある. 南陽郡の北, 黄河近くの盆地にできた当時中華第二の大都市である. 更始帝を立てた緑林軍一行は, ここに帝座を移さんと考え, 劉秀を司隷校尉に任命, 先行して宮府を整え修めるように指示した.
少し前, 長安反乱軍からの更始帝を迎える使者が軍を率いて 洛陽を通過していたのであるが, その軍兵の布冠貧衣であったのを見た 洛陽市民は, その威厳のなさを笑わない者はなく, 一部にはその殺伐たる空気を恐れて逃げ去る者が出たほどであった.
劉秀は洛陽到着後, すぐさま配下を属縣(支配地域の町村)に派遣して 命令系統確保を文書で指示, 従事司(警官)を統率して治安維持を図った. 司隷校尉 劉秀の僚屬(同僚と配下)を見るに及びて, 民衆は歓喜し, 洛陽のある老吏など「図らずも, 今日, 再び 漢官の威儀を見ることができようとは」と, 感動のあまり手放しで落涙したほどである. 秩序回復と, 漢礼の復活を優先させた劉秀は, 洛陽識者の好感を得, 更始帝遷都の次第を難なく整えた.
北渡河 ………. 地図1
更始帝の洛陽到着と同時に劉秀は破虜将軍と兼任で大司馬代行を命じられ, 十月, 節を持して北へと黄河を渡った. 河北域の鎮撫を命じられたのであるが, 「軍を率いて」ではなく「節を持して」渡ったのである. 節とは八尺の竹柄に牛の尾毛を三重に先につけた軍権の象徴であって, 権威を示す道具である. 体良く兵を取り上げられ, 側近, 幕僚だけを 連れて河北に派遣されたのである.
洛陽圏内はまだ, それだけでも充分で州郡守, 縣令, 三老, 佐史に至るまで 審査, 任免することができ, 王莽の苛政を除いて 囚人 労役者を解放し, 政務を安定させることができた. 吏人喜び争いて牛酒を持ちて迎えると記述される.
しかし, 洛陽圏外に出れば, 緑林軍更始帝の節など認められるわけがない. 劉秀一行の行程は邯鄲(かんたん)に及んで, 途端に はかばかしくなくなるのであった.
邯鄲の王朗挙兵 ………. 地図1
邯鄲を治めていたのは趙の繆王(劉元)であったが, すでに亡く, 子の劉林(りゅうりん)が代わって治めていた. この劉林は, 邯鄲の多くの民を率いて乱世に戸惑い疲れ, 何か頼れるものにすがりたい気分であったのであろう. 劉秀に願い出て,
「赤眉(せきび)軍が現在 河東にあり, わずかに黄河を隔てているだけでございます. どうか緑林系百万の軍で赤眉軍を掃討していただけないでしょうか.」
劉秀は困った. 確かに兵権の証として節を持ってはいるものの, 軍から遠ざけられたと言って良い境遇である. 泰山一帯を支配する赤眉軍を相手に まともに戦える兵力を, 更始帝に要請できる力は劉秀にはなかった. もしあったとしても, それだけの兵力を東に移動すれば, 首都長安を含む西の防備ができなくなるであろう.
承知したと虚言を弄する謀略も, そのような力は現在無いと手の内を見せる 度胸もなく, 劉秀は邯鄲を去った. 北方, 真定(しんてい, 常山とも)に移動したのである.
これは, 政治的に重大な失策であった. 不安を訴える者を放置してはならないのは政治の鉄則である. 安心させてこそ, その者の力を十分に発揮させ, 用いることもできる. 安心させることができなくとも, 解決方針だけは示さねばならない. 万が一, 間違って不安を増大させても, 解決方針さえ示せば, そちらに突進させることができる. しかるに, 劉秀は結果的に黙殺したことにより, 大都市 邯鄲を握る劉林の不安を増大させて, しかも放置してしまったのである. 政治的には愚策中の愚策であったと言う他ない.
この失策による被害は迅速でかつ重大だった. 不安を煽られた劉林が, 王郎(おうろう)と名乗る占い師に, ころりとだまされて「王郎は, 実は成帝の隠し子, 劉子輿(りゅうしよ)の 世を忍ぶ仮の姿である」などと信じみ, ついには王郎を立てて天子となし, 邯鄲を王郎に明け渡してしまったのである. 野望たくましい王郎の対応は素早かった. 即座に周囲の郡国に使者を遣わし, 瞬く間に勢力圏を広げていった.
十二月に王郎が挙兵して, 翌正月にはその勢力が真定に迫り, 劉秀はさらに 北方の薊(けい)へと逃れた. しかし, 勢力を強固にした王郎は, 檄を飛ばした. 「劉秀を捕らえたる者, 十万戸の侯に封じる」 これは効果があった. 故 廣陽王の子, 劉接(りゅうせつ)が, 檄に応じて薊の城内で兵を挙げたのである. 城内は騒然とし, 混乱した. しかも, ちょうどそこへ, 王郎の使者が来たのだからたまらない. 薊の縣令以下, 官吏総出で使者を城外に迎えに出る次第となったのである.
劉秀は南に向けて逃げた. 夜はあえて城邑に入らず, 宿舎や食糧を道の傍らに 求め, ようやく饒陽(じょうよう)に至った.
劉秀一行は皆飢えていたため, 劉秀は偽って王郎の使者だと名乗り, 伝舎と呼ばれる客舘に迎え入れられることに成功した. しかし, 飢えは理性を凌いでしまっていた. 饒陽の伝吏が食事を用意したところ, 一行は奪い合うように争って食べたのである. これでは乞食も同然で, 使者だと信用しろという方が無理である. 怪しんだ伝吏は鼓楼に登り, 数十も太鼓を叩いて叫んだ.
「邯鄲の将軍の御着きである」
劉秀一行は皆, 色を失った. 一番慌てたのは劉秀である. 彼は真っ先に馬車で逃げようと走り出したのだ. しかし, 部屋も出ずに諦めてしまい, 席にトボトボと戻って 邯鄲の将軍の情けを請おうとさえ言い始めた.
この危機を救ったのは名さえ伝わらぬ饒陽の城門守備隊長である. 彼は「いったい, この広い天下のどこに, 長者を閉じ込めようとする者がいるだろうか」 と言い, 伝吏の閉門要請を蹴ったのである.
劉秀一行はなんとか城南に逃れ, 昼夜に兼行し, 霜雪を蒙犯して走った. ちょうど寒さが厳しい時節で, 皆, 手足や顔に裂症を作ったという. 呼沱河(こたか)という河では舟が見当たらなかったものの, 氷が張るのに運良く遭遇して かろうじて渡ることができ, その氷も残り数車が渡りきらぬうちに融け去るという危うさであった.
この苦難の逃避行は, もとはといえば邯鄲太守劉林を不安にさせたことに 始まっている. 人を不安にすることの愚かさを十分身に染みて学んだ劉秀は, これ以降, 類い稀な人心収攬術を発揮することになる.
下博城の西にあたる地域で劉秀一行は道に迷い, 路傍に立つ白衣の老父に尋ねたところ, すっと指を挙げて老人は 静かに述べた.
「努力なさい. ここを去ること八十里, 信都(しんと)郡は 長安のために堅く節義を守っておる」
この一言で劉秀一行は救われた.
信都郡 ………. 地図1
疲労困憊して逃れてきた劉秀一行は, ようやく信都(しんと)郡に至り, 太守 任光(じんこう)に門を開いて迎え入れられた. 早速, 劉秀は近隣の縣(町)で徴兵して四千の兵を得, 堂陽, 貰縣を撃って これを降した.
この劉秀の勢いを見て, 旧王莽配下の和戎(わじゅう)郡の卒正(太守), (ひとう)が郡を挙げて劉秀に付いた. また, 昌城の人, 劉植(りゅうしょく), 宋子の人, 耿純(こうじゅん)などが宗親子弟を率いて, その縣邑に拠って 劉秀派であることを通告して来るなどして友好的な勢力が増えた.
しかし,勢力圏を拡大したと言っても,信都郡近辺の小規模町村が なびいた程度であって,とても大都市邯鄲を擁する王郎軍と 直接対決するほどの勢力ではない. そこで劉秀軍は邯鄲を迂回して,さらに北の方に戦線を広げ, 下曲陽(かきょくよう)を攻めとった頃には ようやく数万人の規模にまで成長した.
この時点で戦略的に見てみたい. 邯鄲を南に置いて南北に伸びる王郎勢力圏を 縦軸に十字架を作ると,その東に出た枝が現時点での劉秀軍勢力圏に当たる. そこからまっすぐ邯鄲を目指せば背後を突かれやすい. 劉秀軍はどう進むべきか.
幸い,王郎の勢力は邯鄲の兵力で脅かして急速に成長したものであり, そのため,邯鄲圏以外の勢力は積極的に荷担していない. つまり,脅かせばどちらにもなびく存在であった. 河北の大半を占める北方諸郡にとっては, 現在もっとも自分にとって脅威である存在こそが, 自らの属すべき勢力なのである.
劉秀軍は邯鄲を南西に望んで北西に向かった. 一つに王郎勢力の分断を狙い, 2つに北方諸郡に近い領域で大勢力を成すことで, 彼らを味方につけるためである. 王郎を討つのに,まず彼を支える勢力域を奪い, その後に本拠を攻めるという地道ながら上策を取ったわけである.
しかも,戦い方も地道である.かなり西に遠い中山国を撃ったと思うと, 盧奴(ろど)という黒池という意味の名を持つ町を陥しただけで 道を引き返した. この長距離のとんぼ帰りは,いわば軍の増強と宣伝を兼ねたパレードである. 増強とは,戦いを避けて 通過域の村々の奔命兵(ほんめいへい)と呼ばれる 村自衛のための予備役兵を徴発することで, 簡単に言えば,村の消防団のオヤジたちをかき集めたのである. さらに宣伝とは, 周辺の大きめの町には激を飛ばして王郎から離れることを説いて まわったことである. これは兵員に余裕がある限り,遠くまで派遣した.
このパレードで集まった兵力が,そろそろ一つの軍を形成するに 見合うだけになったのがようやく中山国に入ろうかという頃で, そこに位置した盧奴(ろど)町は,いわば劉秀軍の攻城戦訓練に さらされたわけで,とんだ災難であった.
軍を整えて河北平野に引き返した劉秀軍は,中規模都市の攻略にかかる. 常山郡(じょうざんぐん)の新市(しんし),真定(しんてい), 元氏(げんし,常山郡郡都,正確には元に阜偏がつく), 防子(ぼうし,房子とも書く)を次々説得し,または制圧し, 王郎勢力を分断して十字架の要,常山郡をその支配下に収めたのである.
常山郡失陥の報に王郎は驚いた. 彼は将軍 李育(りいく)に兵を率いさせ,防戦に出した. この将軍は,河北劉秀軍にとって初めてのマトモな敵将となる.
邯鄲攻防 ………. 地図1
劉秀軍は常山郡の抵抗が案外と少なかったのに気を良くし、 南に隣接する趙国(郡)へと兵を進めていた。 そこで、これを迎え撃つ李育は 郡境ちかくの柏人(はくじん、[木百]を用いることも) という地に急ぎ兵を伏せた。 劉秀軍前軍を率いていたのは朱浮(しゅふ)と 禹(とうう)である。 彼らが慢心して進軍するのを見過ごした李育は、 後方から輜重(補給物資輸送)部隊を攻撃した。 驚いたのは劉秀前軍である。 不意を後ろから突かれて混乱し、あっさり逃げ散ってしまったのである。 この戦果で李育は物資を得て退却をはじめた。
劉秀は後方に居て前軍の敗報を聞き、急ぎ前軍の残兵を収め、 軍を立て直すと、追撃戦に移った。 戦乱と凶作で物資は不足がちの時期であるから、 物資は貴重である。急行して奪回しなければならなかった。
一方、勝った李育は、物資は多ければ多いほど 良いという判断だったのであろうが、欲張りすぎた。 すべての物資を運ぼうとしたため、行軍速度が遅くなったのである。 そのため軍営地柏人城に入る直前に、追撃してきた劉秀軍 本隊に捕捉されてしまった。 伏兵という小人数の部隊構成で、 しかも多くの輜重車両を運転していたのであるから、 李育の軍に当然勝ち目は無かった。 李育はやむを得ず輜重を放棄して柏人城に籠城するよう指示した。
物資を奪回して、劉秀軍は引き続き柏人城攻略に移ったが、 李育は固く守って下らず、仕方なく劉秀軍は攻撃目標を変えた。 大軍勢であるから、食料補給が難しく、 一箇所での長期戦はできないのである。 そこで、趙国侵攻の前に信都郡に近い鉅鹿(きょろく)郡を攻略して、 勢力範囲を拡大しておくことにしたのである。
北西に軍を返して、鉅鹿郡の小さな町、 廣阿(こうあ)を抜いた劉秀軍の元に、 続々と援軍が到着していた。 一軍は北の方、上谷(じょうこく)郡太守 耿況(こうきょう)、 漁陽(ぎょよう)郡太守 彭寵(ほうちょう)からの援軍で、 呉漢(ごかん)、寇恂(こうじゅん)といった武将が率いる 突騎(とっき、重装騎兵)であった。 当時は、騎乗の技術的困難さから、 特に訓練された兵だけしか突騎になれない時代である。 強力な突撃部隊である突騎とは、 兵質でたとえるならば現代の特殊空挺部隊に相当し、 兵力で言えば戦車部隊に相当する、 まさに当時最強といっていい部隊であった。 もう一軍は西の方、更始帝が送った援軍で、 率いる将は尚書僕射(しょうしょぼくや)の謝躬(しゃきゅう) である。 尚書僕射は主席皇帝秘書官であるから、地位は低いけれども 皇帝の腹心が任命される。 援軍という名目ではあるが、 いわば、急に大軍を擁するようになった劉秀への お目付け役である。
これらの援軍を得て劉秀は喜び、士卒をおおいに饗して士気を挙げ、 東へ進んで鉅鹿郡の郡都、鉅鹿を包囲して攻めた。 守る王郎側の将軍は王饒(おうじょう)である。 彼は良く防戦し、1ヶ月以上におよび城を守りとおした。 邯鄲の王郎は、倪宏(げいこう)、劉奉(りゅうほう)の二将に 数万の兵を授けて鉅鹿の救援を命じた。
攻城戦は下手でも、劉秀軍は大軍である。 しかも突騎まで擁しているのである。 倪宏、劉奉の二将は、柏人(はくじん)県の東北の 南欒(なんらん、正確には欒に木がない)の地で 劉秀軍に迎撃されて大敗し、数千の戦死者を出して 退却した。 鉅鹿救援は失敗に終わったのである。
しかし、いまだ鉅鹿城は落ちない。 こうなると、大軍を擁する劉秀軍に食料問題が生じる。 鉅鹿郡辺縁の食料が少なくなって補給能力に難が出てきたのであろう。 四月、劉秀軍は鉅鹿を後回しにして軍を動かし、王郎の根拠地 邯鄲を囲んだ。 数で脅かしつつ 連続して攻めに攻め、 五月甲辰の日についに邯鄲城を陥して ついに王郎を誅殺した。
王郎の本拠を落としたことで、王郎の外交文書等も、 多数回収された。 以前、王郎に友好的な態度を示したことのある 人々にとっては、 王郎と内通した証拠ともなりうる文書である。 その数、数千章にのぼったという。 しかし、劉秀はちらとも見ずに、諸将立会いのもと、
「いまにも内通者として殺されるのではないかと、 不安で夜も眠れない人々を安心させて差し上げよう。」
と、すべて焼き捨ててしまった。 不安に耐えかねた諸将が軍中に乱を成すのを未然に防ぎ、 その心を得たのである。 劉林を不安にしたばかりに王郎に苦しめられたという 教訓を生かしたわけである。
邯鄲落城後、更始帝から侍御史(じぎょし)が派遣されて来て、 「節を持して劉秀を蕭王(しょうおう、蕭は徐州沛郡の県)に するゆえ兵の指揮権を返上して首都長安に速やかに詣でるがよい」 という旨、劉秀に告げた。 しかし、劉秀は辞退したのである。
「河北は未だ平定されてはおりませぬゆえ、 御召しに応じるわけにはまいりますまい。」
本紀ではこれをもって劉秀の更始帝に対する独立とする。 時に長安では政治が混乱を極め、 四方の諸勢力は更始帝に背叛していたのである。 本紀に曰く、「 雎陽(すいよう、正しくは且ではなく目、商丘に同じ)には 梁王(りょうおう、梁は陳留ともいい今の開封を指す) 劉永(りゅうえい)が立ち、 巴蜀には公孫述(こうそんじゅつ)が王を称し、 李憲(りけん)は自立して淮南王(わいなんおう)となり、 秦豊(しんぽう)は自ら楚の黎王(れいおう)と号し、 張歩(ちょうほ)は琅邪(ろうや)に起こり、 董憲(とうけん)は東海(とうかい)に拠り、 延岑(えんしん)は漢中(かんちゅう)に起こり 田戎(でんじゅう)は夷陵(いりょう)に挙兵し、 ならびに将帥を置いて郡県を侵略せり。 また、別に号する諸賊あり、 銅馬(どうば)、大[月彡](たいほう)、高湖(こうこ)、 重連(じゅうれん)、 鉄脛(てっけい)、大槍(たいそう)、尤来(ゆうらい)、 上江(じょうこう)、 青犢(せいとく)、五校(ごこう)、 檀郷(だんごう)、 五幡(ごばん)、 五櫻(ごおう)、冨平(ふへい)、獲索(かくさく)、 おのおの部曲を領せり。」 読んだだけでは想像もつかないので、 地図にしるすと、このようになる。
群雄割拠地図
このなかで、劉秀は河北に勢力を確立し、 広大な中国に一雄として名を挙げたのであった。
劉玄伝
劉玄
劉玄(りゅうげん)、字(あざな)は聖公(せいこう)、 光武帝劉秀の族兄、つまり一族の同世代のなかでも年長者である。 通常の列伝ならば、ここで風貌、人格の説明が入るのだが、 劉玄の伝にはそれが無い。 これは、劉玄の名を借りているものの、 彼を擁立した緑林軍という反乱勢力の消息を伝えることが、 この伝の目的だからかもしれない。 同様に、赤眉軍に擁立された劉盆子の伝も、 盆子の風貌、人格を冒頭で伝えてはいない。出奔
劉玄は、弟を人に殺された。 そこらの酔漢に喧嘩で殺されたのなら、 単身仇討ちに出向いても良いのだが、 どうやら都尉(市警察軍の署長)に殺されたらしいのである。 刑殺であったのかどうか、そのあたりの事情は伝に無いが、 二人の都尉に関わるらしいので、 おそらくは死刑に処されたのであろう。 そうなると、仇とは言っても、簡単に討てる相手ではない。 そこで、劉玄は豪傑を客として集めてもてなし、 よってたかって討ってもらおうと考えたのである。 さっそく遊侠の旦那衆に集まってもらい、 酒宴でもてなしたところまでは、大成功である。 酔って歌い出した客のひとりなどは 「朝(あした)にも両都尉を煮殺さん」 と歌い、それこそ劉玄の願いどおりであった。
この宴会に遅れてやってきた遊侠がひとりあった。 酔った衆は喜んで、彼に罰杯を呑ませる歌を歌わせる、 大盛りあがりであった。 が、しかし、あげくの果てにスープの調味にまで追いたてられて、 この遊侠は激怒した。 罰杯、歌舞ならば宴の肴で許されようが、 誇り高き侠客に 下男 奴隷の所業をせよとはなにごとか。 縛り鞭打つこと数百回とある。 へべれけに酔って抵抗もできない親分衆とともに、 劉玄もぐったりするほど鞭打たれた。 それだけならばまだしも、 この宴会の目的を知っていたこの遊侠は、 役所に訴え出たのである。 舂陵(しょうりょう)の劉玄、 両都尉をみだりに殺さんと衆を集めるなり。
劉玄は逃げた。ぼろぼろの体ではあったが 刑吏につかまれば弟同様、 即死刑は間違いない。 身ひとつで口惜し泣きに泣きながら、 宴会の跡もそのままの家を捨てて、 南のかた平林(へいりん)へと逃亡したのである。 しかし、あまりに急ぎすぎた。 刑吏は逃げ遅れた劉玄の父、劉子張(りゅうしちょう)を捕らえて、 劉玄の身代わりにするぞとふれまわったのである。 平林の街に隠れた劉玄は、ほとほと困り果てた。 逃げれば父が死に、出頭すれば自分が死ぬ。 困り果てて平林の城外をうろついていた劉玄は、 墓地に向かう貧しい葬列を見た。 遠い哭声を聞けば、若い男が早死にしたらしい。 近づいて誰ぞか存じませんがと悔やみを述べれば、 あんたに似た息子じゃったと母親らしきが泣く。 劉玄は驚いた。これは身代わりに使える。 早速その夜、かくまってくれていた知人と二人して 柩を掘り出し、 「劉玄は死んだ」と称して 知人にその柩を送っていってもらったのである。
知人は、父 劉子張の解放を確認して平林に戻った。 それに安堵した劉玄は知人に深く感謝して、 これ以上の迷惑はかけられぬと平林を辞し、 どこへともなく逃亡の旅に出た。
緑林
王莽(おうもう)の建てた新王朝の末期、 帝国南部は飢饉がつづいていた。 飢えた人々は群れて野や沢に分け入り、 自生する山芋や蓮根(れんこん)のたぐいを掘って 食いつなぎ、 それでも追い付かなくなると 仲間同士で奪い合ったりと、 たいへんな騒ぎであった。 この難民の群れの中にあって、 次々起こるいさかいを治めて公平であった人物たちは、 やがてこの難民集団の長と目されるようになった。 新市(しんし)出身の王匡(おうきょう)、王鳳(おうほう)といった 人々がそれである。
王匡、王鳳に率いられるようになった難民集団は、 頭目の公平さが魅力となり、 衆を増やして数百人を数えるまでになった。 こうなると、流賊や難民というより、 ちょっとした勢力である。 地方官の取り締まり程度なら、逆に撃退できるほどである。 官の捕縛を恐れずに済みそうだとなると、 罪を得たり仇と狙われたりして亡命している無頼の徒も、 この勢力に加わってくるようになった。 馬武(ばぶ)、王常(おうじょう)、成丹(せいたん)といった、 将たる人材がそろいはじめたのである。 また、人数が多くなると、 野草の採取だけでは食いつなげない。 人数を頼みに、 城壁に守られていない中小の集落を攻めては食糧を得、 緑林(りょくりん)の山を頼みに、 官の掃討から逃れ隠れるようになったのである。 これで上手く食って行けるとなると、噂が噂を呼び、 数ヶ月のうちにたちまち七、八千人の大集団となった。
緑林山は江夏(こうか)郡に属し、 ひいては荊州(けいしゅう)の牧(ぼく、軍務政務監督官)の 管轄である。 荊州七郡百十五城を監督するとはいえ、 北の三十余城を擁する州内最大の南陽郡は 前隊大夫(南陽方面軍司令官)の監督下にあって、 州牧の管理権はとどかない。 他の江夏郡、南郡、長沙郡など諸郡の実権は 各郡の太守にあり、郡軍の兵権は郡都尉にある。 そこで、江夏郡の都尉に緑林の賊の討伐を督促したが、 返ってきた答えは拒否である。 江夏郡十余城、総数でも三万の守備軍をすべて発しては、 十余の城を他の諸賊の攻勢から守れず、 かといって一万程度の軍では、 緑林山の険に拠る八千を討伐するのは無理である。 憤激した着任して間もない荊州牧は、地皇二年(21AD)、 お膝元の南郡の予備役兵を召集。 総勢二万の軍勢で緑林賊討伐に撃って出た。
迎える王匡(おうきょう)ら率いる緑林の衆は、 この二万の討伐軍の来襲を聞いて迎撃に出ると決めた。 衆が増えすぎているのである。 地道に守って撃退するより、 一戦迎え撃って負ければ散り、 勝てばその軍需物資を得るという作戦の方が、 増えすぎた衆の維持には得策と判断したのであろう。 無名ではあったが、馬鹿ではなかったのである。
決戦の場は雲杜(うんと)である。 この一戦に命を賭けた緑林の衆と、 数を頼んで押し寄せた急造の荊州牧の軍と、 軍神の祝福を受けたのは緑林側であった。 おおいに牧軍を破り数千人を殺し、その輜重を獲る。とある。 緑林の勢力は軍装を手にしたのである。 勢いを得た緑林の衆は境陵(きょうりょう)の県城を攻め落とし、 つづけざまに雲杜(うんと)県、安陸(あんりく)県をも攻撃し、 多く婦女を略奪して緑林山中に帰還した。 とくに婦女略奪については 「家族をつくる気になったことを物語る」とする陳舜臣氏の 説がもっともらしいように思われる。 雲杜の戦勝で軍備がととのい、 衆が定住できると思う程度に生活が安定したことで、 緑林への参加者は激増した。 各地の飢民、流民がなだれこんだのである。 衆は五万余を数え、州や郡といった地方組織では 制圧できる規模ではなくなった。 緑林は兵威を増し、乱世の一軍として割拠したのである。
離合
翌地皇三年(22AD)、緑林軍は半減した。 狭い山中に人口が増えすぎ、疫病が大流行したのである。 疫病を防ぐにはその地を去るのが良策である。 それでも三万近く残った衆を北と西、二手にわけて行軍することとした。 「王常(おうじょう)、成丹(せいたん)らは、 西のかた南郡(なんぐん)に入りて下江兵(かこうへい)と号し、 王匡(おうきょう)、王鳳(おうほう)、馬武(ばぶ)及び、 その支党 朱鮪(しゅゆう)、張仰(ちょうぎょう)ら、 北のかた南陽(なんよう)に入りて新市兵(しんしへい)と号す。」 とあるが、張仰だけは、他の伝では下江兵にあるので 新市兵にあったというのは誤りであろう。 ともあれ、各自将軍を自称し、進撃を開始したのである。
話は北上した新市兵に移る。 七月、南陽郡に侵入した新市兵は、最初の大城 随(ずい)を攻略して未だくだせず、 早くも苦戦を強いられていた。 しかし、江夏に覇を唱えし緑林の兵来たるの報は、 南陽郡に動揺をもたらした。 平林の人 陳牧(ちんぼく)、廖湛(りょうたん)は、 千余人の衆を集めて平林兵(へいりんへい)と号し、 緑林軍に応じた。 このとき、平林近くをうろついていた劉玄(りゅうげん)は、 陳牧らの軍に従って安集掾(あんしゅうえん、人事官補佐)に 任命されていた。 また、舂陵(しょうりょう)で 劉[糸寅](りゅうえん、伯升)、 劉秀(りゅうしゅう、後の光武帝)兄弟が挙兵したのも この頃である。 南陽の緑林軍は、 在地諸勢力の合流を受けてその勢力を増やし、 そして変質していったのである。
地皇四年(23AD)正月、緑林軍は、王莽(おうもう)軍 前隊大夫(南陽方面軍司令官)甄阜(しんふ)、 屬正(副司令官)梁丘賜(りょうきゅうし)率いる 十万の兵を破って両将を斬った。 劉玄はこの戦勝で「更始将軍」の号を得る。
登極
南陽郡の都、宛(えん)を包囲し 破竹の勢いを示す緑林軍のもとには、 次々と参加を願う軍衆が到着し、 どこにだれがいて何人率いているのかすら 把握が困難になりつつあった。 軍制の確立と命令系統の統一が必要となったのである。 そのため、諸将は協議のうえ、劉玄を立てて皇帝にすることとした。 以上が劉玄伝に記された、擁立の経緯である。 しかし、その裏には、台頭する伯升派を抑え、 早めに高位を確保しておきたいという、 緑林軍首脳の思惑があった。
二月辛巳、[シ育]水(いくすい)のほとりにある 開けた砂地に壇を設け、兵を連ねて大いに会し、 更始帝は即位位した。 壇上に登り、南面し、群臣の祝賀を受けた。 軍中であるから、ここで諸兵も群臣も皇帝の言辞を待ったが、 もとより惰弱と言われた更始帝である。 羞じて汗を流し、手を挙げて、言うあたわずと伝えられる。
儀式的にはぱっとしなかった更始帝であるが、 さっそく即位にともなう政務処理は行った。 天下に大赦し、元号を建てて更始元年とし、 ことごとくに諸将を拝置したのである。 伝に連なるところを見れば、 族父 劉良(りゅうりょう)を国三老となし、 王匡(おうきょう)を定国上公に、 王鳳(おうほう)を成国上公に、 朱鮪(しゅゆう)を大司馬に、 伯升を大司徒に、 陳牧(ちんぼく)を大司空にしたとある。 他は皆、九卿か将軍である。 緑林軍首脳が政権の枢要を占め、 伯升派は疎外されたのである。
しかし、伯升派は強かった。 五月、伯升軍は南陽郡都、宛(えん)城を抜いたのである。 六月、更始帝は宛城に入り、これを都とした。 皇帝がいてもおかしくない程度の大都市を やっと手中にしたのである。 ことごとくに宗室および諸将を封じて列侯となした。 列侯となるもの百余人と伝にある。 この宛城を落としてくれたのは伯升であるが、 伯升の評判はますます高まり、 更始帝の影は薄くなるばかりである。 更始帝、そしてその政権を支える緑林軍首脳は 伯升の威名を憎んだ。 そして、ついに伯升を誅殺し、 光禄勲 劉賜(りゅうし)をもって大司徒の後任となしたのである。
進撃
前の鍾武(しょうぶ)侯 劉望(りゅうぼう)は、 緑林軍とは縁の無い男である。 彼は、乱世と見るや、 兵を起こして近隣を攻略し、 汝南(じょなん)一郡を有するほどの勢力を築いた。 汝南郡は、南陽郡の東隣である。 時に王莽の納言将軍 厳尤(げんゆう)、 秩宗将軍 陳茂(ちんも)の二将が、 昆陽の戦いに敗れて王莽を見限り、 この劉望のもとへ走って帰属していた。 この劉望が、更始帝に刺激され、 八月、ついに自ら立って天子を称したのである。 厳尤を大司馬、 陳茂を丞相という配置である。 守勢に回った王莽は、 太師 王匡(おうきょう)、 国将 哀章(あいしょう)に命じて 洛陽を守備する構えをとらせた。 対して攻め手は更始帝である。 定国上公王匡を洛陽攻撃に北進させ、 西屏大将軍 申屠建(しんとけん)、 丞相司直 李松(りしょう)に軍を与えて 北西に山道を進ませ武関を攻略して、 まっすぐ首都長安を突かせた。 長安は、震動した。
明らかな王莽の劣勢に、 このとき、全国のの豪の者たちが動き始めた。 皆、その州の牧や郡の太守を殺して兵を握り、 将軍と自称し始めたのである。 漢の年号を用いてもって詔命を待つものも多く、 これは今のうちに地方を握り、 のちのち有力になった勢力に併合してもらい、 新しい朝廷で高位を得ようという連中である。 わずか数十日の間に天下の情勢は一気に変容したのだ。
首都長安も例外ではなかった。 長安内でも兵を起こす勢力があり、 これが未央宮(びおうきゅう、皇帝居宮)を攻めた。 九月に東海の人 公濱就(こうひんしゅう)が、 王莽を池中の楼閣 漸台において斬った。 璽綬を収め、首を伝えて宛に送り、 ここに王莽の政権は滅びた。
王莽の首がとどいたとき、 更始帝は、時に仮皇宮の黄堂(皇帝居室)にいた。 取りて見て喜びていわく、 「王莽このごとくにならざれば、まさに霍光と等しかるべし。」 と伝えられる。こんなことにならなければ、 霍光という昔の漢王朝の大忠臣にならび賞される人物になれただろうに、 というわけである。 これを聞いた寵姫の韓夫人は、笑って、 「もし『こんなこと』になってなければ、 私たちはどうやって今のこの地位を得られましょう。」 と答えたという。 更始帝は悦び、王莽の首級を宛城の市場に懸けさせた。
十月、 奮威大将軍 劉信(りゅうしん)が 汝南に割拠していた劉望を撃殺した。 併せて厳尤、陳茂の両将も誅された。
遷都
王莽の首が体を失った月、洛陽も陥落した。 洛陽は全国でも第二の大都市である。 更始帝も、ついに北方、洛陽に都することとした。 王莽側の洛陽守将 王匡、哀章は生け捕りにされたが、 更始帝が皇宮を洛陽に移してきたときに、 二将とも斬刑に処された。
洛陽に移った更始帝は、 劉賜(りゅうし)を丞相とした。 しかし、これに不満なのは長安を落とした申屠建に李松である。 彼らは長安から駅伝で乗輿服御を洛陽に送り、 また、中黄門の従官を遣わして更始帝を奉迎し、 長安への遷都を進言した。 ついに更始二年の二月、更始帝は洛陽より西した。 が、このときひとつ凶事があった。 初め、出発するのに李松が馬車を奉引していたのだが、 馬が、突然何かに驚き走り、北宮の鉄柱門にあたったのである。 三馬皆死し、続漢書に 「馬禍也。時に更始、道を失いまさに亡びんとする徴(しるし)」。 と記される。
初め王莽が敗れたときには、ただ未央宮のみが焚かれ、 そのほかの宮館はひとつも壊れたものが無かった。 宮女数千、後宮に列なり、 鉦鼓、帷張、輿車、器服、太倉、武庫、官府、市里、 すべてもとのままであった。 更始帝はすぐに長楽宮に入り、 前殿に上った。 中庭には郎吏が席次順に並び、更始帝を迎えたが、 例によって 更始帝は恥じ怯え、首をうつむきて、 席でもぞもぞとするばかりで、 あえて見ようとはしなかったという。 引見を終えて、 後から到着してきた諸将に、 更始帝は捕虜数や掠奪した物資の量を問うた。 宮仕えの長い左右の侍官たちは、 この新しい皇帝陛下の 下世話な質問に驚いて視線を交し合ったという。
政治
長安にようやく腰をおちつけた更始帝に、 李松、棘陽の人 趙萌(ちょうぼう)の二人が 早速にもといって進言したことがある。 諸功臣をことごとく王にすべしというのである。 更始帝ちかくにあった朱鮪は反対し、 漢王朝の高祖 劉邦(りゅうほう)が作った、 劉氏にあらざれば王とすべからずという 決まりを根拠に、思いとどまるよう奏上した。
更始帝は、まず先に問題のない宗室を封じた。 順番に列記すれば、 太常将軍 劉祉を定陶王に、 劉賜を宛王に、 劉慶を燕王に 劉歙を元氏王に 大将軍 劉嘉を漢中王に、 劉信を汝陰王に、それぞれ封じたのである。 そして、のちについに、諸将をも封じた。 長くなるので一覧すると、
王匡 比陽(ひよう)王
王鳳 宜城(ぎじょう)王
朱鮪 膠東(こうとう)王
衛尉大将軍 張仰 淮陽(わいよう)王
廷尉大将軍 王常 [登邑]王
執金吾大将軍 廖湛(りょうたん) 穣王
申屠建 平氏王
尚書 胡殷 隋王
柱天大将軍 李通 西平王
五威中郎将 李軼 舞陰王
水衡大将軍 成丹 襄邑王
大司空 陳牧 陰平王
驃騎大将軍 宋佻 潁陰王
尹尊 [堰邑](えん)王
といったぐあいである。 ひとり朱鮪のみは辞した。 「臣は劉宗にあらず。あえて典範を干さず。」 と、筋は通したのである。ついに最後まで譲って受けなかった。 そこで更始帝は朱鮪を遷して左大司馬とした。 また、劉賜を前大司馬となし、李軼、李通、王常らと 関東を鎮撫させるべく出陣させた。
諸将封王を奏した 李松は丞相、 趙萌は右大司馬となり、 ともに宮中の諸事を司った。 更始帝は、趙萌の娘を後宮に納れ、夫人とした。 彼女は寵愛され、ついに趙萌は更始帝に政権を ゆだねられるまでになった。 更始帝が政事を放り出して打ち込んだものは、 酒である。 日夜後宮に入り浸っては婦人たちと酒を飲み、 歓談していたのである。 群臣が奏事ありとして更始帝の出御を願っても、 たいてい酔いつぶれていて、 すぐには謁見に出られないありさまである。 困った近臣は、やむをえず侍中を身代わりに 帷(とばり)の中に座らせておき、 そこで奏上を受けることとした。 しかし、更始帝と戦陣をともにした諸将である。 声が更始帝ではないのはすぐにわかってしまった。 退出して皆、怨みを言ったとある。 ところが、怨みの言には続きがあった。 「成敗いまだ知るべからず。」 つまり、可と言われようが、不可と言われようが、 それは皇帝自身の言葉ではないのだから、 従う必要はない、好き勝手にやってやろうというのである。 長安に移った更始帝政権は急速に統制を失っていったのである。
皇帝が酔いどれであっても、後宮がしっかりしていれば、 皇帝をたしなめて政事を執らせる可能性もあった。 しかし、後宮の筆頭たる更始帝の古女房の韓夫人は、 夫以上の酒飲みであった。 酒の席には必ずはべり、随一の酒飲みと目されていたのである。 これでは、夫である更始帝をたしなめるどころではない。 常侍(じょうじ、宦官なので後宮に入れた)が奏上の文書を 取り次いできたのを見咎め、 「帝は今まさに私とむかいあって飲まれているというのに、 よりにもよってこんな時に奏上とは何事か。」 怒声を発するやいなや立ち上がり、 文書を取り上げて打ち破ってしまったほどである。 夫に酒を絶たせることなど、期待するだけ無駄という女性であった。
権勢を極めたのは趙萌である。 権力をふるって私腹を肥やすのに余念が無かった。 ある郎吏が、たまたま朝廷にふらりとやってきた更始帝をつかまえ、 趙萌が放縦であると訴えたが、 虫のいどころが悪かった更始帝に剣を抜かれて その場で撃たれる始末であった。 しかし、更始帝も例のごとく酔っていたであろうから、 剣はかすりもしなかったであろうし、 万一あたってもたいした傷ではなかったようだ。 更始帝もその臣下は気に入っていたようで、 その後のおとがめは全く無かった。 それどころか侍中に昇進させたらしい。 ところが、これにおさまらないのは趙萌である。 さっそく件の侍中を逮捕した。 逮捕の報に驚いた更始帝が、 命ばかりは助けてやってくれと嘆願したが、 趙萌は更始帝の要請をさらりと蹴って、その侍中を斬った。 皇帝の威令などというものはすでに無かったのである。 先の封王の件で誠意を見せた朱鮪は、 李軼とともに命を山東に受けて戦陣にあり、 すでに長安にはいなかった。
長安は悪政にあえいだ。 皇帝は酒びたりで威令も無く、 権力者 趙萌は財を積むのに熱心で、 王匡、張仰といった緑林のガラの悪い連中が 横暴を極めているとくれば、悪政以外のなにものでもない。 官爵の授与もまったくでたらめで、 緑林出身以外の高官といえば、 ほとんどが将軍たちに小銭を貢いだ悪賢い商人であった。 あるいは給仕人や料理人まで官爵を得た。 彼らは、刺繍された衣装、錦の袴に身をつつみ、 都大路をおお威張りで練り歩き、 道中口汚くののしったりと、 人望を失うことなら大得意であった。 当時、長安で楽しまれた語り草に曰く、 「 かまどの世話すりゃあ中郎将、 羊肩をあぶれば騎都尉になれる、 羊頭なんかあぶった日にゃあ 関内侯にだってなれちまう。 」
諫言
軍師将軍 李淑(りしゅく)は、 豫章(よしょう)の人である。 彼は上書して更始帝を諌めた。
『 今、賊の取り締まりは始まったばかり。 王化は行われたわけではありません。 百官、有司は、よろしく任務を慎んでおこなわねばなりません。 三公(首相クラス)は、上は星の運行に応じ、 九卿(大臣クラス)は、下は河海を統括し、 そうして天の意に沿う治世をおこなわねばなりません。 陛下には、下江平林の勢によって帝業を定められたといえども、 時に応じて対処していかねばなりません。 まだまだ安穏としていられる状況ではないのです。 制度を改革し、英俊を集め、才能によって官爵を与え、 そうして国中をただしてゆかねばなりません。 今、公卿、大位は、みな戦陣にあって 戦っていないものはなく、 尚書、顕官は皆出て、亭長の賊捕の遂行をしやすくし、 そうして陛下の補佐、綱維の任にあたっている、 そうなっていなくてはなりません。 名と器とは聖人の重きとするところです。 ところが今、重任の地位に非才の者があたっておりますのに、 民衆を助け王化を促進し理を行おうと望まれるのは、 いわば、 木によって魚を求め、 山に登って真珠を採ろうというもの。 全国で善政が望まれているのですから、 漢の祭りを慎んで執り行われますよう。 臣は、憎むところがあったり、自分の昇進を求めて、 このようなことを申しているのではありません。 陛下の近頃の挙措を惜しんで申し上げているのです。 材を破り、錦を傷めぬよう、その道の職人に任せるように、 よろしく人材に官爵をお与えになりますよう。 古の失政の誤りと同じ点を除き、 聖人の治世にならわれますよう。 』
更始帝は怒って李淑を投獄し、関中(首都圏)の人心は離れた。 四方、怨叛すと史書に記される。
いっぽう、地方では、更始帝の諸将が勝手に州牧、 郡太守を任命したので、あちこちで任命の重複があり、 州郡の管理は錯綜していた。
王昌(王郎) 伝
王郎
王昌またの名を王郎(おうろう)という。 趙国は邯鄲(かんたん)の人である。 もともと占い師で、星歴に詳しく、邯鄲の天をみて 「この河北の地に天子の気がある」と言っていた。詐術
時の趙国の繆王(ぼくおう)の子に劉林(りゅうりん) という者がおり、王の跡を継いで趙国を治めていた。 彼は奇術好きで、任侠をきどり 趙国や魏国の豪傑たちとの交友を好んだ。 乱世である。豪傑たちとの交友は兵力につながり、 保身手段としても有効であったのだろう。
王郎にとって、この庶民と交友をもちたがる世間知らずは、 格好の餌である。 奇術を面白がる劉林にあること無いことを可笑しく話し、 親しくなって生活費を稼ぐことなど、朝飯前どころか 無意識にだってできるくらいであった。 ここで若造を手玉にとって一生を安穏に暮らせば、 ただの詐欺師で終わるものを、 野望を逞しくした王郎は若造の握る兵力に目をつけた。
劉林が領する邯鄲は大都市である。河北地方随一と言ってよい。 その大都市を背景に兵を募れば、河北地方を握ったも同然にちかい。 ましてや世は乱れ、 誰が最後に皇帝になるかは、全くわからない状況である。
王郎も乱世に打って出ることを望んだ。 皇帝になれるかもしれないのだ。
世は新王朝の治世を恨み、先の劉氏の漢王朝の再興を望んでいた。 しかし、王郎は劉氏ではない。これは不利であると悟った王郎は 劉氏に化けることにした。加えて、できることなら劉林より 帝室に近い血筋に化ける方が、兵力掌握、皇帝即位に有利である。
王莽(おうもう)が新王朝を建て、 漢の世を奪ったころの首都長安に 「我こそは漢の成帝の子、劉子輿(りゅうしよ)である」と 自称して王莽に斬られた人物がいた。名を武仲(ぶちゅう)という。 王郎はこの先例を利用することにしたのである。
王郎は秘話を打ち明けるふりをして劉林に語った。
「本当の劉子輿とは実は私のことなのだ。 母は故成帝の歌姫で、成帝の寵をうけて妊娠し、後宮に一室を賜った。 しかし、趙皇后の嫉妬は深く、害されそうになったために、 奴隷の子と取り替えて偽ったのだ。 そのおかげで、生き延びることができたのである。 十二歳のときに天命を知る郎中 李曼(りまん)卿とともに 蜀に行き、十七歳で楚の丹陽に至り、二十歳にして長安に戻り、 中山国に転じ、燕国や趙国の往来に忍び、 もって天の時を待っていたのである。」
誘惑
劉林は戸惑った。 彼とて占い師のこんな話を鵜呑みにするほど馬鹿ではない。 ありえないことではないと思ったものの心から信ずるには程遠い。 しかし、劉林は疲れていたのである。 ちょうど首都長安の新王朝は倒れ、政局の混迷は深まっていた。 代わりに建った緑林軍の更始帝の勢力と 山東の大勢力赤眉軍の境界近くに位置する邯鄲は、 そのどちらから攻められてもおかしくないという、 政治的にも軍事的にも舵取りの難しい状況に置かれていた。 とりあえず、更始帝からの使者劉秀(りゅうしゅう)を 迎えて友好的な関係を作ったものの、 赤眉軍が攻めてきても到底助けてはもらえそうにないのである。 こんな難しい立場なぞ、誰かに代わってもらいたいくらいだと 考えていた。ちょうどそんなときに王郎に野心を表明されたのである。
劉林は大豪族の李育(りいく)、張参(ちょうさん)たちに 打診してみたところ、彼らは王郎擁立に乗り気であった。 うまくいけば新しい王朝の重鎮になれる機会と思ったのであろう。 加えて、本当に赤眉軍が黄河を渡って攻めてくるという噂が 流れてきた。
劉林は焦った。もうあとはどうなってもいいから、責任を誰かに 押し付けて逃れたくなったのである。 急いで「劉子輿(王郎の詐称)を擁立して、 緑林軍とは縁を切る。」と赤眉軍に使者を走らせた。 要するに中立になるから攻めないで欲しいと申し送ったわけである。 そして車騎数百で邯鄲城の趙王王宮に突入して、 緑林軍派の人員を追放し、王郎を立てて天子とした。 劉林は丞相、李育は大司馬、張参は大将軍である。 時に更始元年十二月、漢王朝再興を願う民心を得て、 百姓は多く本物の劉子輿だと信じたという。
檄文
邯鄲を掌握した王郎は、早速河北制覇に乗り出した。 大都市の兵力で脅し、劉子輿の名声で帰順を促したのである。 幽州冀州に武将を派遣し、檄を州郡に撒いた。
檄文に曰く、 「部の刺史、郡の太守に告げる。 朕は孝成帝の子、子輿である。 昔は趙氏の禍に遭い、今は王莽(おうもう)の簒殺によって、 天命を知る者たちに身を護られつつ、姿を変えて河浜に隠れ、 趙魏に足跡を隠してきたのだ。
王莽が帝位を盗み、罪を天に得たものの、 いまだ天命は漢王朝を助けている。 東郡の太守 義(てきぎ)、 厳郷侯 劉信(りゅうしん)をして 兵を擁せしめ、服属しないものを征討させるであろう。 朕が民間に隠れているのは天下に知れ渡っており、 南陽郡などの諸々の劉氏は朕のために先駆したのである。
朕、天文を仰ぎ観るに、時を得たのを知り、 今月壬辰をもって趙宮にて即位した。 気は休みて薫り蒸し、時に応じて雨を得たり。 国のために子が父を襲うのは古今容易なことではないと聞いている。 劉聖公(りゅうせいこう、更始帝)は、 朕のことをいまだ知らないのであろう。 そのため一時的に帝号を称してるだけである。
義兵を興しておおいに朕を助ける者は、皆、封土をあたえ、 子孫に継がさせよう。 すでに劉聖公と 太守 には勅使を送り、功臣となすゆえ すみやかに朕のもとに参られよと伝えておる。 刺史、太守はみな劉聖公が任命した者なので、 いまだ朕を知らずに疑っておろう。 強き者は武力をたのみにし、弱き者は恐れおののいておろうが、 乱世ゆえ戦い傷ついたものが大半であろうから、 朕はそれをはなはだ悼み、使者をやって詔書を下し、 帰順をうながすのである。」
ここで 義(てきぎ) という人物が出てくるが、 彼は初期に王莽に叛旗をひるがえして敗れた人物である。 百姓が漢王朝を思い、多くの民が 義は未だ死んでいないと 希望し信じているために、 故意に偽って人望集めに利用したのである。 この檄文によって、趙国以北、遼東以西の河北地方は 風に従ってなびくように ほとんど王郎勢力下に入ってしまった。
劉秀軍
河北を席捲した王郎だが、その王郎に従わなかった郡がある。 信都(しんと)郡である。 その信都郡に更始帝軍大司馬代行の劉秀が、北の薊(けい)より 逃れてきて兵を発して傍らの縣(町)を従え、 ついに柏人(はくじん)を攻めてきた。 しかし、王郎軍は柏人防衛に成功。 劉秀軍は諦めて東北の鉅鹿攻めに転じた。 包囲された鉅鹿郡の太守は王饒(おうじょう)である。 彼は城に拠って数十日、連日の攻撃に耐え続けた。
王郎軍の堅い守備に阻まれて難渋していた劉秀軍であるが、 耿純(こうじゅん)という武将が劉秀に説いて言うには、
「久しく王饒に耐えられては、兵が疲弊します。 それより、大兵精鋭で敵の本拠地邯鄲を攻めるべきです。 もし王郎が誅殺されれば、王饒なぞ戦わずに降伏しましょう」
劉秀はこの作戦を容れ、将軍 満(とうまん)を 王饒包囲軍留将としておき、自らは軍を邯鄲に進めた。
邯鄲攻防
邯鄲は大都市だけに大城である。 劉秀軍は、その郭北門外に駐屯した。 城から距離をおいて軍営を置き、王郎軍を挑発したのであろう。 劉秀軍は2度も城攻めに失敗しており、 大城を攻めて落とせる自信があったはずがない。 ここで、王郎は籠城せずに撃って出たのである。 河北はなびいたばかりで、どこからも援軍のあてがないからか、 天子を称した者の威厳にかかわると思ったのか、 劉秀軍に勝てると思ったためか、その理由はわからない。 しかし、数戦して王郎に利あらず、王郎は講和を求めた。
講和の使者は諌議大夫 杜威(とい)である。 杜威の降を請いて曰く
「恐れ多くも成帝の御子である。天子としてお迎えなさるのが 礼儀であろう。」
劉秀の答えて曰く
「たとえその成帝御自ら生き返られたとしても、 とうてい天下は得られないであろうのに、 子輿(しよ)などと詐している者ごときが天下を得られようか。 天子として迎えることなど無理である。」
「請い求めるに、万戸侯の地位では。」
「命が助かるだけでも良い方ではないのか。」
「わかりました。邯鄲は田舎町といえども、力を併せて固く守れば なお日月を稼げましょう。 君臣ともに降伏せずに、ついに命を失うことになったとしても。」
杜威は辞去し、劉秀軍は城攻めに移った。 急攻二十余日、王郎軍少傅 李立(りりつ)の反間によって 邯鄲の城門は開けられ、劉秀軍が突入。 邯鄲は落城した。
王郎は夜をついて逃げたものの、乱戦の路上に 劉秀軍武将王覇(おうは)の刃をうけて落命した。 詐術をもって乱世を駈け抜けた一人の占い師の最後であった。
劉[糸寅]伝
劉[糸寅]
斉の武王、劉[糸寅](りゅうえん)、字(あざな)は伯升(はくしょう)、 光武帝劉秀の長兄である。 (敬意を表してか、列伝では字の伯升をもって呼ばれるので、 以下それに従う。) 剛毅で太っ腹な性格であり、遠大な野望を抱いていた。 王莽(おうもう)に乗っ取られて滅びた、 漢王朝を再興しようというのである。 「常に憤憤と慮を懐(いだ)く」とあるから、 熱い思いを胸に秘め、 常に瞳を燃やしているような男であったのであろう。 そんな人間である伯升は、家の仕事なぞ手伝いもせず、 身を傾け産を破って天下の雄俊と交わりを結んだ。機宜
王莽の親政も八年を過ぎるころ、 その失政から各地に盗賊が群れ起ち、 とくに南方、長江中流域が最もひどい状況となった。 伯升のいる南陽郡は長江中流に近い。 挙兵には絶好の機会であった。
諸豪傑を召集した伯升は、計議して曰く、
「王莽は暴虐にして、人民は頼るものも無く崩壊した。 今、旱魃が毎年のように続き、反乱軍が並び起っている。 これこそ、天が王莽を滅ぼそうとしている証拠。 高祖劉邦の偉業を再び興し、 万世を定める秋(とき)である。」
今さら挙兵の必要を訴えられなくとも、 もとよりその心づもりの者ばかりである。 すみやかな衆議一決ののち、早速兵力確保の手配がなされた。 伯升たちは豪族か一匹狼の集まりであって、 最初から人数が集まっている盗賊や流民の集団ではない。 これから募兵しなければならないのである。 伯升は、親類、客将を派遣して各地で挙兵させ、 現地の流民、盗賊を吸収し、 それを合流させる策に出た。 晨 (とうしん)を 新野(しんや)に挙兵させ、 劉秀を李通(りとう)、李軼(りてつ)らとともに、 宛(えん)に挙兵させるといった具合である。 伯升自身は、地元舂陵(しょうりょう)に挙兵した。 一族子弟あわせて八千の兵を客将に部署させ、 みずから柱天都部(ちゅうてんとぶ)と称したという。 柱天都部とは、 天を柱(支)え、部(衆)を都(統)べる意であり、 豪放な命名に、その大望がうかがえる。
しかし、大望を抱いて、志を高くしたところで、 兵少なくして戦に負けてはお話にもならない。 当時、一郡の兵は五万程度である。 戦乱で分散、減員していても、二万は下らない。 たかだか一万強の兵を率いる伯升軍では勝ち目は薄いのである。 そこで、挙兵当初からすでに計画されていたのであろう、 すぐ南に隣接する反乱軍、緑林軍の一隊との合流を画策した。 一族の劉嘉(りゅうか)を使者にして、 新市兵主将 王匡(おうきょう)や、 平林兵主将 陳牧(ちんぼく)らを勧誘して 兵力増強を図ったのである。 当時、二万弱程度と思われる緑林軍の新市、平林兵は、 まったくの流民集団である。 物資の不足を嘆く緑林軍にとっても、悪い話ではない。 この合流は難無く果たされた。
小長安
緑林軍と合流した伯升軍は、 西に向かい、長聚(ちょうしゅう)を撃ち、 唐子郷(とうしごう)を屠り、 守備についていた湖陽(こよう)の尉(市軍将軍)を殺し、 進んで棘陽(きょくよう)を抜き、 まさに破竹の勢いであった。 南陽郡南部を制圧した伯升軍は 意気揚がり、ついに南陽郡都 宛(えん)を攻略せんと 北上を始めた。
場所は小長安という集落であった。 時、くしくも天空に濃霧が満ち、視界は白く煙っている。 訓練の無い流民の多い伯升・緑林連合軍は、 行軍停止を余儀なくされた。 軍令が簡略であるため視界が悪くては 作戦行動がとれないのである。 霧の晴れるのを待つ伯升軍の回りは冷たい白一色であった。 と、白い視界に次々と黄色い旗が浮かび上がり、 またたくまに林立する黄色い軍団となった。 黄色は土徳を唱える王莽軍の色である。 前隊大夫(南陽方面軍指令官) 甄阜(しんふ)と 屬正(副将軍) 梁丘賜(りょうきゅうし) 率いる 十万を越える王莽軍であった。
おそらく、伯升軍の位置を捕捉した甄阜(しんふ)が しかけた会戦であろうが、濃霧のために 伯升軍にとっては奇襲でしかない全くの遭遇戦となった。 しかも、伯升軍は応戦はおろか、退却さえできなかった。 訓練されていないがゆえに真っ先に統制を失った緑林の兵が、 わめき叫び、われさきに逃げ出したため、 大混乱に陥ったのである。 対して王莽軍は正規軍である。 濃霧の中でも統制はある程度とれた。 しかも、五万に足りない混乱した伯升軍を相手に、 訓練された正規兵十万である。 こうなると、会戦などではない。 白霧に包まれた小長安は、一方的な殺戮の場となった。
全くの伯升軍の大敗であった。伯升の家族でも、 姉 劉元(りゅうげん)、 次弟 劉仲(りゅうちゅう)が乱戦の中に散った。 一族で数えれば戦死者は数十人に及んだとされる。 伯升は混乱の戦場から逃れて敗兵を集め、 さきに陥とした棘陽(きょくよう)の城壁に拠った。
破釜
前隊大夫 甄阜(しんふ)は勝ちに乗じた。 行軍速度の遅い輜重部隊を藍郷(らんごう)に留めて補給基地とし、 精兵十万を率いて南下したのである。 黄淳水(こうじゅんすい)を渡って [シ此]水(しすい)に臨み、 これら二つの川に挟まれた地に軍営を築いた。 しかも、後ろの黄淳水にかかる橋を切って落とし、 自ら退路を絶って、南陽郡南部奪回への意気込みを示した。
軍の戦意高揚を図って、 小競り合いを試みた伯升軍ではあったが、 数回試みてすべて敗れ、 かえって新市平林兵の戦意を落とす結果となった。 さらに悪いことに、彼らは王莽軍の威容におびえて、 離散の動きすら見せはじめたのである。 伯升の憂患すること甚だし。と後漢書にある。
これを救ったのは緑林軍の別働隊、下江兵である。 いったん新市兵と別れて長江に沿って西に進んだのであるが、 厳尤(げんゆう)率いる王莽軍に阻まれ、 長江沿いにうまく勢力を伸ばせずに荊州に戻り、 そこで荊州牧を破って宜秋(ぎしゅう)に勢力を回復していたのである。 さっそく伯升はこの下江兵を吸収しようとする。 自ら交渉に赴いて、 下江兵の中でも教養と信望のある部将を選んで説得したのである。 下江兵は、その兵五千余と後漢書にはあるが、 実際にはもっと多かったと思われる。 この下江兵と伯升軍の合流を果たすために、 交渉役となった下江兵部将 王常(おうじょう)が尽力するのであるが、 王常伝には下江兵首脳陣は衆を頼んで伯升の下に付くのを嫌ったとある。 伯升・新市平林連合軍と下江兵とは対等、 あるいは下江兵が優勢であったのであろう。 この独立不羈を好む下江兵との合流をなんとか果たした伯升は、 おおいに軍士に饗し、盟約をもうけて三日間の休息をとった。
三日後、伯升は兵を六部に分け、 部隊を密かに潜行させて夜間急襲して 王莽軍補給基地 藍郷(らんごう)を得た。 その日のうちに輜重物資を回収した伯升は、 次の作戦にすぐさま撃って出た。 補給基地を失って士気を低下させた王莽軍を 翌日早朝に挟撃したのである。 伯升軍は南西から主将甄阜(しんふ)の軍を討ち、 下江兵が南東から副将梁丘賜(りょうきゅうし)の軍を攻めたのである。 早朝からの戦闘は激しかったものの、 短時間で勝敗はついた。 朝食時には、まず梁丘賜の陣が破られ潰走し、 それを望見した甄阜軍も散壊しはじめたのである。
伯升軍は急追に入った。 先の敗戦の恨みも加わって、容赦無い追撃となった。 追撃された王莽軍は悲劇であった。 敵の恨みを買っていたこともあるが、 逃げようにも背後の川の橋は自ら落としてあったのである。 川に飛び込むより他に逃げようが無かった 王莽軍前隊は壊滅した。 伯升軍に斬首された者、 黄淳水に溺死した者、あわせて二万余にのぼったという。 この敗戦で、甄阜、梁丘賜、両将軍は戦死し、 これと合流を目指して行軍中であった 王莽軍の納言将軍 厳尤(げんゆう)と 秩宗将軍 陳茂(ちんも)の軍は、 宛(えん)城へと退却を始めた。
伯升は突然に好機を捉えたと思った。 南陽郡都 宛(えん)の守備隊はほとんどいないはずである。 戦勝の勢いで進めば、 一気に落とせるに違いないのである。 すぐさま兵を整列させた伯升は、 兵糧物資を焚き、鍋釜を破って、 軍衆に不退転の決意を告げ、 鼓を打ち鳴らして猛然と進軍を開始した。
不運だったのは厳尤、陳茂率いる王莽軍である。 宛への退却途中に、この血気逸った伯升軍と 育陽(いくよう)城下で遭遇したのである。 たちまち突撃してきた伯升軍に打ち破られ、 三千余の戦死者を出し、 厳尤、陳茂、両将軍は軍を棄てて逃走するほか無かった。
地皇四年(23AD)年正月、散在した王莽軍の小隊を蹴散らし、 ついに伯升は南陽郡都、宛(えん)を包囲した。
即位
南陽郡都 宛(えん)は、 さすがに国内屈指の大都市とあって、 方面軍の守備無しといえども、 猛虎のごとき伯升軍に包囲されても簡単には陥ちなかった。 あせったのは伯升である。 一気呵成で押し寄せたものの、長期戦の様相を見せはじめては、 士気にかかわる。 そこで、伯升は号を改め、自ら柱天大将軍と称した。 要するに景気付けである。
この景気付けが効いたわけでもあるまいが、 首都 長安で次々と敗報を受ける 皇帝 王莽(おうもう)の憂慮はつのるばかりであった。 農民の反乱や異民族の離反は、 「卑賤の者に何ができよう」とあなどっていた王莽だけに、 漢王朝の血筋を引く伯升が勢力を持つと、 過剰なほどに警戒したのである。 恐れのあまり、伯升の首には 「封邑五万戸、黄金十万斤、爵位上公」という 破格の懸賞がかけられ、 長安じゅうの官署、全国の郷亭(村落)に告げて、 伯升の像を描いたものを目標に、 毎朝弓を射させたという。 しかし、王莽の兵威は落ちるばかりであった。 すでに良将 田況(でんきょう)は閑職に左遷されて兵から遠ざけられ、 猛将 廉丹(れんたん)は昨年十月に敗死して山東の王莽軍は敗勢である。 そして今、南陽方面軍 甄阜(しんふ)、梁丘賜(りょうきゅうし)の勢は、 壊滅である。 いよいよ乱世であるのは、誰の目にも明らかであった。
南陽の伯升・緑林連合軍は、兵威ますます盛んであった。 宛(えん)城は、未だに落ちないものの、 連日軍に志願する者がひきもきらないのである。 衆十余万に至るとあるので、倍以上の増員であった。 ここで、焦りが生じた。 焦ったのは緑林軍の首脳である。 彼らは伯升配下の豪傑、良将を恐れたのだ。 有能な部将はほとんど伯升の配下である。 彼らの功績が大きくなれば、 自分たちの高位が危うい。 ましてや伯升が首座につけば、 有能だけに自分たちにも成果を要求してくるであろうし、 ことによっては追放されるかもしれないのである。 彼らは伯升の頭を今のうちに抑えて、 自分たちの地位を確実にしておきたかった。 伝には新市平林の将帥が策動したとあるが、 とくに積極的に動いたのはむしろ 屈膝を嫌う下江兵の将帥であろう。 彼らは伯升抜きで会議して、 惰弱な劉聖公(りゅうせいこう、劉玄)を 皇帝とすることに決めてしまい、 それからその会議の席に伯升を呼んで同意を求めた。
伯升は諌止した。曰く
「 諸将軍は幸いにも漢の宗室を尊立せんとしておられる。 その徳ははなはだ厚しと言えよう。 しかし、私は時期尚早ではないかと申しあげる。 今、赤眉軍が青州徐州に起こり、その衆は数十万と言う。 われら南陽勢が宗室を立てたと聞こえれば、 赤眉軍もまた宗室を立てる可能性がある。 そのようになれば、内紛が起こることは必定。 今、王莽が滅びてもいないのに、 宗室同士で攻めあい、天下の人々に疑いを抱かせ、 自ら権威を損なうなどしておれば、 とても王莽を破れるものではありますまい。 それに、過去、兵に首たるというだけで号を唱えた者に、 成功したものは少なく、 陳勝(ちんしょう)しかり、項籍(こうせき、項羽)もまたしかり。 さらには、舂陵(しょうりょう、挙兵の地)は、ここ宛(えん)を 去ることわずかに三百里。 たったこれだけの制圧では成功するには未だ足りないかと思われる。 やにわに自ら尊立して天下に狙われては、 つぎつぎ攻められ兵は疲弊しよう、 後から興った勢力にその疲弊を突かれれば、いかがなさるおつもりか。 とても善い取り計らいとは申せぬと存ずる。 今しばらくは王と称し、 もし赤眉が賢者を立てれば軍を率いてこれに従うべきであり、 もし誰も立てないなら、王莽を破ってから赤眉軍を降すべきかと。 尊号を奉じるのはその後で十分。 どうぞ各将には、よくよくお考えいただきたい。 」
諸将の多くは、伯升の考えに同意を告げたが、 ここで昂然と抜刀して立った男がいた。 下江兵首将 張仰(ちょうぎょう、仰に人偏無し)である。 彼は手にした刀を地に撃ちおろし、 「疑事、功無し」と喝を飛ばした。 疑いながら行っては成功しないという故辞である。 続けて「今日のような議事は二度も行うことはできぬ。」 と言いながら、諸将ににらみをきかせた。 独立不羈を好む張仰にふさわしい行動といえよう。 会議の趨勢は決した。 南陽の緑林軍は劉聖公を尊位につけたのである。
名実
劉聖公は即位して更始帝と号し、 緑林の首脳を新しい朝廷の要職につけた。 即位のために大勢の兵の前に出ただけで、 緊張で固まってしまうような更始帝である。 まったく張仰たちの言いなりである。 一方、その張仰たちに煙たがられた 伯升には、官位は大司徒を与え漢信侯に封じたものの、 伯升系の有能な部将たちには上位の官は与えず、 良くて雑号将軍という程度のあつかいであった。 ここまで伯升に従ってきた豪傑たちもこれには失望し、 ほとんどの者が不服であったという。当然であろう。
実際に、実力名声ともに伯升のほうが更始帝より上であった。 それを示す一例が伝にある。 緑林軍の一隊、平林軍が新野(しんや)の県城を攻めたが 落とせなかったときのことである。 今回は守りきったとはいえ、 緑林軍本隊に来られては守りきれないと見た 新野の県令(市長) 潘臨(はんりん)が、 城壁の上から平林軍に向かって宣言したのである。曰く、 「司徒 劉公(伯升)の保証があれば、こちらから降伏しよう。」 そして、実際に伯升軍の到着と共に開城したのである。
この名声の差は、時間がたつと共に縮まるどころか開きが増した。 五月に新野を降伏させた伯升軍は、 取って返して六月には南陽郡都 宛(えん)を攻め取ったのである。 さらに、伯升の弟 劉秀(りゅうしゅう、後の光武帝)が 昆陽(こんよう)に四十二万の王莽軍を打ち破ったとくれば、 伯升の威名が天下にとどろかないほうがどうかしている。 更始帝とその周囲は、動揺をきたしはじめていた。
謀議
能力の無い者が上位にあれば、能力のある者を恐れる。 能力のある者を使う能力さえ無いために、 有能を排除して自分の地位の保全を図るのである。 この場合、有能は伯升であり、無能は更始帝とその周囲である。 更始帝と旧緑林軍首脳からなる朝廷は、 伯升の誅殺を謀ったと後漢書にある。 しかし、実際は謀るもなにも、あったものではない。 要約すれば、「呼び出して剣を奪って殺してしまえ」 という相談になったのである。 罪状のでっちあげすらない、 謀議などとは恥ずかしくて呼べないお粗末さである。
更始帝は諸将を召集して大会を開いた。 おそらく宛(えん)を陥落させた祝賀会でも企画したのであろう。 伯升暗殺担当は、ずばり更始帝本人である。 会も宴に入り、座興もあり雑談もあり、無礼講となったあたり、 更始帝は何気ない風を装って伯升に声をかけた。
「[糸寅](えん 伯升の名)や、その宝剣は見事である。 朕に良く見せてはくれぬか。」
もとから人前で声が震える更始帝である。 しかし、この日の更始帝は、 酒が入っているのに顔面蒼白で指先まで震え、 汗ばんだ手をしきりに服でこすっている。 大勢の視線にさらされた緊張のあまりにしては度が過ぎた。 ところが、もとから剛毅な伯升は、
「拙官の剣に御玉言を賜ろうとは、恐悦至極。 とくとご覧くだされよ。」
などと気さくに佩剣を取次ぎの小官に渡そうとした。
「いや、いかん!」
すっとんきょうな奇声を挙げたのは更始帝である。 その声に何事かと一座の耳目が伯升と更始帝に集まった。 当の更始帝は、自分の奇声に驚きあわてて、 ますますしどろもどろである。
「い、いや、その、宗室の流れを汲む縁じゃ、あ、それ、その、 無礼は許すゆえ近う寄って親しく見せてはくれぬか。」
最初はあっけにとられた伯升も、 ゆったりと笑むと更始帝のそば近くまで近づいて、 宝剣を捧げた。
伯升の宝剣はわが手にある。彼は丸腰で目の前に平伏している。 しかし、すらりと抜刀してその首を討つ わが身が想像できない更始帝である。 胸の動悸は激しく、しばらくは剣の柄に落とした視線を 動かすこともできない。 柄の見事な象嵌が眼に入っているが、見えてはいない。 ただ白熱した視界に踊る色彩でしかない。 長い時間、微動だにせず手にした宝剣だけが震えている。 宝剣のたてる音も聞こえていない。 と、今聞こえている音が、自分の心音以外に無いことに不意に気付いた 更始帝は、我にかえってうろたえた視線をさまよわせた。
更始帝の視線を捉えたのは繍衣御史の申屠建(しんとけん)である。 旧緑林幹部の彼は、つと席を立ち、御前ちかくまで進み出て、
「みごとな玉を得ましたので、この祝事に際して献上申しあげる。」
と小官を介して玉決(ぎょくけつ 決は玉偏)を奉呈した。 決は、決断の意味に通じ、 古く玉決を献じることで決断を迫った例がある。 今回もその例であった。早く伯升を討てという催促である。 しかし、呆然と玉を受けた更始帝は声すらあげず、 宴席の終わるまで宙に浮かせた視線すら動かせずに硬直しきっていた。
宴終わっての帰り道、伯升に近づいてきた男がいる。 伯升の母方の伯父、樊宏(はんこう)である。 周囲に緑林軍系の人影が無いことを確かめる視線を配りつつ曰く、
「昔、鴻門の会(こうもんのかい)で軍師 范増(はんぞう)は、 玉決を挙げて項羽に劉邦殺害の決断を迫ったという。 今の会での申屠建の行動も、同じ意味があったのでは。」
伯升は笑んで応えなかった。
また、伯升と共に兵を挙げた李氏の一党に 李軼(りいつ)というものがいた。 李軼は権力を志向し、更始帝やその周囲に媚びへつらって仕えていた。 伯升の弟 劉秀は彼を深く疑い、常に信用してはならない人物だと 伯升に訴えたが、これにも伯升は笑って応じなかった。
二鳥
伯升配下、劉稷(りゅうしょく)は、猛将である。 劉姓からわかるとおり伯升の一族で、 頑固一徹な驍将として名が挙がっていた。 陣を陥としいれ包囲を潰し、幾多の戦陣を駆け抜けて、 その勇は三軍に冠たりと賞された男である。 更始帝即位の時に、彼は別働隊を率いて 南西の魯陽(ろよう)を攻撃中であった。 その戦陣に、思いもよらぬ報せを持った早馬が到着した。 使者の言うには、劉玄なるものが即位、号は更始帝なりというのである。 応じた劉稷の第一声は怒声となってほとばしった。
「もともと兵を起こし、大事を図ったのは伯升兄弟であろう。 更始とはいったい何奴か。」
斬って捨てる勢いに、身の危険さえ感じた使者は早々に退散して 事の次第を更始帝に告げた。 更始帝周囲が快く思わなかったのも致し方ない。
しかし、劉稷の戦功は抜群である。 城を落として帰陣して、これを賞しないのは士気にかかわる。 そこで、更始帝は彼に抗威将軍の位を授けることにし、 拝命の使者を派遣した。 が、そこは真っ直ぐな劉稷である。 認めてもいない皇帝からの使者に任命なぞされては、 君臣の義にもとるのである。 当然のように彼は任命を蹴った。 一大騒動である。 任命の使者は皇帝の代理である。 使者に無礼を働くのは皇帝に無礼したのと同義である。 更始帝と諸将は、素早く兵数千で劉稷の宿舎を包囲し、 彼を逮捕した。
刑は斬首である。 当の劉稷はひょうひょうとしたものであったが、 これに待ったをかけた人物がいる。 誰あろう伯升その人である。 彼は大司徒であるから、司法の最高責任者なのである。 その伯升が弁護するのであるから、 刑の実行は不可能となり、伯升は劉稷を助けることができる。 しかし、それでは緑林系の諸将が、そして何より更始帝がおさまらない。 ここで更始帝に入れ知恵したのは 李軼(りいつ)と朱鮪(しゅゆう)である。 この機会に伯升も同罪として劉稷ともども捕らえてしまえ、 一石二鳥である、と。
「伯升を捕らえて即日これを害す。」
史書に述べられた、その最期の記述である。
任光伝(子 隗)
任光
任光は字(あざな)は伯卿,南陽の宛(えん)の人である. 若い時から忠義厚く,郷里 宛の税務調査員をやっていた.信都郡太守
緑林軍更始帝本隊に宛が攻め落とされた時,軍兵が任光の 冠服が立派なのを見て,衣を奪って殺そうとした. そこに偶然 光禄勲 劉賜(りゅうし)が通りかかり, 任光の容貌を見て「長者である.指一本触れてはならん」 と命を助けただけでなく彼の物は何一つとして奪うことを禁じ, 以降,任光は劉賜配下の武将として 安集(あんしゅう)の掾(えん,属官)となった. 偏将軍に就任し,劉秀の別動隊に加わって昆陽の戦いに 参戦したことを契機に戦功を建て,更始帝洛陽遷都の際に 信都郡太守に任じられた.
守誠
信都郡は緑林軍勢力でも東の方で突出しており,赤眉軍や 山東の諸勢力の複雑に入り交じる地域である. そこに発生したのが邯鄲(かんたん)の王郎(おうろう)独立である. 大都市の兵力に恐れをなした近隣郡国は皆 王郎に降伏してしまった.
しかし,任光は,都尉(とい、郡軍長官)李忠(りちゅう), 令(太守副官)萬脩(ばんしゅう), 功曹(人事官) 阮况(げんきょう), 五官掾(主席事務官) 郭唐(かくとう)らと 意を同じくして郡を固く守ることを 誓いあい,王郎の檄を持って降伏を勧めんと郡府にやってきた 廷掾(ていえん,下級官)を市中で斬った. この時点で,河北で王郎に友好を通じないのは任光預る信都郡と 隣の和戎郡だけとなったのである. 任光は急ぎ百姓に告げて廻って精兵四千人を徴して城を守った.
劉秀挙兵
更始二年の春,劉秀(りゅうしゅう)は薊(けい)からの逃避行で道に迷い, 何処に向かっているのか,何処へ向かうべきなのかもわからず さ迷っていた.そこに信都郡が漢朝のために忠節を守り邯鄲軍を 拒んでいるという情報がもたらされ,劉秀一行は馳せて信都郡に至った.
迎える信都郡は,援軍の見込みもなく孤立感を深めていたところであり, 軍は従えぬものの漢朝更始帝の節(せつ)を持した大司馬代行の到着と 聞いて大いに喜び,官吏民衆そろって万歳を唱え, 門を開いて迎えに走ったという.無論,任光も李忠,萬脩と共に官属を 率いて迎えに出,劉秀一行を伝舎(でんしゃ,使節宿泊所)に招き導いた.
さて,伝舎に入った劉秀は任光に問うた.
「伯卿(はくけい,任光のあざな)どの.今は勢力虚弱なれば, ここより南に勢力を持つ緑林軍系の 城頭子路(じょうとうしろ)や刀子都(とうしと)の軍に 合流したいと思うのだが,いかがでしょう.」
「いけませぬ.」
「駄目ですか?こんなに兵力は少ないのですよ.一体どうしろと言うのです.」
「兵を募って命令を発し,出兵して近隣の縣(町)を攻めるべきです. 降伏しなかった者から財物を没収し, それを軍資金に兵をさらに招くことができますから, なにも黄河を渡って南に避ける必要はありません.」
劉秀は,この言に従って兵を挙げ,任光を左大将軍に任命し, 侯を武成侯とした. 後任の信都郡太守には南陽出身の宗廣(そうこう)を用いた.
河北戦役緒戦
兵を率いた任光は一番近い堂陽(どうよう)の縣城を目標に定め, 寡兵をもって攻めるに情報戦を用いた. まず「大司馬劉公が,東方から城頭子路や刀子都の兵,百萬を率いて 諸々の反対勢力を討伐にやってくる」と書かれた檄文を数多く作り, 騎兵をもって堂陽縣の背後, 信都郡と鉅鹿郡の境界あたりにばらまいたのである. 噂は噂を呼び,あたり一面に虚報が広まり,吏民みな檄に動揺した. 頃合いを見計らった任光は,夕方の薄暗がりの中,劉秀軍を堂陽縣境に進めた. 黄昏が消える頃,それまでゆっくりと進めていた兵を集め, 騎兵を揃え,大量の炬火(たいまつ)を配って号令した.
「あたり一帯,この炬火で満たせ.」
堂陽の縣城の中は大恐慌であった. 百萬と号する劉秀軍の兵列が夕闇に姿を隠したと思いきや, 次々と炬火がともり,東の沢,西の丘,あたり一面に広がっていくのである. ついには光る炬火に覆われた大地は,見渡す限り星空のごとくとなり, 天の白い星々の輝きと地の赤い営火のきらめきが呼応するように縣城を 押し包んでしまった.
堂陽縣は夜半にもならぬうちに降伏した.
信都郡一帯をすぐさま押さえた劉秀軍は, 短期間で兵衆おおいに盛んとなり, 城邑を攻めてついに邯鄲を屠り, その後,任光を元の信都郡太守に帰任させた.
内伝–城頭子路
城頭子路(じょうとうしろ)は東平(とうへい)の人である. 姓は爰(えん),名は曾(そう),字(あざな)は子路(しろ). 肥城の劉[言羽](りゅうく)と兵を廬城頭(ろじょうとう)に挙げ, ゆえにその兵を城頭子路と号した.爰曾は都従事(としょうじ)だと 自称し,劉[言羽]は校三老(こうさんろう)だと称した. 黄河と済水の間を攻撃略奪して廻り,軍は二十萬を越え, 更始帝が即位した時,緑林軍系に仲間入りして 爰曾は東莢太守に 劉[言羽]は済南太守にそれぞれ任命され, 領地内での大将軍権限の行使を認められた. しかし,その年のうちに爰曾は配下に斬られてしまい, 自然と劉[言羽]が城頭子路軍主将となった. そこで,更始帝は劉[言羽]を助國侯に封じ, 兵を奪って封国に追いやった.
内伝–刀子都
刀子都(とうしと)は東海の人である. 兵を郷里の東海で挙げ,徐州[亠兌]州の境界付近を勢力圏にした. 軍勢は六,七萬である. 更始帝が即位した時 緑林軍に友好を通じ,徐州の牧に任命された. しかし,刀子都は間もなく その部下に殺されてしまい, 配下の軍は率いるものもなく流浪して賊となり, その後,檀郷(だんごう)軍に吸収された. 檀郷(だんごう)軍の将帥は董次仲(とうじちゅう)といい, 荏平に挙兵した人である. 彼は,黄河を渡り魏郡清河(せいが)に至り, 五校(ごこう)軍を合わせて十余萬の軍となった. と,そこに洛陽入城を果たした劉秀軍から 呉漢(ごかん)率いる檀郷勢力討伐軍を派遣され, 年改まって建武二年の春に壊滅した.
再び任光伝
同じ建武二年任光は阿陵侯に封じられ,食邑萬戸を与えられた. 建武五年の冬に卒し,子の隗が後を継いだ. ちなみに信都郡挙兵時代の仲間,阮况(げんきょう)は南陽太守, 郭唐(かくとう)は河南尹として,それぞれ治績を挙げた.
任隗伝1
隗(かい)、字(あざな)は仲和。若くして黄老を好み、 清く静かにして欲の少ない人物であった。 得た奉秩(給料)は、常に宗族に振舞ってしまい、 一族の孤児、寡婦を収め養った。 顕宗(明帝)は、これを聞いて任隗を抜擢して朝請(ちょうせい)に奉じた。 後に羽林左監、虎賁中郎将に遷され、また、長水校尉に遷された。 粛宗(章帝)が即位すると、任隗は、以前から粛宗と敬愛しあい、 しばしばその行いを賞賛されていたので、 将作大匠(しょうさくたいしょう)に任命された。 将作大匠は、建武(光武帝治世)以来つねに謁者が兼任していたが、 このときに初めて独立して任命されたのである。 建初五年に太僕に遷り、八年に竇固(とうこ)に代わって 光禄勲になる。 歴任したところでは皆、称賛されるところがあり、 章和元年に司空に拝命された。 任隗は、義を行ない、内に修め、名誉を求めず、 清廉公正をもって世に重きをなした。
任隗伝2
和帝が即位すると、竇憲(とうけん)が権を執り、 権威裕福をひとりじめにし、 内外の朝臣でこれに震え怯えない者はなかった。 時に竇憲は匈奴を撃ち、国家財政を浪費した。 任隗は奏議して竇憲を罰し、 これに伴って左遷された者は前後十名にのぼった。 独り、司徒の袁安(えんあん)と心を同じくし、 力をつくして重きを持ち、正しいことにもとづき、 硬言直議して回隠するところ無し。 その語は袁安の伝に見える。 永元四年に死亡。
任氏三伝
任隗の子、屯(とん)は、父の死に伴いあとを継いだ。 和帝は任隗の忠義を思い、追って任屯を抜擢して 歩兵校尉となし、西陽侯に移封した。
屯卒し、子の勝が嗣いだ。
勝卒し、子の世が嗣ぎ、北郷侯に移封された。
趙熹伝
趙熹
趙熹(ちょうき)、字(あざな)は伯陽(はくよう)、 南陽は宛(えん)の出身である。 若くして節操ありと評される人物であった。 その評判を得たきっかけとなる事件とは、 以下のようなものである。 あるとき、趙熹の従兄がある人物に殺された。 当時の気風としては、こういう場合、 仇討ちは美徳であり、 ぜひともされねばならないことである。 普通は子が親の仇を晴らすのであるが、 この従兄に子が無かったために、 従弟にあたる趙熹は自分が仇を討つべきと考えた。 時に趙熹十五歳である。 常に報復を思い、兵を練り、 また、剛勇と友誼を結んだ。 そしてついに好機をとらえ、 仇の家へと討ち入った。ここまでならば、乱世の常。 ちょっとした豪者ならば誰でも経験があり、 また、南陽にそのような者は多い。 しかし、討ち入った趙熹が目にしたものは、 一家全員、流行り病で病床にあり、 抵抗するものとて一人としていない、 安閑とした家屋であった。 事情を了解するや趙熹は、 「病に乗じて仇を討つなど仁者の心にあらず」 と称し、兵を収め、 誰にも危害を加えることなくその場を去った。 去りぎわに一言を残して。
「もしも病が癒えたなら、我を避けて、みなで遠くにに逃げよ。」
その心意気に感謝して、仇の家のものはみな伏して 最上の叩頭の礼をおくったという。
後に病の快癒した仇は、趙熹に深く感じ入り、 自らを縛って趙熹を訪ねていった。 趙熹に一命を捧げたと言える。 が、しかし、訪問をうけた趙熹は面会を謝絶した。 仇はあくまで仇であって、 許すべからざるものであるとの初志を貫いたのである。 後に再び機会をとらえて、趙熹は仇を討ったという。 こえが信義の人、趙熹の名を広く世に知らしめた事件の顛末である。
誘降
さて、話は飛んで、 ときに南陽郡では緑林軍が更始帝(こうしてい)を立て、 勢力を拡大しようと各地の都市や豪族の荘園に 攻勢を強めている時期のことである。 舞陰(ぶいん)に勢力をもつ豪族、李(り)氏は、 更始帝の勢力に隣接はしたものの、 堅固な城を持ち、更始帝に容易には屈しなかった。 更始帝側も、友好的ではないが、 かといって敵でもない李氏を、 敵にまわす余力は無かった。 柱天将軍 李宝(りほう)を使者に、 平和裏に勢力下にとりこもうとしたのである。 しかし、李宝の説得に舞陰李氏は動かなかった。 更始帝側に信頼を置けないというのが最大の理由である。 勢力下に入ったところで、 兵力と財物だけ取り上げられてはかなわないというところであろう。 けれども、舞陰の李氏とて更始帝の大勢力との対決は 避けたいところであった。 そして、舞陰李氏の出した条件はこうである。 「宛(えん)の趙氏に、熹という信義で名を著わした男がいる。 彼が保証するならば勢力下に入っても良かろう。」
更始帝は趙熹を招いた。 当時、趙熹のいた宛(えん)は、まだ更始帝の勢力下に入っておらず、 交戦中であったはずなので、 どのように趙熹を招いたのかはよくわからない。 そして、招きに応じて現れた趙熹は、 まだ二十歳にもならない若造であった。 年齢でははるかに上をいく更始帝は笑って言ったという。
「繭栗の犢、豈に能く重きを負いて遠きに致さんや」
繭栗(けんりつ)とは子牛の生え始めの小さな角のことで、 犢(とく)とは子牛のことである。 ようするに「角の生え始めた子牛よ」と呼びかけたことになる。 しかし、茶化したのではなく誉めたのである。 おそらくこれ以降であろう、繭栗は、転じて「固い節操」を 意味するようになる。
さっそく趙熹は郎中(ろうちゅう) 行偏将軍事(こうへんしょうぐんじ)に叙され、 舞陰へと出立した。 郎中とは皇帝側近であり、行偏将軍事とは偏将軍と同じ 軍権を持つということである。 偏将軍とは、郡の軍権を握る都尉より一級上であるから、 編入された李氏の兵をそのまま配下にできるよう、 配慮されたのであろう。 この兵権の元、無事に舞陰李氏との併合処理を済ませた 趙熹は、周辺の制圧に討って出た。 舞陰は南陽郡の東端に位置し、 北に潁川(えいせん)郡に隣接し、 南東には汝南(じょなん)郡が近い。 そこで趙熹はまず潁川側に入って 非友好的な諸豪族を攻撃し、 また南下して汝南との境界付近を行軍して 武威を示したのである。 その後、宛攻囲中の更始帝の戦陣に帰還して、 更始帝におおいに喜ばれ、 「名家の駒なり」と賞賛を浴びている。
雌伏
その後、趙熹は更始帝側の将軍として、 王莽(おうもう)政権の崩壊を決定付けた、 昆陽(こんよう)の戦いにも参戦する。 王莽が王尋(おうじん)、王邑(おうゆう)に百万を号する兵を授けて 首都を出発させたという報告を受けた更始帝は、 趙熹を五威偏将軍に任命して、昆陽救援に赴かせたのである。 この昆陽の大激戦の中、趙熹が、 城外から救援する劉秀(りゅうしゅう、後の光武帝)の軍にあったのか、 それとも城内で篭城戦を戦い抜いたのか、どちらかは定かでない。 しかし、激戦を厭うはずもない趙熹が、 負傷するほど力戦したことは確かで、 この功で中郎将(ちゅうろうしょう)に昇進し、 勇功(ゆうこう)侯に封じられた。
昇り調子に思われた趙熹の人生であるが、 しかしそれも更始帝の運命が尽きると同時に下降に転じる定めであった。 同じ反乱勢力の赤眉(せきび)軍の吸収に失敗し、 かえってその反攻を受けた更始帝勢力は、 またたくまに瓦解していったのである。 首都長安で防戦していた趙熹もついには赤眉軍に囲まれ、 乱戦に果てようかというところを、 家の屋根伝いに走って逃げて、ようやく難を逃れた。 趙熹は下って野に伏した。
戦火に燃える長安は赤眉軍に制圧され、 生まれ故郷の南陽にもどるしかすべのない趙熹である。 彼は、韓仲伯(かんちゅうはく)など親しい友人や各々の家族など、 数十人で集まりとなって山道を急いだ。 武関(ぶかん)を越えて、 長安の赤眉軍の影響下から逃れることには成功したものの、 女子供を含めて数十人の集団である。 南陽まで100km以上の行程を、 盗賊その他の害を受けずに済む可能性はほとんど無かった。 あまりの心配に、韓仲伯は、 「わが妻の美しさにひかれた乱暴者に途中襲われては嫌なので、 妻を捨てて行こうと思うがどうか」 などと言い出した。 これには趙熹は激怒した。 絶対にそんなことは許さないと断言し、 美しくなければ良いのだと仲伯の妻の顔に泥を塗り、 鹿一頭も乗れるかというほど小さい車という意味の鹿車(ろくしゃ) というボロ車に彼女を乗せ、 趙熹自身がその車を押して歩くという挙に出た。 そして道中盗賊に逢うごとに、 病状が悪いのだ、と情けを請うては免れた。 当時の盗賊はほとんどが食うに困った農民が元であるから、 彼らとて困っているものを襲うのは本意ではなかったのであろう。 おかげで一行は、 丹水(たんすい)まで無事にたどり着くことができた。 丹水で山道は終わり、 眼前には南陽の丘陵地帯が広がっているのである。
この丹水で、趙熹は見覚えのある一行を見た。 近づいてみれば更始帝の親族の一行である。 彼らも赤眉に追われてここまで逃げてきたのであろう。 声をかけてみれば、みな裸足で飢え困りはてて、 これいじょう動くこともならないありさまであった。 これを見て悲しんだ趙熹は、 持っていた衣料や食料をことごとく与えて合流し、 かれらを護って帰郷させた。
仕官
趙熹がほうほうのていで故郷の宛(えん)にもどってみれば、 そこは再び戦場であった。 聞けば、劉秀(りゅうしゅう)が登極して光武帝(こうぶてい)と称し、 南陽郡をいったんは平定したものの、 部将 奉(とうほう)が 叛旗をひるがえしたのだという。 もともと趙熹は 奉とは仲が良かったこともあり、 たびたびこのような戦いは止めよと手紙を送った。 しかし、この手紙は 奉に 黙殺されただけではなく、趙熹にも不利になった。 この手紙のやりとりを知ったある小者が、 手柄欲しさに光武帝に走り、 趙熹は 奉と謀議しておりますと 訴え出たために、光武帝に疑われたのである。
かなり光武帝をてこずらせたものの、 奉は敗北し、 南陽郡は再び光武帝の支配下に入った。 このとき、光武帝が得たもののひとつに、先の趙熹の手紙の束があった。 紐をほどいて簡札に目を通した光武帝は驚いた。 趙熹は謀議するどころか、昔の友誼も感じさせずに手厳しく 奉を諌めていたのである。 「趙熹は真の長者(徳のある者)である」と公言した光武帝は、 さっそく趙熹を徴して引見し、鞍馬を賜り、公車を待詔させるなど、 厚意を示した。
趙熹の光武帝下の初仕事は簡陽(かんよう)の接収である。 荊州北部はほぼ制圧しつつあった光武帝であるが、 長江を渡って南岸はまだ手付かずであった。 そこで趙熹を簡陽侯相(侯代理)に封じ、 先発している騎都尉 儲融(ちょゆう)から兵二百を受けて、 簡陽を勢力下にとりこむように命じたのである。 ところが趙熹の返答は否であった。 兵は不要と言い切った趙熹は、 馬車ひとつで簡陽へと向かったのである。 単車とあるので、おそらく軍装騎乗でなく、 平服乗車であったろう。
簡陽に到着した趙熹は、門前払いを食った。 城中の民は戦乱に狩り出されるのを嫌い、 守城の吏は王莽に任命されたものであるから、 解任を嫌ったのである。 しかし、趙熹は粘った。 城中の大夫(たいふ)を呼び出し、 国家の威信を説いて説得に尽くしたのである。 もとより信義に厚く、弁舌というよりは誠意であたる趙熹である。 おそらく対応したのが守門の将ででもあったのであろう、 門を開き、自分の両手を前に縛って罪を認め、 自ら帰服したという。 城壁を守る諸軍営もことごとく趙熹に服した。
これを知った荊州の牧(監督官)は趙熹を 「激務をこなす才能のある人材」として上奏し、 これを受けて「趙熹を平林(へいりん)侯相となす」 とする詔勅が発せられた。 趙熹は、すでに降伏した者を集めて兵力とし、群賊を攻撃し、 県邑を平定するなど功をあげ、 後に懐(かい)という大県の令(れい、市長)となった。