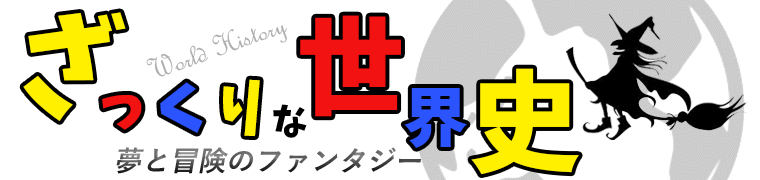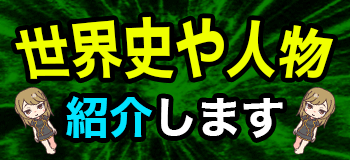三国志 人物紹介
袁紹 天下統一の大本命も…。
えんしょうほんしょ ?~202
汝南郡汝陽県の人。後漢末の代表的群雄。4代にわたって司空を出すという後漢きっての名家に生まれる。司隷校尉(首都の長官、行政権、警察権をもつ)のとき宦官誅殺する。このころまで特に曹操と親交を結んでいた。何進が殺害され董卓が洛陽で権力を握るようになるとこれをさけるため渤海に逃れる。その後曹操の提唱した反董卓連合軍の盟主をつとめた。そのどさくさで冀州を強奪し、自己勢力の基盤とした。その後公孫[王贊]と血みどろの戦いを繰り広げ、最終的には袁紹の勝利に終わる。しかしそのころ中原では曹操が相当の基盤を持っていた。いよいよ曹操と決戦となった。しかし袁紹は自己を過大視し、せっかくの多勢と豊かな物資を生かせず、さらには参謀の至言も生かせず曹操に官渡で決定的に破れる。官渡での敗北後袁紹は悶々たる日々を送り、苦悩のうちに病死した。
袁紹、これもまた敗れ去った群雄である。しかし袁紹個人の資質を度外視して、当時の袁紹の立場を分析すると、天下統一の可能性は大いにあったと思われる。しかし歴史はそうのようにはならなかった。
まず天下を統一する資質という点で袁紹は曹操に劣っていたと解釈するのが妥当であるように思われる。特に一番問題だったのが袁紹の名門意識である。名門ゆえ袁紹には恵まれた点がおおい(元から名声があったので人材、物資が集めやすいなど)のだが、そのことを認識しないで、むしろ当たり前と思ったところが袁紹の悲劇だった。平時ならば名門は名門らしくしていればそれでいいのだろうが、乱世では名門であり続けるためには努力が必要である。しかし袁紹は名門であることはもはや自明であり、それはあたりまえであると錯覚していたふしがある。
これは致命的である。つまり彼は乱世に生きながら、乱世の意味を理解していなかったのである。そもそも旧来の秩序がもはやうまくいかなくなったから乱世になった。つまり歴史の流れから言って、袁紹の生きた時期はまさに変革期であった。にもかかわらず彼は従来の秩序にもたれかかって勢力を打ち立てようとしたのだ。これでは敗れ去るのも当然といえよう。現代にたとえて言えば、ある会社の2代目社長が「おれは社長だから偉い」と勘違いしているようなものだろう。ほんとうは能力があって、すばらしいから社長になるべきなのにである。
袁紹はあくまでも旧来の人物だった。しかし晋が結局門閥貴族の争いが原因で滅亡したところを見ると、結局当時の中国というのは革新をはかろうとしつつもまだまだ古かったと見ることができる。そのことから考えて、袁紹が天下を統一し、旧来の門閥貴族が支配していくという構図もあながち不可能ではなかったと思われる。(どうせ長続きしなかっただろうが) しかしそれは無理だったのである。結局曹操という傑物が同時代にいたのが不運といえるだろう。曹操はその革新性という意味ではまさに時代を超越していた。
それにしても袁紹は滅びる大企業のトップのようである。沮授や田豊が時期をとらえた適切な進言をしたのにもかかわらず彼はその進言をいれることができなかった。有能な部下の進言もそれをいれる気がなければまったく意味がないのである。現代の会社組織でもよく権力を行使できる地位にあるものが、情報を客観的に判断できず、むしろ自分の主観的好みのみで判断してしまう場合がある。いくらよい情報を部下が提供してもそれを使いこなす上司が無能なら全く意味がないのである。彼は変革期には不向きだったといえよう。
袁紹も結局真の意味では人とのコミュニケーションをとれない人物だったといえよう。確かに進言を聞いているように思われるのだが、その進言を聞く行為というのはあくまでも形式的であり、実質的にはまったく人の言葉をいれない人物だったといえる。こうなっては人間終わりである。こうはなりたくないものである。
結局袁紹は私利私欲しかわからない人物であった。私利私欲に溺れ、大義をわすれた人間は悲劇的である。
袁紹は最後自分の後継者すら決められないまま病死した。袁家滅亡に立ち会わなかっただけ幸せといえるかもしれないが、それにしてもさえない最後である。
袁術 金持ちの坊ちゃん
えんじゅつ こうろ ?~199
汝南郡汝陽県の人。袁紹の従弟、あるいは兄弟とも言われる。後漢を代表する名族の出身。しかしその能力はほとんどないといさえ言える。最後は呂布や曹操、そして劉備に攻められた。袁譚を頼って流浪中路頭にて死亡した。
そもそもこの人物は語るに値しないと言える。あまり魅力的な人物とはいえない。個人的には侠気のある人物だったらしいが、君主の器ではまったくなかった。ちなみに侠気がある例としては、宦官を討伐したりしている。
まず董卓が中央に乗り込んできたとき、袁術はとりあえずかかわりあいになるのをさけて、南陽郡に逃げた。そして運良くそこを根拠地とすることができた。
曹操が提唱した董卓討伐軍に参加したときもかなり利己的、不可解な行動を起こしている。後方補給を担当した袁術だが、大活躍しそうだった孫堅に食料を送らなかった。当時袁術のある意味では部下的存在であった孫堅の名があがるのを恐れたからであろう。
そもそもその袁術の家格からして、孫堅、(そしてその後継者たる孫策)らは袁術の部下であっても良かったはずである。しかし二人ともそうそうに袁術を見限っている。孫堅のばあい、その呪縛から抜けられなかった部分もあったようだが、孫策は袁術をそうそうに見限っている。もし袁術に能力があれば、孫策もそのもとにとどまっているはずである。
袁術は自分で軍団を動かすようなことは案外しておらず、どちらかと言えば、周りの群雄の間に立って適当に命令するだけであった。例えばある件で劉表と不仲になれば孫堅に命じて討伐させてみたり、呂布を利用して劉備を攻めさせたり、なんにしてもその戦術は自己の利益のことしか考えていないのではないか、と思う。
孫策から玉璽を譲り受けた袁術は、何を思ったかついに帝位を僭称してしまう。みのほど知らずもいいところである。そして宮廷では贅沢をきわめた生活をしたという。領内は荒れ放題になったそうである。また軍事的には呂布を攻めたりしてみたものの大敗した。
結局のところ袁術というのは個人的利益でのみしか動けない男であった。少なくとも大儀を感じるなんてことはまったくない。人間自分の欲にとらわれたら最後はこうなると言う見本であろう。彼は最後、土民に、水をめぐんでくれといったが、土民は水を捨ててまでして、「あなたにあげる水はない、のむなら血を吸え」と言ったという。
結局のところ袁術ごときくだらない人間と言うのは、金持ちとか名門の家でよく現れると思う。権力がある家に生まれて、かつあまりまともに育たないと、こうなってしまうという見本である。まあ少なくとも金持ち的な侠気はあるのかもしれないが、しょせん人の心はわからないのである。すくなくとも人間こうはなりたくないものである。
董卓 破壊者
とうたく ちゅうえい 139~192
隴西郡リントウの人。黄巾の乱以前は異民族討伐のプロとして活躍した。何進が宦官に謀殺された後、どさくさにまぎれて献帝を擁立した。以後専横を極めたが最後は呂布に殺された。
若い頃から羌族の酋長らと親交を結んでいた。その関係かきわめて彼の軍団の軍事力は高かった。そのせいか、異民族平定のプロとして活躍した。なお董卓自身の腕力もなかなかなもので、弓がうまかったという。
しかし董卓には軍団を率いる才能はあったにせよ、戦略をたてるとか大局を見るといった能力はまるでなかったらしい。後漢の将軍皇甫嵩のもとに董卓は一応所属したが、皇甫嵩に戦略の面ではついぞ及ばなかったらしい。しかしこの皇甫嵩との対立(というか逆恨み)が董卓の朝廷への恨みを募らせていったらしい。そのせいかなお董卓の軍団は後漢末すでに半独立状態にあったという。案外自分が中央で活躍できる好機を伺っていたのかもしれない。
絶好のチャンスが訪れた。何進が宦官を誅殺しようとして各地の軍団を集めたとき董卓の軍団も呼ばれた。しかし当の何進は宦官に殺され、洛陽は大混乱に陥った。朝廷に恨みを抱き、しかしある意味ではあこがれ抱いていたと思われる彼は、その動物的嗅覚で、どさくさで何進の軍団やらを吸収し、さらに呂布を籠絡して丁原の軍団を手に入れ、単一の軍団として最強の勢力を得るに至った。そのおかげで洛陽を制圧できたのである。
洛陽を制圧した彼は、霊帝を廃して献帝を擁立した。また宮中の婦女に暴行を加えた。皇帝の陵墓を暴いた。ある村を全滅させた。などなど悪行きわまりない。しかし董卓、この人物は三国志演義においてきわめて重要な人物である。なにせ彼のおかげで大混乱が生み出されたからだ。なんにしても彼のような破壊者がいたからこそ、後漢の秩序はほぼ完全に破壊されたといえよう。
袁紹、曹操らが董卓討伐を訴え挑んできたときも、長安遷都で乗り切った。この発想もなかなかすごいといえる。少なくとも董卓は軍事的にきわめて強力だったことを示している。
長安に遷都してからの彼は、宮中の官僚の目をくりぬいたり、釜ゆでにするなど、ますます悪行はエスカレートしていった。び城を建設しそこに30年分の食料を蓄えた。また貨幣経済を破壊させるほど貨幣を乱造した。
かれの圧政は限りなく続くと思われたがついには王允の連還の計にかかった呂布に殺害された。結局、破壊者は暗殺で最後を終えたのである。いかにも彼らしい最後といえよう。
なお彼の遺体は市中においたままにされた。はらの上に灯心をおいてへそにさしこんで火をつけたところ、3日間燃え続けたという。それほどまで彼は太っていたのだろうか。なんにしても晩年のやりたい放題が彼の体をそうさせたのであろう。
董卓の暴虐な振る舞いの数々はとても誉められたものではない。倫理的には最低のことばかりである。しかし一人の人間の生き様としてみた場合ある意味で、その破壊衝動に忠実に従ったという意味では、すがすがしいといえよう。とにかく軍略も戦略もあったものじゃない。彼はただ暴力、破壊衝動に忠実に生きたのだ。
中原をさまよう虎 呂布
りょふほうせん ?~198
五原郡九原県出身。前漢の名将李広になぞらえて飛将と呼ばれる。最初丁原に仕えるも董卓に誘われるや否やこれを誅して董卓に仕えた。董卓とは父子の契りを結んだ。しかしその後王允の計にのって董卓を誅した。しかし董卓の元部下李[イ寉]郭[シ巳]らに長安を追い出され、各地を流浪する。袁術、袁紹らにはつき返された。曹操が留守の[亠兌]州を襲ってみたりもしたがだめだった。そこで劉備に身を寄せた。そして劉備が袁術を討伐している隙に徐州をのっとってしまう。その後は袁術と組んだり、その同盟を破棄したりと相変わらずのむちゃくちゃ振りを見せつける。最後は曹操とその下に当時居た劉備の軍勢によって捕らえられる。呂布は命乞いをしたが最後は「丁原、董卓のことをお忘れになるな」という劉備の進言により、曹操は呂布を処刑した。呂布の最後であった。
呂布の経歴を上で述べたが、ほんとむちゃくちゃな人生である。彼の裏切りの遍歴はすごい。
呂布という男は多分、本当の馬鹿であろう。少なくとも打算で裏切り行為をしたとは思えない。もし彼が打算で人を裏切っていたのなら、さすがの彼にだれもついていかなかっただろう。しかし呂布はまがいなりにも軍団を引き連れていくことができた。これは彼にどこか人をひきつけるものがあったからだろう。
彼のひきつけるものといえばやはり彼の圧倒的な(個人的)武力であろう。彼の強さは郡を抜いている。もちろん演義の話であり、割り引く必要があるにせよ、虎牢関で関羽と張飛と劉備三人を同時に相手にしても、呂布はまったく平気だったという。それに典韋と許[ネ’者]が同時に呂布にかかったときもまったく相手にならなかったという。
それに彼には名馬赤兎がいた。この馬の脚力はずば抜けていたらしい。どのような馬でも追いつけなかったという。それに呂布の出身地は現在の蒙古らしいから、呂布の馬術もまた優れていたのだろう。
彼は弓の術にも優れていた。これも演義の話かもしれないが、袁術と劉備が戦っていたとき、呂布はとんでもない弓術を見せつけることにより、両軍を和解に導いたことがある。
確かに彼は個人的戦闘力はずば抜けていた。しかし彼は人間を使うとか、組織を動かすといった才能はほとんどなかったと思われる。なんにしても呂布は自分個人の戦闘力にしか想像が及ばなかったのだろう。強いやつが世の中を治める。この程度の認識しかなかったと思われる。
私は呂布のその圧倒的武力には惹かれるものの、呂布のような生き方はしたくない。結局彼は人の信頼を得ることはそうなかった。彼が信頼できたとすればせいぜい「妻」あるいは「女」あるいは家族である。確かに家族の信頼は大切だと思う。しかしやはり部下や同輩と友情あるいは信頼を築いてこそ人間として生きる価値があると思う。
そういった意味で呂布ごとき生き方は私から見れば非常に不幸だと思う。
ちなみに陳寿いわく、呂布ごとき生き方をしていて滅亡しなかったものはないという。私もそう思う。
司馬懿 複雑な心の持ち主
しばい 179~251
字は仲達。河内郡温県のひと。後漢末京兆の尹司馬防の第2氏。最初後漢に仕える。その後荀[或〃]に推挙されたりしその後魏に仕える。最初は魏では割と下級の文官であったが、徐々に頭角を現し、次第に曹操の側近となる。その後曹丕の代になると丞相長史に任ぜられる。曹丕は死ぬ間際、陳羣、曹真らと共に司馬懿に後事を託した。曹丕の後の曹叡(明帝)の代になると、魏領に蜀の諸葛亮が進入してくるもこれをよく防ぎ、相手の諸葛亮を五丈原で陣没させた。その後大尉となった司馬懿は遼東で反乱を起こした公孫淵を討伐しこれも平定した。明帝の死後、曹爽一族に迫害されそうになるも、司馬懿はクーデターを起こして、迫害から身を守った。そのさい丞相に任命された司馬懿は政治の実権を完全に握った。その後73歳で死亡。晋朝により宣帝とおくりなされた。
司馬懿仲達。この人物ほど実体のつかみにくい人物はいまい。とにかく経歴を見ると彼に様々なシーンがあったことが伺える。おおむね司馬懿には4つの時期があると思う。最初に曹操につかえたころ。このときは曹操をあまり好意的に思っていなかったものの、乱世の英雄として尊敬はしていたに違いない。司馬懿自身、曹操に背くなどということは全く考えていなかったろう。また司馬懿自身の地位もさほど高くなかった。次の時期は曹丕に仕えていた頃。このころは曹丕(文帝)を支える実力中堅幹部だった。曹丕と司馬懿は一種の信頼関係があり、司馬懿は曹丕には一番芯から臣従したと思われる。曹丕は司馬懿を父曹操からかばったことが相当あったらしい。第三の時期は、軍事的実力を見せつけていく時期である。詳細は省くが、司馬懿はよく諸葛亮の侵攻を防いだ。その後司馬懿は公孫淵を葬った。第四の時期は明帝の死後である。このころの司馬懿は政治的手腕、軍事的手腕両方においてもはや魏一番であった。明帝死後の魏に対しては司馬懿はあまり忠誠心はなかったと思われる。
それぞれの時期いずれにおいても彼は優れた判断と実行力を持っていた。第1と第2の時期においては的確な進言をして曹操や曹丕を救っている。特に関羽が襄陽に侵攻してきたさい、呉を使ってそれを防ぐという策を進言したり、素晴らしかった。第3の時期では諸葛亮を防いだことが素晴らしいであろう。彼は蜀の国力を冷静に見抜き、容易には諸葛亮の挑発に乗らなかった。血気にはやる諸将をおせえた統率力も見事といえる。また孟達が反乱を起こしたとき、すさまじいスピードでこれを破ったことも彼一流のセンスだろう。第四の時期では司馬懿は政治、軍事の実権を奪い、それをみごとに統率した。そのことが彼の能力を示している。
なんにしても彼が一流の人物だったことは疑いようがない。政治的手腕、軍事的手腕いずれも素晴らしかった。
しかし彼の人物像というのはいまいち浮かんでこない。そのせいで日本でもそして中国でもいまいち司馬懿は人気が出ないのであろう。よく言われることだが、司馬懿は日本の武将で言えば、立場的には家康ににていると思われる。最終勝利者はあまり人気が出ないのである。
司馬懿はそもそも名門の出であり、曹一族より家格は上であった。当時、いくら既存の秩序が崩れていたとはいえ、そのような家格というのは当然まだまだ重視されていただろう。だから当時の人は魏から司馬懿が実権を奪ってもそんなには拒絶反応を起こさなかったのかもしれない。また魏の朝廷の人物が実は司馬懿と同じ儒教的精神を持っていたことも見逃せない。
何にせよ、司馬懿については私も未だによくわからない。ただ一つ言えるのは結局司馬懿が一番賢かったという点であろう。名門出身でありながら、頭脳もよし、判断力も申し分ない彼は、時代にあった行動をし、長生きをし、結果天下の実権を握るに至った。彼の経歴を見るに大筋では大義にもとることはしていない。彼はきわめて減点が少ない男であった。
司馬懿は人生全体で言えば、きわめて矛盾した行動をしている。また儒教倫理を重視しているのに魏から事実上政権を簒奪している。しかし一方で、彼は献策はおおむね誠実だった。なんにしても時代に誠実だったが、行動はあまり誠実でないときもあった。彼個人の評価は僕ごとき若輩には全く不能である。ただ歴史の流れに忠実だった人であり、少なくとも時代を読んでいたから最終勝利者になれたのであろう。
たぶん臣下としての司馬懿も、政権を奪取した司馬懿も、両方とも彼なのである。その昔秀吉が信長には極めて忠実だったのに、信長の死後は一転して信長の子供など無視して政権を奪ったように。信長臣下の秀吉、天下統一期の秀吉、両方とも秀吉であるのと同様であろう。
なんにしても三国志世界で一番賢かったのは彼であろう。また司馬懿てき生き方も、一概には非難できまい。とにかく司馬懿は容易にはつかみずらい大人物なのである。わたしは司馬懿が嫌いではない。しかし司馬懿的生き方に少なくとも夢はあまり抱けない。名門の家の人が頭が良くて、立派な行いをしている。それが司馬懿なのだが、それは確かに非難はできないもののあまりおもしろくないのである。
荀[或〃] 王佐の才
じゅんいく 163~212
字は文若。穎川郡穎陰県の人。名士層出身。はじめ袁紹に仕えたが、その馬鹿さ加減に失望し曹操に仕えた。曹操に有為なる人材をたくさん推挙した。また多くの的確な進言で曹操を励ました。しかし曹操の勢力が大きくなり曹操が魏公に上ろうとした時、それは臣道にもとると不快感を示したことから、曹操に疎んじられるようになった。自殺か病死かは不明であるが、とにかく不遇の最期を遂げた。
荀[或〃]はあまり印象に残らない人物である。それは魏には多くの参謀がおり、しかも曹操自身も能力があったため、呉や蜀に比べて個々の参謀が際だたないからであろう。
しかし荀[或〃]は当時のかなり身分の高い全国的な評価のあるカギョウから「王佐の才」があると評された。これは当時の上流社会で彼が最高の評価を受けていた証である。また曹操をして「われの子房(張良)なり」と言わしめている。
実際にも荀[或〃]の功績は曹操の派遣に大きく寄与した。たとえば長安を脱出した献帝を許都に迎え入れるように進言したのは荀[或〃]である。当時、曹操陣営の中でも帝を招くことは行動の制約がでるからという理由で反対するものが多かった。しかし荀[或〃]は「帝を招き入れ後見人を得る」ということの効果の大きさを見抜いていたのである。帝という大義名分を得た曹操陣営は袁紹の焦りを引き出せたからである。
また曹操の人材充実面に関しても大きな功績があった。荀[或〃]が推挙した人物には、郭嘉、ギシサイ、荀攸、鍾ヨウ、陳羣、司馬懿、華[音欠]、王朗、などいずれも魏の重臣である。
官渡の戦で曹操を励まし、敢闘させたのも荀[或〃]の励ましがあったからである。
ところで荀[或〃]について語るときどうしてもふれなければいけないのが彼の最後についてである。
多くの書物では、曹操が魏公に上ることは、漢王朝に仕える臣下として信義にもとるので、荀[或〃]は漢王朝の臣下としてこれに反対した。曹操はそれに不興を感じて荀[或〃]に暗に死を示唆し、荀[或〃]は自殺したということになっている。一見筋が通っているようであるが、大いに謎の残る最後である。
荀[或〃]ほどの頭脳の持ち主なら、曹操の野望など当の昔に見抜いていたであろう。また漢の臣下としてという大義名分だが、そもそも荀[或〃]は漢にそんなに忠誠心熱かっただろうか?考えてみて欲しい。
荀[或〃]は曹操に天子奉戴を進言したが、そのときの進言内容を考えて欲しい。
「春秋時代の周王朝の襄王が亡命したとき、諸侯であった晋の文公は王が都に戻れるように手配したから諸侯は文公に従うようになった」
「漢の高祖は、義帝が殺されたとき(項羽が殺した)喪に服した。だから人心を得たのだ」
これらの進言はいずれも実権が後に保護したものに移ることを示唆している。少なくとも擁立したものが権力を得る(劉邦、晋の文公)ことを容認した進言である。荀[或〃]に漢王朝に忠誠心があるならこんな進言はしまい。
彼は漢王朝を曹操の覇権のための手段として用いなさいと進言しているのである。彼は漢王朝を相対化し、リアルに見つめている。その感覚はむしろ曹操に近い。
いずれにせよ荀[或〃]は漢に妄信的な忠誠心などなかったであろう。ではなぜ荀[或〃]はそれにも関わらず不遇の最期を遂げたのか?
渡辺精一氏によると、荀[或〃]は後継者争いに巻き込まれ、それで死んだのだろうと言われている。私もそう思う。荀[或〃]ごとき頭がいいものが漢王朝への忠誠などをあの時点で曹操に進言するとは思えないからである。
もし本当に曹操が栄達するのが嫌だったのなら、それこそ張良のように、故郷に引きこもったであろう。それも自ら進んで。わざわざ異郷で最後を遂げるとは思えず、荀[或〃]はやはりお家騒動に巻き込まれ死んだと解するのが妥当であろう。
陳羣 有能なる行政官
ちんぐん ?~235
字は長文。穎川郡許昌県の人。名家出身。清流派知識人。はじめ劉備に仕える。しかし劉備が進言を用いなかったので曹操に仕えるようになる。人物鑑定眼に優れた。公正な判断力と道義を重んじる性格で慕われた。法務官僚。235年逝去。
陳羣は演義では地味である。王朗、華[音欠]らと共に、魏の行政を司った人物だからである。そもそも王朗、華[音欠]らは演義では極めて扱いが不当である。また劉備につかえていたのに曹操に仕えたという点からして、演義受けが悪いのは当然である。
しかし魏にとっての大功労者であることは間違いない。彼の行政での実績がそれだけ優れているからである。
ではなぜ行政がそんなに大切なのだろうか。一見戦争の現場とは関係ないようなので問題となる。
しばしば、我々は戦争での勝負というと、どうしても前線のドンパチばかりを想像してしまうが、それは間違いである。近代以降では「総力戦」として語られるが、近代以前の戦争でもそのような側面がなかったわけではない。思うに政権として筋を持たせるためには軍事だけでは全く意味がないのである。軍事と行政の高度な統合が必須である。軍事だけ強くてもそのようなものは結局滅ぼされてしまう。継続性がないからである。つまり政権に継続性を持たせるためには陳羣のような優秀な行政官僚は必須なのである。
また彼の人物鑑定眼はしばしば曹操を助けた。
行政でも陳羣は主に司法分野を担当した。彼の判断は公正であり、人々は敬慕していたといわれる。例えば曹操が肉刑(むち打ちの刑)を復活させようとしたとき、時流に合わないとこれをいさめた。また刑罰をときに減刑した。彼は官僚といえども情実が働く、人間としての温かさがあった。
また陳羣は「九品官人法」を起草した。これは地方に中正官をおいて人材を9等級にわけて、推薦させるものであった。これは従来の郷挙里選の弊害をおさえ、貴族を押さえようとするものであった。魏の後もこの制度は続けられた。
曹丕が魏国の皇帝に就任するときは、「禅国の詔」を起草した。また曹丕をして「我が顔回なり」と言わしめた。君主からの信頼が厚かったことは曹操が死ぬとき、曹丕が死ぬときそれぞれで後事を託されたことに現れている。
(注 司馬懿は3度も託されているぞという方もいるかもしれないが、司馬懿の場合、曹叡が死ぬときは、本来後事を託されていなかったが、強引に割り込んだというのが通説である)
このように人間的にも大きく、見識があったのが陳羣である。地味ではあるがこのような人物がいてこそ、国家は成り立つのである。
愛すべき英雄
字は孟徳。魏の太祖。武帝。はい国[言焦]県の人。漢の曹参の子孫?。祖父曹騰は宦官で中常侍。父曹嵩は夏侯氏の出。当初後漢に仕える。後漢では少壮官吏として大いに活躍する。黄巾の乱では潁川でこれを鎮圧し名をあげた。その後宮廷で宦官と何進の権力争いが起き、董卓が乗り込んできたときはこれを嫌って曹操は帰郷した。帰郷した曹操は董卓討伐軍を呼びかけた。討伐軍は、曹操ほか多くの群雄で構成されるも戦意はいまいちであった。しかしほかの諸侯の軍が尻込みする中、洛陽から撤退する董卓軍を追撃ししすいにて徐栄と戦闘するも敗れた。董卓討伐連合軍崩壊後、曹操は[亠兌]州に基盤をおいた。曹操は呂布、劉備、袁術、張繍らと闘い、大局では勝利を収め、次々と勢力を拡大していった。また黄巾の残党の青州兵を吸収し、屯田制度を実施するなど、政治的にも一流であった。また献帝を許に迎えて、大義名分を得たことも大成功であった。その後官渡にて河北で勢力を伸ばしていた袁紹を打ち破り、中原での覇権を打ち立てた。しかしその後荊州を鎮圧すべく赤壁にて呉の水軍と対決するも破れた。しかしその後も曹操の圧倒的な戦力は衰えなかった。213年には魏公、216年には魏王と、曹操は確実に頂点に近づきつつあった。あとは皇帝に就くだけとなるも、ついにつくこともなく220年死亡した。
三国志演義では最初、曹操は、悪い事なかれ主義の官僚がおおい後漢のなかで、ひときわ目立つ清廉な官僚として登場する。そのころの曹操は優秀な官僚であった。現代風に言えば、優秀な中堅幹部といったところであろう。曹操は若いころある人物鑑定家に治世の能臣乱世の奸雄と評されたらしいが、言いえて妙であろう。
さて曹操は何を理念に行動していたのであろうか。私が思うに彼は天下の秩序を回復することを第一義に据えていたと思われる。しかし後漢復興のような馬鹿馬鹿しい理念はまったく持ち合わせていなかったろうと思われる。曹操を「(事実上の)簒奪者」として捉え、悪玉である、とするのが従来の物語であった。劉備を善玉とし、曹操を悪役とする構図である。しかしその見方はまったく間違っていると私は考える。
まず後漢末の中国の荒れ具合は想像を絶するものだったのだ。ある資料によると、戸籍上三国時代の中国の人口は後漢の最も多いときの10分の1に落ち込んでいたという。(もちろん戸籍外の人口もあるだろうからそこまで単純にはいえないが、そもそも人口が減ったのは間違いなかろうし、そもそも中央政府の権威などもそうとう減少していたのであろう。)それはものすごいことである。まさに民族の一大危機といってよかろう。黄巾族の反乱はそうとうなダメージだったのである。そんなとき、中国を統一するには従来の秩序などに頼っていては、かえって時間がかかるだけなのだ。とにかく混乱をいち早く収束させるには、曹操のように一種果断な実行力と決断力を兼ね備えたものの活躍でしか無理なのである。
黄巾族の思想時代は、わりと革新的である。そもそも西暦200年ごろといえば日本はまだ弥生時代である。そんなときにある意味では共産主義的な思想にもとづいて、反乱をおこした中国人民はすごいとおもう。ただその思想内容はいい部分があるにせよ、各地の秩序は大いに乱れてしまったのだ。それに黄巾族の主張はある意味で反儒教であった。
彼にはその無秩序ぶりがいやだったに違いにない。彼は本質的にはやはり儒教的バックボーンがあったろう。そもそも秩序が乱れていたのは大勢の人々が死んでいくことから考えていやだったに違いない。彼も本質的には儒教的秩序をうちたてることを考えていたに違いない。
ただ普通の知識人階級ならばそこで「後漢」の復興を考えるのだろうが、曹操は違った。彼はそこにあまりこだわらなかったのである。その原因として曹操の家柄があったと思われる。曹操の祖父は大宦官で政治的には大きな権力をもっていたものの、宦官は所詮宦官であり、その家柄という点では大いに馬鹿にされていた。曹操は自分の家柄に大きなコンプレックスを持っていたと思われるのである。たとえば若いころ清廉な官僚として活躍していても所詮宦官の家柄ということで馬鹿にされていたこともあったに違いない。そんなとき曹操は思ったはずである。家柄がどうした、俺はただ能力があるのに、家柄ごときで馬鹿にしやがって、と。曹操は今に見ておれと思ったに違いない。
彼はともかくその家柄コンプレックスと自身の優れた洞察力をばねにして、驚くほど果断な政策を実施して見せたのだ。彼は自身のコンプレックスをばねにして、いわゆる建前にこだわらない、すぐれた戦略を実施することができたのだ。このことはたとえばあの司馬懿のつまらなさと比べると、すごく人間的である。私はそんな曹操に惹かれるのである。
乱世の姦雄
曹操は昔は人気はなかった。また中国民衆からの受けもあまりよくなかった。それは曹操があらゆる非常な手段を用いて天下に向かったからであろう。乱世の姦雄、とは私は賢く、実行力もあるけどもどこか狡猾な英雄くらいにとらえている。つまり乱世の姦雄といわれるのは彼にとって本望だろう。曹操の長所は伝統を理解しつつも伝統に逆らえるところだが、逆にとらえれば伝統を破壊する破壊者ということになるのだから。長所と短所は表裏一体である。曹操のように長所が並はずれている場合は短所もまた並はずれているはずである。
非常な手段を用いることは、時には必要である。しかし曹操といえども、たまには判断ミスを犯すのか、非常でない際にも非常時の手段をとって大いに彼の名声を落としたことがある。徐州における大虐殺などその典型例であろう。そもそも大虐殺は必要なかったのに、彼は私憤でそれを実行してしまった。
また人材登用に関しても彼は乱世の姦雄ぶりを発揮した。曹操は人材登用と起用法に関しては確かに一流であった。曹操は能力主義的な登用に長けていた。彼は有能な人材を見抜くことができたし、使いこなすこともできた。しかし、彼の人づかいは、劉備のような義を元にしてものではなく、あくまでも曹操の覇業に役に立つかが根本にあった。役に立たなければ切り捨てる。気に入らなくなれば切り捨てる。例えば現代でも、大企業から小企業まで不況によるリストラが流行っている。曹操の場合は、そもそも会社経営をうまくしているわけだから、リストラをする正当性はあるわけだが、それにしてもそのリストラ的行いはときに非情であり、彼の人気を大きく落とす原因となっているだろう。
荀[或〃]の例がある。荀[或〃]は曹操の覇業に大いに貢献した人物である。例えば許昌に献帝を迎えよ進言したのは荀[或〃]である。また袁紹との戦いで適切な進言をしたのも荀[或〃]である。とにかく曹操の覇業に大いに貢献したことは間違いない。しかし魏公になる曹操を荀[或〃]はいさめた。曰く漢王室復興が我々曹操軍の使命ではなかったか、と。確かにそれまでの曹操は内心はともかくとして、表面上は漢王室の守護者として戦っていた。荀[或〃]の言葉は正論である。しかし曹操はその進言があってからというもの荀[或〃]を遠ざけた。また暗に自殺を強要したと言われる。いくら意見が合わないからと言っても、長年の功臣にたいしてあまりにも非情な措置と言わざるを得まい。
また荀[或〃]の例でいくらか述べたが、曹操の漢王室へのアプローチというのもある意味非情であった。曹操の場合、漢王室に関してはまったく忠誠心がなかったと思われる。特に許昌に献帝を迎えたのは完全に大義名分を得るためだったと思われる。彼は錦の御旗をおおいに利用した。漢王室の守護者という地位は彼に大いなる利益をもたらした。袁紹が曹操との決戦をいたずらに急いだのは曹操が献帝を事実上擁立し、大義名分を得ていて、そのことを袁紹が気に入らなかったからである。また荀[或〃]のように漢王室の守護者としての曹操に使えるものもおれば、曹操個人に内心では仕えているものもいたが、なんにしても曹操軍という新興の軍団に人材が集まりやすくなった一つの原因はやはり献帝の守護者だったところにもよると思われる。このように漢王室を利用したことは覇業には確かに極めて有効ではあるが、その光景はまさしく会社乗っ取りみたいなものであり、すくなくとも道義的には誉められたものではない。もっとも道義にとらわれない、それが曹操の魅力といえば魅力なのかもしれないが。
曹操の元にはたくさんの軍師がいたが、どのものもあまり道義を感じさせない。荀[或〃]は例外だが、だからこそ彼は死に至ったのである。例えば郭嘉は、曹操の大のお気に入りだが、郭嘉自身は、同輩にはあまり好まれていなかったという。程[日立]もかなり狷介な性格だった。賈[言羽]は謀略が趣味のような男だが、やはり道義は感じない。なんにしても劉備と諸葛亮のような、さわやかな主従関係はありえないのである。
なんにしても、曹操は長所と共に短所も際だつ男である。短所も魅力といえば魅力であるが、それにしても曹操のすさまじさは際だっている。それが乱世の姦雄たる曹操の本質だろう。
中原での戦い
曹操は戦闘においていつも優れていたというわけでもない。少なくとも三国志演義などを読んでいると曹操が勝つシーンというのはたいがい印象が薄く印象に残るのはたいてい負ける部分ばかりである。曹操はいつ戦いに勝っていたのだろうか?
言葉遊びのようにも思えるが、曹操は戦わずして勝っているのである。もちろん実際に戦闘を行い勝利をあげた戦いもあった。しかし曹操の本質は戦わずして勝利をあげるところにある。そもそも洋の東西を問わずして戦いに勝つものは、実際の戦い以外にも様々な手を打つものである。例えば関ヶ原の戦いで徳川方が勝ったのは、家康の謀略が勝っていたからであり、小早川の裏切りもその謀略の副産物ということができる。また第二次大戦でミッドウエーの戦いで日本軍が敗れたのは戦闘技術が劣っていたと言うよりは、その周辺の能力すなわち謀略、情報収集能力、兵站力がアメリカ軍よりも劣っていたからである。
曹操の場合は三国時代のアメリカだったのだ。統合作戦本部、が謀略を練るブレーンが荀[或〃]郭嘉らの清流派諸子である。そして情報収集は彼らが的確に行っていたのだろう。曹操は彼らブレーンの意見を統合し、そして実行に移した。それも的確にである。曹操は最終判断を下す才に長けており、それがここの戦闘に負けても戦術的には勝利を挙げる要因なのである。つまりのところ曹操は戦術的に他の群雄に負けたことはほぼ皆無だったのである。戦闘で負けても戦術面ではまったく負けたことはなかったのである。そして戦術は戦闘に勝る。ここの戦闘にいくら勝利をあげたところで、戦術が間違っていればまったく実効的効果がないことは、項羽の例で証明済みである。
三国志のゲームで私が疑問に思うのは兵站のことである。曹操軍の兵站は荀[或〃]らの働きにより保たれていたが、普通の群雄ではそうそう保たれたものでもなかったと思われる。つまり兵站が優れていると言うことは優れた軍団にのみできるのであり、光栄のゲームのように兵糧が無条件で他の戦場に持ち越せるというのは現実離れしている。兵站力をゲームで数字化することは困難だろうが、是非改善してほしいものである。兵糧部隊の警備とか言う問題ではない。もっと大きなことである。
曹操の戦略というのは実にオーソドックスである。基本的に弱いところを攻めてそれを自己の勢力に取り込み、徐々に勢力を拡大していく。強い勢力との争いは避けると言うことである。つまり、勝てるみこみのある戦闘しか行わないとのである。一見例外のように思えるのが官渡の戦いである。少なくとも曹操は袁紹の勢力よりも劣っていた。曹操にとってかならず勝利ができる戦闘ではなかった。しかしそれにしても袁紹との戦いを200年頃まだ回避したのは曹操の戦術眼の確かさを示している。つまり戦闘を曹操が袁紹と対決できる勢力にするまで引き延ばした曹操の戦術勝ちである。ある時期までは曹操は袁紹に相当媚びを売っていた。その割り切りたるや、マキャベリスト曹操の面目躍如である。これは信長がある時期まで武田信玄と友好関係を保っていたことと極めてにている。
曹操はもっぱら黄巾族の残党を平定して、中原を押さえた。つまり曹操は最初は主に黄巾族と戦ったのだ。その典型例が青州黄巾との戦いである。最初は戦闘力の劣る曹操は黄巾に劣勢だったが、戦術面で勝る曹操は最終的に青州黄巾に勝利した。この勝利で曹操軍団に青州兵が加わり、軍団が強化されたのである。
その後群雄との争いで呂布、劉備、袁術との戦いなどがあるが、いずれも他者の利害を巧みに操り、最終的には曹操が勝利をあげている。[亠兌]州を呂布に襲われたときは、荀[或〃]、程[日立]らの働きで持ちこたえることができたし、袁術を巧みに撃破したし、劉備は呂布との間を不仲にすることで退治した。
文章にしてみるといやに簡潔であるが、それは曹操の戦略も簡潔だったからであろう。曹操の軍団はいつも行動が素早い。また戦いもあっさりしている。つまり簡潔だからこそ戦いに勝てたのだ。負け戦の記述が多いのは、負け戦の方が簡潔でないからであろう。もちろん曹操悪玉論で、曹操の悪い面を取り上げようとしているのかもしれないが、と同時に曹操が勝利をあげた中原の戦いは曹操軍団の戦い方が簡潔なので描写がしにくいからではなかろうか。
官渡の戦い(改訂版)
袁紹との戦いは曹操にとって苦しい戦いだった。少なくとも曹操にとって勝ちが計算できない先の読めない戦いだったに違いない。
袁紹との戦いは曹操側が画策したものではない。しかし袁紹が画策したわけでもない。両者の衝突はいわば宿命的なものであった。戦いは必然だったといえる。曹操にとっても、袁紹にとっても、お互いが目の上のたんこぶだったのだ。
しかし戦いに向けての両者の態度は全く異なっている。曹操は袁紹との戦いに向け周到な謀略を実行し、かつ官渡に拠点を築いた。それに対し袁紹側は曹操対策は皆無であった。
袁紹は驕慢だった。劉備が徐州で曹操に反旗を翻したとき、曹操は都の許都を留守にして劉備を討伐した。これは袁紹勢力との関係を考えると極めて危険だった。しかし袁紹は田豊の進言を聞かず、息子の病気がを理由として出撃しなかったのである。とんでもない怠慢である。乱世に生きる人の行動とは思えない。そもそも戦争など勝てばいいのであって、いくら闇討ちでも、決戦で勝利しようともとにかく勝てばいいのである。袁紹はそのことを完全に忘れていた。袁紹にしてみれば曹操など微弱であり、いつでもうち破れる。だから今は出撃しないぐらいの軽い気持ちでの戦争回避だったのだろう。また曹操は袁紹のそういう甘い性格を見切っていたと言えるだろう。
袁紹の驕慢さは官渡の戦いでも如実に現れている。官渡の戦いは事実上天下分け目の決戦となった。曹操側が能う限り戦闘準備をしたのに対して、袁紹軍には多くの欠点があった。まず第一に袁紹は戦力的には曹操軍より優勢なのに短期決戦にしてしまったこと。こうなった原因は袁紹軍の戦闘準備の不足である。また袁紹のせっかちな性格、曹操軍への侮りもあった。袁紹軍は大軍で総勢12万と言われる。当然後方の兵站の拠点が必要である。しかし袁紹は十分に準備してこなかった。そのため袁紹は兵站面の心配から、兵力面では優勢なのに強引に曹操軍に挑まなくてはならなくなったのである。そのため袁紹軍は不用意なぐらい曹操の築いた拠点に突っかかって戦闘を実施している。これは兵站面から考えると極めて危険である。また用兵面において余裕をなくしてしまった。
逆に曹操の側から評価すると、官渡にかなり以前から一大兵站上の拠点を築いていたことが大きなアドバンテージであった。また事前に戦闘準備を行い、戦術研究も十分にしていたフィールドで決戦できたのも大きなアドバンテージであった。
袁紹は定見なくただ軍を進めただけであり、それはさながら現実無視であった。数を頼みにしていたもののその戦いぶりのでたらめさは目を覆うばかりである。結局のところ短期決戦で一気に決着をはかろうとするからそういうことになったのである。だがそれにしてももう少しやりようがあったのではないかと思ってしまう。なぜ袁紹側が白馬を攻めなければならないのか?その意味は限りなく薄い。別に袁紹ほどの大軍があるならば、田豊の進言にもあるように黎陽で拠点を築いて持久戦に持ち込めばよかったのである。曹操が突っかかってこざるを得ないようにすればよかったのである。そうしていたとすれば袁紹は後詰め決戦ができた。そもそも短期決戦は勢力が微弱なものがとる戦法である。短期決戦といえばかっこよく聞こえるが、基本的に投機性の高いものである。短期で勝負を決しようと言うのだから負けた場合軍隊は総崩れになる。また仮に短期決戦を用いる場合は、兵力は機動性が高く、かつ集中が行われなければならないのだが、それは袁紹軍の場合ない。総帥がでたらめだったし、袁紹には機動と集中の意味を全く分かっていなかった。
200年2月から4月頃まで、白馬で戦闘が行われた。白馬では曹操軍の劉延が約1000騎で守っていた。約2ヶ月、劉延はこれを袁紹軍の猛攻からよく保った。しかし陥落しそうになったので曹操の参謀荀攸が計略を実行した。白馬より南方の渡河点、延津に兵力を集中し、対岸の袁紹を延津の対岸に釘付けにすることによって、隙をついて顔良を奇襲しこれをうち破るというものであった。これはいわゆる後詰めの応用である。奇襲は成功し、白馬で袁紹軍の勇将顔良が関羽によって討ち取られた。袁紹軍は先鋒に兵力を逐次投入し結果各個撃破されたのだ。
顔良惨殺。このことに怒った袁紹はなぜか大軍を延津に渡河させ、(黄河を背にして)背水の陣をひくことになった。韓信の場合は背水の陣を逆手にとって勝利に至った。しかしこれは寡兵で敵をうち破る作戦である。袁紹のような大軍がなぜ寡兵で敵をうち破るときにつかうような投機性の高い戦いを展開する必要があるのだろうか?まったく理解に苦しむ。短期決戦を志向し、かつ背水の陣をひくというのは戦術面での袁紹軍の選択肢を著しく狭めたのであった。また袁紹は戦いの場で感情に流されている。そもそも顔良がうち破られたその怒りにまかせて渡河したとすれば、感情のみで死地に自ら赴くようなものである。
延津を支えきれないと読んだ曹操は果断な撤退を敢行する。袁紹軍全体が兵力を頼みに曹操側につっこんでくる。曹操は機動性のある袁紹軍の文醜隊のみを自軍の陣営中に深く入り込ませ、伏兵にて文醜隊をおそうとした。この作戦も見事に的中し、文醜は乱戦の中で討ち取られた。
袁紹は顔良、文醜という麾下の勇将が討ち取られたことに激高し、一気に曹操軍を攻め立てた。二度の前哨戦は曹操の勝利に終わったが、それでもまだ袁紹軍の方が兵力的には圧倒的に優勢だった。袁紹はしばらく戦を優勢に進める。袁紹も官渡付近ではさすがに手堅い戦術を採った。曹操に対してじわじわ押し立てていくという正攻法で、このとき曹操軍は負傷者が続出、曹操は官渡に籠城することとなった。袁紹は大軍で一気に官渡にこもる曹操軍をうち破ろうとした。そのとき袁紹は官渡を落とす、という局地戦的視点では持久戦を覚悟したのだという。(もちろん大局的には短期決戦を志向している。この時期袁紹の参謀沮授は袁紹に敵の消耗を強いる恒久的持久戦を主張したが、袁紹はそれを却下している)
袁紹側では許都急襲策が(官渡を攻め立てているときに)提案された。しかし袁紹はこれを却下した。理由は不明である。袁紹の大局観のなさが原因であろう。そもそも今回の官渡の戦の目的が献帝奪還なのか、それとも曹操軍と決戦するのかその優先順位が全く明らかでなく、袁紹は決断を下せなかったのである。曹操側は許都をおそわれていたら危なかっただろうと思われる。また袁紹は許都強襲はしなかったが、代わりに劉備を派遣し、曹操軍後方攪乱作戦を実施したものの、そもそも劉備の兵力が微弱であった。また大軍が分散するのも問題だが、官渡に釘付けになっているのも軍隊の機動という観点から見て大いに疑問である。
一方曹操も官渡の籠城戦では相当弱気になっていた。一時官渡からの退却を考えたという。しかし曹操側の参謀荀[或〃]が曹操を励ました。官渡で戦わないでどこで戦うのか、と。曹操は結局官渡に居続けた。ひいた方が負けるのは確実だった。
袁紹は官渡を攻めるに当たって、弓を高い櫓から放ったり、例の公孫[王贊]との戦いで用いた地下道作戦で、曹操を苦しめた。しかし曹操側も発石車や逆地下道作戦を用いて袁紹に対抗した。
戦闘は膠着状態に陥った。もはや200年も10月まで来ていた。こうなってくると、食糧が問題になってくる。
結局のところ兵站面で袁紹軍の無茶ぶりは明らかであった。そもそも10万程度の大軍を越冬させるなどと言うのは無茶であろう。また袁紹軍の兵站はそもそも破綻していた。戦前に戦闘準備を行っていなかったからである。袁紹の本拠地から渡河していると言う点から考えて地勢的な不利は明らかである。
最終的には許攸の投降による烏巣の襲撃が曹操軍の勝因である。ただしそこに至るまでの経緯を見ると、曹操軍は勝つための努力をたくさん重ねていたのに対し、袁紹軍はそれが全くない。曹操は機を見るに敏であった。また参謀の意見を的確に採用した。それに比べ袁紹はまったく逆であった。袁紹は現実を見ていなかったと言えるだろう。彼は戦の状況に対応していくという姿勢にかける。ただ闇雲につっこんでいっただけである。さながら猪武者である。
赤壁の戦い(曹操軍の視点)
官渡で敗北を喫した袁紹はその後病死した。袁一族はその後袁尚派と袁譚派に分かれた。曹操はその争いに巧みに乗じて袁一族を確実に追い込んだ。冀州を平定後曹操は[業β]城を造営し、根拠地とした。幽州、[千千]州、などを完全に平定したのは207年であった。
いよいよ華北を平定した曹操はいよいよ南方に目を向けた。曹操は当時、華北の混乱を避けて非常に繁栄していた荊州にねらいを定めた。曹操にしてみれば荊州を平定すればもはや残るは孫呉のみである。天下統一も目前と思ったのであろう。
荊州平定に関しては曹操の思惑通りだったと思われる。曹操が一度南下する姿勢を見せると劉表の跡をついだ劉[王宗]は早々に降伏してしまった。ここに荊州軍は早々に帰順することになった。許都を出発するときは10万程度だったと思われる曹操ぐんだがこの時点で7,8万は増えたのではなかろうか。
劉備を曹操は追撃しているが当時の劉備の勢力は話にならないほど微力である。曹操は当時の荊州の物資の集積地江陵に劉備が入るのを阻止しただけで、真剣に追撃しているようには思えない。なんにしても孫呉を打ち破ればそれで事実上天下は統一と思っていた節がある。また孫呉も荊州軍のように容易く降伏すると見ていたのではあるまいか。
曹操が孫呉をターゲットとして考えれば、荊州から攻め入る以外にも合肥から柴桑を目指すコース、あるいは信陽から江夏を目指すコースも考えられた。しかし曹操は江陵から柴桑を目指すコースを取った。このルート選定は大軍の運用を考慮しているのである。すなわちほかのコースでは大軍の運用は難しかったということであろう。逆にいえば、曹操にしてみれば一番遠回りでも用兵上一番やりやすいコースをとったわけであり、この点では間違ってはいない。
しかし大局的戦略はそんなに間違ってはいないが、局地的戦術で大きな過ちがあった。まず曹操は水軍の運用に関しては素人同然だったこと。そのため帰順して間の無い荊州水軍を有効に活用できなかった。それに曹操軍(元々の軍)は水上戦闘ではまったく素人同然であり、水上の風土にも慣れていなかったこと。そのため曹操軍内で疫病が発生したこと。この二つの要因から曹操軍はほとんど戦闘能力を喪失していた。
曹操はさすがに袁紹とは異なり、数を頼みに強引な決戦を挑むようなことはしていない。この点誤解があるようだが赤壁はあくまでも呉が決戦を仕掛けたのである。曹操は水軍で要塞を築き徐々に呉を圧迫していく戦略をとろうとしていたのである。よく演義などで[广龍]統の火計の為の戦術とされる連環の計であるが、あれは別に計略でもなんでもなく、曹操が水上要塞を築くために船をつなげたに過ぎないはずである。しかし先にも述べたように水上においては、戦闘技術が曹操軍には無かったのであった。そのため鎖のつなぎ方が実践的でなかった可能性は大いにある。そんな原因もあって呉軍の挑んだ決戦に曹操軍は容易に敗れてしまったのである。
また周瑜の用兵は見事だったといえるだろう。少なくとも水上戦闘においては周瑜の用兵が曹操を完全に上回っていた。また呉軍は周辺地理を把握しており、いわゆる「東南の風」が例外的に発生することも当初から見抜いていたと思われる。東南の風が偶然に吹いたからそのときに決戦を呉が挑んだというよりは当初から呉は東南の風が吹く日を決戦決行日と定めていたのではなかろうか。また黄蓋の苦肉の計も見事であった。
曹操は官渡ではすばらしい指揮振りを見せたが、赤壁ではとりたててよい指揮振りを見せたとはいえない。それは華北と華南の違いといえるであろう。水上の戦いというのは陸上とは勝手が違うからである。また袁紹や袁術、劉表などと異なり、孫呉には優秀な人材がいた。少なくとも赤壁においては孫呉が曹操を上回ったといえるだろう。
曹操とて敗れたとはいえ、致命的な損害はこうむっていない。大きな痛手ではあったろうが曹魏は揺ぎ無かったのである。それは孫呉の戦術的な優位性は所詮長江の上でしか発揮できないからである。依然中原の覇者は曹魏であり、それは結局三国時代になっても変わらなかったのである。赤壁の戦いで曹操は天下統一の意図がとりあえず阻止された。しかし彼はその後も天下統一は狙っていたと思われる。結果的に曹操は天下統一できなかったがそれは赤壁の戦いで敗れたのが原因であるもののそれはその軍勢が敗れて疲弊し統制が取れなかったからというよりは、孫呉、そして後の蜀漢政権が地の利を生かしたそこそこ陣営のそろった政権になってしまったからである。
曹操が天下統一できなかったのは曹操の戦略が誤っていたのではなく、戦闘技術が無かったからである。もちろん孫呉や蜀漢が愚かならば統一できただろうが、孫呉、蜀漢は先の劉[王宗]や袁術、袁紹などよりは愚かでなかったので曹操は統一できなかったのである。
曹操は赤壁以後はもっぱら涼州、益州平定を目指し、そこから天下統一を狙ったと思われるが、劉備が益州を奪ったことによりそのもくろみも実現せずに終わる。(なおその侵攻ルートで晋が天下統一した)
結局曹操は天下統一できなかったがそれはやむをえなかったであろう。また、逆説的であるが、もし曹操が天下統一するということも十分にありえたと私は考える。しかしそうなったとしたら三国志などという書物はそもそも成り立たないわけである。曹操も傑物だったが、孫権や劉備も傑物だったのであり、そうした英雄が同時代に存在したからこそ、三国志は面白いのである。
蜀 221~263
蜀は221年に劉備が皇帝に即位することにより成立した政権である。先主劉備は黄巾の乱以来中原各地を転戦するも流浪する運命にあった。しかし諸葛亮を得てからは戦略が首尾一貫することになり、赤壁の戦後、荊州の一部をドサクサで奪って以来、勢力が伸張する。同族の劉璋から蜀を奪って中原回復の根拠地とするを目指すも、魏と呉により荊州を奪われ、以後劉備政権は蜀の地の地方政権となる。221年に皇帝に即位した劉備は夷陵の戦の敗北のショックで死去。以後劉備の息子劉禅が即位した(後主)。以後もっぱら国政は諸葛亮の手にゆだねられることとなり、諸葛亮は内政を充実させ、呉との関係に始末をつけた後、魏への侵攻を開始する。しかしその戦は兵站の困難さにより容易には進まなかった。諸葛亮は234年、陣没する。その後丞相は蒋[王宛]、費[ネ’韋]とつづき、もっぱら蜀は守勢でどうにか安寧を保つ。しかし費[ネ’韋]死去後、姜維は北伐を敢行、蜀経済は疲弊した。宮中では黄皓ら宦官がはびこり、まるで後漢末のような様相を呈した。最後は結局鍾会率いる魏の征蜀軍の別働隊に進入を許した。劉禅はさしたる抵抗もせず、降伏した。
敵は外にあらず、時代にあり。 姜維
202~264 きょうい はくやく
姜維字は伯約。天水郡冀県の人である。
もともとは魏の人である。しかし何らかの事情により諸葛亮が祁山に兵を進めたとき蜀に投降したのである。三国志演義では諸葛亮の計略で投降したことになっているものの真偽は不明となっている。ただ諸葛亮が蒋えん(変換不可)に宛てた手紙で
姜伯約は忠もて時事に勤め、思慮精密なり。そのいだけるところをみるに、永南(李邵、蜀の名臣)李常(馬良)の諸人も及ばざるなり。その人涼人のすぐれたるしなり。とあるので諸葛亮は彼を相当評価している事が知れるのである。
諸葛亮の死後丞相の位を継いだのは蒋えん、費い(丞相ではないが)らであるがこれは姜維に能力が無かったからではなく姜維が魏の降将であり立場が不当に低かったからだと思われる。当時の蜀漢は荊州あるいは益州出身者が要職を勤めていたのである。
もちろん蒋えん、費いらは蜀をよく保った。後の蜀において4人の英明たる宰相として上げられる『四相』にあげられているのは、諸葛亮、蒋えん、費い、董允の4人であり、彼らの守勢の政治こそ当時の蜀の人民の間では受け入れられていたと思われる。
蒋えん、費いが存命中のとき姜維は兵をだすことができなかったが彼らの死後姜維は出兵が出来るようになったのである。
姜維は毎年のように魏領に出兵を繰り返した。時には大勝し時には惨敗した。しかし姜維には別の敵が迫っていたのだ。
このころの蜀漢においては宮中と府中が混同され、後漢末のように宮中が政治やら軍事に口を出すようになっていたのだ。このころ黄皓が宮廷で暗躍し、姜維は彼らによって大将軍の地位を追われそうになったのである。姜維はこれを察知し262年以降成都に戻る事はなかった。大将軍にはとどまれたもののもはや宮廷、府中の腐敗ぶりは目を覆いがたく、姜維の軍事的才能をいかすことはできなくなった。
姜維は263年の対魏防衛戦においてもその軍事的才能を発揮した。彼は防衛線を幾重にも張るのではなく、ある一部分に難攻不落の要塞を築きその地点を絶対死守しそのほかの地点の敵は遊撃軍が撃破するという積極的作戦を実施した。その結果鐘会ら率いる魏軍は撤退を考えたほどであった。しかしそのあるいみでは遊撃軍たるべき後方にいた蜀軍は少数のとうがい率いる軍に敗れ敗退してしまったのだ。
こうして成都はあっさりと降伏したのであるがその戦いぶりは戦いとは言えず、蜀はもはや国家としての機能が停止していたと言えるだろう。人民は94万、兵士10万、食料もあったのであるから、蜀の人民は救われたと言える。
つまり姜維は確かに軍事的才能を宮中の堕落などで生かせなかったのは不運であった。しかし人民から見れば時代に合わなかったひととみる事もできる。
ちなみに姜維は蜀降伏後もあきらめず、鐘会を扇動し反乱を起こさせどさくさで蜀を復興させようとしたといわれる。彼の諸葛亮などが有していた価値観に最後まで殉じたといえよう。そういったいみでもやや時代遅れだったとおもう。ただその執念深い人柄には敬意を表したい。すがすがしさも感じる。
なお剣閣の伝説で剣客を去って鐘会とともに成都に向かおうとしたとき姜維は諸葛亮から授かったという兵法書をある一人の兵士に託したという。その時彼は必ず戻ってくるからそれまでここを守っておけと命じたという。たくらみがばれた姜維は鐘会らとともに処刑されたがその兵士はまだ石になった今となっても姜維を待っているのだという。それだけ姜維のたくらみに実現可能性があったということだろうか。
神? 関羽
?~219 かんううんちょう 前将軍、漢寿亭侯
河東群解県(山西省運城県)出身。劉備旗揚げの頃からの宿臣。たえず劉備と行動を共にし、曹操に臣従を進められてもその劉備への忠義は揺るぎもしなかった。最後は同僚をあなどる性格が災いし呉に処刑された。
この人物はとにかく忠義の固まりである。とにかく劉備への忠義は揺るぎなく、このことは称賛に値する。すくなくとも羽は主君にとってはこれほど便利な存在はないと言うくらいの忠義を持っていると思われる。とかく曹操の元に一時期属していたことを悪く言う人がいるが、あれは成り行き上仕方ないし、そもそも劉備の逃走があまりにも見事すぎるのである。あの場合劉備の方がむちゃくちゃであったと思われる。
関羽はかなりの教養人だったがその教養は儒教が根本であろう。その儒教をもとにして、関羽は臣としての筋を通したのだ。つまり劉備の恩が第一。でも曹操の恩にも応えねばならない。それが顔良を斬るという行為なのだ。筋を通した彼は立派と言えよう。
彼が豪傑だったという証拠は彼の華々しい戦歴から言って明らかであろう。顔良を殺した、ほうとくをとらえ処刑したなどが有名であろう。(華雄を殺した、文醜を殺したなどは正史にはない) また赤とばに乗っていたなどというのも彼の並々ならぬ怪力を示している。
また数々の戦場で劉備の別働隊として戦術単位の隊長を果たしてきたことも劉備陣営には貴重であったろう。
しかし関羽といえども弱点はある。プライドが高すぎたのだ。例えば五虎大将軍で関羽が筆頭だったが、黄忠と同列にされるのをいやがったのはその典型だろう。
その気位高い性格が災いし、関羽はびほう、ふしじんらの裏切りもあって、はん城攻撃中に呉にけいしゅうを奪われてしまった。彼の戦略官としての限界が現れている。彼はどうにも大局観はなかったのだ。
宋代以後とくに関羽への民間の信仰は高まった。それは彼の劉備への揺るぎない忠義心に惹かれたからだと思われる。劉備は関羽(そして張飛)のために私憤で呉を攻めた。つまり劉備、関羽、張飛の三人のつながりはそれほどだったのである。劉備の行為は皇帝としては全くほめられたものではない。しかし皇帝にそこまでの情を抱かせるほど、三人は一体だったのだ。
関羽の劉備とのつながりはすがすがしいものである。現実の世界には裏切り、欲、打算がうずまいている。すくなくとも表面上はそれらを感じさせない関羽の忠義にわたしは惹かれる。
とにかく現実はとにかく、演義の蜀の武将のエピソードというのは、人間味にあふれている。我々は三国志の人物の能力に惹かれるのではなく、人間に惚れているのだ。関羽は特にその典型だろう。
再評価を 魏延
?~234 ぎえん ぶんちょう
魏延字は文長。義陽郡(河南省)の人である。最初劉表の部下で後劉備配下となる。漢中太守などを歴任。リュウビには信任されていた。しかし諸葛亮とはそりがあわなかった。最後は馬たいに殺され、非業の死をとげる。
彼の生涯はまさに典型的武人そのものである。功にはやり抜け駆け、勝手に城を開城、韓玄の首をきって投降するなどやることはむちゃくちゃである。
ただ彼とてだいたいのときは命令に従ったし、何より彼は歴戦の勇者である。入蜀、漢中攻め、南蛮征伐、北伐等ではいつも部隊を指揮しそれなりの戦果をあげてきた。
つまり本当の戦闘のプロ、現代風にいえば性格の悪い中堅幹部といったところか。
もちろん魏延の位はただの中堅ではない。しかし性格的には所詮その程度といったところであろう。楊儀ごときただの事務屋とあんなに反目しあったのは彼の人間が小さかったからであろう。ギエンほどの武勇の持ち主ならもう少し度量があればもっと評価されていたような気がする。
もっとも三国志にでてくる武人は偏屈なやつが多い。たいていは主君には忠実だが部下、同僚にはとんでもない態度を取る場合が多い。(ギエンも劉備を主君と奉じ、割合忠実だったように思える。)
孫権配下の凌統や甘寧なども相当あらくれものだし、行動もむちゃくちゃだし、ハンショウなども晩年はとんでもない行いを平気でおこなったという。
関羽も同僚をあなどり裏切られ、張飛も部下に裏切られたが、これらからも彼ら三国志の武勇の英雄が性格的にゆがんでいたかがわかる。
でもそんな彼らは決して人気は低くない。関羽などは神としてまつられているくらいである。
それに比べギエンの評価は低過ぎないだろうか?もっと評価されてもいいのではないだろうか?(もっともギエンの性格の悪さは呉の孫権にまで伝わっていたと言うから、その性格は相当悪かったのだろう。)
第一次北伐のときの長安急襲の策などは戦術家としてのすばらしさもみせつけていると思うのだが・・・。
彼の不運はその不仲な同僚が楊儀、そしてそれにつながる諸葛亮だったところだろう。つまり敵対する同僚が孔明だったのが不運だったのだ。孔明の人気は中国、日本のそれぞれで高い。その孔明に敵対する悪者め!みたいな感じで魏延がとりあげられてしまったのだろう。
しかし現在では孔明はむしろ政治家として適性があったと言われ、ギエンの献策が正しかったとする意見も多い。また孔明死後殺されたのも派閥あらそいみたいなもので別に魏延が蜀に反抗したわけでもあるまい。
いまこそ魏延の再評価を。ただの武人としてはギエンも傑物である。
果断な実行力。諸葛孔明
181から234 しょかつりょう/こうめい
諸葛亮孔明。琅邪郡陽都の人である。(現在の山東省)蜀の丞相。劉備陣営に迎えられ、外交、政治面で活躍。劉備の死後は政治に加え軍政、軍力の最高指揮官を兼ねた。5度北伐を敢行するも志半ばで五丈原にて没する
この人は本当に有名な人であり、わりと三国志に詳しくない方でも知っている。書店などに行っても経営学のヒントとかとして書かれたりしているのである。
まずよくあがる疑問がある。そして最後まで解けない疑問がある。なぜ孔明は劉備に仕えたのか? 普通の解釈すると劉備の人柄に魅せられたとか、劉備の漢帝国復興の大儀に魅せられたとかいうように考えるだろう。
もちろんそういう部分もあろう。しかし私は孔明の意地が一番の背景だと思う。孔明の兄諸葛瑾は呉に仕えていた。また後の魏において諸葛誕の反乱を起こした一族もいた。つまり孔明以外にも歴史に名を残す一族の人物がたくさんいたのだ。また一族に限らず、天下に諸葛亮のライバルはたくさんいた。魏や呉には諸葛亮が仕官する年齢になった頃にはすでにたくさんの人材がいて、もはや諸葛亮を満足させるようなポストはあいていなかったように思われるのである。魏や呉にはもはや既存の知識人階層の秩序は形成されていたのである。諸葛亮は加えて次男であった。だからある程度リスクを犯すことができたのであろう。
諸葛亮は劉備、そして劉禅に忠実に仕えた。もちろん本心から忠誠を誓っていたに違いない。彼が誠実な人物であったのは間違いない。しかし諸葛亮はただの誠実野郎で、劉備の大義に魅せられただけではないと思う。あくまで彼個人のプライドを賭けた、彼の存在を歴史に残そうとする作戦のために、劉備に仕えたとも思えるのである。
例として適切かどうかわからないが元首相、外務大臣の広田弘毅は東京裁判でほとんど自身についての弁解をほとんど行いませんでしたがこれは主に広田の東洋的価値観に依拠すると思われる。広田は「自分の業績は自分が定めるものではない。後世の人が定めるものである」と述べている。(広田は自己弁解を行わなかったせいで文官で唯一絞首刑となった。この判決は当時連合国の間でも疑問がもたれた)この価値観はつとめて前近代的東洋思想だと思う。つまり歴史の流れの中で自分を位置付ける。西洋的な神と個人の一対一の関係とはわけが違う。ですから私は諸葛亮は歴史に名を残したかったというのは歴史の中で業績をあげたい、それもおおきな業績をあげたいという野望があったという意味で述べたのです。歴史の流れの中で輝く存在になりたい、それが諸葛亮の望みだったと思う。しかしそれはあくまで西洋的自己顕示欲というよりは、東洋的な歴史の流れに依拠するもだと思う。
もちろん彼は当時の儒教的考えに依拠した政治体制の復活を考えていたとは思う。しかしそれは後漢の復活というわけではないはずである。劉備、劉禅を皇帝に即位させる、それが彼の目標となったのだ。彼は自己の目標の実現のため、蜀の地の内政を充実させた。そして軍備を整え、5度も北伐を実行した。その実行力には感嘆するほかない。理想を実現するために行動した。両者の高度な次元での融合は見事と言うしかない。
諸葛亮は蜀の行政を把握し、かつ軍を率いて北伐した。その政治能力、統率能力は参謀の域を越えている。
諸葛亮は戦術面がやや劣るものの戦略指揮官、行政官としては超一流であった。劉備死後の蜀漢は事実上諸葛亮が君主のようなものであった。劉禅の立場は後漢の献帝ぐらいのものだったのではないだろうか。つまり蜀漢の中で後漢における曹操と同じような地位だったといえるのである。それでも私心を捨て、少なくとも自分の一族のために金をためたりしなかった諸葛亮は清新だったといえる。
諸葛亮のまねをしようとした姜維は結局民衆に嫌われた。あまりにも軍事負担が大きくなりすぎたからである。それに比べ諸葛亮は過大な軍事行動をしてもなお、民衆にうらまれなかったのである。いや、彼一流の政治感覚により、民衆に嫌われないよう彼が慎重に施策を実施していたのである。その能力たるやすさまじいといえる。諸葛亮が人身掌握に長けていた証拠であろう。
だから諸葛亮が54歳で過労で死んだのは当然であろう。民衆を納得させつつ、5度の大きな軍事征伐をこなすというのは並大抵の人間ではできないからである。
諸葛亮について考えると、まさに彼は自分の信念に準じた。信念実現のための行動もまた見事である。その実行力や、一個人としてすばらしいものだった。
趙雲 ダンディ!
ちょううんしりょう ?~229
常山国真定出身。陳軍将軍、永しょう亭侯。最初公孫[王贊]に仕えるも田楷援軍のときから劉備に仕える。その後しばらく趙雲は郷里に戻ったので劉備とは離れ離れになっていたが、劉備が袁紹に身を寄せていたときに再会する。その後はまさに劉備軍の中核として働いた。
趙雲、三国志演義ではまさに必殺仕事人といった趣である。その仕事振りは見事である。たとえば有名なものとして、劉備が孫権のもとで遊び暮らしそうになったとき、それに換言したり、とか諸葛亮の北伐のとき、撤退戦で一騎も失わずに帰還したとか…。
しかしこれらの事柄は正史には載っていない。あくまでも他の歴史書に載っていることなのである。しかしだからといって趙雲の価値が下がるものではない。さいきん趙雲はたいしたことなかったという説が唱えられているが、そんなことはまったくないのである。
たとえば長坂橋で阿斗を救い出したのは事実だし、諸葛亮から絶大なる信頼を得ていたことは紛れもない事実なのだから。
漢中の戦いで、城の門を全開にして、はったりを利かせて曹操に疑念をいだかせ撤退させたエピソードは彼の大物振りを示している。(いわゆる空城の計)ちなみに劉備はこのことを聞いて、「子龍は一身これ胆なり」と言ったという。
どのエピソードも趙雲の武勇のすばらしさ、そして冷静な判断力、勇気を示している。
彼は天下の戦略をたてていくような諸葛亮のごとき知略はなかった。しかしひとたび戦略を与えられればそれに沿って戦術を遂行するという知略は持ち合わせていた。趙雲の戦歴を見るに、戦術的誤りというのはほとんどないのである。
彼ごとき人材は組織にぜひ必要である。そういった意味で劉備、趙雲、孔明という三人がそろった期間があまりにも短かったのは残念である。
演義では、趙範の親戚の美人の女を、倫理的観点から妻にするのをことわったりするエピソードなどもあり、どうしても優等生的イメージが付きまとう。しかし正史の記述をみるに彼はまさに誠実かつ強い武人であり、優等生ではないだろう。彼はひたすら職人だったのだ。それは現代の軍隊で言えば、大将とかではない。ちょっと例えが悪いかもしれないが、戦闘機のりでエース(たくさん敵を撃墜した人)という感じだろうか。
張飛 劉備をうらぎらない
?~221 ちょうひよくとく(正史では益徳)
琢郡のひと。劉備挙兵以来の忠臣。劉備に従い各地を転々とした。まさに劉備の忠実な家臣である。最後は部下に殺された。
正史には桃園の誓いのエピソードはない。しかしそれに類するエピソードは劉備、関羽、張飛の間であったと思われる。それだけ彼らのつながりは強固だった。
張飛はあまりにも勇猛だった。呂布には劣るかもしれないが、少なくとも当時では最強の部類だったと思われる。関羽とどちらが強いのか興味深いところではある。ちなみに張飛は身の丈180くらい、蛇矛をふるうという豪傑だった。
張飛は戦略やら戦術を考えるというタイプの人間ではない。関羽や劉備がまがいなりにもそういうことを考えていたと思われる。しかし張飛はそういうことは全くなかった。張飛がぎゃくにすがすがしいのは、全くそういうことを考えなかった点であろう。張飛はただ劉備に従えばいいと割り切っていたようだ。自分は戦場で暴れればいいと思っていたようである。
(張飛の個人的戦闘シーンは多岐に上る。呂布と戦闘したときは、やや呂布が優勢だったものの、ほぼ互角に戦った。呂布をして「世のなか広しといえどもこんな豪傑がなぜ士卒をしている」と言わしめた。馬超とも一騎打ちしたが、結局決着はつかなかった。張[合β]とも戦ったが、見事にうち破った。)
その割り切りはある意味すがすがしい。勇猛でもたとえば呂布のごとく私利私欲に徹したあまりすがすがしくない人物もいる中、彼の劉備に仕え、漢室復興を目指すというのはモラルが高いといえる。
諸葛亮が劉備に仕えたときも、二人のその接近ぶりに当初は嫉妬したものの、孔明の知謀を認めてからはすがすがしく従っている。彼は自分が認めた人物には極めて忠実だった。(孔明の場合、劉備があそこまで認めているなら、という気持ちもあるだろうが)
劉備にここまで忠実に従った臣というのは張飛ぐらいであろう。関羽や趙雲はほかの君主にも仕えていたことはある。しかし張飛にはそれがない。
張飛の三国志の中での最大の見せ場といえば長坂橋の戦いでのエピソードであろう。曹操軍の遠征により、新野から南下して江陵を目指していた劉備軍は、領民をつれたせいで歩みが遅く、長坂付近で補足されてしまった。まず見せ場は趙雲にある。曹操軍が占拠した領域から劉禅を救い出したのは趙雲である。そしてその趙雲が劉備のほうにむけて戻っていたとき、長坂橋にて一人仁王立ちした張飛に「後はたのんだぞ」といわれたのは有名である。張飛は実際に長坂橋で曹操軍をくい止めた。やはりその戦闘力は圧倒的であった。曹操はこのとき「張飛は一人でも100万の軍勢と渡り合えると、昔関羽がいっていた。それに張飛の後方の森では伏兵の気配がする。ゆえに一人といえども早まるべきではない」として結局張飛を取り逃がした。
張飛に一時的に時間を浪費させられた曹操は結局劉備を補足できなかった。張飛の大功績である。思うに張飛は曹操軍を止めて劉備を逃がすためにはここで戦死してもかまわないと思っていたと思われる。その決死の覚悟が、曹操に早まるべきでないとの疑念を起こさせ、結果曹操軍の進撃を一時的に遅らせるという成果を発生させたのであろう。
張飛は入蜀にさいして諸葛亮などと同じ頃、蜀に攻め込んだ。途中厳顔と戦闘を行った張飛は、彼らしからぬ知略を持ってして厳顔をとらえた。これは彼が戦術レベルで大きく成長していたことを示している。また厳顔の人物に惚れ込んで厚遇している。
張飛は劉備など目上の者には忠実だった。厳顔を厚遇したのもその例であろう。しかし張飛は士卒を馬鹿にする傾向があり、それが原因で最後は部下に殺された。張飛は君主にはきわめて都合のいい人物であった。しかし士卒にとっては迷惑な人間だった。たぶん自分の勇猛さに自信があったのだろう。それに酒癖も悪かったということであろう。なんにしても非常に惜しまれる点である。
なんにしても張飛はまさに劉備の股肱であった。劉備と張飛、そのふたりの関係はすがすがしくすばらしい。張飛が死んで、劉備はますます正常の判断力を失うが、それもやむを得ないかもしれない。
参謀、法正
176~220 ほうせいこうちょく
右扶風び県出身(現在のせんせい省)。劉璋の配下であったが、劉備にのち仕える。尚書令、護軍将軍。
戦術眼は確かなものを備えていたらしい。ただ劉備に仕えてから昔の恨みを果たすため復讐の行為を行うなど、人格的に狭い人物であったろうと思われる。劉備は法正を相当重用したらしい。法正は蜀の名士であり、蜀の知識人をまとめる役割を演じていたのであろう。なお諸葛亮は法正とライバル関係にある。
私はこの法正は、魏延の謀臣版だと思う。劉備に仕えた時期もおおむねいっしょだし、旧主を見限ったと言う過去をもつ点でもいっしょだからだ。また二人とも有能だった。
劉備は魏延、法正を大変に信頼していたらしい。そのため法正が孔明の法家の思想に反した(私怨を高い地位につくことで晴らすと言う行為)のに孔明も(劉備存命中は)手出しできなかったようだ。つまり法正が生きていた場合諸葛亮に処分された可能性すらあるということである。もし長生きしていたら裏切り者として処罰されていたかもしれない。
魏延は孔明死後まで生き残ったため、裏切りものの烙印を押された。だが法正は早死にした。だからどの三国志演義でもそこそこの人物として描かれているのであろう。だがしかし同時に法正の蜀における役職の高さが演技ではいまいち見えてこない。
もし彼が長生きしていたら、蜀の運命も変わっていたかも知れない。少なくとも彼には戦術眼はあった。もし法正とほうとうが生きていれば…。まあよく言われることであるが。多分戦場に赴いて指揮するのがほうとうと法正であり、孔明は丞相として後方で補給を担当したであろう。このような二人の関係がうまくいったらの場合であるが。
うまく機能すれば劉邦の部下ショウカのような役割を孔明は遂行したであろう。ただしその場合は荊州人と益州人の対立をうまく抑えることができるかが焦点である。
その場合の軍団の総大将は誰だろうか?魏延かもしれない。
法正の早すぎる死は蜀にさまざまな影響を与えた。諸葛亮に権力が集まったのは彼の死の影響もたぶんにある。仮定しても意味が無いのだが[广龍]統、法正らの死が蜀の選択肢を著しく狭めたのは事実であろう。
馬鹿かそれとも英明な君主か。劉禅
207~271 りゅうぜん こうし
蜀漢の第二代皇帝。無能な皇帝とも言われる。魏に降伏しその後は安楽公として一生を送る。
この人物ほどののしられている人物もいまい。なにしろ彼の幼名「阿斗」は中国では無能者もしくは馬鹿、あほの意味で使われているとのことである。
実際彼の業績というのはあまりない。華々しく戦闘を指揮したとかいうこともない。行政的にも彼の大功績というものもない。(もっとも彼が決して悪い人間ではないというエピソードはある)
そのことこそ異常である。ふつう皇帝などをやっていれば、限りなく残虐なエピソードとか、人間の嫌な部分を誇張したようなエピソードなどがあるはずなのだ。それがないというのはよほど彼が主体性がない人物であったのだろう。
しかし彼が馬鹿だったのかといえば決してそうでもないように思える。本当の馬鹿であれば自分の器以上のことをなそうとし、それゆえに人々に害をもたらしたであろう。(例えば、日本の例で言うと、武田信玄亡きあとの武田勝頼など)
多分彼は皇帝に不向きであったのだ。彼は田舎でせいぜい大地主をやっとくぐらいのうつわだったろう。生まれるところを間違えたのである。少なくとも諸葛亮にはやりたい放題やらしているし(そのことが本当に責任ある皇帝としてあるべきことかはべつにして)、コウコウ(例の宦官)にもおもいっきりやりたい放題させている。結構まともではないか。
つまり、自分にとって適正な位置に着けなかったのが彼の悲劇であり、彼を馬鹿とののしるのはちょっと気の毒ではないか。彼は少なくとも自分の器に忠実だったと思う。
例えば野望に燃えた、劉備、曹操らに比べると少なくとも器は小さいし、彼らほど魅力のある人物ではない。
しかし彼は一人の人間として立派に生きたのだ。器をわきまえた人物だったのだ。我々庶民、能力が大してない者にとって彼の生き方はある意味では参考になる。自分の能力をわきまえ、自分なりに生きる。これも一つの生き方だろう。
総括として彼は馬鹿な君主でもなく、英明な君主でもない。かれはただの人間であった。そして一人の人間としては十分立派な人生を生きたと言えよう。彼は生まれる家を間違えたのである。
彼は個人としてはきわめて幸せな人生を送っただろう。なにせ最後はもっとも適していそうな「安楽公」として最後をむかえることができたのだから。
ただ英雄とはお世辞にも言えぬ。
ベンチャー企業の親玉
琢郡琢県出身。黄巾の乱時に挙兵。以後各地の群雄の元を転々とした。諸葛亮が配下となって初めて戦略の方向性をさだめることができた。諸葛亮の天下三分の計にしたがって荊州に根拠地を得て、その後蜀の地をのっとる。最後は関羽、張飛のあだ討ちのためという、無謀な夷陵の戦に打って出たが負けた。失意のうちに白帝城にて死去。
前漢の景帝の子、中山靖王劉勝の末裔といわれる。しかし劉備の代までにはかなりおちぶれた生活をした。ただ劉備も遊学していたというから最低の階層までは落ちぶれていなかったと思われる。いわゆる旧家といったところであろうか。
劉備、関羽、張飛、の桃園の誓いなんていうエピソードがあるがあれはフィクションである。ただ彼が若者から慕われていたのは事実であるようである。彼はどちらかといえば遊びが好きで、勉学は好まなかったらしいが、とにかく豪傑が集っていたのである。
彼は曹操のような官僚への道は歩まなかった。もちろん立場的に無理だったのもあるだろう。しかし彼は現実的な計算でその道を歩まなかったのではないだろうか。もはや後漢王朝の命運はつきかけており、とうじ各地では反乱も相次いでいたというから、もはや彼は後漢に見切りをつけていたのではないだろうか。
彼は商人のボディーガードみたいなことをしていたようだ。悪く言えばやくざ的なことをしていたようである。当時後漢はもはやかなり荒れていたのであろう。商人たちにとって彼らのような豪傑集団は自分の身を守るのに有効だったのだろう。
たしか黄巾の乱を鎮圧するための義勇軍に劉備たちが参加しようとするとき、ある商人が馬、武具等を援助するという出来事が描かれているものがある。くさい話では、それは商人らが、劉備らの大儀に賛同して馬を貸したなどという。しかし多分そうではなくて、あくまでも彼らと劉備は普段から付き合いがあったと見るべきである。だから出兵のときも援助があったのであろう。
劉備は黄巾の乱が勃発すると、配下を率いて官軍に参加しある程度の戦功を挙げた。その功で彼は中山国の尉に任命された。
よく後漢再興のため劉備は挙兵した、などと描かれるが、私はそれはかなり怪しいと思う。確かに彼は秩序を回復しようという大儀は持っていたと思う。ただ後漢を復興させようなどとは腹のそこでは思っていないと思われる。かれは大義名分として劉の姓を利用したと思うのだ。そこに彼のしたたかな計算が見える。後に彼が一群雄として、中原で戦いを繰り広げるようになってからはじめて訴えだした、というのが真相ではなかろうか。
それを裏付けるエピソードがある。劉備の家の東南に、高さ5丈を越える桑の木があった。それを見た人々は「この家からは貴人が出るだろう」といったそうである。それに劉備はその木の下で遊んでいたとき、「俺は将来この木のような車蓋をつけた車に乗るんだ(皇帝になるぞ)」といったのだという。もっとも後世のつくり話っぽい感じはするが。
ただ彼が何事が大事を成し遂げるのではないかというのはこの挙兵のころから思われていたようである。もちろん後世の人の作り話かもしれない。ただ少なくとも彼になにかしらのカリスマがあったことは事実なのだろう。また彼は背が高く1メートル80くらいあったらしい。そして口数少なく、大物の風格があったのだという。ちなみに曹操が背が小さく、曹操はそれを気にしていたとも言われる。
結論。この時期の劉備はあるベンチャー企業の親分といった立場だと思う。
乱世の梟雄
劉備は中原の戦いにおいて、群雄の一人ではあったけれども、その地位は決して安定したものではなかった。彼の戦歴は確かにすごいと思うが、その戦歴は彼の意図したとおりに動いたわけではない。ただ彼は時代の波に翻弄されていただけである。少なくとも諸葛亮孔明に出会うまでは。
彼は公孫[王贊](さん)やら田楷やら陶謙やら曹操やら袁紹やら呂布、劉表などの配下になることが多く、まるで本当にただの傭兵豪傑軍団のままであった。彼は戦功をあげたときもあったが、負け戦も多かった。負ければ他の群雄の元へと言った感じである。
このころの劉備には、たしかに天下に秩序をもたらそうとの意思はあったのかもしれない。しかしそれにしたって天下を統一の具体的方法がわかっていたとは思えない。どちらかと言えば自分達の軍団を守るのが精一杯であったのではないだろうか。そこまでしか頭が回らなかったと言えよう。それは劉備にすくなくとも曹操ほどの洞察力はなかったことを示している。
彼の人格のすばらしい点としては、カリスマ性と夢を持ちつづけたところであろう。彼にカリスマ性があるのは前にも述べたとおりであるが、このことを示すエピソードがこの時期の劉備にもあらわれている。例えば陶謙が劉備にほれ込み、徐州を譲った件。曹操暗殺計画で献帝から頼りにされた件。曹操が劉備にこの世の中で英雄は「君と余」だけである。と言った件。
よくよく考えてみれば、劉備などたいした基盤も持たず、曹操や袁紹に比べて天下統一する可能性は低かったのに、これだけ惚れられていたのである。これはやはり彼の人をひきつけるカリスマと言うことができるであろう。人心を得る術を彼は心得ていたのかもしれない。(また人心を得るためかもしれないが、この時期の劉備の戦術はある意味では「弱肉強食」の時代の流れに半分逆行していた。そのことは人心を得るのには良かったが、当然基盤は不安定になる)
彼はまだ自分のカリスマ性を存分に発揮できる場を与えられなかった。しかし人生、耐えて耐えていけばいつどんな出会いがあるかわからないものである。それこそ「孔明との出会い」である。これにより彼は人心を得るだけでなく、人心を巧みに操作すると言う術を駆使できた。少なくとも彼のカリスマが孔明の戦略と重なってはじめて、蜀建国となったのである。)
夢を持ちつづけたからこそ、彼はいつも主君を変えてまで、生き残ったのだろう。けっして小さな打算で生き残ったのではないと思う。小さな打算で中原を流浪した呂布は殺された。だが劉備は殺されなかった。それは彼が夢を持っていたからであろう。教訓として、やはり人生耐えなければならない。どんなことがあってもそして先が見えなくても生きのこなければならない。劉備のように中年を過ぎてからやっと「天下への道」の指針を与えられるときもあるのだから。素質はいつ開花するかわからない。出会いはいつあるかわからない。今を生きることに精一杯でもいい。とりあえず精一杯にこなしていけばいつか道は開ける。そういったことをこの時期の劉備の生き方から学べるのではないだろうか。要はあきらめないことである。
水を得た魚
劉備は曹操の元で一時期すごしていた。しかし董承らの曹操暗殺計画に加わっていたことがばれ、もはや曹操の元にはいられなくなった。劉備はいろいろな紆余曲折を経て、結局劉表のもとで保護されることになった。
劉備は曹操が袁紹勢力と北方勢力平定に動いている間、平和であった荊州にて、「脾肉の嘆」とよばれるほど平和な日々を送ったと言う。この時期の劉備は一体何をしていたのだろうか。
多分たいした事はしていないはずである。まず、平和だったのは別に劉備の努力のおかげではない。劉備は劉表のもとにいただけであり、そもそも主体的に戦略を定めることなどできなかったろう。さらに劉備が本当にこの時期、天下への展望を持っていたなら、荊州をのっとる工作をするべきだったのである。(もっとも劉備の性格や特質から考えると、謀臣がいない限り、このような行動はできないと思われるが)
しかし、劉備には以前にも述べたが、なにかしら人の心をひきつける何かがあった。それに少なくとも曹操許すまじという気概、さらには秩序をもたらそうという意志はまだもっていたのであろう。そして彼の、「節度を守る、漢王室を復興する」という意志は、荊州の知識人にもあまねく広まっていたに違いない。(なにより彼の戦歴もそれを証明しているし)
その意志にひかれて、徐庶や諸葛亮、[广龍]統などが劉備の陣営に加わったのだろう。天下の大勢はもはや曹操にあった。将来を考えるなら曹操に仕官するのが一番である。しかしどうしても曹操が嫌な者、もしくは一発逆転に賭けた者、あるいは歴史に名を残したかったものがこの時期劉備陣営に加わったのであろう。
おもえば幸運な出会いであると思う。劉備ははじめて戦略を得た。その場しのぎではなく、大きな戦略を与えられたのだ。
一方徐庶や孔明などは歴史に名を残した。少なくとも魏に仕官するよりは、名前は残ったはずである。
なんにせよ、劉備と徐庶、孔明らはお互いをある意味でうまく利用することにより、お互いがともに大きな成果をあげていけるようになった。劉備が孔明との関係を「水を得た魚」と言ったのはまさにこのことをさすのであろう。
いずれにせよ、ここには自分の可能性に最後までかけた男たちのドラマがある。劉備がえらかったのは決して可能性を捨てなかったところだ。たとえ卑怯者と言われようとも、逃げつづけたのはすごいことだ。最後まで意志をもって貫けば、どんな出会いがあるかわからないことを劉備と孔明らの出会いは物語っていると言えよう。
蜀の劉璋を攻めたことは、彼の従来の立場をとるとすれば、できなかったはずである。しかし彼はあえて非情な決断した。これは劉備が自分では思いつかないにせよ、他者から的確な進言をもらえば、天下統一に向かって判断できたことを示している。
ただ惜しいかな、劉備と孔明ら参謀との出会いは少し遅かった。彼は晩年、関羽、張飛を失ったことで、すっかり老いてしまい、その結果夷陵の戦に出てしまった。これは彼の寿命であろう。蜀を手に入れた彼は皇帝になったけれども、もはや彼は歳をとりすぎていた。
ただ、ある一人の男の生き様として、劉備の場合はまさにすばらしかった。関羽や張飛とのつながり、諸葛亮との信頼、など彼をとりまくエピソードはすがすがしい。確かにその性格だからこそ天下は取れなかったかもしれない。でも彼は大人物であった。そしてもう少し時の運に恵まれたとしたら、中国を統一できていたかもしれない。
周瑜
しゅうゆ 175~210
字は公瑾。廬江郡序県の人。一族からは過去、大尉や県令を勤めるなど、名家の出。当初袁術が周瑜を用いようとするも周瑜は袁術の能力のなさを見切っていたので仕えなかった。孫策の挙兵に途中から手勢を率いて合流、孫策はこれを「君がきてくれたので、我がことなれるも同然だ」と言ったという。孫策に従い皖県を攻めたとき、その地の豪族の橋氏の娘を娶ったが、そのとき孫策も橋氏の娘を娶ったので、孫策とは義兄弟ということになった。孫策の死後は孫権に忠実に仕えた。曹操の南下に対しては魯粛らとともに主戦論を説いた。総司令官として呉軍を率い、苦肉の計などの謀略を併用して曹軍を火計で打ち破った。その後南郡の曹仁を攻めたりもしたが負傷。蜀へ出兵しようといている最中に亡くなった。
周瑜と孫策はもともと気心が知れる、まさに盟友だったようだ。その交わりは少年時代にはじまった。以後孫策が死ぬときまで変わらなかったと思われる。二人の交わりは「断金の交」と呼ばれるほど硬いものであった。その二人はまさに協力して、呉の版図をつぎつぎとひろげていった。孫策が若死にしなければ、呉は孫策と周瑜の元、少なくとも蜀の地を併呑したであろう。
周瑜は度量が大きい。それは孫権が孫策の跡を継いだときに典型的に現れている。孫策の死は呉政権に大きな動揺を与えた。当時の呉政権は孫策や孫堅の個人的カリスマ性を基盤にしていて、揚州への基盤はあまりなかった。よって君主個人の死は大きな痛手だったのである。孫権は弱冠19歳で何の実績もなかった。特に揚州の豪族は自分たちの領土さえ安泰ならば主君は誰でもいいという発想(後の赤壁の戦の降伏論につながる)が強かったので当初孫権に尊敬をはらわなかった。また北方からの名士張昭らも、孫策個人の度量に魅せられ政権入りしたわけで、孫氏に忠義を誓っていたわけでもなかった。そんな中、周瑜は孫策との契りを忘れず、あえて義侠的な精神から、いちはやく孫権への忠誠を誓った。(また周瑜は孫権にも非凡なものがあるのを見抜いていた)周瑜のような名家のものが率先して(孫権への)忠義を表したことは、孫権の権威を高めるのに大きな役割を果たしたのである。
また赤壁の戦においても、主戦論を展開したが、周瑜個人のことを考えれば、別に戦などしなくてもよかったのだ。周瑜は家柄がよかったので当時魏に降伏しても領地を得たであろう。それでも彼が主戦論を展開したのはひとえに孫策との友情に基づいている。孫策と創業した呉を守ろうとしたのだ。周瑜は友情に厚い、義侠心にとんだ男だったのだ。義侠心はなにも劉備と関羽と張飛にだけあったのではない。孫策と周瑜の間にも強固にあったのだ。友情を貫いた周瑜は素晴らしい人間だったといえるだろう。また蜀との対比で申し訳ないが、劉備の遺沢をうけた諸葛亮が劉禅を懸命に守り立てていく姿と似ているではないか。なのにどうして周瑜の実績はあまり強調されないのだろうか?劉禅と孫権ではもちろん孫権のほうが人物として大きかったのは間違いないが、それは結果論である。少なくとも孫策死後すぐの孫権と劉禅は立場がそんなに異なるとは思えない。また孫権の権威とて、周瑜を用いて赤壁の戦を勝ったことにより高まった一面もあろう。周瑜に託した孫権は確かに立派かもしれないが、あの場合むしろ孫権のために、主戦論を展開し、苦肉の計など謀略を駆使して、火計で曹軍を破った周瑜の方が立派である。
周瑜は義侠心に富み、かつおおらかで決断力があり、まさに王佐の才を備えていた。その早すぎる死が惜しまれるところである。
周瑜は呉の大功労者である。成り上がりでもともと揚州への基盤が薄かった孫氏が基盤を確立できたのもひとえに周瑜の働きがあったからである。しかし孫権は晩年思い上がり、周瑜の功績を過小評価したと言われる。(このことにつき渡辺精一著 三国志人物鑑定辞典を参考にした) 孫権の老いぼれ、晩年は初心を忘れたといえよう。孫策が若死にしなければ呉の運命も変わっていたと思われるが、そのことは非常に残念である。
陸遜
りくそん 183~245
字は伯言。父陸康は孫策に殺される。呉郡呉県の人。親の敵の孫策の娘を妻とする。当初は後方にて賊の退治などにあたっていたが、関羽攻めのとき抜擢された。呂蒙死後はその後継者となり蜀の劉備の率いる軍勢を打破した。その後も荊州方面の守りで活躍した。244年に丞相となり、孫家のお家騒動に巻き込まれ最後は孫権に問責され、陸遜は憤り死亡した。
陸遜は名門の出身である。にもかかわらず孫権に忠実に仕えたことは彼がいかにすばらしい人物であったかの証左である。
陸遜は当時の揚州の名門の陸家の出身であり、本来孫一族とは微妙な位置に立っていた。それは孫策や孫権が呉郡や会稽郡の名士層を一時的に弾圧したからである。これは孫呉政権の矛盾として存在しつづけていた。それゆえ陸遜は孫家のために積極的に働かなくてもよかったはずである。しかし彼は誠実に孫権のために仕えた。これはすばらしいことである。
ただし陸遜個人はともかくとして、呉の名士層全体を見ると、孫権との関係は実に微妙そのものである。魏と孫権が結ぶことがあったが、それは同盟というよりは、臣従である。実質的にはともかく、孫権は魏に形式的には従属しているのである。これはなぜだろうか? 第一には魏と蜀同時に敵に回すのは呉にとって不利であるという計算であろう。しかし第二に考えるに、呉の臣は本気で曹操への臣従を望んでいたのではないかということである。孫策や孫権が取り立てた武人はともかく、名士層はどうにも魏が擁する名ばかりの「漢」への臣従を望んでいたのではないかという気がしてならない。孫権が関羽や劉備を攻めたのは(または攻めさせた)のは自らの領土欲もあるだろうが、どちらかといえば家臣を統制するためではなかったのだろうか。だとすれば呉に荊州攻めを打診した魏の深慮遠謀もすごいし、また臣従という苦渋の決断で家臣を統御し、結果荊州を得た孫権も相当な政治力であると評価できる。
陸遜の荊州や夷陵での戦いで一度は影で呂蒙の謀略に参加し、一方では劉備の侵攻をふせいだその手腕は立派といえよう。現場指揮官としてすばらしいと思うのである。名士層にこのような傑物がいたことは、まさに孫権にとっても幸福だったといえる。夷陵の戦いの当初、陸遜を呉の諸将はあまり評価していなかったといわれる。孫権の抜擢は確かにすばらしいものであった。それに陸遜はすでに山越の平定などで実績を上げている。にもかかわらず諸将の評価は低いという。私はむしろ「評価したくなかった」のではないかと推測する。夷陵の戦いの呉軍の参戦武将は陸遜はともかくとしてあとは朱然、潘璋、宋憲、徐盛など名士層ではない武人ばかりである。孫呉政権の性質上、揚州の土着名士と武人の間にある種の派閥争いがあったのは紛れもない事実だからである。劉備が諸葛亮を登用するのを嫌がった関羽張飛のような心境だったのかもしれない。
派閥争いはともかくとして、そのようないろいろな対立のあったものをひきいて劉備を破った陸遜はなおさらすばらしい手腕があったといえよう。その統率力は見事というよりほかない。また石亭の戦いでは南下してくる曹休軍を打ち破っている。
陸遜は内政面においてもすぐれた手腕を発揮した。
陸遜の憤死の原因となった孫権の後継者問題でも、陸遜は正統論を唱えた。死して家に財産は残さなかった。清貧である。彼は当時の一流の名士として立派に生きたといえよう。
親の敵の一族のためにも彼は誠実に仕えたのだ。それは彼が名士として、人民を慰撫し、なるべく故郷の揚州に戦乱が及ぶのを避けようとしていたのかもしれない。いずれにせよ高いモラルの持ち主だったということができる。
魯粛
ろしゅく 172~217
字は子敬。臨わい郡東城の人。最初袁術に仕えるもすぐ見限る。周瑜とは孫権に仕える前から親交を結んでいた。孫権の代になり周瑜の推薦で孫権に天下取りを進言し、気に入られ仕える。人物は豪快、かつ侠気にあふれるすばらしい人物であった。
魯粛というと皆さんはどのように思われるのだろうか。三国志演義では魯粛は散々である。ただのお人よしである。孔明には翻弄され、周瑜には叱責され、まったくさえない人物であるかのように思える。
しかし魯粛は実際にはそのようなお人よしではない。孫権にとってはある意味では周瑜と並んで、もっとも頼りにしていた人物である。孫権に天下を取らせようとまじめに考えていたのは周瑜と魯粛しかいないと思われる。
それは赤壁の時の主戦論の主張に現れている。魯粛と周瑜のみが明確に徹底抗戦を主張した。魯粛と周瑜のみが「孫氏のため」に働いていたといえるだろう。張昭ら非戦論者は、後漢に対しては忠実だったといえるが、孫氏に対しては魯粛や周瑜ほど忠実だったとはいえない。
それはいわゆる「名士」の問題にも絡んでくるのだが、要するに当時の揚州の名士にとってまだまだ孫氏はただの成り上がりに過ぎなかった。また揚州の名士には天下取りなどという野望はない。あくまで意識は長江流域で終わっている。また張昭ら北国出身の名士にとって、孫子はさほど命をかける存在でもなかったのではないかと思われる。(注 武人を除く)
魯粛は孫権にとっての諸葛亮である。諸葛亮に匹敵するぐらいのものが魯粛にはある。魯粛は孫権に対して忠実だったのだ。その事実はきわめて重要である。よって魯粛は孫権のために劉備と同盟を組んだのである。けっして孔明に踊らされたからではない。実際、劉備と組んで孫権は勝利を得た。当時流浪の軍団の劉備と同盟を組むなどということはよほど大きな視野がなければできない。
つまり、中国世界を統一するという価値観をもち、それをしかも「孫氏(この場合孫権)」にとらせようとしていたという点で魯粛はまさに孫権の股肱なのである。呉のほかの家臣(周瑜を除く)はよかれ悪かれ、そのような強烈な天下とりの意識はなかったと思われるのである。
主君に義侠的に付き合った熱い男…それが魯粛である。若い孫権に天下を取らせよう。その思いは劉禅の元で天下統一戦を無謀にも仕掛けた諸葛亮にも通づる。多くの人命が失われることを考えると、天下統一をめざす戦争が妥当かどうかは一概には言えないが、少なくとも魯粛がもう少し生きていれば天下3分は長く続かなかったと思われる。
彼はまず魏を蜀とともに滅ぼし、そのあと蜀と天下2分の状態に持ち込み、蜀に勝ち天下を統一しようと考えていたのではないだろうか。実現可能性は限りなく低そうだが、その孫権に対する義侠的な仕え方はある意味さわやかである。