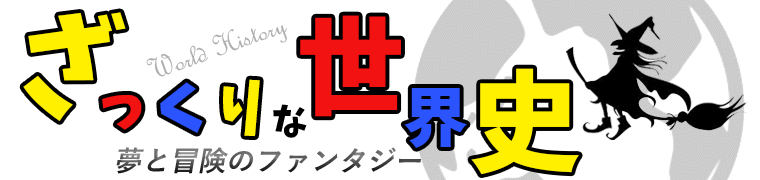中国近代史について
1, アヘン戦争はなぜ起きて、中国はなぜ負けた?
(~1840年代)
今から二千年以上前、まだ紀元前の頃、秦の始皇帝が中国を統一した。以後、数千年来、中国では王朝がめまぐるしく交代し、時には何カ国にも分裂することがあったものの、皇帝による独裁政治が続いた。もちろん、その間、中国と世界の連絡がなかったわけではないが、しかしより直接的に中国が世界との交渉を持つようになるのは、ヨーロッパにおける産業革命の発生と発展、その浸透、つまり世界史的な意味での「近代」になるまで待たなければならなかった。18世紀後半のことであり、中国では非漢族の満族王朝である「清朝」の時代である。
産業革命によって飛躍的に発展したイギリスは、そこで生産された莫大な商品の捌け口を求めて世界中に発進し、植民地を作るなりして商品市場を拡大、それと同時に商品生産に必要な原料の輸入も大規模に行うようになり、そこで目をつけたのが広大な国土と、非常に多くの人口を抱えた中国であった。
しかし、世界は中華のみ、その他は蛮族の住む辺境、と考えていた中国にはそもそも基本的に「国」という概念が無く、対等の交渉を望むイギリスと折り合いがつくはずもなく、イギリスとの貿易も旧態依然の「朝貢貿易」(蛮族が中華の威信に恐れおののいて、貢ぎ物を持って中華皇帝にささげ、皇帝は恩恵として、その貢ぎ物の数倍にも当る品物を蛮族に下賜するというシステム)の一環に過ぎなかった。貿易場所も広州一港に限られていた。
時あたかもイギリスでは飲茶の習慣が大流行、お茶は生活必需品となったが、その一大産地が中国だった。規制の厳しい貿易体制で、必死にお茶の輸入に励んだイギリスだったが、それに見合う中国への輸出品が無く、貿易赤字は増すばかり。途方に暮れたイギリスが対中貿易の秘策として考案したのがアヘン貿易だった。
アヘンは中国でも早くから薬用(主にその麻酔効果)として用いられてきたが、イギリスはこれをインドなどで大量生産し、中国に「麻薬」として輸出、お茶の輸入と拮抗させることで、貿易赤字を解消。それどころか、莫大な利益を得るようになり、今度は中国が貿易赤字で悩まされることになる。
中国では18世紀末まで、数千年来で最も安定した時代が百年以上続き、その安定が政府の政策と相俟って、人口の爆発的増加を招き、しかし耕地面積はそれ相応には増えず、完全な自給自足体制だった中国は慢性的な食糧不足を引き起こし、社会不安が増大、各地に相次いで起こった反乱が物語っているように、まさに世紀末の様相を呈していた。
19世紀になっても事態は変わらず、むしろ深刻化、イギリスが運んでくるアヘンという麻薬を受け入れる素地が、社会全体に存在していた。1839年にはアヘンの輸入量が4万箱になり、一箱が大体常習者(中毒者)の一年分の量に相当するから、当時の人口が4億として、老若男女あわせて百人に一人がアヘン中毒者という異常な事態に陥っていた。そんな状態だったから、清朝当局がアヘン貿易を非合法化したところで密輸が絶えるわけもなかった。
時の皇帝自らも吸引者だった(という噂がある)清朝ではあるが、さすがにその深刻さに気付き、アヘン対策に乗り出す。問題の抜本的解決を図るために、アヘン厳禁(密売者や「アヘン屈」と呼ばれる吸引所の従業員、吸引者に対する極刑)が実施に移されたのは当然であった。
しかしこれはアヘン貿易によって潤っていたイギリスには相当の打撃だった。密輸用に備蓄していたアヘンをすべて没収され、アヘンを今後中国に持ち込まないという誓約書の提出に反対したイギリス側は、議会に逆恨み的に中国側の横暴を訴えて、議会は僅差でこれを採択。つまりイギリス世論では過半数以上の人々がこの全く義のない戦争に賛同したことになる。
中英間でこうして戦争が始まった。
当時の世界最強国イギリスが、軍隊までアヘン漬けになっており、全く使い物にならなかった清朝軍を各地で撃破、1840年から始まったこの戦争も1842年には南京で講和条約が結ばれ、領事裁判権を認め、関税自主権を奪われ、戦費とアヘン代の賠償、香港の割譲、五つの港の開港などが約された。
2, 太平天国はなぜ起きた?
(1850年~1860年代)
アヘン戦争で負けた後、清朝はフランスやアメリカ、後になってロシアとも、開国の不平等条約を結び、否応なく「近代世界」に巻き込まれていくことになる。
アヘンの密輸は完全に黙認され、中国社会の不安は全く解消されず、ますます深刻化していく社会不安を背景に、アヘン戦争の十年後、中国全土を揺さぶることになる「太平天国」と呼ばれる農民一揆が勃発した。
そもそも世界は中華のみ、その他は蛮族の住む辺境、と考えていたのは漢族であり、漢族が非漢族王朝に反対するのは、根強い文明・文化、民族差別からは当然の趨勢であった。これが太平天国が大きく発展した要因の一つ。
もう一つは客家の問題。客家とはもともと中国北方にすんでいた漢族で、戦乱などの政治的理由で南方に追われた人々であり、原住していた人々にとっては「客」なので、客家と呼ばれる。しかしそのお客はひどく疎まれた存在で、各地で起こった原住民と客家の対立は武装闘争に発展するほどひどく、官憲の介入が必至だった。しかし官憲は必ず原住民をひいきとしたから、もともとお客さんであった客家には拠り所が皆無な上に、官憲にまで目をつけられ、そのような彼らの立場は推して知るべし、積もり積もった不満が爆発するのも時間の問題であった。太平天国の主要幹部が客家であったのも偶然ではない。
中国の当時の社会不安はまた貧富の格差によっても現れ、助長されていた。太平天国では意識的に平等思想を掲げたため、多くの人に共感された。これも太平天国が猛威を振るうことのできた原因である。
このように様々な要因があって、開港によって布教が許された西洋のキリスト教の影響を受け、1850年、広西省の金田村で挙兵した大平軍は、広西省一帯で武装闘争した後、北上を開始、湖南省を席巻し、湖北に入り、中国の要衝、武漢を落としてからは、東進、1853年には副都ともいうべき南京を攻略、ここに都して「天京」と改称し、太平天国はついに建国した。
移動に次ぐ移動で、初めて拠点を得た大平軍は、南京一帯を固めると同時に、南京から一挙に首都北京をつこうとする北伐軍と、武漢一帯の再攻略を目標とする西進軍を組織、二面作戦に出た。これが大いに裏目に出て、西進軍は安徽省一帯、湖北省の一部でそこそこの活躍をするものの、北伐軍は全滅という惨状、しかも上海で起こった秘密結社の武装蜂起ともうまく連絡が取れず、アヘン戦争後の五口開港によって外国勢力の新たな拠点として発展してきた上海を手中にすることもできなかった。さらに同じキリスト教系として「兄弟国」と見なしていたイギリスやフランスの支援を得るどころか、中立を保たせることにすらも失敗してしまう。
これに反して清朝は、太平天国が猛威を振るう最中に起こったアロー号事件、それから発展した第二次アヘン戦争でイギリスとフランスの連合軍と戦うはめに陥り、首都北京をつかれるという絶体絶命の危機も何とか切り抜けて、更に両国に太平天国鎮圧の協力を取り付け、またアヘン漬けの軍隊では内乱平定の役にも立たなかったので、漢人官僚に命じて、団練と呼ばれる、正規軍とは別の軍隊を創設させ(のち、これが正規軍となり、もともとの正規軍は徐々に淘汰されていくことになる)、これを太平天国にあてた。
一時怒涛の勢いを見せた太平天国も、北伐軍の壊滅あたりを契機として衰微、さらに幹部間同士の大規模な内部分裂もあり、1850年代終りには、もうすでに往年の力はなく、団練と外国人部隊に圧倒されることが多くなった。幹部間では、中国歴代王朝の宮廷と全く同質の権力闘争が行われ、初期の宗教的、平等主義的理念が完全に失われたことも太平天国の寿命を縮めた。1864年、天京は陥落、一応、これをもって太平天国は滅びた。一部残党が各地で武装闘争を続けるものの、それも1870年代には終焉する。
この時期、太平天国以外でも、主に農民による武装一揆が起こっている。社会不安と清朝に対する抵抗が主な原因だった。注目すべきは少数民族による闘争も相次いで起こっていることだろう。これらは清朝反対もあったが、漢族官憲に対する闘争という側面もあり、単純に反体制闘争とは割り切れない。しかし、その中の最大のものだった太平天国が、キリスト教による集団の潔癖性というのもあって、これら各地の一揆と横のつながりに欠けたのが、太平天国失敗の要因の一つである。
3, 洋務運動って何?
(1860年代~1890年代)
第二次アヘン戦争で締結された講和条約ではアヘン貿易の合法化の外、専門的に外交に従事する官庁の創設を迫られ、公文書中に蛮族の総称として用いられた「夷」の字の使用を禁じられ(その代わり用いられたのが「洋」という漢字で、外国関係の事務、という意味の「洋務」ももともとは「夷務」といっていた)、中国も世界的な近代外交の枠組みの中に取り込まれていくことになる。世界は中華のみ、ではすまなくなり、「中華」という概念もそれに合わせて徐々に変化していく。
一方、中国北方では帝制ロシアの活動が活発化していた。何度かの脅迫的交渉とその結果締結された条約で、中国東北部と西北部の広大な領地をロシアに掠め取られた。また新彊ではロシアが関与したと思われる独立運動も盛んになってきていた。
二度のアヘン戦争という対外戦争の経験から、世界は中華のみ、その他は蛮族の住む辺境と信じて疑わなかった人々でも、さすがに西洋の武力的優位性を認めざるを得なかった。それは硬直化した王朝宮廷の人々より、実務に携わる漢人官僚によってより強く認識され、北方のロシアの脅威もそれを後押しした。そうした中で、あくまで「中華」の優位を固持し、部分的に「蛮族」の優れた部分を認め、それを取り入れて、「中華」の再興を図ろうとする動きが出てきた。それが洋務運動である。
「中華」の優位は道徳や倫理の方面に、「蛮族」の優れたものは産業の方面にそれぞれ現われ、太平天国が完全に消滅しない頃から、中国の伝統的道徳・倫理を支柱とする政治体制に手を加えずに、産業の振興、特に機械化が進められた。
内乱平定が主要な任務だった1860年代から70年代にかけては、ほとんど軍需産業のみに限られ、またほとんどが国営企業として誕生したが、内乱が鎮圧されて相対的に平和になった70年代後半からは、既存の軍需産業を側面から支援する形でその他の産業が育ち始め、後には全く軍需に関係ない方面にも拡大されて、企業形態も半官半民のものや完全な民営のものまで出現しだすようになった。
その過程で、外国の事物輸入に必須の外国語教育が行われ始め、数多くの各分野の著作の翻訳がなされ、直接産業育成・振興に関わりのない、西洋の政治体制や思想の類も中国に紹介されていった。
何はともあれ、主に国営企業では腐敗や汚職が蔓延ったとはいえ、この時代の産業の発展は大変な勢いがあり、新彊の独立運動を平定し、新彊に省を設けることに成功、更に1880年代後半までにはアジア最大の艦隊を持つに至ったのである。
しかしそれも1883年から起こった中法戦争で少なからず亀裂が生じた。ベトナムの保護国化を望むフランスとベトナムを中華体制の属邦(「中華」ではないが、辺境の中でも限りなく「中華」に近い「地域」)的地位のままにしておきたい清朝の間で戦端が開かれた。この戦争、実際の戦闘そのものは決して清朝の絶対的不利ではなく、むしろ清越国境地帯で展開された陸戦では清朝軍の有利のうちに進んだのであったが、結果だけを見れば清朝の敗北であり、ここまで発展させてきた洋務運動の成果がほとんど発揮されなかったではないか、と問題になった。
そもそも「蛮族」の如何なるものも認めない保守的な勢力は依然として根強く、当初からこの運動は順風満帆ではなかった。むしろ、洋務運動を推進した人々の方が少数派であったとも言える。しかし洋務運動も中法戦後、疑問が膨らんだとはいえ、保守勢力の反対を受けながらもその基本的方針は続行され、それなりの成果はあった。しかし1894年から始まった甲午中日戦争と翌年の敗戦で、この運動は重大な方向転換を迫られることになる。
4, 甲午中日戦争で中国はどうなった?
(1894年~1895年)
ベトナムと同じく中華の属邦の一つだった朝鮮では、その体制の存続、少なくとも影響力の確保を狙う清朝と対露対策とともに領土的野心を持つ日本が衝突した。日本では日清戦争と呼ばれるこの戦争は、中国では甲午中日戦争、あるいは、ただ単に中日戦争(主に中法・中日両戦争、というような場合)とも呼ばれ、朝鮮の農民反乱を契機として1894年に起こった。
明治維新以来、挙国一致で急激により徹底した西洋化を進めることで富国強兵を図ってきた日本軍が、洋務運動を進めてきたはずの清朝軍を圧倒、海戦でも陸戦でも勝利を収め、奉天を陥落させ(この時も日本軍による虐殺事件があった)、威海衛にあった洋務運動の成果の象徴であった清朝のアジア最大の艦隊(もっともこの戦争が始まる前までには、日本軍の艦隊が質量ともに上回っていた)を壊滅、翌1895年下関で条約が結ばれ、戦争は終結した。この馬関条約(下関条約)の過酷さは、台湾およびその周辺諸島と遼東半島の割譲、清朝の国家予算の数倍にあたる戦費賠償、などでも分かる。この戦争が日中両国の近代における明暗を分け、さらに、現在にまでつながる両国関係に影響を及ぼすものになったといっても過言ではなかろう。
遼東半島に関しては、後に三国干渉により、日本はこれを放棄する。しかしそれは日本とロシアのなお一層の対立をもたらす結果となった。日本の対外政策の根幹は依然として対露戦略であり、朝鮮がその重要な役割を果たすものとして認識され続けた。こうして日露戦争が準備されていくことになった。
清朝が洋務運動によって進めてきた富国強兵むなしく、日本軍に完敗してしまった理由はいくつか考えられる。
一つに、洋務運動も30年経ち、当初の勢いが無くなって、運動そのものが形骸化してしまっていたことがあげられる。また30年も続いたわりには、運動が全中国に浸透しない、依然として、「中華」の絶対優位を盲目的に信じている人による妨害があったこと、さらに清朝そのものがすでに腐敗の極みに達していて、運動が有効に働かなくなっていたことがあげられる。そもそも1890年代になると日本との開戦必至という状況になっていたにもかかわらず、清朝首脳はほとんど軍事的措置も講じず、更には大庭園の構築に戦費を使ってしまうというありさまで、挙国一致で戦っていた日本と比べ、主戦、避戦の意見も統一されないような状態だった。清朝の軍隊が四十年前の太平天国鎮圧時に創設された団練の延長戦上にあって、長い年月が新しく正規軍として認められたその団練も腐敗させたのと比べ、日本は西洋式の軍隊をすでに整えていたことも重要である。
何はともあれ、この敗戦は中国近代にとって決定的だった。イギリスやフランスと比べると非常に馴染みの深い、かなりはっきりとしたイメージのあった「蛮族」に戦争で負けてしまったのだから、中華にとっては驚天動地の出来事だった。戦争中に、従来の農民一揆や秘密結社とは一線を画すより新しい形式の清朝打倒のための革命団体が誕生し、敗戦直後には洋務運動とは決定的に異なる、政治体制の変革をも求める変法運動が急速化し、清朝当局も完全な西洋式軍隊の創設を含めた軍事改革に着手した、などなどこれら一連の動きはこの戦争と無関係ではない。さらに、馬関条約では、外国勢力の中国に対する直接投資の大幅な規制緩和が認められ、外国資本が中国に深く浸透することによって、中国経済がより世界と密接に結びつくという質的変化をもたらした。
こうした変化が、中国近代史の新たなページをめくることになった。
5, 変法運動って実際何だったの?
(1898年)
甲午の敗戦によって、清朝頼むに足らず、清朝を完全に打倒して、すなわち革命を起こして、世界的潮流に対応した国家を建設して「中華」の復興を果たそうとする革命運動が盛んになりつつあったものの、依然としてそれはまだ少数派であり、多くの有識者の間では、産業方面ばかりでなく、政治体制の方面でも大幅に西洋文明を輸入し、場合によっては文化の方面も勉強して、清朝の面目を一新することで、「中華」を再興しようとする動きが活発になってくる。目指すは日本の明治維新やロシアのピュートル大帝の改革などで、具体的には皇帝専制を止めて立憲君主にして、議会を開設しようとするもの、これを変法運動という。
政治体制の変革をも視野に入れ、より積極的に西洋から学ぼうとする姿勢は確かに洋務運動とは異なる。しかし核としての「中華」の優位は依然として存在しており、精神的な拠り所となっている点では、洋務運動の延長線上にあるとも言えなくはない。
こうした動きは1880年代から、中法戦争の敗戦に刺激されて始まっており、中日戦争の敗戦はそれを更に促進した。列強の中国進出が激しくなり、帝国主義化してきたという状況のもと、政治体制の変革が急務と考えられるようになった。
時の清朝皇帝も年若く、それゆえに開明的で、こうした動きに同調して、変法派と呼ばれる官僚を多く登用し、1898年には変法維新と呼ばれる一連の改革が実行に移された。
しかしその実体は、勅令の乱発によって内政をただ単に混乱させただけで、しかもその勅令も地方官吏に従わすだけの権威もなかった。
この頃になるともうすでに中央の権威は失墜していた。というのも、太平天国や各地の内乱の鎮圧は基本的には地方ごとによって行われ、そのため、各省トップが軍事権を中心とする政治的実権を握っており、その傾向は洋務運動によって、宮廷のある保守的雰囲気の濃厚な北京やその周辺で運動を行うよりは北京から遠く離れた地方で行うほうが都合もよかったため、助長された。だから実際に政治を取り仕切るためには地方官僚を動かさなければならなかったわけである。
しかし多くの地方官僚は中央で表面的には維新が行われているものの、保守勢力は依然として強力であり、いずれ保守による巻き返しがあってこの維新も失敗するであろうと確信していたから、皇帝の命令といえども、とてもではないが従う訳には行かなかった。
事実その通り、中央の実権は、依然として「中華」の絶対的優位を主張する保守派に奪取され、その維新はわずか三ヶ月をもって、血の弾圧を受けた。この弾圧は保守勢力によって徹底的に行われ、以降、外来のものに対する全否定の傾向を強め、更には排外的傾向をも助長することになる。
徹底的な弾圧を受けた変法派はその多くが日本に亡命、なおも活動を続ける。日本では、革命を実行して清朝を打倒しようとする急進派と言論を戦わせ、有利のうちに進める、という成果を上げるものの、清朝の復興を目標とする彼らの運動は清朝そのものに弾圧され続ける、という矛盾を抱えていた。
6, 義和団はなぜ起きて、八カ国聯軍の侵略を許したの?
(19世紀末~20世紀始め)
甲午敗戦後、変法維新の失敗と相前後し、日本を含めた列強は勢力範囲の確定と称して中国分割競争を始め、「中華」の危機感は増すばかりだった。「中華」復興のためには外国勢力に反対、抵抗しなければならない、それは立場の違いを超えて中国人の共通認識になりつつあった。
世界は中華のみ、その他は蛮族の住む辺境という考え方そのものにすでに排外的傾向をはらんでいるといえる。中華世界以外の異質の存在が目の前にあるということが違和感となって現れるからだ。
アヘン戦争によって開国させて以来、欧米列強はほとんど当然の如く宗教活動にも力を入れた。キリスト教の布教がそれである。中国においてはキリスト教の存在自体がすでに異質であり、違和感があったのであるが、それに輪をかけるようにして、一部布教者とその追随者の行いが悪質なものであったため、中国人によるキリスト教およびその布教に反対する風潮が蔓延した。特に山東省ではそれが顕著だった。布教者と追随者の悪質行為に対しては暴力も辞さず、時には組織的に行われた。そんな中で生まれてきたのが義和拳という一種の拳法であり、その集団としての義和団である。
義和拳とは肉体を鍛えれば神通力によって弾丸をも防ぎ得るという、民間宗教と在地拳法が融合したようなもので、折りからの排外的風潮も手伝って、その集団は急速に発展、外国勢力からの要請もあって、清朝当局はその取り締まりを行うが、発展の勢いは衰えることなく、1899年までには山東省の全域で義和団は盛んになり、排外反清の色彩を強くし、北京を目指して北進を始める。
翌1900年、これに慌てた清朝は、宮廷内の保守排外の空気も手伝って政策を変更、義和団を手懐けることで外国勢力と対峙しようとし、北京に入った数万の義和団と協力して、列強に宣戦を布告、北京の公使館街を攻撃する。公使館街にいた各国公使は駐在させていた守備兵数百でもって篭城してこれに対抗、急を聞きつけた八カ国は連合軍を組織して北京にむかった。
いくら篭城されたとはいえ、数万の兵力を持って公使館街を攻略できなかった義和団と清朝軍が八カ国聯軍に敵うはずもなく、清朝の皇室はこぞって北京を脱出して西安に逃れ、列強に和を乞い、転じて義和団弾圧に踏み切る。結局、清朝は1901年に八カ国と講和条約を結び、莫大な戦費賠償はもちろん、北京を中心とした地域に各国の駐兵権をも認めさせられ、ここにおいて、清朝の権威は完全に失墜する。
義和団の乱において、義和団の排外闘争は理由の無いことではなく、同情の余地はあるが、これを利用した清朝は政策を二転三転させるのみならず、無謀にも八カ国に対して宣戦を布告し、近代外交においては考えられない公使館への攻撃を行うなど、中国権益を拡大したいと考えている列強に願ってもない名目を与えてしまうという墓穴を掘り、弁解のしようもない。
その後、清朝は列強にしっぽを振る飼い犬と成り下がり、ちょうど十年で滅亡することになる。その間、列強の要望と自身の延命措置のための所謂「新政」というものが行われるが、結局それは変法運動の焼き直しに過ぎず、スタートもスピードも遅すぎた。しかもその「新政」が清朝滅亡に大きく貢献することになるのだから、もう目も当てられない。
7, 辛亥革命って難しい?
(1900年代~1912年)
1911年10月10日、武漢三鎮の一つ武昌で軍隊によるクーデターが勃発、辛亥革命が始まる。武昌でクーデターを起こした軍隊は清朝の延命のために行われた「新政」で各地に創設された新軍と呼ばれるものの一つで、団練を発展させ正規軍化しようとしたものであったが、この新軍に革命派が工作を行ったことにより、革命クーデーターが起きたわけである。この革命クーデターは各省に飛び火し、1911年末までにはほとんどの省が清朝からの独立を宣言している。
義和団の乱以後、清朝に望みを繋ごうとする変法派に同情する人々は日増しに減り、清朝に見切りをつける人々が増えた。そういった人々を中心として武力で革命を起こして清朝を打倒しようとする勢力が台頭してきた。彼らを革命派というが、彼らは清朝打倒という一点のみで一致しているだけで、革命の方法や革命後の方向などで意見が食い違い、とてもではないが一枚岩とは呼べず、むしろばらばらの状態だった。
1904年から始まった日露戦争は主に中国を主戦場として戦われたが、日本が何とか辛勝する、という形で戦争は終結、ロシアに代わって、日本が中国北方を脅かす存在となったものの、日本の勝利は中国に明治維新の再評価のきっかけを与えるのに充分だった。清朝内部では「新政」によって、議会制の道を開き、立憲君主制に変貌して、復興を遂げようとしたが、しかしそれらはすべてが裏目となる。憲法制定と議会設置の期限を定め、予備議会ともいうべきものを地方に設置するが、そこは急速に立憲化を目指そうとする人々によって占拠され、その圧力により、憲法制定と議会設置の期限を早めたのはいいが、そのための準備としてとりあえず形成した内閣は大臣をほとんど満族で占めた露骨な延命措置であったため、人口の大部分の漢族の更なる反感を買い、さらに新政のための資金として鉄道国有化政策を進めようとするが、これも失敗、特に四川省では大きな混乱を招くだけとなった。
そうした清朝に対する不信が増大する中で武昌において新軍による蜂起が起こったため、革命が瞬く間に全国を席巻することになった。と言っても、この革命の過程で革命派が完全な主導権を握ったわけではなく、清朝の立憲化を推し進めようとした立憲派の協力も仰がなければならなかったし(彼らは満族中心の内閣の成立によって清朝をすでに見限っていた)、さらに清朝の地方官僚にも頼らなければならなかったぐらいで、それだけでも革命派というものが力がなく、その内部がばらばらであったことが分かる。結果的に共和国が建国されることになったから、辛亥革命は共和革命だ、と言われるが、革命派が以上で述べた通りにばらばらで、革命派の中でもどれほど革命後の共和国建設をイメージとして持っていたか、さらに清朝方面の力が不可欠であった革命であったことを考えると、民主共和革命というよりは、漢族による満族に対する民族革命と言ったほうがよい。
清朝も、新軍の中でも中央の最精鋭の軍隊を繰り出してこれを鎮圧しようとするが、その指揮官に裏切られる始末。辛亥革命が清朝打倒に成功したのは革命派の力量よりも、この清朝最精鋭の軍隊の寝返りということの方が大きい。結局、独立した各省の代表が上海や南京、武昌で会議を重ねた結果、1912年1月1日にアジア最初の共和国である中華民国が成立することになった。何はともあれ、辛亥革命は数千年来続いた皇帝専制の体制が崩壊した大事件であったのは確かだ。
この中華民国で臨時大総統に選ばれたのが孫中山である。
8, 孫中山って一体どんな人?
(~1925年)
革命の父で、中華民国を創設した人物と知られている孫中山、実はこの人、その一生涯失敗ばかりしていた人で、そもそも中華民国の成立と彼はほとんど対極にあった。
甲午戦争中、中国初の革命団体である興中会を設立したのは確かに彼である。がそれ以降、彼は何度も反清武装闘争を試みては失敗している。1905年、いくつかの革命団体が統一して活動しようとする主旨のもとで、東京で中国革命同盟会が結成されたが、その総理に選出されたのも彼である。しかしそれは彼が最も早くから革命活動に従事してきた、ということだけではなく、「失敗の教師」であり、反清運動のシンボルとしての存在だったからだ。つまり反清闘争の「回数」を買われたわけだ。同盟会が結成されても革命派が一致団結したわけではない。同盟会とは名ばかりで、実際は各革命団体がそれぞれ思うままに運動していたに過ぎない。この点で、同盟会の総理として、彼が成功した、とは言い難い。
そもそも孫中山は北京から最も遠くはなれた広東一帯で革命武装蜂起を行って、そこを清朝から独立して革命の根拠地とし、準備が出来次第北伐を行って北京の中央政府を転覆するという構想の持ち主で、事実、彼の反清闘争はそのすべてが南方各地で行われている。しかし清朝を転覆させた切っ掛けとなる武昌蜂起は中国中部の長江流域で、しかも革命が各省に飛び火するという形で辛亥革命は行われた。孫中山が考えていた革命の構想とは全く異なる推移だったわけだ。
武昌蜂起のニュースを亡命先のアメリカで聞いた孫中山は、その後欧米各国を回って、武昌蜂起から二ヶ月以上過ぎた12月の終りに中国に戻り、独立各省代表から臨時大総統に選出される。しかし彼のその前後の主張を見ると、これも彼の本意ではなかったはずだ。というのも、革命発動後は急激に民主共和化するのではなく、ある一定期間、軍政府を設けて、その大元帥(もちろん彼自身が就任)による独裁で、革命後の混乱を乗り切る、と彼は考えていたからだ。「大総統」は彼の望むところではなかったのである。
だからこそ、臨時大総統就任後四ヶ月足らずで、清朝皇帝退位などを条件として、すでに軍閥化していた清朝最精鋭の新軍(北洋軍閥)に簡単に政権を渡すことができたのだろう。軍閥の武力に対抗できずに軍閥に革命の成果を奪われた、とよく言われるが、少なくとも彼自身が「大総統」というものに対して魅力を感じなかった、という要素があったはずだ。民国成立直後から始まる議会制の導入を含めた急激な民主化に対し、彼は絶対反対、ではなかったが、かなり消極的な賛同、に止まっているのも、彼の考えた民国と実際の民国がかけ離れたものであることがうかがえる。
軍閥に政権を禅譲後、彼は紆余曲折を経て、今度はその軍閥政権に反対する革命を起こすことを一生涯の仕事とする。第二革命はものの見事に失敗、1917年から始めた広州に軍政府を創設して北京にあった軍閥政権に対抗しようとした革命運動も一年満たないで失敗、その後もう一度広州に戻って政権を樹立するもののこれまた失敗、三度広州に戻って、自身が創設した国民党をソ連共産党の経験によって改組し、中国共産党との合作を進め、広州の政権を固めたのが1924年、彼の生涯から見れば最晩年である。
広州を革命根拠地として北伐を敢行する、という彼がずっと描いていた革命戦略は彼の死後になって、彼が作り上げた国民党の手によってなされていくことになる。その北伐がある程度成功したから、彼の業績も光るわけであるが、彼の実際の活動は失敗に次ぐ失敗であった。失敗に次ぐ失敗、その原因を求めるとすれば、革命を主張しながら、孫中山はずっと自身の軍隊を持つ、という最も基本的なことを等閑にしてきたことがあげられる。彼自身の軍隊はソ連との提携と共産党との合作という過程ではじめて形作られていくことになる。
9, 結局中華民国って?(1)
(1912年~1928年)
さて、孫中山を迎えて成立したはずの中華民国であったが、その政権はすぐに北洋軍閥の手に渡ってしまう。革命派が軟弱であったことはもちろんだが、当時の中国では軍閥に対抗しうる軍事力を持った集団が存在せず、清朝打倒も彼らがいなければおぼつかなかったのだから、それは必然の結果だった。一つ強調しておくことは、軍閥が強引に政権を奪取した、という訳ではない、ということだ。当時の法体系では最も合法的な手段を通して実現した政権交代であった。
軍閥に政権が委ねられたとはいえ、皇帝専制の帝国体制が崩壊し、民選議会を主軸とする民主体制が構築された。軍閥、という語感の中には「武断」とか、「横暴」とかがどうしてもついてまわりがちであるが、彼らもこの風潮を完全に無視することはできなかった。中華民国成立の翌1913年にはすでに第一回国会が開かれ、急激に民主化が進められたが、しかしこの急激性が中国史上最初の民選議会制の寿命を縮める結果になってしまう。
革命後の混乱を受けて、急速に国家を統一して難局を乗り越えなければならない時、時の大総統は国会の強大な制約を受けて思うように政治ができず、身動きが取れなかった。業を煮やした大総統は国会最大政党を非合法化、国会の法的効力をなくした上で解散させ、大統領権限を強化し、皇帝専制の復活を図る。
ちょうどこの前後、第一次世界大戦が勃発、ヨーロッパ各国が戦争で忙しくなり、中国進出の足が鈍ると、日本はその機をとらえて、連合軍側に参戦、ドイツ権益の集中する山東省に出兵してこれを占領、1915年には二十一ヶ条要求を中国政府に叩き付ける。革命後の混乱と帝制復活に奔走していた中国は、最後通牒を突きつけてきた日本に独力で抗することもできず、この修正案を受け入れる。
1915年末にはとうとう帝制が復活するが、各方面から反対の声が上がり、南方各省では独立してこれに対抗、南北対立の局面を迎える。北方内部でも帝制に対して不協和音が響き、帝制復活劇は三ヶ月程で失敗する。しかしこの帝制復活も革命の混乱を強権による行使で中国を統一し、難局にあたるという試みの一つだったことは、強調されなければならない。
帝制は解消されたものの、南北対立はますます深刻化する。南北融和策として、解散された国会が復活され、一時、再び統一的局面を迎えるものの、北京政局は、大総統・国務院(内閣)・国会の三つ巴の権力闘争が湧き起こる。その間隙を縫って、今度は退位した清朝皇帝を引きずり出す、清朝を復活させようという動きまで現れた。
人口大多数の漢族が満族王朝の復活を望むはずもなく、この清朝帝制復活はわずか数日の茶番で終わったが、この帝制復活の一連の動きの中で国会が再び解散され、帝制復活失敗後、国会が再開されることがなかったから、孫中山は、辛亥革命後に自身で組織した秘密結社的革命団体を核として広州に乗り込み、国会議員を広州に徴集、広州軍政府を樹立して大元帥に就任した。こうして中国は北洋軍閥政権の北京と広州の別系統の政府が対峙する南北分裂時代を迎える。
北洋軍閥を主体とする北京政府では権力闘争が絶えず、広州でも一致した行動が取れず、どちらも一方を「討伐」することができないまま、この南北分裂の局面は1928年に再び国民党によって中国の統一が宣言されるまで続くことになる。この過程で、国会を中心とした民国の一連の「民主」的改革も形骸化していく。急激すぎた「民主」への移行は失敗、その反動として、「民主」に対する反省と「独裁」に対する願望が、後の国民党政権の独裁体制確立の一助となった。
北京の中央で軍閥同士の闘争が進む一方で、中国各地でも軍閥が林立し始め、広州の政府を含めて、中国はさながら、群雄割拠の様相を呈する。そもそもあの広大な国家が一つになること自体容易ではないし、事実、各省、各郷村では言葉も違えば文化も違う、さらに、この時は国内外の情勢が最も不安定な時で、しかも清末から助成されていた権力の地方への下放傾向も手伝い、また辛亥革命そのものが各省のそれぞれの独立によって実現したことなども要因となって、中国分裂は必至だった。そこに軍閥同士の攻めぎ合い、軍閥対広州の政府の闘争によって、その傾向が一層進んだ。対外的に非常に苦しい局面にある時だけに、国際社会において如何に「中華」を復興させるか、という最重要目的達成のため、中国では統一がもっとも危急を要す課題となった。
そうした環境のもとで、辛亥革命後間もなくから、知識人による科学や民主といった言葉を掲げた啓蒙運動が始まっていた。科学や民主を謳って旧来の「儒教」倫理観の徹底的打破を狙ったこの運動は、ある意味では、「中華」の全否定の試みであり、それは時として白話文の普及という文学革命を重要な内容とし、それなりの成果を収めた。しかし依然として文盲率が90%を越えるこの国で行われた啓蒙運動であり、文学革命であったから、知識人に対する影響は計り知れないものがあったものの、全中国として見た時、それは決して過大評価できるものではない。しかしこの新文化運動と呼ばれる一連の啓蒙・文学運動は皇帝専制の体制が終了したものの、民主・共和の理想と、現実の軍閥同士の抗争の間のギャップに義憤を感じて成長した運動であったことは確かである。
対外的に言えば、第一次大戦の終結とその講和条約が締結されたパリでの会議は、中国にとっては一大転機だった。世界は中華のみ、の国が初めて出席した国際会議ということだけでその意義は大きい。さらに、政治的にも、経済的にも、軍事的にも、最も弱い立場として出席したにもかかわらず、列強と対等、もしくはそれ以上に渡り合い、列強が強要する列強自身の利益に符合し中国を犠牲とする講和条約調印への拒否を決める。中国国内ではこのパリ会議を中国外交の失敗ととらえ、1919年5月4日に五四運動が湧き起こるが、当時の状況から考えれば、パリ会議は中国近代外交の華々しい登場を飾った舞台といってもいいだろう。そして後のワシントン会議では、日本に占領されたドイツ権益だった山東省を日本から奪い返すという実質的成果を上げるに至ったのである。更に重要なことは、これ以後、中国は国際社会における「中華」の位置を模索し、その中で「中華」復興を目指すことになる、ということだろう。
1914年から1918年の第一次大戦中、中国の経済は相対的に著しい発展を遂げている。列強の介入がほとんどなくなった状況のもとで、中国固有の経済が奮闘した結果であった。しかしながら、政治的には終戦後も分裂的局面は改善されず、その混乱の中から、以後の中国の政治舞台で活躍する二大革命政党、中国国民党と中国共産党がそれぞれ、1919年と1921年に誕生している。混乱による中国の弱体化とそれにともなう列強の更なる進出に対する脅威が、こうした新しい歴史の動きを生み出したのである。
10,結局中華民国って?(2)
(1927年~1937年)
1917年に起こったロシア革命と、その後設立されたコミンテルンの世界戦略を背景に、孫中山と国民党はソ連との提携を決定、1923年からは国民党をソ連共産党の経験によって改組する作業を進め、中国共産党との合作を決め、1924年1月、新生国民党とそれと合作した共産党による、対北方軍閥政権、対帝国主義列強(当然ソ連は例外視されていた)の統一戦線が樹立される。
その間、北方では軍閥内部の闘争が激化し、特に中央政権はめまぐるしく変わり、時として賄賂の横行する選挙で大総統に選出されるという、民主共和の理念からは完全に遊離した状況が生まれ、泥沼の権力闘争が続いていた。それでも孫中山死後の1926年から国民党を主体とした北伐軍が進撃を開始すると、北方各軍閥は危機感を持って団結、北伐軍に対抗しようとしたが、時の大勢はすでに決していた。北伐軍は怒涛の快進撃を続けたが、それはむしろ腐敗の極みに達していた軍閥各軍が弱すぎたためであろう。軍閥の連合軍は各地で撃破され、1928年の終りには、国民党によって中国は再び統一された。
1926年から始まった国民党の北伐は孫中山の遺志を継いだものであり、共産党との提携とソ連の後ろ盾により、1927年には武漢や南京といった長江流域の都市を占領していった。しかし、その過程で、主導権争いと共産党への対応の違いで、国民党は内部闘争をし始め、国民党の指導で設立される政府(国民政府)が武漢と南京に二つできてしまう。南京の国民政府は反共をいち早く明確にし、これにテロを加え、弾圧に踏み切った。武漢の国民政府は国民党でも左派的な人々によって設立されていたため、共産党に対しては寛容だったものの、国民党の再統一の必要性が痛感されるに至り、反共に転じることになる。こうして共産党と手を切ることで、国民党は南京の国民政府のもとで統一し、北伐を進め、1928年には一応全国統一を果たす。
それでも国民党内部の闘争が完全に解消されたわけではなく、また全国を統一したといっても、主に各地方に割拠した軍閥の国民党と国民政府に対する帰順を認めるという方法が取られたため、彼らがいつ国民党とその政府に離反してもおかしくない状況が続き、事実、1930年頃までは内戦が絶えなかった。また国民党内部の権力闘争も激化することはあっても解消することはなかったから、国民党自身が爆弾を抱えているようなものだった。
1930年頃になると国民党は不安定ながらも、全国統一をほぼ実質的なものにした。翌1931年からは日本が満洲侵攻を始め、そこを中国本土と切り離して傀儡政権を樹立するという大きなアクシデントがあったものの、東北部と一部北方を除き、中国全土は近代史の中では最も安定した局面を迎えることになる。「国内を先に安定させて、その後国外、特に日本の侵略に対抗する」という国民党の方策がはじめは順調であった。活発な外交を行い、国際的地位の向上を図るとともに、国内では共産党の徹底的弾圧を進め、さらに経済的建設に着手、幣制などの改革を通して、それは大きな成果を上げた。
1930年代前半は、第一次大戦中とともに中国経済の発展期であり、それを側面から後押しし、またそれに誘発されるように、学術研究分野でも言論分野でも活発な活動が行われることになった。特に「独裁か民主か」を問う言論合戦が有名である。1930年代、国民党はドイツやイタリアの成功に鑑み、強力に国内体制を整備していくためファシズム的な方法を採用した。ファシズムの体制では確かに効率よく国内建設を進められるが、しかし必然的に独裁体制とならざるを得ず、それに対する不満と糾弾として提起されたのが、「民主と独裁」論争だった。民国初期の議会制を思い起こさせる「民主」は中国ではあまり歓迎されず、むしろ民国初期のような混乱を招くだけと認識され、この論争は実績を残しつつある国民党の「独裁」が支持された。
国民党によるファシズム的戦略が功を奏し、対外的にも国際的地位を向上させて、アヘン戦争以来の不平等条約の漸次改正を行い(不平等条約の完全撤廃は40年代を待たねばならなかったが)、「中華」の復興を遂げつつあり、共産党の包囲作戦も紆余曲折は経たが、共産党壊滅も時間の問題と目され、国内体制の整備も進み、経済建設も順調、順風満帆と思われたが、1937年7月に情勢は一変する。もちろん、日中全面戦争の勃発である。
11,抗日戦争はなぜ起こり、なぜあんなふうになったの?
(1931年~1945年)
1905年日露戦争勝利後、特に1910年併合が決まって、朝鮮問題が一段落すると、日本の対外的な矛先は中国東北部、所謂「満洲」と呼ばれる地域に向かい、「満洲問題の根本的解決」が対外的な最優先課題となった。朝鮮を自国領としてしまったために、満洲における影響力の拡大に迫られた結果である。
1917年ロシアで社会主義革命が起こる前までは、ロシアと協力関係を結び、満洲権益の独占のため、あの手この手でその地歩を固めていった。ソ連誕生後、新生ソビエトは帝国主義的なやり方に強硬に反対するようになる。そんなソ連が日本と協力関係を結ぶはずもなく、それどころか帝制ロシア時代、中国から獲得した数々の中国権益を中国へ返還する声明を出す。中国にとっては願ってもないことで、大喜びされ、中ソ関係(国民党・共産党とソ連)が急速に接近するきっかけともなったが、日本にとって、ソ連は一転して満洲権益を脅かす存在となった。
それ以後、東北に割拠した軍閥に援助することで、日本は東北部での活動を活発化させていくが、国民党による対軍閥の北伐軍が快進撃を続けると、その方向を徐々に転換せざるを得なくなった。東北に割拠した軍閥は1928年までに国民党に忠誠を誓い、これを利用して権益を拡大することも望めなくなった。
業を煮やした日本の出先軍部は満洲を混乱に陥れるべく事件を引き起こし、それを契機として、日本の満洲侵攻が始まる。出先軍部の独断専行も、後には日本の中央政府に承認されることとなる。1931年9月のことであり、日本では満洲事変と呼ばれるこの事件、中国では九一八事変と称される。これ以後、日中間は束の間の安定を迎えることがあったものの、基本的には1945年まで交戦状態であって、これを十五年戦争と呼ぶこともある。
そもそも日本は二十一ヶ条(1915年)で、甲午・日露両戦役で得た「中華」の民からの得難い尊敬の念を自ら捨て去り、第一次大戦の講和条約では外交的なミスから五四運動(1919年)を引き起こさせ、20年代にも出兵までして時には内戦に干渉、中国の日本に対する憎しみは「中華」の自尊心も手伝って最高潮に達し、それは甲午の勝利で急速に蔓延してしまった日本の中国に対する蔑視感情を刺激し、増幅する。つまり、憎悪が増せばさらに蔑視が進み、蔑視が進めば更に憎悪が増す、という悪循環を繰り返すこととなった。この悪循環がこの戦争の根底にあった。何はともあれ、第一次大戦にこりて世界的潮流としての平和ムードがあり、更に日本も調印したパリにおける不戦条約締結(1929年)以後は、武力の使用そのものに対する見方が変わっていたから、日本がそれを率先して使用したこの戦争において、日本の正義が世界に認知される余地はなかった。
ほとんど電撃的に満洲一帯を支配下に治めた日本軍は、続いて、清朝の最後の皇帝を引きずり出して、これをはじめは執政、後には皇帝とする満州国を建設、傀儡化した。中国ではこの政権を最大の憎しみを込めて偽満州国と呼ぶ。
満洲を手中に収めた後、日本軍は漸次南下を開始する。1935年までには華北一帯に脅威を与えるようにまでなった。そして1937年7月7日、北京近郊の盧溝橋で「事件」が起こる。この七七事変の勃発が日中両国の全面戦争の始まりとなった。
国民党は、国内を先に安定させて、その後国外、特に日本の侵略に対抗するという方策を、全面戦争の勃発で放棄せざるを得ず、共産党と再び協力関係を結ぶことに決したが、国民党のファシズム体制はなおも持続され、それはある程度において、日本軍の撃退、少なくとも戦争の泥沼化に貢献するところとなった。国民党は国内の主要な産業を西南地方に移転することで戦争の長期化を図り、首都も南京から武漢を経て重慶に移し、徹底抗戦の体制を、これもやはりファシズム的な効率のよさによって築き上げた。
華北一帯を攻略すべく、日本軍は南下を続けるとともに、同年8月には上海にも軍隊を派遣、三ヶ月の日中間による攻防の末、上海を落とした日本軍はそこから西進、中国の首都南京を目指した。同年12月、南京を陥落させた日本軍が南京で「事件」を起こしたのは有名なことである。
南京陥落後、日本は武漢を目指し、更に南方にも戦線を拡大、中国の意図通り、戦争は長期化、泥沼化の様相を呈してきた。日本軍が多くの都市を占領したものの、それが点と線の支配に過ぎなかったのはよく知られている。
1941年からはアメリカとも開戦、日本は更なる泥沼の中を進んでいくことになるが、これも抗日戦争にアメリカを主とする連合軍を引きずり込むという国民党の対外政策の一環と無関係では有り得ず、日本はものの見事にそれにはまってしまったわけだ。国民党の最高幹部が日本に実質的投降を表明するという重大なアクシデントがあったものの、国民党の「戦略」が、「戦術」面では優勢に立っていた日本を圧倒した。こうした背景のもとで、中国は日本以外の国々との間で、不平等条約を完全に撤廃、香港やマカオの植民地の問題は残されたものの、国際的地位は飛躍的に向上した。
その後、中国戦線はほとんど膠着、主要な戦線は太平洋上やその諸島、東南アジアとなり、日本は中国においてもいくつか大きな作戦をこころみるが、すべて失敗、太平洋戦線で着実に追いつめられた日本が、二度の原爆投下を経て、1945年8月15日に連合国に対して無条件降伏、十五年にわたった日中戦争も自動的に終結した。しかしこの終結は日中両国間に蔓延る蔑視と憎悪という溝の完全な解消を意味しなかった。その根本的な解決にはまだまだ長い時間がかかるだろう。
12,合作?内戦?国民党と共産党
(1919年~1949年)
1945年日本は降伏、戦争の長期化による徹底抗戦は実を結んだものの、中国のほぼ全土が戦場となり、国土の退廃は覆うべくもなかった。殊に国民党にとっては途方もない痛手であった。30年代からのファシズム体制による国内建設が遅れたばかりでなく、その成果も多いに削り取られた挙げ句、さらに抗戦中すでに対立が表面化していた共産党は、抗戦以前の瀕死状態を脱して、むしろ戦争を有効に活用してその勢力を拡大、国民党と拮抗しうるほどの一大勢力となってしまっていた。アメリカの調停などもあって、戦後間もなくは国共両党提携の兆しがみられたものの、抗戦中にすでにくすぶっていた火種は消しがたく、国民党の共産党に対する嫌悪と共産党の国民党に対する不信はそれぞれ容易に解消するものではなかった。間もなく、国共は全面的に対決する。
国共両党の因縁は思いのほか根深い。
中国初の革命団体である興中会を結成(1894年)し、各革命団体が集合した中国同盟会の総理に選ばれ(1905年)、辛亥革命後には総理に絶対服従の秘密結社的な革命団体を創設(1914年)した孫中山は、1919年、より開放的な革命団体として中国国民党を組織した。軍閥政権に対抗して広州で初めて軍政府を建てたが失敗に終わった、ちょうどその頃である。1921年には、ロシア革命(1917年)の影響を受けて中国共産党が誕生した。
ソ連共産党とコミンテルンは中国共産党に影響力を行使してその活動を指導し、援助すると同時に、孫中山の中国国民党を、中国においては最も進歩的な団体として、これとも接触を始めた。孫中山自身もロシア革命とその後のソ連の成長に興味を持ち始め、ソ連とのつながりを強化していくことになる。世界では例を見ないソ連式の経済政策にひどく共感するが、最も重要なことは、孫中山がソ連との接触によって、初めて自身の武力を持つようになったことだ。国民党の軍隊で、北伐の主力を成した国民革命軍はその発展した形態である。
コミンテルンが国民党に近づき過ぎることは、ロシア革命をモデルとする理想主義的傾向の強かった誕生間もない中国共産党に不快感を与え、かつ、コミンテルンは国民党と共産党の合作、しかも対等の協力関係ではなく、共産党員が一個人として国民党に加入するという方法、を指示、共産党はこれに猛反発を試みるが、中国共産党はあくまでコミンテルンの下部組織であるから、この指示は絶対命令であり、覆すことはできなかった。
ソ連の援助を得て、国民党をソ連共産党風に改組し、革命の新たな段階を築こうとする孫中山は、共産党との合作にも基本的に合意し、1924年、広州にてこれは完成する。第一次国共合作である。
ソ連共産党とコミンテルンのもとで創設された共産党と、同じくその影響を多分に受けて改組した国民党には共通点が多い。どちらもソ連共産党をモデルとしたため、基本的には革命政党である。革命を起こして現政権の転覆を図る団体である革命政党は、今現在一般に政党と呼ばれる議会政党とは区別されなければならない。国共両党どちらも革命政党として、「以党建国」(党による国家建設)・「以党治国」(党による国家経営)・「一党専政」を掲げている。つまりは独裁である。党による独裁で、革命を進めて国家を樹立し建設していくという思想を持っている。マルクス主義を奉じる共産党は理論としてすでに独裁の不可避性を説いているし、国民党も孫中山の理論に基づけば独裁的である(そもそも孫中山自身がすでに多分に独裁志向的だった)。両党とも独裁を容認するどころかそれを積極的に推し進めることを目標としている。独裁は例外なく排他的であり、両党の合作も、この点で、行き詰まりを見せるのは時間の問題とも言えた。
それでも孫中山在命中は、表立った抗争はなく、むしろ共産党は孫中山の庇護のもとで、勢力の拡大に努め、徐々に台頭してくる。1925年3月、孫中山が死ぬと、国民党は早くも共産党問題をめぐって分裂し始める。このまま国共合作を続けて、とりあえず北伐を敢行して北方の軍閥政権を打倒する、という考え方が一つ、勢力台頭の著しい共産党をこのまま放置するのは危険であり、合作を終わらせ、むしろそれに弾圧を加えるべき、というものが一つ、意見は真っ向から対立した。
それでも北伐は一応順調に進められた。しかし北伐の進軍を利用し、共産党はますます勢力の拡大に努め、国民党の共産党に対する警戒は高まるばかりだった。1927年4月、南京に国民政府を建てた国民党の一派はついに共産党弾圧を始める。武漢に国民政府を樹立した国民党のもう一派も後にこれに歩調を合わせ、7月までには国共合作は国民党による共産党に対する血の弾圧で幕を閉じる。
この度の国共合作を通じ、国民党は党組織を一新し、革命政党として発展を見たのみならず、軍閥政権を覆して、全国統一を果たしたのであり、これらのことは共産党およびその背後にいるソ連を抜きにしては考えられなかった。一方の共産党もまたこの期間、劇的な発展を遂げる。創設当時、限られた地方に全国で数百しかいなかった党員も、国共合作を通じて、その間の活動で全国の主要な地方に党員は万を数えるまでになっていた。
国共分裂後、国民党が政権を取ったこともあり、共産党の活動は完全に非合法化し、地下に潜って地道な活動を続けていくほかなかった。それでも共産党独自の軍隊を持つようになり、今までの都市部の革命によって社会主義を目指すという路線が見直され、中国の広大な農村地帯に着目して、ここに主要な活動の場所を見出していくようになる。ロシア革命を模範とする理想主義的傾向の是正が行われ始めた。
1930年代になると、国民党はその独裁的傾向と国際的潮流が合致してファシズム体制による国内建設を進め、上述のように、それは一定の成功を収める。共産党に対しても徹底的な弾圧を繰り返す。数十万から百万の軍隊を繰り出して大規模な共産党狩り作戦をも敢行する。江西省を根拠地とした共産党もこれに耐えられず、陜西省まで逃走。しかし国民党は共産党を敗走させはしたものの、これを壊滅することにはついにできず、むしろこの逃走を許したことが国民党には致命的となった。共産党から見れば、逃走であっても「勝利的」であり、今でもこの敗走を「長征」と称し、語り継がれている。この過程で共産党はコミンテルンの束縛を完全にではないものの、かなりはっきりとした形で振り払った、というのも特筆すべきことである。
1937年日中全面戦争が始まると、抗日戦争としてこれに一致団結しなければならないという気運が高まる中、瀕死の共産党が渋る国民党を何とか説得、日本に対する新たな国共合作がなった。第二次国共合作である。
抗日戦争の主力はやはり国民党軍で、共産党軍は広大な農村地帯に点在してゲリラ戦にあたった。正面で戦わなければならない国民党軍の消耗は激しく、それに対し共産党軍はゲリラ戦を有効に展開して自身の勢力拡大につなげた。瀕死の重傷を負いつつも、そこから戦争を利用することで復活を遂げつつあった共産党に対し、国民党が警戒するのは当然の成り行きといえた。抗日戦争中すでに国共の合作にひびが入り、武力闘争も起こしていたのはこのためである。こうして国共両党は終戦を迎え、国共は再び全面抗争に突入したのである。
戦争中に劇的な発展を遂げたとはいえ、量的には依然として共産党不利であったが、共産党は思想方面を強力に武装化することで、独裁体制の不可避的な帰結としての腐敗の極みに達していた国民党を質的に上回った。戦後の二大大国の対立的局面を予測していたアメリカは、腐敗しきった国民党に幻滅していたものの、それなりの同情を寄せ、相応の援助を施したが、それも1948年後半、戦局が完全に共産党有利となると、国民党援助から手をひき、国民党はこうして国内外で孤立無援となり、1949年終りまでにはその大陸勢力はほとんど壊滅、主要幹部が台湾にわたって、そこで中華民国を存続していくこととなった。
共産党は自身の指導による政府を設立、国名を中華人民共和国とし、1949年10月1日、その成立を宣言した。中国大陸は共産党のもとで「中華」復興を目指すことになる。
大陸の共産党と台湾の国民党、その争いは今に至るまで全く解決されず、将来的にも解決の見通しは立っていない。